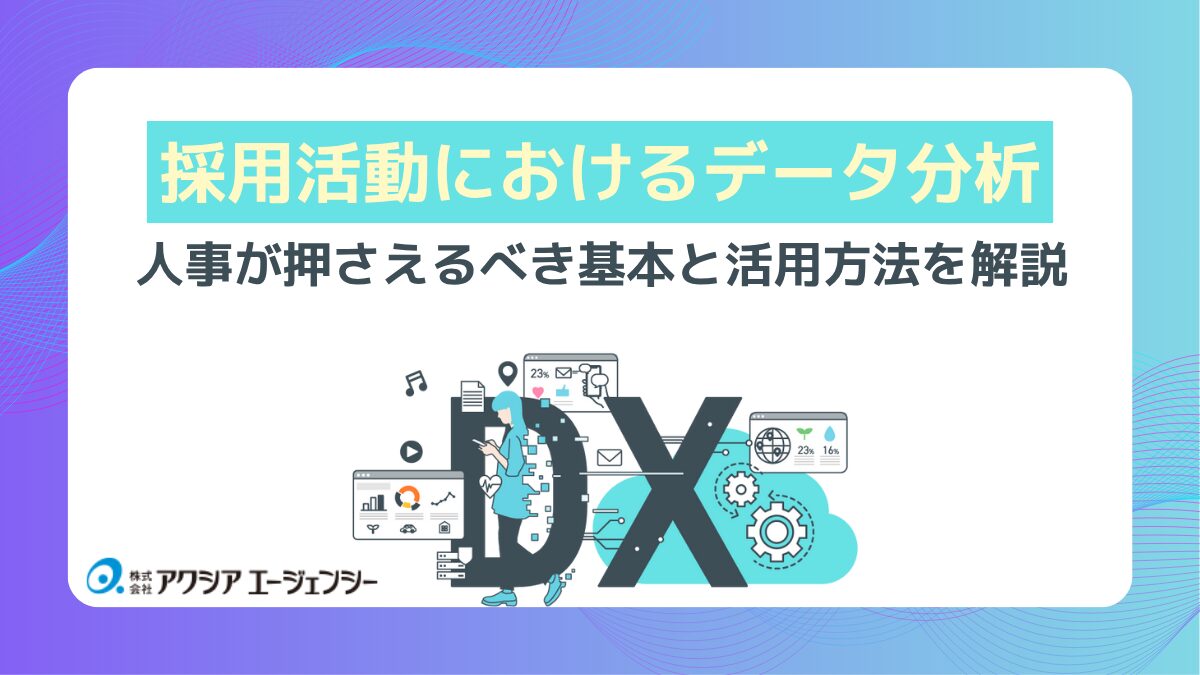採用活動において、より質の高い人材を確保するためには、人の感覚や経験に頼るだけでは不十分です。採用に関するあらゆるプロセスや数値を「見える化」し、客観的なデータに基づいた意思決定を行うことが重要です。
この記事では、採用データの基本的な種類や分析手法、具体的な活用例、さらにはAIを活用した予測分析まで、人事担当者が今すぐ実践できるノウハウを幅広く紹介します。これからの時代に不可欠なデータ分析のスキルを身につけ、採用活動をより戦略的に進めていきましょう。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ
- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる
- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー
採用データ分析の意義と目的
採用データを活用することで、現状の把握から課題の特定、そして戦略の見直しまで、さまざまな改善が可能になります。ここでは、採用データ分析が持つ意義と目的について説明します。
採用データ分析の意義
近年の採用活動では、単に母集団を集めるだけではなく、「どのような施策がどのような成果を生み出しているのか」を把握することが求められています。なぜなら、成果と紐づいていない施策を続けることは、コストやリソースの無駄につながるリスクがあるからです。
そのために有効なのが、データ分析を活用した可視化の取り組みです。
掲載した求人広告の応募者データや、採用イベント・説明会などの参加者データを分析することで、現在行っている採用活動の有効性や問題点を明らかにできます。たとえば、説明会から応募への移行率や、書類選考から内定までの通過率を数値で把握することで、離脱ポイントやボトルネックが具体的に見えてきます。また、平均的な選考通過率や内定率を指標として用いることで、各施策の成果を数値で比較検討できるようになります。
このように、データを用いた分析は、採用活動の「見えづらい部分」を可視化し、改善の方向性や次の採用戦略を定量的に導き出す手段となります。
採用データ分析の目的
採用データ分析の主な目的は、採用活動の課題を発見し、対策をして解決につなげることです。
まず、求める人材像(ペルソナ)を具体的に定義し、そのターゲットに合った応募者層が集まっているかを検証することで、アプローチの方向性を最適化することが可能になります。
たとえば、面接の実施状況を分析し、通過率や辞退率、評価のばらつきといった情報を把握することで、選考プロセスそのものに問題がないかを見直すきっかけになります。選考の進め方に改善点があれば、対応することで全体の効率も向上します。
また、これまで採用業務を担当している個人の感覚に頼りがちだった判断を、データに基づく客観的な検証によって補完できる点も大きなメリットです。実際にどの選考フローが採用の成功に寄与しているのかを明らかにし、課題の要因を具体的に把握することで、採用活動全体の質を高めることができるのです。
このように、採用データ分析は「分かりづらい」を「分かる」に変える手段として、今後さらに重要性を増していくでしょう。
採用活動で収集すべきデータとは
採用活動の効果をより高めるには、どのようなデータを収集すべきかを理解することが大切です。ここでは、基本となるデータの種類と活用方法のポイントを紹介します。
応募数・応募経路などの基本データ
応募経路の多様化と分析の必要性
応募数や応募経路に関するデータは、採用活動の第一歩として必ず押さえておくべき基本情報です。どの経路からの応募が多いのかを分析することで、応募者の流れや傾向が見えてきます。求人媒体、企業のサイト、広告、リファラル、スカウトサービスなど、複数のチャネルを比較して効果を検証することが大切です。
効果的なスカウト活動の発見
スカウトメールなどのダイレクトリクルーティングについては、全体の送信数のうち、エントリーに至った人数や応募後からの行動データを収集することで、その手法の効果を見極めることができます。応募者の属性やニーズに合わせた戦略がどれだったのかを分析すれば、今後の施策にも活かせます。
選考プロセスの歩留まりデータ
選考過程において、どれだけの候補者が通過し、どれだけが辞退しているのかといった「歩留まりデータ」は、採用の改善を図る上で欠かせない情報です。書類選考、面談、最終面接といった各ステップの通過率や辞退率を記録・比較することで、選定基準の妥当性を客観的に評価できます。
また、面談内容や評価レポートを記録しておくことで、候補者を多角的に判断できる材料にもなります。セミナー参加者の情報や評価資料なども含め、次の選考に役立てましょう。
採用コスト・時間の把握
採用にかかるコストと所要時間の把握も欠かせません。求人媒体費や面接対応などの人件費などのコストに加え、内定までにかかる平均的な期間などをデータ化しておくと、活動全体の費用対効果が明確になります。
なお、新卒採用と中途採用では、かかる時間や費用が大きく異なります。それぞれの特徴に合わせてスケジュールを設計し、適切なタイミングで採用活動を進めることで、より効果的・効率的な採用が実現します。
採用データ分析の基本手法
採用データを効果的に活用するためには、正しい分析手法を理解することが不可欠です。ここでは、基本的な3つの分析手法について解説します。
応募経路ごとの採用率分析
応募者がどの経路から応募してきたかを把握することで、採用戦略の見直しに役立てることができます。代表的な応募経路としては、求人サイト、会社のホームページ、紹介、スカウト、SNS、広告などがあり、それぞれの経由で入社に至る割合には差があります。
たとえば、新卒は求人サイト経由が多く、中途はスカウトや人材紹介が中心になる傾向があります。職種によっても効果的な経路は異なるため、職種別にデータを分類して分析するのが効果的です。
さらに、面接官のフィードバックを活用することで、どの経路から来た応募者が高評価を得ているのかを確認でき、今後の採用チャネルの選定に活かすことが可能です。
歩留まり率とその計算方法
歩留まり率とは、各選考段階での応募者の通過割合を示す指標です。たとえば、書類選考から一次面接、二次面接、最終面接、内定といったプロセスごとの通過人数を記録し、下記のように計算します。
通過数 ÷ 応募数 × 100 = 歩留まり率(%)
この数値を出すことで、選考フローのどこにボトルネックがあるのかを推測できます。また、内定辞退が多い場合は、その理由を明確にすることも大切です。自社の平均歩留まり率と業界の水準とを比較することで、改善のヒントが得られるでしょう。
採用の費用対効果を評価する方法
採用活動にかかる費用を正しく評価することも重要です。まず、広告掲載料、人材紹介手数料、パンフレット制作費、説明会開催費など、すべてのコストを洗い出します。
その上で、採用に至った人数や応募者の質、成果の出た採用手法などを定量的に評価し、費用対効果(ROI)を検証します。たとえば、「ある求人媒体で100万円の費用で5人を採用した場合、1人あたりの採用単価は20万円」というように算出します。
このように費用と成果を数値で示すことで、どの施策に予算を集中すべきか、客観的に判断できるようになります。
採用データの具体的な活用方法
収集した採用データは、分析するだけでなく実際の施策に生かすことが重要です。ここでは、戦略の見直しや媒体選定などにおけるデータ活用の具体例を紹介します。
採用戦略の見直しと改善
採用戦略をより効果的なものに改善する第一歩は、過去の施策に対するデータをもとに現状を正しく見直すことです。応募数や通過率、内定率などの数値を比較し、どの施策が効果的だったのかを明確にすることが必要です。
改善すべき領域を見つけることができれば、その内容に応じた具体的な手法を立案します。たとえば、母集団形成が弱い場合は利用している求人媒体の見直し、選考の歩留まり率が低い場合は面接官へのトレーニング研修導入などが考えられます。
なお、戦略の改善は一度で終わるものではありません。実施後は定期的にデータを分析し、効果測定と調整を繰り返すことが重要です。こうしたPDCAサイクルを回すことで、持続的な改善が可能になります。
媒体選定と出稿プランの最適化
求人媒体の選定は、採用成功の鍵を握る重要なポイントです。候補者の属性や求める人物像に応じて、適したメディアを選ぶことで、質の高い応募を得る可能性が高まります。求人サイト、SNS、ダイレクトリクルーティングなど、各媒体の特性をよく理解した上で、自社に合うチャネルを選びましょう。また、広告の出稿タイミングや内容も、計画に基づいて最適化する必要があります。
求人の出稿費用や掲載回数についても、「1人あたりの採用単価」として評価し、費用対効果を定量的に把握することで、より効率的なプランへと最適化する仕組みを整えることが求められます。
応募数を安定的に確保するためにも、計画的な出稿戦略を立て、必要に応じて相談・修正を行う柔軟な体制を持つことが大切です。
選考後のフォローも丁寧に
とはいえ、採用活動は「人とのつながり」が基本。特に選考が終了した後のフォローアップも、内定者とのつながりを深め、辞退を防ぐために欠かせない取り組みとして重要です。優秀な人材ほど他社からも人気で声がかかりやすいため、内定後の対応が入社意欲に大きく影響します。内定後の不安を解消するために、面接官や担当者からの定期的な連絡、丁寧なメッセージ送信、懇親イベントの開催などを通じて、信頼関係を築くことが重要です。
連絡の際には、注意点を押さえつつ、企業の魅力や働く環境について改めて伝えることも意識しましょう。こうした施策によって、候補者の入社意欲を高めることができます。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ
- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる
- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー
採用分析に活用できるツールをご紹介
採用データを効果的に活用するには、分析を支えるツールの選定と運用が鍵となります。ここでは、実務で役立つ代表的なツールとその活用方法を紹介します。
ATS(採用管理システム)
ATSは求職者の情報を一元管理できるシステムで、選考状況の可視化、メール対応の自動化、面接日程の調整など、採用業務全般をサポートする機能が備わっています。
まずは、ATSの基本機能をしっかり理解しましょう。
応募者の属性や進捗状況を整理しやすくするためには、入力するデータの形式や管理ルールを統一するなどをして情報を整え、担当者がアクセスしやすい便利な形で管理を行う必要があります。また、人事担当者が日々行っている作業に合わせて、必要な通知やステータス管理のカスタマイズを行うと、実務の負担の軽減・業務の効率化にもつながります。
さらに、インターンシップや会社説明会の参加者データもあらかじめ記録しておくと、後の選考時に役立ちます。
BIツール
採用データをわかりやすく可視化したい場合、BI(Business Intelligence)ツールの活用がおすすめです。BIツールでは、グラフや一覧表を使って情報を視覚的に整理でき、複雑なデータや分析結果も一目で把握しやすくなります。
BIツールを使用するにあたり、まずは「何を可視化したいのか」を明確にすることが大切です。応募経路別の内定率、選考ステップごとの歩留まり率、媒体別コストなど、目的に応じて必要なデータを整理しましょう。
そのうえで、Looker StudioやTableau Public、Power BI Desktopといった無料ツールを活用すれば、初期費用をかけずに可視化の実践が可能です。見やすい資料を作ることで、社内への共有やレポート作成の質も向上し、分析の説得力が増します。
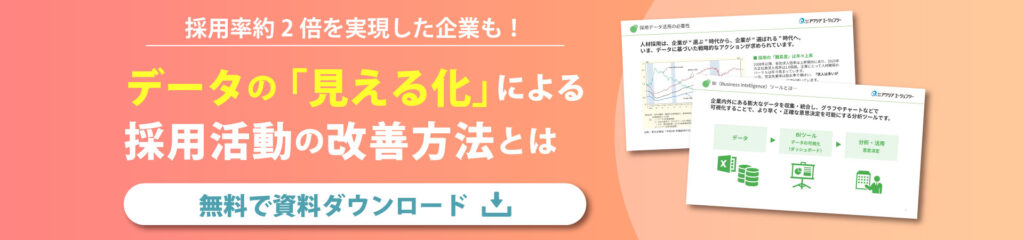
データ分析を行う際の注意点
採用データの分析には、正しい進め方と意識すべきポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、分析を始める前に知っておきたい基本的な注意点を紹介します。
分析目的の明確化とデータの選定
データ分析を始めるにあたって、まず重要になるのが「目的の明確化」です。
何のためにデータを収集するのかがはっきりすれば、それに必要な情報を絞り込むことができ、効率的なデータ収集ができます。たとえば、「面接通過率を改善したい」という目的がある場合、面接の通過率や評価項目に関するデータに注目すればよいことが分かります。
また、分析の対象となるターゲットを特定することで、求めるデータの詳細や特徴が把握しやすくなります。たとえば、新卒向けか中途向けかによって、収集すべき情報や分析の軸も変わってきます。
目的とターゲットが明確であるほど、収集したデータの活用がしやすくなり、課題の把握や目標達成へのステップが具体的に見えてきます。
定量データと定性データのバランス
採用データの分析では、「定量データ」と「定性データ」の両方を組み合わせて活用することが大切です。
定量データ
応募数、通過率、内定数など数値として明確な情報を示すもので、採用活動の成果を数値的な基準で評価するのに役立ちます。外部との比較や進捗の追跡に適しています。
定性データ
面接官のコメントや応募者の感想、辞退理由など、具体的な内容や背景を理解するための情報です。数値だけでは見えない問題の原因を探る手がかりになります。
これら2つをバランスよく活用することで、数値に現れにくい問題も把握しやすくなり、より説得力のある分析結果につながります。データ分析における信頼性を高めるためにも、どちらか一方に偏らず、両者の統合的な運用が求められます。
KPI設定と分析サイクルの構築
採用活動の改善には、効果を測るためのKPI(重要業績評価指標)の設定と継続的な見直しが欠かせません。ここでは、KPIの運用と改善サイクルの構築について解説します。
採用KPIの設定とトラッキング
目標と基準を明確に設定する
まずは、採用における具体的な目標を明確にし、それに応じた指標を定めます。たとえば、「面接から内定までの所要日数を短縮する」「1人あたりの採用コストを下げる」といった具体的な目標が、KPI設定の出発点となります。
目標が決まったら、それを達成するために追うべき指標を選定します。そして、どの数値をもって達成とするかの基準も併せて設けることが重要です。このとき、過去の実績や業界水準などを参考にして現実的な数値を設定すると、KPIが機能しやすくなります。
定期的な確認と柔軟な調整がカギ
最後に、KPIが実際の成果を正確に見極められているかを定期的に確認し、うまくいっていない場合は基準や手法の見直しを行います。こうしたトラッキングと調整を繰り返すことが、効果的なKPI運用につながります。
継続的な改善を支えるデータの活用
採用活動は、一度方針を決めたら終わりではありません。効果を高めるためには、日々の業務を振り返り、データに基づいて改善していく姿勢が重要です。
たとえば、歩留まり率や採用単価、求人広告の反応率などの数値データを調査・可視化することで、「なぜ思ったより応募が集まらなかったのか」「どの業務に時間をかけすぎているのか」といった課題を具体的に分析できます。
こうした分析結果は、図やレポートなどで可視化することで、社員同士の共有がスムーズになります。承諾や組織の協力を得やすくなるため、実行フェーズへの移行もスムーズに進むでしょう。
こうしたKPIとデータ分析のサイクルを維持することが、採用活動全体の強化につながっていきます。
採用データの予測分析とAIの活用
近年では、AIを活用した予測分析が採用活動にも広がりを見せています。これまでのように過去のデータを振り返るだけでなく、未来の動向を見通すことで、より柔軟で精度の高い意思決定が可能になります。
AIによる予測分析がもたらす新たな視点
AI技術、とりわけ機械学習を活用した予測分析は、従来の分析では見えにくかった傾向やパターンを捉えられるようになります。
たとえば、応募者の行動履歴や志望動機の文章を解析して、内定辞退の可能性を予測したり、ミスマッチによる早期離職のリスクを見積もったりすることが可能です。
また、エンゲージメントの高い人材を特定することで、より質の高い採用につなげることもできます。AIを使うことで、情報処理のスピードと精度が大きく向上し、採用課題に対策する力も高まります。
精度を高めるカギは正確な母集団データ
AIによる予測分析を成功させるためには、分析の土台となる正確なデータを収集することが前提となります。応募者の属性、行動履歴、選考結果など、できるだけ多角的なデータを蓄積することで、予測の精度が格段に向上します。
特に、エントリー段階からの記録を丁寧に残しておくことが、後の分析で大きな価値を生むポイントになります。
採用活動に広がるAI活用の可能性
2025年現在、多くの企業がAI導入を検討・実施しており、Googleアナリティクスなど他部門で使われていたデータ分析技術を採用活動に応用する動きも進んでいます。情報の活用次第で、悪い傾向を早期に察知し、改善につなげることも可能です。
AIの導入は、単なる業務の自動化だけでなく、母集団の理解を深め、データをもとにした戦略設計を支援する存在として、採用活動全体をレベルアップさせる可能性を秘めています。
まとめ
ここまで紹介してきたように、採用活動をより戦略的に進めるためには、データ分析の活用が欠かせません。数値として示される定量的なデータと、応募者の声や行動から得られる定性情報を組み合わせた分析は、採用に関する意思決定の質を高め、より納得感のある判断につながります。
特に、選考プロセスや応募者対応などの場面では、単に感覚だけに頼るのではなく、実際のデータをもとに判断することが求められます。SNSでの反応やアンケートの回答、行動ログの記録なども、貴重な分析材料となります。
また、分析手法は一度だけでなく、繰り返し実施することでその精度と信頼性が高まり、新たな発見をもたらす可能性があります。こうしたプロセスを継続することで、採用活動全体の改善に結びつけることができるのです。
採用データはただの記録ではなく、企業の採用戦略を支える基盤です。その価値をしっかり理解し、最大限に引き出す戦略的な視点を持つことが、これからの採用成功への近道となるでしょう。
人事DXのお悩みはアクシアエージェンシーへ
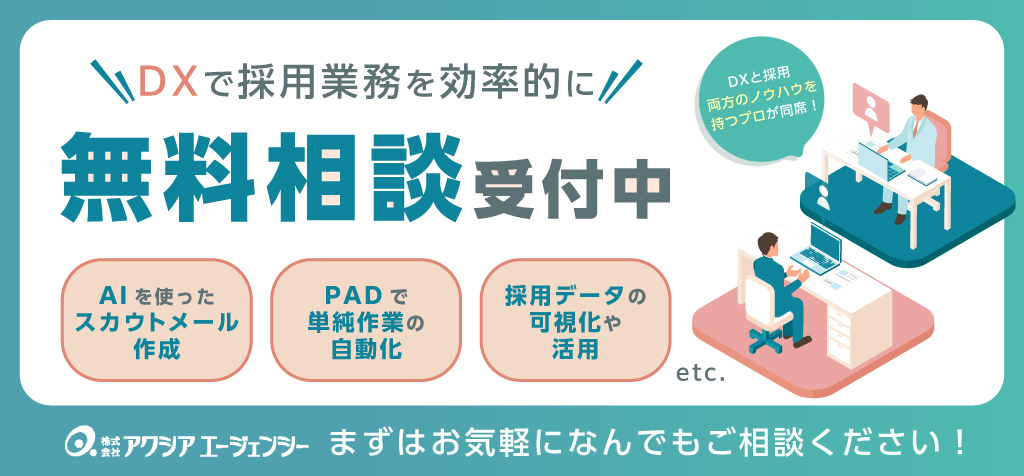
採用に関する総合コンサルティングを行っているアクシアエージェンシーでは、採用業務に関するDX化のお手伝いをしております。業務効率化だけではなく、母集団形成や採用コストの削減など、あらゆる観点での支援が可能です。

・面接調整や進捗管理に、毎日追われている
・スカウトや選考対応が、担当者に依存して属人化している
・採用データはあるのに、改善につながっていない
このようなお悩みをお抱えの企業様はぜひ一度、お話しをお聞かせ下さい。状況を整理し、問題・課題を把握する段階からはもちろんのこと、導入後もより良い採用活動に向けた効果改善などのサポートも行います。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
.jpg)
企業のニーズや状況に合わせた
ツールのカスタマイズが可能
アクシアエージェンシーは、採用までのプロセスを一気通貫で支援。BIやATS、AI、RPA、API連携を活用し、企業ごとの課題に応じた運用設計も専任チームが柔軟に対応します。

データドリブンで
改善が“感覚”から“戦略”に変わる
属人的な採用活動を、KPIダッシュボードを活用してデータ起点の戦略型業務へ転換。リアルタイムで状況を可視化し、“なんとなく”の施策から脱却できます。

仕組みの“導入”だけで終わらない
伴走型パートナー
ツール導入で終わらせず、実務への落とし込みから運用定着までを伴走支援。業界や体制に応じて柔軟に設計し、“使われないDX”を防ぎます。
貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!