人材採用にかかるコストは年々増加傾向にあり、多くの企業が「費用対効果」の見直しを迫られています。求人広告費や紹介料、説明会運営費、さらには人事部門の工数に至るまで、採用活動は決して小さくない投資です。しかし実際には、その投資がどれほどの成果を生んでいるのか、明確に把握できていない企業も少なくありません。
近年、経営層が採用活動に求めるのは「人数確保」ではなく、「投資に対するリターン(ROI)」です。採用は感覚や経験に頼る時代から、数値に基づく戦略的な判断へとシフトしています。つまり、人材採用も営業やマーケティングと同様に、投資効果を定量的に可視化し、改善していく姿勢が求められているのです。
本記事では、採用ROIの基本的な考え方から、実務で活かせるKPI分析手法、投資配分の最適化、DXによる工数削減、そして経営層に響くレポートの作り方まで、具体的な方法を徹底解説します。「なんとなく採用している」から、「数字で語れる採用」へ。その第一歩を踏み出しましょう。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ
- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる
- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー
はじめに
採用活動にかかるコストは年々増加しています。求人広告費、人材紹介会社への仲介手数料、採用イベントや説明会の運営費用、そして人事担当者の工数まで含めると、ひとりの採用に数十万円から数百万円規模の投資が必要になることも珍しくありません。しかし、多くの企業では「これだけ費用をかけてどれだけの効果が出ているのか」を正確に把握できていません。結果として、採用活動がブラックボックス化し、経営層に「採用ROI(費用対効果)」を示せず、予算の妥当性を説明できないという問題が生じています。
近年、経営層が人材投資に求めるものは単なる「採用数」ではなく、ROI(Return on Investment)=投資に対してどれだけリターンを生み出しているか です。人材は企業にとって最も重要な資産でありながら、マーケティングや営業のように「数値で効果を可視化する仕組み」が未成熟な領域でした。しかし、労働人口の減少と採用市場の競争激化によって、採用費用対効果を経営に説明する必要性はこれまで以上に高まっています。
データをもとに判断する「データドリブン採用」
ここで鍵になるのが データドリブン採用です。応募数や内定承諾率といった採用KPIを正しく設定し、チャネル別にCPA(Cost per Application:応募単価)やCPO(Cost per Offer:内定単価)を計算することで、どの採用手法にどれだけの費用をかけるべきかを明確に判断できます。また、採用コスト削減だけでなく、定着率や入社後パフォーマンスといった「質」を含めて評価することで、より本質的な採用ROIの改善が可能になります。
たとえば、広告に頼るだけではなくリファラル採用やダイレクトリクルーティングを活用すれば、CPAやCPOを下げながら採用の質を高められます。また、採用DXを取り入れることで面接調整や候補者対応を効率化し、工数削減によるROI改善にもつなげられます。つまり、採用ROIを高めることは「コストを削る」ことではなく、投資配分を最適化し、効果を数値で示すこと なのです。
本記事では、
- 採用ROIが注目される背景
- 採用ROIの基本式と考え方
- データドリブンで可視化する具体的手法
- ROIを高めるための施策と改善ポイント
- 経営層に伝わるROIレポートの作り方
- 成功事例と失敗回避のポイント
を徹底解説します。
「採用費用を正しく評価したい」「経営層に納得感のあるROIを提示したい」「データで採用KPIを改善したい」と考える人事・経営企画担当者にとって、本記事は実務で活かせる具体的なヒントになるはずです。
第1章:なぜ採用ROIが注目されているのか
これまで多くの企業では「採用活動は必要コスト」として扱われ、費用対効果の検証は十分に行われてきませんでした。しかし近年、採用ROI(Return on Investment)が注目されるようになっています。その背景には、採用市場の変化と企業経営における人材の位置づけの変化があります。
1. 採用コストの増加
求人広告の出稿費用や人材紹介会社への成功報酬は年々高騰しています。さらに、オンライン説明会やSNS広告など採用チャネルの多様化により、コスト構造は複雑化しています。
- 求人媒体費
- 人材紹介料(採用年収の30〜35%が一般的)
- 採用イベント・合同説明会の運営費
- 採用担当者や面接官の工数
これらを合計すると、新卒1人あたり数十万円、中途では100万円を超えることもあります。採用費用対効果を可視化しなければ、投資配分の最適化は不可能 です。
2. 経営層が人材投資に「成果」を求め始めている
これまで経営層は「採用人数の確保」を成果とみなしていました。しかし労働人口の減少と事業環境の不確実性が増すなか、単に人数を揃えるだけでは経営に貢献できません。
- 入社後すぐに離職してしまえばROIは著しく低下
- 採用した人材が成果を出さなければ投資は回収できない
- 「どれだけ費用をかけ、どんな成果を得たのか」を数値で示す必要性が高まっている
つまり経営層は「人材採用も他の投資と同様にROIで評価すべきだ」と考えるようになっているのです。
3. 定着率・パフォーマンスの重視
採用ROIは「採用人数 ÷ 投資コスト」ではありません。本質的には 入社後の定着率やパフォーマンスを含めた投資対効果 です。
- 内定承諾率が高くても、入社後に離職すればROIは低下
- 短期離職が多ければ、再び採用コストが発生
- 入社後に成果を出せる人材を採用することがROI最大化につながる
このように、採用の質 を定量的に測る視点が不可欠になっています。
4. データドリブン採用の浸透
採用DXの進展により、応募数や通過率、承諾率、定着率といった採用KPIをデータとして収集・可視化できる環境が整いました。
- 媒体別のCPA(Cost per Application:応募単価)
- 内定者1人あたりのCPO(Cost per Offer:内定単価)
- 採用フロー全体の歩留まり率
これらを数値化することで「どのチャネルに投資すべきか」「どの工程に改善余地があるか」が明確になります。
注目されるポイント
採用ROIが注目されるのは、
- 採用コストの増加
- 経営層の視点変化(成果重視)
- 定着率や入社後パフォーマンスの重視
- 採用DXによるデータ活用環境の整備
といった要因が背景にあります。今や採用は「人数確保」から「ROI改善」へと進化しており、データドリブンで費用対効果を可視化することが、採用担当者の必須スキル となっています。
第2章:採用ROIの基本式と考え方
採用ROIを正しく理解し、数値で示すためには「どのように計算するか」を明確にする必要があります。ROIは本来、投資に対するリターンを示す指標ですが、採用における「リターン」は単に採用人数だけではありません。採用の質や定着率、さらには入社後のパフォーマンスまで含めて考えること が重要です。ここでは採用ROIの基本式と考え方を整理します。
1. 採用ROIの基本式
一般的なROIの式は次のように表されます。
ROI(%)=(成果 ÷ 投資コスト) × 100
採用活動における「成果」と「コスト」を定義すると、採用ROIは以下のように計算できます。
成果(リターン)
・採用人数
・採用後の定着率
・入社後のパフォーマンス(生産性、売上貢献度)
・内定承諾率の改善
投資コスト
・求人広告費
・人材紹介会社への成功報酬
・説明会・イベント費用
・採用担当者・面接官の工数(人件費換算)
・採用管理システム(ATS)や関連ツールの費用
成果を「採用数」に限定せず、「質」や「定着」まで含めることが、採用ROIを正しく評価するポイントです。
2. 採用における主要KPIとROIの関係
採用ROIを考える上では、いくつかの採用KPIを分解して把握する必要があります。
- CPA(Cost per Application:応募単価)
採用チャネルごとに応募1件あたりにかかった費用。 - CPO(Cost per Offer:内定単価)
内定1件あたりにかかった総コスト。 - 内定承諾率
内定者のうち承諾した割合。低ければROIも低下。 - 定着率
入社後6か月・1年・3年での在籍率。短期離職が多いとROIは悪化。
これらのKPIを組み合わせることで、採用ROIを多面的に評価できます。
3. 定性的な効果も考慮する
採用ROIは数値で示すことが基本ですが、定性的な効果も無視できません。
- ブランド価値の向上(採用広報による企業イメージ改善)
- 社員エンゲージメント(リファラル採用の推進による社内活性化)
- 将来の母集団形成(SNS発信やタレントプール運営)
これらは直接的な数値化が難しいものの、長期的なROIに大きく寄与します。
4. ROIの算出例
例えば、ある企業が以下のコストで10名を採用したとします。
- 広告費:300万円
- 人材紹介料:200万円
- 説明会運営費:50万円
- 採用担当工数:50万円
=総コスト:600万円
成果として「10名採用」「1年後定着率80%」「承諾率70%」を考慮した場合、採用ROIは以下のように算出できます。
- 10名 × 定着率80%=8名が定着
- 600万円 ÷ 8名=1人あたり75万円のコスト
- 業績貢献度(仮に1人あたり年間500万円の売上貢献)を考慮するとROIは大幅にプラス
このように数値で説明すれば、経営層に「採用は投資であり、リターンを生んでいる」ことを納得させやすくなります。
考え方のポイント
採用ROIの考え方は、単なる「コスト削減」ではなく、
- 成果=人数+承諾率+定着率+パフォーマンス
- コスト=広告費+紹介料+工数+ツール費用
- KPI=CPA、CPO、内定承諾率、定着率
といった指標を組み合わせて 投資対効果を正しく可視化すること にあります。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ
- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる
- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー
第3章:データドリブンで採用ROIを可視化する方法
採用ROIを経営層に納得感を持って説明するためには、「感覚的な報告」から脱却し、データに基づく可視化=データドリブン採用 に取り組む必要があります。ここでは、ROIを数値で見える化するための具体的なステップと方法を紹介します。
1. 採用KPIを分解して追跡する
採用ROIは単なる「採用人数 ÷ コスト」ではありません。採用プロセスを細かく分解し、それぞれのKPIをデータとして管理することで、ボトルネックが明確になります。
追跡すべき主なKPI:
- 応募数:媒体ごと・チャネルごとの応募者数
- 通過率:書類・一次面接・最終面接ごとの歩留まり
- 内定承諾率:内定を承諾した割合
- 定着率:入社後6か月、1年での在籍率
- CPA(応募単価):応募1件あたりのコスト
- CPO(内定単価):内定1件あたりのコスト
これらを時系列で追跡すれば、改善すべき施策が数字で見えてきます。
2. 採用チャネルごとの費用対効果を比較
求人媒体、エージェント、リファラル、ダイレクトスカウト、SNSなど、採用チャネルごとにROIは大きく異なります。
例:
- A媒体:応募数は多いが、内定承諾率が低く定着率も低い
- Bエージェント:応募数は少ないが、承諾率と定着率が高くROIが優れている
- リファラル:CPAが低く、定着率が高いためROIが非常に高い
この比較を行うことで、「費用対効果の高いチャネルに投資を集中する」 という戦略的判断が可能になります。
3. 工数削減効果もROIに含める
採用ROIは広告費や紹介料だけでなく、人事担当者や面接官の工数コスト も考慮すべきです。採用DXを導入し、
- 面接日程調整の自動化
- FAQ対応のチャットボット化
- 内定者フォローの一斉配信
などを実現すれば、工数削減によってROIが向上します。単純に「外部コスト」だけを見るのではなく、社内工数削減の効果もROIに換算する ことが重要です。
4. 入社後パフォーマンスとの連動
短期離職やミスマッチ採用が増えると、採用ROIは大きく低下します。そのため、採用ROIは「入社数」だけでなく、定着率や入社後の業績貢献度 と連動させることが求められます。
例:
- 内定承諾率が高くても、半年以内の離職が多い場合 → ROIは低い
- 採用数は少なくても、定着率90%以上で高パフォーマンスを発揮 → ROIは高い
この視点を取り入れることで、採用ROIは「数」ではなく「質」を反映した指標に進化します。
5. ダッシュボード化で経営層に提示
エクセルやスプレッドシートでの集計に留めるのではなく、BIツールやATSのダッシュボード機能 を使えば、リアルタイムにROIを可視化できます。
- 媒体別のCPA、CPOをグラフ化
- 内定承諾率や定着率を月次で比較
- 投資配分のシミュレーション(広告費を削減した場合の効果など)
経営層にとって「一目で理解できるビジュアル化」がROI説明の説得力を高めます。
可視化のポイント
採用ROIを可視化するには、
- 採用KPIを分解してデータで追跡
- チャネル別に費用対効果を比較
- 工数削減効果もROIに算入
- 入社後の定着率・パフォーマンスと連動
- ダッシュボードで経営層に提示
というプロセスが必要です。データドリブン採用を実践することで、採用は「感覚的な活動」から「経営に説明できる投資」へと進化します。
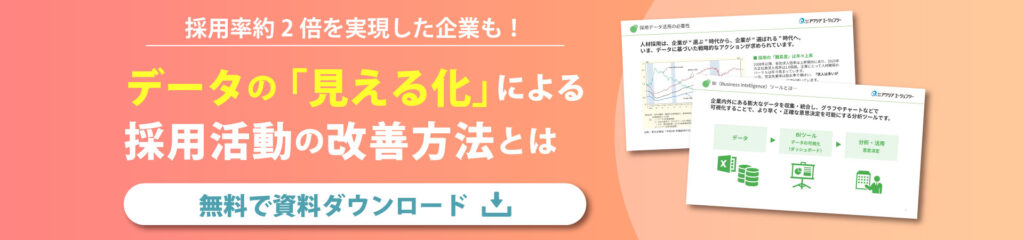
第4章:採用ROIを高めるための具体的施策
採用ROIを可視化できても、実際に数値を改善しなければ意味がありません。ROIを高めるには、コストを減らすことと成果を増やすこと の両面からアプローチする必要があります。ここでは、データドリブン採用の考え方を活かしながら、具体的に実践できる施策を整理します。
1. 媒体選定の最適化
従来は「応募数が多い媒体が良い」と判断されがちでしたが、今後は 応募の質と定着率まで含めて評価すること が不可欠です。
- 応募数は多いが承諾率が低い媒体 → ROIは低下
- 応募数は少ないが定着率が高い媒体 → ROIは向上
データを基にCPA(応募単価)やCPO(内定単価)を比較し、投資配分を最適化することが重要です。
2. リファラル採用・ダイレクトリクルーティングの活用
リファラル(社員紹介)やダイレクトリクルーティングは、広告費や紹介料を抑えつつ、企業文化にマッチした人材を採用しやすい手法です。
- リファラルは定着率が高いため長期的にROIが高い
- ダイレクトリクルーティングは広告依存を減らし、候補者母集団の質をコントロールできる
広告出稿に偏らず、こうしたチャネルを組み合わせることで、採用費用対効果は大きく改善します。
3. 採用DXによる工数削減
採用ROIには人事担当者の工数も含まれるため、採用DXで業務を効率化することがROI改善のカギ です。
- ATSで候補者進捗を一元管理 → 工数削減+属人化防止
- MAツールでメールやLINEを自動化 → 応募者対応スピード向上
- チャットボットでFAQ対応 → 人事の負担を削減
これにより、限られた人事リソースでも高品質なフォローが可能となり、内定承諾率や定着率の向上にもつながります。
4. 定着率を高めるオンボーディング強化
採用ROIを長期的に改善するには、入社後の定着率を高めること が欠かせません。短期離職が多いと再び採用コストが発生し、ROIは著しく低下します。
- 入社初日からのサポート体制を整える
- 内定者フォローを強化し、不安を解消する
- メンター制度や研修設計で早期戦力化を支援
定着率の改善は「採用ROIを高める最大のレバレッジ」といえます。
5. データを基にした投資配分の見直し
採用ROIを継続的に改善するには、データ分析を基に投資配分を定期的に見直すことが必要です。
- 半年ごとにチャネル別ROIを算出
- CPAやCPOの推移をトラッキング
- 内定承諾率・定着率を加味して「投資すべきチャネル/削減すべきチャネル」を判断
感覚ではなく数値で意思決定することで、ROIの最大化が実現します。
施策のポイント
採用ROIを高めるための施策は、
- 媒体選定の最適化(質重視)
- リファラル・ダイレクトリクルーティングの活用
- 採用DXによる工数削減
- 定着率を高めるオンボーディング強化
- データに基づく投資配分の見直し
に集約されます。これらを組み合わせることで、コストを抑えつつ成果を拡大し、採用費用対効果を継続的に改善できる のです。
第5章:経営層に伝わるROIレポートの作り方
採用ROIを高めるには、単に数値を算出するだけでは不十分です。最も重要なのは、経営層が納得し、次年度以降の採用投資に前向きな意思決定をしてもらえる形でレポートすること です。経営は人材を「戦略的資産」と見ていますが、その投資対効果を数字で説明できなければ、採用予算は簡単に削減対象となってしまいます。ここでは、経営層に響くROIレポートを作成するポイントを解説します。
1. シンプルで分かりやすい指標を用いる
経営層は採用現場の細かなデータすべてを見る必要はありません。重要なのは 誰でも直感的に理解できる数値 に整理することです。
代表的な指標:
- CPA(Cost per Application:応募単価)
- CPO(Cost per Offer:内定単価)
- 1人あたり採用コスト(総コスト ÷ 採用人数)
- 内定承諾率(承諾者数 ÷ 内定者数)
- 定着率(入社後の在籍率)
これらを組み合わせて「費用対効果が高い/低い」を明示するだけで、経営層は状況をすぐに把握できます。
2. グラフやダッシュボードで可視化する
数字だけを並べても説得力は弱まります。グラフ・チャート・ダッシュボード を活用して「一目でわかる形」にすることが重要です。
- チャネル別のCPA・CPOを棒グラフで比較
- 内定承諾率や定着率の推移を折れ線グラフで表示
- 投資配分とROIの関係を円グラフで表現
ビジュアル化により、経営層は「どこに投資し、どこを削減すべきか」を直感的に理解できます。
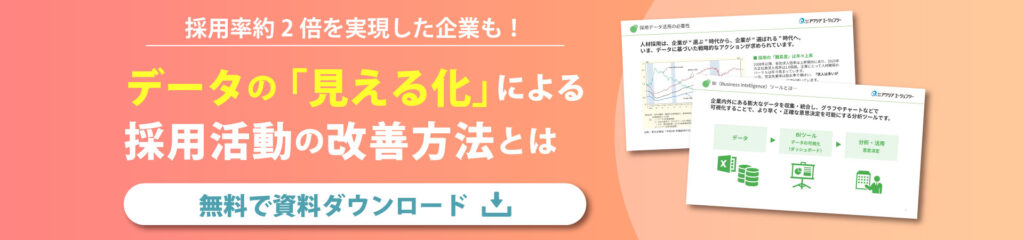
3. 成果と課題をストーリーで伝える
ROIレポートは「数値の羅列」ではなく、ストーリーを持った説明 が効果的です。
例:
- 前年度は広告費中心でCPAが高騰 → データ分析に基づきリファラル強化へ投資シフト
- 結果としてCPOが20%削減され、承諾率も改善 → ROIが向上
- ただし定着率に課題が残るため、来年度はオンボーディング強化を提案
このように「データ → アクション → 成果 → 次の改善点」の流れで説明すると、経営層は意思決定をしやすくなります。
4. ROIを事業成果と結びつける
採用ROIは「採用数」だけではなく、事業成長への貢献度 とリンクさせてこそ経営に響きます。
- 採用した人材が新規事業の立ち上げに貢献
- 営業職採用による売上拡大効果
- 技術職採用による生産性向上
採用KPIと事業KPIをつなげることで、経営層は「採用は単なるコストではなく投資である」と認識できます。
5. 改善アクションプランを提示する
ROIレポートは「現状報告」で終わらせてはいけません。必ず 改善に向けたアクションプラン を添えることが重要です。
- CPAをさらに下げるためにリファラル施策を拡大
- 承諾率を上げるために学生フォローDXを導入
- 定着率向上のためオンボーディングプログラムを改善
「課題 → 解決策 → 期待効果」を明示すれば、経営層は予算承認に前向きになります。
ROIレポートのポイント
経営層に伝わるROIレポートは、
- シンプルな指標で整理
- グラフで直感的に可視化
- ストーリーで成果と課題を説明
- 事業成果と結びつけて意義を示す
- 改善アクションを提案する
という流れで作成することが効果的です。これにより、採用ROIは「現場の報告」ではなく、経営に資する戦略指標 へと進化します。
第6章:成功事例と失敗回避のポイント
採用ROIを高める取り組みは、実際の企業で成果を上げている事例もあれば、期待通りに効果が出なかった失敗事例も存在します。両者を比較することで、何が成果を分けるのかを明確にできます。ここでは 成功企業に共通する要素 と 失敗に陥りやすい落とし穴 を紹介します。
成功事例
事例1:チャネル別ROI分析で広告費を最適化
大手小売業A社では、従来は複数の求人媒体に均等に投資していました。しかしデータドリブン採用の仕組みを導入し、チャネルごとにCPA(応募単価)とCPO(内定単価)を算出。
- A媒体:応募数は多いが承諾率が低くROIは悪化
- B媒体:応募数は少ないが定着率が高くROIは向上
成果:このデータを基に投資配分を変更した結果、採用コストを削減しながら定着率を改善。採用費用対効果の向上を実現しました。
事例2:ATS導入による工数削減と承諾率アップ
ITベンチャーB社では、採用管理がExcel中心で属人化しており、候補者対応が遅れて辞退が相次いでいました。ATS(採用管理システム)を導入し、候補者進捗を一元管理。自動リマインド機能で面接日程調整のスピードを改善しました。
成果:内定承諾率が上昇し、採用ROIも改善。工数削減効果により担当者の負担も軽減しました。
事例3:オンボーディング強化で定着率向上
製造業の中堅企業C社では、短期離職が多くROIが低下していました。そこで入社後のオンボーディングプログラムを刷新。オンライン研修、メンター制度、定期的なフォロー面談を導入しました。
成果:1年以内離職率が改善し、採用コストが大幅に減少。結果的に採用ROIが安定的に向上しました。
失敗事例と回避策
失敗1:ツール導入だけで満足
ATSやBIツールを導入したものの、運用ルールを整備せず現場に浸透しなかったケース。
回避策:導入時に「誰が・どう使うか」を明確化し、研修を徹底する。
失敗2:数値だけに偏り、質を見落とす
応募数やCPAだけを追いかけ、結果的に短期離職者が増加してROIが悪化。
回避策:承諾率や定着率など「質を測るKPI」を必ず含める。
失敗3:複雑すぎる指標設計
あまりに多くのKPIを設定し、現場が混乱して改善が進まなかったケース。
回避策:最初は「CPA」「CPO」「承諾率」「定着率」の4つ程度に絞る。
失敗4:短期成果を焦りすぎる
ROIを数か月単位で評価しようとして誤った判断を下す。採用ROIは入社後の成果や定着まで含めるため、短期評価では正しく測れません。
回避策:短期KPI(CPAや承諾率)と長期KPI(定着率)を組み合わせて評価する。
成功事例の共通点
成功事例に共通するのは、
- データを根拠に投資配分を見直した
- 採用DXを導入して工数を削減した
- 定着率改善に取り組んだ
一方、失敗例は「ツール導入で満足」「数だけを追う」「指標が複雑すぎる」「短期評価に偏る」といった特徴があります。
つまり、採用ROI改善のカギは シンプルに始め、質を含めたデータで改善を積み重ねること です。
第7章:まとめと実践チェックリスト
採用ROIを高めることは、単なる「コスト削減」ではありません。投資と成果を正しく数値化し、経営に説明できる形に整えることこそが本質です。採用市場が厳しさを増す今、人事は「人数を確保する担当者」から「投資効果を最大化する戦略パートナー」へと役割を変えることが求められています。
記事の要点整理
- なぜ注目されるのか:採用コストの増加、経営層のROI志向、定着率・パフォーマンスの重視、採用DXの普及。
- 基本式と考え方:ROI=成果 ÷ コスト。成果は採用数だけでなく、承諾率・定着率・入社後パフォーマンスまで含める。
- 可視化の方法:CPA、CPO、内定承諾率、定着率といった採用KPIをデータドリブンで管理し、ダッシュボードで可視化。
- 具体的施策:媒体選定の最適化、リファラル・ダイレクト活用、採用DXによる工数削減、オンボーディング強化、投資配分の見直し。
- 経営層へのレポート:シンプルな指標、グラフ化、ストーリー性、事業成果とのリンク、改善アクションの提示。
- 成功と失敗の分岐点:成功企業はデータを基にROI改善を継続、失敗企業はツール導入で満足・数だけ追求・短期評価に偏る。
実践チェックリスト
✅ 採用ROIを算出して経営層に説明できる仕組みを持っているか?
✅ 採用KPI(CPA、CPO、承諾率、定着率)を定期的に追跡しているか?
✅ 採用チャネル別に費用対効果を比較・評価しているか?
✅ 採用DXを導入し、工数削減をROIに反映できているか?
✅ 内定者フォローやオンボーディングで定着率改善に取り組んでいるか?
✅ ROIを事業成果(売上・生産性向上)と結びつけて説明しているか?
✅ 改善アクションを毎年レポートに盛り込み、継続的に改善しているか?
まとめ
採用ROIを高める取り組みは、人事部門の「感覚的な活動」を「データに基づいた投資判断」へと変えます。データドリブン採用を実践し、CPAやCPO、内定承諾率、定着率といった指標を継続的に改善することで、採用活動は経営に直結する戦略領域となります。
まずは小さな一歩として、チャネル別のCPA算出や内定承諾率の可視化 から始めましょう。その積み重ねが、経営層に納得感を与え、安定した採用予算の確保や組織成長につながっていきます。
人事DXのお悩みはアクシアエージェンシーへ
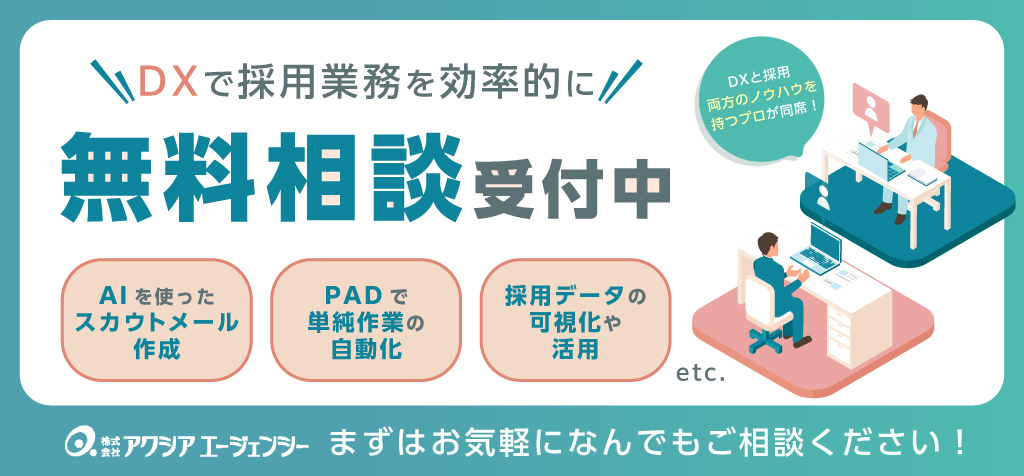
採用に関する総合コンサルティングを行っているアクシアエージェンシーでは、採用業務に関するDX化のお手伝いをしております。業務効率化だけではなく、母集団形成や採用コストの削減など、あらゆる観点での支援が可能です。

・面接調整や進捗管理に、毎日追われている
・スカウトや選考対応が、担当者に依存して属人化している
・採用データはあるのに、改善につながっていない
このようなお悩みをお抱えの企業様はぜひ一度、お話しをお聞かせ下さい。状況を整理し、問題・課題を把握する段階からはもちろんのこと、導入後もより良い採用活動に向けた効果改善などのサポートも行います。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
.jpg)
企業のニーズや状況に合わせた
ツールのカスタマイズが可能
アクシアエージェンシーは、採用までのプロセスを一気通貫で支援。BIやATS、AI、RPA、API連携を活用し、企業ごとの課題に応じた運用設計も専任チームが柔軟に対応します。

データドリブンで
改善が“感覚”から“戦略”に変わる
属人的な採用活動を、KPIダッシュボードを活用してデータ起点の戦略型業務へ転換。リアルタイムで状況を可視化し、“なんとなく”の施策から脱却できます。

仕組みの“導入”だけで終わらない
伴走型パートナー
ツール導入で終わらせず、実務への落とし込みから運用定着までを伴走支援。業界や体制に応じて柔軟に設計し、“使われないDX”を防ぎます。
貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!

