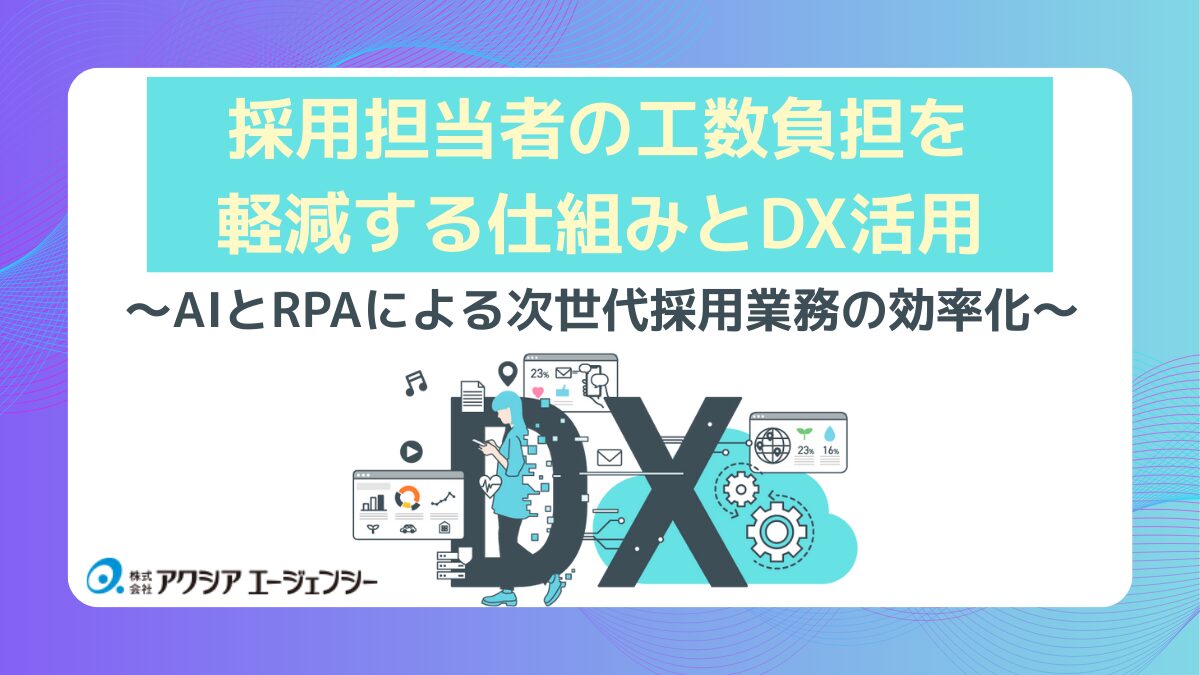採用を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化しました。働き方の多様化や価値観の変化、そして労働人口の減少といった要因から、従来の手法では思うように人材を確保できない時代になっています。そんな中で、求人票の作成や応募者対応、面接日程の調整、内定フォローなど、多くの業務を同時にこなす採用担当者の負担は増す一方です。
こうした背景から今、注目されているのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」による採用業務の効率化です。AIやRPAといったテクノロジーを活用することで、担当者の手を煩わせていた定型業務を削減し、戦略的な業務にリソースを集中できる環境を整える企業が増えてきました。
本記事では、採用担当者が日常的に抱える工数負担を整理したうえで、AIやRPAを活用した具体的なDX推進のポイントを解説します。採用現場をより効率的に、そして本質的に変革するためのヒントをお届けします。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ
- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる
- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー
1. はじめに:採用担当者を取り巻く現状
企業を取り巻く採用環境は、ここ数年で大きく変化しています。労働人口の減少、働き方の多様化、そして求職者の価値観の変化により、「良い人材を採用する」こと自体が容易ではなくなってきました。求人媒体に求人を出せば応募が集まる時代はすでに過去のものとなり、今や企業は採用活動において、より戦略的かつ効率的なアプローチを求められています。
こうした中で最前線に立つのが、採用担当者です。求人票の作成、媒体選定、応募者への対応、面接日程の調整、合否連絡、内定後のフォローなど、採用プロセスのほぼ全てを担うのは人事担当者であり、日々膨大なタスクを処理しています。特に中途採用とアルバイト採用の双方を担当する場合、業務範囲はさらに広がり、同時進行で数十名、場合によっては数百名規模の候補者対応を進めなければなりません。
その結果、本来もっと時間を割きたい「候補者体験の改善」「採用広報やブランディング」「経営層や現場との採用戦略設計」といった高付加価値業務が後回しになり、どうしても「目の前の事務作業」に追われる状況が続きがちです。採用担当者の工数負担は年々増すばかりで、燃え尽きやモチベーション低下を招くケースも少なくありません。
そこで近年注目されているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)による採用業務の効率化です。採用管理システム(ATS)を活用して情報を一元化するのはもちろん、AIによる求人原稿の自動生成やレジュメ解析、チャットボットによる応募者対応、さらにはRPAによる定型業務の自動処理など、テクノロジーを活用した取り組みが広がりを見せています。これらを導入することで、これまで人手に頼らざるを得なかった「単純で時間のかかる作業」を大幅に削減することが可能になります。
AIとRPAの活用は、単なる効率化のための手段ではありません。AIは候補者データから適性やスキルを分析し、最適な人材を見極めるサポートを行い、RPAは応募者情報の転記や日程調整など繰り返し発生する作業を自動化します。つまり、AIは「考える領域の支援」、RPAは「作業領域の代行」という役割分担を果たすのです。これにより採用担当者は、事務処理に費やしていた時間を戦略的な業務へと振り向けられるようになります。
本記事では、採用担当者が抱える典型的な業務負担を整理した上で、その負担を軽減する仕組みと、AI・RPAを含むDX活用の具体的なポイントについて詳しく解説します。テクノロジーを賢く使うことで「採用担当者が楽になる」だけでなく、「企業全体の採用力が高まる」ことを目指すヒントをお伝えします。
2. 工数がかかりやすい採用業務の整理
採用活動は「人と人をつなぐ仕事」であり、担当者の細やかな対応が求められます。しかし実際には、その多くが「定型的で繰り返し発生する事務作業」に時間を奪われているのが現状です。ここでは、採用担当者が特に多くの工数を費やしている代表的な業務を整理します。
① 求人票の作成・修正
- 職種ごとに異なる求人票を用意し、媒体ごとにフォーマットを調整する必要がある
- 同じ内容を複数媒体へ入力するため、二重作業・修正漏れが発生しやすい
- 更新や差し替えが多い職種では、担当者が常に作業に追われる
② 応募者対応・問い合わせ対応
- 「応募したが履歴書は届いているか?」「勤務時間を詳しく知りたい」といった問い合わせに1件ずつ対応
- 応募後の自動返信メールは出せても、その後の細やかな連絡は担当者が手作業で実施
- 対応が遅れると候補者体験が損なわれ、辞退につながるリスクも
③ 面接日程の調整
- 候補者の希望日程を確認し、面接官の予定とすり合わせて日程を確定
- 変更・キャンセルが発生すると再調整に追われ、同じやり取りを何度も繰り返す
- 特に複数拠点や複数面接官が関わる場合、膨大な調整コストがかかる
④ 選考進捗の管理
- 応募から内定までの進捗をExcelやスプレッドシートで手動管理している企業も多い
- 合否連絡のステータス更新が遅れると、情報共有にタイムラグが発生
- 担当者が「情報の番人」となり、作業が属人化してしまう
⑤ 内定者フォロー・入社準備
- 内定通知、承諾書の回収、入社書類のやり取りなどをメールや郵送で実施
- 質問対応や不安解消など「人ならではのケア」が求められる一方で、書類処理に時間が取られる
- 特にアルバイト採用では大量の書類や契約処理が一度に発生することも
⑥ 媒体管理・効果測定
- 複数媒体に求人を掲載する場合、効果測定や応募データの収集に工数がかかる
- どの媒体からどれだけ応募があったかを集計するだけでも手間がかかり、分析や改善に時間を回せない
ポイント
こうして整理すると、採用担当者の工数が集中するのは「人の判断が必要な場面」ではなく、入力・調整・連絡・更新といった繰り返しの事務作業に偏っていることがわかります。つまり、ここにこそDX、特にAIやRPAを導入する余地があります。
3. 工数負担を軽減する仕組みづくり
採用担当者の業務は「人と組織をつなぐ重要な役割」である一方で、その多くが細分化され、日々大量のタスクに追われています。求人票作成や媒体への入力、候補者とのメール連絡、面接日程の調整、進捗管理など、どれも必要不可欠な業務ですが、こうした作業が積み重なることで担当者の時間を大幅に圧迫しています。結果として、「採用戦略を練る」「候補者体験を改善する」といった高付加価値の業務にリソースを割けないという悪循環に陥りがちです。
この状況を打破するためには、単に「がんばって効率的に仕事を回す」のではなく、仕組みそのものを見直すことが必要です。ここで言う仕組みとは、標準化・自動化・見える化・役割分担の4つを柱とする考え方です。それぞれを整備することで、担当者の負荷を根本的に軽減し、採用業務全体を持続可能な形に変えていくことができます。以下では、その具体的な内容を詳しく解説します。
① 標準化 ― 誰でも同じ品質で対応できる仕組み
採用業務は属人化しやすく、「人によってやり方が異なる」「担当が変わると対応の質にバラつきが出る」といった課題がつきまといます。そこで最初に取り組むべきは、業務の標準化です。
- 求人票テンプレート化
職種ごとに基本的な求人票の雛形を用意し、どの媒体に出しても必要な情報が揃う状態をつくることで、入力や修正の手間を減らせます。さらに、統一したフォーマットを使うことで情報の抜け漏れが防止され、応募者に対する説明責任も果たしやすくなります。 - 面接評価シートの共通化
面接官ごとに評価基準が異なると「なぜ落ちたのか/なぜ採用したのか」が曖昧になり、組織としての一貫性が失われます。評価項目や観点を標準化したシートを用いることで、候補者に対する評価がより公平かつ客観的になり、合否判断の透明性も高まります。 - 定型文の整備
応募受付メールや日程調整の案内など、繰り返し使う文面はテンプレート化しておくことで、返信のスピードと品質を両立できます。候補者に安心感を与える迅速な対応は、採用成功率にも直結します。
このように標準化を徹底することは、担当者の作業時間を削減するだけでなく、候補者に対して「一貫性のある良い体験」を提供することにもつながります。
② 自動化 ― 繰り返し作業をシステムに任せる
標準化で業務の土台を整えたら、次のステップは「自動化」です。自動化は「人の判断を必要としない定型業務を、システムやツールに任せる」取り組みです。
- 自動返信メール
応募があった瞬間に「応募を受け付けました」というメールを自動送信する仕組みを整えるだけで、応募者の不安を和らげ、担当者の返信負担を大幅に減らせます。 - 日程調整ツール
面接官と候補者のカレンダーを照合し、候補者に候補日を自動で提示するツールを使えば、従来のような「この日はどうですか?」といったメールの往復が不要になります。日程調整は採用業務の中でも特に負担が大きい領域なので、自動化による効果は絶大です。 - ワークフローの自動処理
合否判定が入力されたら自動で通知を送る、内定が決まったら必要書類を自動配布するといった仕組みを作ることで、進捗管理や連絡業務のムダを省けます。
この段階ではまだAIやRPAを導入しなくても、既存のATSやクラウドツールだけで十分に実現可能です。
③ 見える化 ― 情報を共有し、属人化を防ぐ
採用担当者の大きな負担の一つが、「情報のハブ」として全てを抱え込んでしまうことです。選考の進捗や候補者情報が担当者の手元にしかなく、現場や経営層が知りたいときにすぐアクセスできない。この状況を解決するのが「見える化」です。
- 採用管理システム(ATS)の導入
応募から内定までの一連の情報を一元管理することで、誰でも必要な時に最新情報にアクセスできます。担当者が「情報を取り次ぐ」負担を大幅に減らせます。 - ダッシュボードでの可視化
応募数や進捗状況、選考通過率などをグラフ化して共有することで、課題やボトルネックを直感的に把握できます。経営層や現場責任者もリアルタイムで状況を把握できるため、迅速な意思決定が可能になります。 - 媒体効果の分析
どの媒体からどれだけ応募があり、採用につながったかを見える化することで、コスト対効果を数値で示せます。これにより、次の採用計画をより合理的に立案できるようになります。
④ 役割分担 ― コア業務とノンコア業務を分ける
採用担当者はどうしても「全部自分でやらなければ」と考えがちですが、業務を分解してみると、必ずしも担当者自身が行う必要のないものも多くあります。そこで重要なのが、役割分担です。
- 事務作業の外部化・自動化
データ入力やメール送信といったルーティン作業はRPAやアウトソースに任せることで、担当者は「人の判断が必要な業務」に集中できます。 - 担当者の時間を戦略的業務へシフト
採用計画の立案、候補者体験設計、面接官のトレーニングなど、人事ならではの付加価値業務に時間を充てることが可能になります。
このように役割を明確に分けることで、採用担当者は「作業者」から「戦略推進者」へと役割をシフトすることができます。
ポイント
工数負担を軽減する仕組みづくりは、必ずしも大規模なDX投資から始める必要はありません。テンプレート整備や定型文の活用など、今日から取り組める改善だけでも、作業工数は確実に削減できます。そのうえで、自動化ツールやAI・RPAを導入すれば、さらなる効率化と採用力強化が可能になります。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ
- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる
- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー
4. AI活用の具体的ポイント
AIは「人の判断を支援し、作業の質を高める」役割を果たします。従来は担当者が経験や勘に頼っていた領域も、AIを取り入れることで効率化と精度向上を同時に実現できます。ここでは採用現場で特に効果が期待できる活用ポイントを解説します。
① 求人票作成・原稿改善の自動化
求人票や募集記事の作成は、意外に時間がかかる作業です。媒体によってフォーマットが異なり、言葉選び一つで応募数や応募者層が変わるため、担当者の悩みの種でもあります。
AIを活用することで、以下のような効率化が可能です:
- 職種情報や要件を入力すると、AIが複数の原稿パターンを自動生成
- 語調や表現を応募者層に合わせて調整(例:学生向け・経験者向け)
- 過去データと比較して「より応募効果が出やすい表現」を提案
これにより、担当者はゼロから原稿を作る負担から解放され、短時間で質の高い求人票を完成させることができます。
② 候補者マッチングとスクリーニング
応募者が増えれば増えるほど、履歴書や職務経歴書の確認作業は大きな負担となります。AIを使えば、応募者のスキルや経験を自動で解析し、募集要件とのマッチ度を算出できます。
- スキルキーワードの抽出と自動判定
- 過去に活躍した社員のプロフィールと照合し、類似度を算出
- 応募者を「高マッチ」「中マッチ」「低マッチ」に分類
これにより、採用担当者は「応募者全員を確認する」必要がなくなり、優先度の高い候補者から効率的に対応できます。
③ 面接質問の自動提案
面接官ごとに質問内容がバラバラだと、候補者の評価基準に差が出てしまいます。AIは候補者のプロフィールや職種要件をもとに、面接で聞くべき質問リストを自動で提案できます。
- 経験やスキルに応じた深掘り質問
- 応募動機やキャリア志向を引き出す質問例
- コミュニケーション能力を測る質問例
面接官が準備にかける時間を減らせるだけでなく、候補者体験の一貫性も向上します。
④ チャットボットによる応募者対応
応募者から寄せられる「よくある質問」はAIチャットボットに任せるのが効果的です。
- 「勤務地はどこですか?」
- 「シフトはどのように決まりますか?」
- 「交通費の上限はいくらですか?」
こうした問い合わせに24時間自動応答することで、応募者の不安をすぐに解消できます。担当者は、個別対応が必要なケースに集中でき、候補者体験も向上します。
⑤ 採用データ分析と改善提案
AIは単に作業を効率化するだけでなく、採用活動全体を「データドリブン」に進化させます。
- 媒体ごとの応募数・通過率・採用単価を自動分析
- 「どの職種はSNS経由が効果的か」といった傾向を発見
- 「面接辞退が多いタイミング」など課題を提示
担当者は感覚や経験だけでなく、データに基づいた根拠ある改善を行えるようになります。
ポイント
AIは人の仕事を奪うものではなく、人の判断やコミュニケーションを補完し、質を高める存在です。採用担当者がAIを上手に活用することで、事務作業に追われる時間を削減し、より「人らしい」業務――候補者との関係づくりや組織の未来を見据えた採用戦略――に注力できるようになります。
5. RPA活用の具体的ポイント
RPA(Robotic Process Automation)は、人がPC上で行っているルーティン作業をソフトウェアロボットが代わりに実行する仕組みです。採用業務では、繰り返し発生する定型作業が多いため、RPAとの相性は抜群です。ここでは特に効果を発揮する活用領域を紹介します。
① 応募データ入力の自動化
採用担当者の負担の一つが、応募者情報を複数システムに転記する作業です。
- 求人媒体や応募フォームに届いた情報をATS(採用管理システム)へ自動登録
- 氏名・連絡先・希望条件などの情報をミスなく入力
- 同じ作業を繰り返す必要がなくなり、データ精度も向上
これにより「入力ミスによる連絡不備」や「二重管理による混乱」を防ぎます。
② 面接日程調整の自動処理
面接日程調整は担当者が最も工数を割く業務の一つです。RPAを使えば以下が可能です。
- 候補者からの希望日を取得し、面接官のカレンダーと自動照合
- 空き時間を候補者に自動提示し、確定後は面接官へ自動通知
- 変更やキャンセルが発生した場合も自動で再調整
これにより、従来「メールの往復」に数日かかっていた調整を、数分で完結させられます。
③ 選考ステータスの自動更新
採用活動では常に候補者の進捗を管理しなければなりません。RPAを導入すると:
- 面接が終了したら自動でシステム上のステータスを更新
- 合否入力に応じて、候補者や面接官へ自動で通知
- 担当者が都度手作業で進捗を追記する必要がなくなる
この仕組みが整えば、常に最新の進捗を関係者全員が確認できる状態になり、情報共有の手間も減ります。
④ 内定・入社手続きの効率化
内定承諾後には多くの事務処理が発生します。
- 内定通知メールや承諾書の送付を自動化
- 入社に必要な書類の回収・確認フローを自動処理
- アルバイト採用における大量の契約処理も一括対応
これにより、担当者は「入社前のフォロー」や「不安解消」といった人ならではの対応に集中できます。
⑤ 媒体効果測定・レポート作成
求人媒体が複数にわたる場合、その効果測定やレポート作成は非常に手間がかかります。RPAを活用すれば:
- 各媒体の管理画面から応募数や費用データを自動で収集
- 集計結果をExcelやBIツールに自動出力
- 月次・週次レポートを自動生成
こうした仕組みを作ることで、分析にかける時間を大幅に削減し、改善策の立案に集中できます。
ポイント
RPAは「人が判断しなくても良い作業」を代行するのが得意です。
- AI → 判断や分析をサポート
- RPA → 繰り返し作業を代行
この両者をうまく組み合わせることで、採用担当者は「考える」「人と向き合う」といった本来の役割に専念できるようになります。
6. 導入・運用の成功ポイント
AIやRPAを採用業務に導入すれば、工数削減や効率化が実現できることは間違いありません。しかし実際には、「システムを導入したものの使われなくなった」「現場がついていけず結局手作業に戻った」といったケースも少なくありません。ここでは、導入から定着までを成功させるためのポイントを整理します。
① 小さく始めて、スモールサクセスを積み重ねる
いきなり大規模にDXを進めると、現場が混乱したり、費用対効果が見えにくくなります。
- まずは「求人票作成」「自動返信メール」など一部の業務からスタート
- 成果が数字で見えたら徐々に対象領域を拡大
- 小さな成功体験を積み重ねることで、現場の理解と協力が得やすくなる
② 「使いやすさ」を最優先に選定する
AIやRPAの精度や機能は重要ですが、現場にとって「難しいツール」では定着しません。
- UIが直感的であるか
- PCスキルが高くない人でも使えるか
- モバイル対応やクラウド連携があるか
特に面接官や現場スタッフも利用する場合、「誰でもすぐ使える」ことが導入成功の条件となります。
③ 業務フローに合わせたカスタマイズ
システムに業務を無理やり合わせるのではなく、現場の実態に寄り添ったカスタマイズが重要です。
- 採用フローを事前に棚卸しし、どこを自動化すべきか明確にする
- 無駄な手順は整理し、効率化を前提にしたフローへ再設計
- 「現場の声」を反映させることで抵抗感を軽減
④ データに基づく改善を繰り返す
AIやRPAは導入して終わりではなく、使うほどにデータが蓄積され、改善余地が見えてきます。
- 「どの工程に最も時間がかかっているか」を定期的に分析
- 媒体効果や候補者動向を可視化し、採用戦略に反映
- システム利用ログをチェックし、使われていない機能を改善または廃止
改善を繰り返すことで、採用DXは「一過性の施策」ではなく、持続可能な取り組みへと進化します。
⑤ 人の役割を明確化する
AIやRPAの導入に対して「人の仕事がなくなるのでは」という懸念が出ることがあります。これに対しては、あらかじめ役割分担を明確にしておくことが大切です。
- AI・RPAに任せること:データ入力、日程調整、定型メール、レポート作成
- 人が担うこと:候補者との面接、カルチャーフィットの判断、採用戦略の立案
「人ならではの価値」に時間を振り分けられることを組織全体に共有することで、不安は期待に変わります。
⑥ 継続的な教育・サポート体制
新しいシステムやツールは、導入後も定期的な教育やサポートが必要です。
- 操作研修やマニュアルの整備
- 活用事例の共有会
- サポート窓口の設置
これにより「導入したけれど活用されない」という事態を防ぎます。
ポイント
DXは目的ではなく、あくまで「採用担当者が戦略的業務に集中できる環境をつくる」ための手段です。小さく始め、使いやすさを重視し、データをもとに改善を繰り返す。この積み重ねが、採用力そのものを強化し、組織の成長へとつながります。
7. まとめ ― 採用担当者の役割の変化と未来像
採用業務はこれまで、人の力に大きく依存してきました。求人票を一つ作るにも、応募者と面接日程を調整するにも、担当者が細かく手を動かし、時間を費やしてきたのが現実です。しかし、AIやRPAをはじめとするDXの仕組みを導入することで、その姿は大きく変わろうとしています。
① 単純作業からの解放
自動返信メールやRPAによるデータ入力の自動化、AIによる原稿作成や候補者スクリーニング。これらの仕組みを組み合わせれば、これまで採用担当者が1日の大半を費やしていた「繰り返し作業」は大幅に削減できます。作業に追われる日々から解放されることは、採用担当者にとって大きな意味を持ちます。
② 「判断」と「人との関わり」へのシフト
AIが候補者データを分析し、RPAが進捗を自動更新してくれる時代だからこそ、採用担当者は「人にしかできない業務」に集中できます。
- 候補者とのコミュニケーションを通じてカルチャーフィットを見極める
- 採用ブランディングを企画し、企業の魅力を発信する
- 経営層や現場と連携し、未来を見据えた採用戦略を立案する
これは、採用担当者を「事務処理担当」から「組織の未来を形づくる戦略パートナー」へと変化させる大きな転換点です。
③ 採用の質とスピードの両立
従来は「数を確保する」か「質を追求する」か、どちらかに偏りがちでした。しかし、AIとRPAを活用することで、効率化によるスピードと、データ活用による精度向上を同時に実現できます。限られたリソースの中でも、より質の高い採用をより早く行えるようになるのです。
④ 採用担当者の未来像
AIとRPAが当たり前になった未来の採用担当者は、こう変わります。
- データに基づいた採用戦略を描く「アナリスト」
- 候補者や社員と深く関わる「コミュニケーター」
- 経営と共に組織の成長をリードする「パートナー」
つまり、DXは「採用担当者を不要にする」のではなく、よりクリエイティブで価値の高い仕事へと進化させるのです。
採用市場の競争は今後ますます激しくなります。その中で勝ち残るためには、担当者の頑張りや根性に頼るのではなく、テクノロジーを賢く活用することが不可欠です。AIとRPAを組み合わせたDXは、採用担当者の工数を削減するだけでなく、企業の採用力そのものを底上げし、組織の未来を切り開く原動力になります。
これからの採用担当者は、単なるオペレーターではなく、人と組織の未来をデザインするクリエイターへと進化していくでしょう。
人事DXのお悩みはアクシアエージェンシーへ
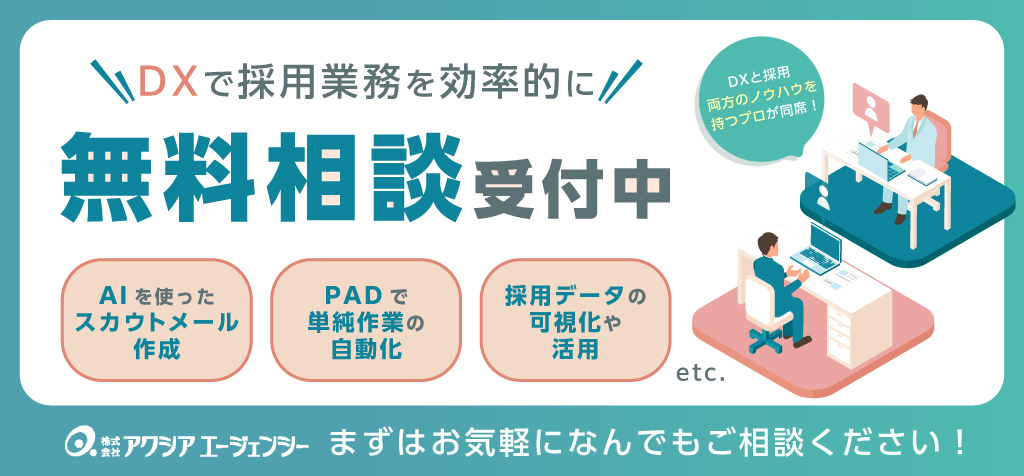
採用に関する総合コンサルティングを行っているアクシアエージェンシーでは、採用業務に関するDX化のお手伝いをしております。業務効率化だけではなく、母集団形成や採用コストの削減など、あらゆる観点での支援が可能です。

・面接調整や進捗管理に、毎日追われている
・スカウトや選考対応が、担当者に依存して属人化している
・採用データはあるのに、改善につながっていない
このようなお悩みをお抱えの企業様はぜひ一度、お話しをお聞かせ下さい。状況を整理し、問題・課題を把握する段階からはもちろんのこと、導入後もより良い採用活動に向けた効果改善などのサポートも行います。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
.jpg)
企業のニーズや状況に合わせた
ツールのカスタマイズが可能
アクシアエージェンシーは、採用までのプロセスを一気通貫で支援。BIやATS、AI、RPA、API連携を活用し、企業ごとの課題に応じた運用設計も専任チームが柔軟に対応します。

データドリブンで
改善が“感覚”から“戦略”に変わる
属人的な採用活動を、KPIダッシュボードを活用してデータ起点の戦略型業務へ転換。リアルタイムで状況を可視化し、“なんとなく”の施策から脱却できます。

仕組みの“導入”だけで終わらない
伴走型パートナー
ツール導入で終わらせず、実務への落とし込みから運用定着までを伴走支援。業界や体制に応じて柔軟に設計し、“使われないDX”を防ぎます。
貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!