採用活動において「内定を出したのに辞退された」という経験をしたことがある企業は少なくありません。求人倍率の上昇や、候補者の選択肢が増えた今の採用市場では、単に内定を出すだけでは入社にはつながらず、いかに候補者の志望度を高め、内定を承諾してもらえるかが成功の鍵を握ります。その中でも近年、注目されているのが「候補者体験(Candidate Experience)」です。これは、応募から内定、入社に至るまでの一連のプロセスで、候補者が感じる印象や体験のことを指します。
本記事では、この候補者体験をKPIとして数値化し、データに基づいて改善を行うことで、内定承諾率を高めるための方法を解説します。感覚に頼った採用活動から脱却し、データドリブンな採用戦略を実現したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ
- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる
- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー
はじめに
いま、日本企業の多くが直面している大きな課題のひとつが「内定承諾率の低下」です。求人倍率の上昇や人材の流動化により、内定を出しても辞退されるケースが増え、「せっかく投資した採用活動が成果につながらない」という状況が多発しています。特に新卒採用市場では、複数社から内定を得る学生が一般化し、企業同士の競争は激化。中途採用でも転職希望者は選択肢を広く持つため、「候補者体験(CandidateExperience)」の質が、入社意思決定の大きな分岐点になっています。
候補者体験とは
候補者体験とは、応募から内定承諾、さらには入社に至るまでの一連の採用プロセスにおいて、候補者が感じる印象や体験価値を指します。たとえば、応募後の連絡スピード、面接での対応品質、情報提供の一貫性、選考中の安心感などがこれに含まれます。これらの要素は、候補者が「この会社に入りたい」と思うか、それとも「他社を選ぼう」と判断するかを大きく左右します。つまり候補者体験の改善は、そのまま内定承諾率の向上=採用ROIの最大化につながるのです。
しかし、多くの企業は候補者体験を「感覚」や「担当者の経験値」に頼って評価しています。人事担当者は「丁寧にフォローしているはず」「面接の雰囲気は良かった」と考えていても、実際には候補者が不安を感じたり、対応スピードの遅れに失望していたりすることが珍しくありません。つまり「企業が思う候補者体験」と「候補者が実際に感じる候補者体験」には、大きなギャップが存在しているのです。このギャップを埋め、内定承諾率を高めるために必要なのが候補者体験をKPIで測る仕組みです。
候補者体験を数値化することのメリット
KPIとして候補者体験を数値化することによって、これまで見えなかった課題が浮き彫りになります。例えば、応募から初回連絡までにかかる時間、面接日程調整に必要なリードタイム、候補者アンケートによる面接満足度スコア、内定辞退理由のカテゴリ分布などです。これらをデータとして追跡することで、「どのプロセスに改善余地があるか」「どの施策が内定承諾率に寄与しているか」が明確になります。
さらに、採用DXの進展によって、候補者体験をデータとして収集・分析する環境は格段に整いつつあります。ATS(採用管理システム)やBIツールを用いれば、候補者ごとのレスポンス履歴や面接官評価を簡単に可視化でき、経営層にも分かりやすく報告できます。従来の「感覚的な採用活動」から、データドリブン採用へとシフトすることで、候補者体験は組織的に改善可能な領域へと変わりつつあるのです。
本記事では、候補者体験をKPIで測る重要性を整理し、データドリブンで改善するための実践的な手法を紹介します。特に「内定承諾率を高めたい」「内定辞退を防ぎたい」と考える採用担当者や人事責任者に向けて、候補者体験をどう数値化し、どう改善につなげるかを体系的に解説していきます。
第1章:候補者体験が内定承諾率を左右する理由
内定を出したにもかかわらず候補者が辞退する。多くの企業で繰り返されるこの問題の背後には、実は「候補者体験(CandidateExperience)」が深く関わっています。候補者が選考を通じて得る体験は、そのまま企業への信頼感や好意度に直結し、最終的な内定承諾率を左右します。ここでは、その理由を掘り下げていきます。
1.第一印象が志望度に直結する
候補者体験は応募直後から始まります。応募した後、企業からの返信が数日遅れると、候補者は「自分は重視されていないのではないか」と感じます。逆に、数時間以内に迅速かつ丁寧な返信が届けば、候補者は「この企業は対応が早い」「安心して任せられる」と感じ、志望度が上がります。
つまりレスポンスタイム(応募から初回連絡までの時間)は候補者体験を測る最初のKPIであり、ここでの印象が承諾率に大きな影響を与えるのです。
2.選考プロセスのスムーズさが信頼感を生む
面接日程の調整が煩雑で、何度も候補日をやり取りしなければならない場合、候補者はストレスを感じます。さらに、面接当日に予定変更が頻発すると、「この会社は組織として計画性がないのでは?」という不信感が芽生えます。
反対に、日程調整ツールや自動リマインドを活用してスムーズに面接が組める企業は、候補者から「効率的で信頼できる」と評価されます。こうした小さな積み重ねが、最終的に内定承諾率の差につながるのです。
3.面接体験が企業イメージを形成する
候補者にとって、面接官との接触は企業を知る最大の機会です。面接官が質問ばかりして候補者を圧迫したり、会社説明が曖昧だったりすると、候補者は「この会社に入社しても大切にされないのでは」と感じます。
一方で、面接官が候補者の話を丁寧に聞き、会社のビジョンやキャリア支援の具体的な取り組みを伝えることで、候補者は「この企業なら成長できる」「安心して働ける」と感じます。面接体験そのものがブランド体験であり、内定承諾率を左右する大きな要素なのです。
4.情報不足は不安を生み、辞退につながる
選考プロセスの中で「この会社はどんな環境なのか」「入社後のキャリアはどうなるのか」といった疑問に十分な回答が得られない場合、候補者は不安を感じます。この不安は、他社からの内定が出た瞬間に「安心できる方を選ぶ」という行動につながりやすいのです。
内定承諾率を高めるには、情報の透明性と一貫性が欠かせません。FAQ集、社員インタビュー動画、内定者ポータルなどを活用し、候補者の疑問を先回りして解消する仕組みを整えることで、候補者体験は大きく改善されます。
5.候補者は比較して意思決定している
候補者は一社だけでなく、複数の企業の選考を同時進行するのが一般的です。そのため「企業イメージ」や「選考体験」は必ず比較されます。
- 連絡が速いか遅いか
- 面接がフレンドリーか形式的か
- 入社後の情報が十分に提示されているか
こうした点を比較したうえで、候補者は「どちらの企業に入社するか」を決めています。つまり、候補者体験の質の差が最終的な承諾率の差に直結するのです。
ポイント
候補者体験は「採用活動の副次的な要素」ではなく、内定承諾率を高める最重要要因です。
- 応募直後のレスポンス
- 選考プロセスのスムーズさ
- 面接でのコミュニケーション
- 情報提供の充実度
- 他社との比較に勝てる体験設計
これらすべてが候補者の意思決定に影響を与えます。したがって、候補者体験をKPIとして可視化し、データに基づいて改善することが、内定辞退防止と承諾率向上の鍵になるのです。
第2章:候補者体験をKPIで測る重要性
候補者体験は、従来「良かった」「悪かった」といった感覚や、採用担当者の主観で語られることが多いものでした。しかし、感覚に頼ったままでは改善の余地が見えず、組織として戦略的に取り組むこともできません。ここで必要なのが候補者体験をKPIで測定する仕組みです。KPIとして数値化することで初めて、候補者体験は「再現性のある改善可能なプロセス」になります。
1.感覚的評価の限界
人事担当者が「自分たちはきちんと対応できている」と思っていても、候補者が同じように感じているとは限りません。たとえば、企業側は「面接は丁寧に行った」と考えていても、候補者にとっては「質問が一方的で不安が残った」と感じることがあります。
このように、候補者体験は企業と候補者の間で大きなギャップが生じやすい領域です。感覚的評価のままでは、そのギャップに気づくことができず、改善の機会を逃してしまうのです。
2.KPI化で改善ポイントが明確になる
候補者体験をKPIとして数値化すれば、「どのプロセスに課題があるのか」が一目で分かるようになります。代表的なKPIの例を挙げると:
- レスポンスタイム:応募から初回返信までにかかった時間
- 面接設定リードタイム:応募〜面接確定までの日数
- 候補者満足度スコア:面接後アンケートやNPSで計測
- 内定承諾率:内定者のうち承諾した割合
- 辞退理由のカテゴリ分析:不安、待遇、競合比較など
これらを定期的に測定することで、採用チームは「何を改善すべきか」を具体的に把握できるようになります。
3.データドリブン採用で承諾率が向上する
KPIを活用して候補者体験をデータドリブンに改善することは、直接的に内定承諾率の向上につながります。
例:
- レスポンスタイムが48時間だった企業が24時間以内に改善した結果、承諾率が15%上がった
- 面接後のアンケートを導入して候補者満足度を追跡した結果、面接官トレーニングを行い承諾率が20%改善した
このように、データに基づいた取り組みは「効果を数値で示せる」ため、採用チームのアクションに説得力を持たせます。
4.経営層への説明責任を果たせる
採用活動には広告費や紹介料など多額のコストがかかります。経営層からは「その投資がどれだけ成果を生んでいるのか」を説明する責任が求められます。
KPIを使って候補者体験を定量化すれば:
- 応募から承諾までのフローがどのように改善されたか
- 承諾率や定着率がどの程度向上したか
- 投資に対してROIがどう変化したか
を数値で示すことが可能になります。これは経営層にとって理解しやすく、採用DXへの投資を継続する根拠にもなります。
5.内定辞退防止のための早期発見ができる
候補者体験をKPIで追跡すれば、「辞退の予兆」を早期に発見できます。
- 面接満足度が低い候補者は辞退リスクが高い
- 返信が遅い候補者は不安を抱えている可能性がある
- 内定後のフォロー接触回数が少ない候補者は志望度が低下しやすい
これらをデータとして把握し、重点的にフォローすることで、内定辞退防止につながるのです。
候補者体験をKPIで測る意味
候補者体験をKPIで測ることには大きな意味があります。
- 感覚的評価から脱却し、客観的に改善点を把握できる
- データに基づいて内定承諾率を高められる
- 経営層に対して採用活動の費用対効果を説明できる
- 内定辞退を未然に防ぐアクションを起こせる
候補者体験は「測れないもの」ではありません。採用KPIとして可視化することで、承諾率を高め、採用の質を継続的に改善できる戦略的資産へと変えることができるのです。
第3章:データドリブンで候補者体験を可視化する方法
候補者体験の重要性を理解し、KPIで測る意義を把握したら、次に必要なのは「具体的にどうやって可視化するか」という実践のステップです。従来の採用活動は、面接官の感覚や人事担当者の経験則に依存してきましたが、それでは改善のサイクルを回すことができません。ここではデータドリブン採用の視点で、候補者体験を「見える化」するための方法を整理します。
1.ATSで候補者の進捗と接触履歴を一元管理
候補者体験を把握する最初の一歩は、データを分散させないことです。Excelやメールのやり取りに頼っていては、誰がいつ候補者と接触し、どんな対応をしたのかが不明瞭になり、体験の質を正確に評価できません。
ATS(採用管理システム)を導入すれば:
- 応募から内定までの進捗状況をリアルタイムで把握
- レスポンスタイムや面接設定リードタイムを自動で記録
- 候補者とのコミュニケーション履歴を一元管理
これにより「どの候補者に対応が遅れたか」「承諾率が下がった原因はどこにあるか」を具体的に把握できます。
2.定量データと定性データの組み合わせ
候補者体験を正しく可視化するには、数値データだけでなく候補者の声(定性データ)も活用することが不可欠です。
【定量データ(KPI)】
・応募〜初回連絡までの平均時間
・面接設定までのリードタイム
・内定承諾率、辞退率
・チャネル別の応募数と歩留まり率
【定性データ】
・面接後アンケートによる候補者満足度
・「この企業を選んだ理由/辞退した理由」の自由回答
・NPS(NetPromoterScore)を用いた推奨度調査
これらを組み合わせることで、「数値では良いが体験としては不十分」といった見落としを防げます。
3.ダッシュボードでリアルタイムに共有
データは収集するだけでは意味がありません。人事チーム内や経営層に分かりやすく共有し、改善の意思決定に活かすことが重要です。
BIツールやATSのダッシュボード機能を活用すれば:
- レスポンスタイムや承諾率をグラフで可視化
- 媒体別の候補者満足度や辞退率を比較
- 時系列で体験改善の効果を追跡
経営層に対しても「数字とビジュアル」で説明できるため、説得力が格段に高まります。
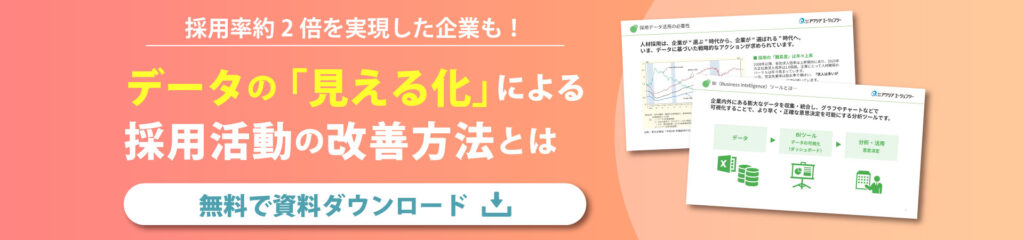
4.候補者ジャーニーマップを作成する
マーケティングにおける顧客体験設計と同様に、採用活動でも候補者ジャーニーマップを描くことで全体像を可視化できます。
応募→連絡→面接→内定→承諾→入社
この一連の流れの中で「候補者がどんな感情を持ち、どんな体験をしたか」を整理するのです。
例:
- 応募後に返信が遅い→不安を感じる
- 面接官が説明不足→企業理解が浅い
- 内定後のフォローが弱い→他社に流れる
このように体験を時系列で可視化すれば、改善すべきポイントが明確になります。
5.採用DXによる自動データ収集
最新の採用DXツールを活用すれば、候補者体験に関するデータを自動で収集できます。
- 日程調整ツールで面接リードタイムを自動記録
- チャットボットで問い合わせ対応ログを収集
- 内定者ポータルで閲覧履歴を追跡
これにより、候補者がどこで不安を感じ、どこで満足しているかをリアルタイムで把握できるのです。
候補者体験をデータドリブンで可視化するには
- ATSで進捗と接触履歴を一元管理
- 定量データと定性データを組み合わせて評価
- ダッシュボードでリアルタイム共有
- 候補者ジャーニーマップで体験を時系列に整理
- 採用DXでデータ収集を自動化
というステップが欠かせません。これにより、候補者体験は「曖昧な感覚」から「数値で改善できる戦略的資産」へと進化します。そして、その改善は内定承諾率の向上と内定辞退防止に直結するのです。
第4章:候補者体験を改善する具体的施策
候補者体験をKPIで測定し、データとして可視化できるようになったら、次に重要なのはどのように改善するかです。多くの企業は「候補者体験を向上させたい」と考えながらも、抽象的な議論にとどまり、実際の施策につながらないことが少なくありません。ここでは、内定承諾率を高め、内定辞退を防止するために取り組むべき改善策を具体的に紹介します。
1.スピード改善―迅速なレスポンスで不安を防ぐ
候補者体験を左右する最大の要素の一つが対応スピードです。応募から初回連絡までのレスポンスタイムが48時間を超えると、候補者の不安は一気に高まります。
改善施策:
- ATSとメール/LINE自動配信を連携し、応募後すぐに自動返信
- 面接日程は候補者がオンライン上で即時に選択できる仕組みを導入
- 自動リマインドで候補者の負担を軽減
これにより「この会社は自分を大切にしてくれる」という印象を与え、承諾率向上につながります。
2.一貫性ある情報提供―候補者の疑問を先回りして解消
候補者が辞退する大きな理由の一つは「情報不足による不安」です。仕事内容、評価制度、キャリアパスなどが十分に説明されないと、候補者は競合他社の方が安心できると感じてしまいます。
改善施策:
- 内定者ポータルを用意し、FAQ・制度説明・社員インタビューを集約
- 採用広報コンテンツを動画・記事で提供し、入社後のイメージを具体化
- 面接ごとに伝える情報を標準化し、担当者による説明のばらつきをなくす
情報を透明に提供することは、候補者満足度の向上と辞退防止に直結します。
3.面接体験の質を高める―面接官トレーニングの重要性
候補者にとって、面接官は企業そのものの顔です。面接で圧迫的な質問を受けたり、準備不足な対応をされた場合、どんなに条件が良くても候補者体験は悪化します。
改善施策:
- 面接官トレーニングを実施し、質問の仕方・説明の仕方を標準化
- 面接中は「候補者を評価する場」だけでなく「候補者に会社を伝える場」と位置づける
- 面接後アンケートを収集し、候補者満足度を数値化して改善
面接体験の改善は、内定承諾率を押し上げる最も即効性のある施策のひとつです。
4.パーソナライズ対応―候補者ごとの関心に寄り添う
全員に同じ内容のメールを一斉送信するだけでは、「機械的に扱われている」と候補者に感じさせてしまいます。
改善施策:
- スカウト文面に候補者の経歴や関心分野を反映
- 面接で聞かれた質問内容をフォローアップメールで回答
- 内定後には、配属予定部署の社員との面談をセッティング
このようにパーソナライズされた接触は、候補者に「自分は特別に見てもらえている」と感じさせ、承諾率の向上につながります。
5.内定後フォロー―志望度の維持が辞退防止のカギ
内定を出した瞬間がゴールではありません。むしろ、その後のフォローが弱ければ候補者の志望度は下がり、辞退につながります。
改善施策:
- 定期的なフォローメール・LINEで接点を維持
- 先輩社員やメンター制度を活用した座談会を実施
- 入社準備や制度説明をポータルで見える化し、不安を減らす
「内定を出してから入社まで」の期間こそが、候補者体験を大きく左右する重要フェーズです。
6.データ分析に基づく重点フォロー
採用DXを活用し、候補者体験に関するデータを定期的に分析することで「辞退リスクの高い候補者」を特定できます。
- メール開封率が低い候補者
- 面接満足度スコアが低い候補者
- イベント参加率が低下している候補者
これらに重点的なフォローを行うことで、効率的に承諾率を改善できます。
候補者体験を改善する具体策6つ
- スピード改善(レスポンスタイム短縮)
- 情報提供の一貫性(不安解消と透明性向上)
- 面接体験の質向上(面接官トレーニング)
- パーソナライズ対応(個別ニーズに寄り添う)
- 内定後フォロー(承諾率維持と辞退防止)
- データ分析による重点フォロー(効率的なリソース配分)
これらを組み合わせることで、候補者体験は飛躍的に向上し、内定承諾率アップと辞退防止を両立できる採用活動が実現します。
第5章:成功事例と失敗回避のポイント
候補者体験をKPIで測定し、データドリブンで改善する取り組みは、すでに多くの企業で実践されています。その中には承諾率の改善や辞退率の削減に成功した事例がある一方、ツール導入やアンケート施策が形骸化してしまった失敗事例も存在します。ここでは両方を紹介しながら、成功のポイントと失敗回避の秘訣を整理します。
成功事例
事例1:レスポンスタイム短縮で承諾率が改善
あるITベンチャー企業では、候補者からの応募に対する初回返信が平均48時間かかっていました。ATSを導入し、自動返信メールと日程調整ツールを組み合わせた結果、レスポンスタイムを24時間以内に短縮。さらに候補者アンケートで「対応が早く安心できた」という声が増え、面接実施率と内定承諾率が改善しました。
事例2:面接官トレーニングで候補者満足度を大幅向上
メーカー企業では「面接官によって対応の差が大きい」という候補者の不満が多く寄せられていました。そこで、全面接官にトレーニングを実施し、質問方法や説明の仕方を標準化。さらに面接後アンケートで満足度を数値化し、毎月フィードバックを行いました。その結果、候補者満足度スコアが上昇し、辞退率が改善しました。
事例3:内定後フォロー強化で辞退を半減
人材サービス業の企業では、内定後の辞退が大きな課題でした。そこで、内定者ポータルを導入し、入社準備の案内や社員インタビュー動画を公開。さらに、先輩社員とのオンライン懇親会を定期的に実施しました。その結果、内定後の不安が軽減され、辞退率が改善。候補者体験の改善が承諾率に直結した好例といえます。
失敗事例と回避ポイント
失敗1:ツール導入だけで満足してしまった
ATSやBIツールを導入したが、現場が使いこなせず、データが入力されないまま放置されてしまったケース。
回避策:導入時に「誰が・何を・どの頻度で入力するか」を明文化し、定着まで伴走する。
失敗2:アンケートを実施したが改善につながらない
候補者アンケートを取ったものの、結果を分析せず放置したため「やりっぱなし」になり、候補者の声を活かせなかったケース。
回避策:アンケート結果をKPIとしてダッシュボード化し、毎月の改善会議で必ず確認する。
失敗3:数値だけにとらわれ質を軽視
応募数や承諾率といった数値目標ばかり追いかけ、面接体験や情報提供の質を改善しなかったため、短期的に承諾率は上がったが定着率が下がったケース。
回避策:定性的な候補者の声も必ず取り入れ、「質と量のバランス」を重視する。
失敗4:短期間で結果を出そうとした
候補者体験改善は長期的に効果が出る取り組みなのに、数か月で成果を求めすぎて投資をやめてしまったケース。
回避策:短期KPI(レスポンス時間や満足度)と長期KPI(承諾率・定着率)を組み合わせ、段階的に改善を測定する。
成功と失敗を分けるポイント
- 成功企業は「小さく始めて、KPIを定着させ、改善を積み重ねる」
- 失敗企業は「導入しただけ」「測定しただけ」で終わってしまう
- 継続的にデータを収集・共有し、改善を習慣化できるかが分岐点
候補者体験は一度改善して終わりではなく、常に変化する市場や候補者ニーズに合わせて進化させる必要があります。そのためにはデータを基盤に改善サイクルを回し続ける仕組みが不可欠です。
「ツール導入=ゴール」ではない
候補者体験をKPIで測定し、データドリブンで改善すれば、承諾率や定着率を大きく引き上げることが可能です。成功事例から学ぶべきは、小さく始めて改善を継続する姿勢。失敗例から学ぶべきは、「ツール導入=ゴール」ではないという教訓です。
この視点を持つことで、候補者体験は単なる「良し悪し」ではなく、内定承諾率を高めるための戦略的レバーとして活用できるようになります。
第6章:まとめと実践チェックリスト
候補者体験は、これまで「感覚的に良し悪しを判断するもの」とされがちでした。しかし採用市場の競争が激化する今、それを主観に任せたままでは内定承諾率を高めることも、内定辞退を防止することも難しいのが現実です。本記事を通じて解説してきたように、候補者体験はKPIとして数値化し、データドリブンで改善サイクルを回すことで、組織的にコントロールできる領域へと進化します。
記事全体の要点整理
- 候補者体験が承諾率を左右する:レスポンスの速さ、面接の質、情報提供の一貫性が志望度を決定づける。
- KPIで測る意義:レスポンスタイム、面接リードタイム、満足度スコア、承諾率などを定量化することで、改善点が明確になる。
- データドリブン可視化:ATSやBIツールで進捗やアンケート結果をリアルタイムに共有し、経営層への説得力を高める。
- 具体的改善施策:スピード改善、情報提供の標準化、面接官トレーニング、パーソナライズ対応、内定後フォロー強化。
- 成功と失敗の分岐点:小さく始めて継続的に改善した企業は成果を上げ、ツール導入だけで終わった企業は効果を得られなかった。
実践チェックリスト
✅レスポンスタイム:応募から初回返信までの時間を計測しているか?
✅面接リードタイム:応募から面接日程確定までの日数を追跡しているか?
✅候補者満足度:面接後アンケートやNPSを実施しているか?
✅内定承諾率:定期的に算出し、部門別・チャネル別に比較しているか?
✅辞退理由の分析:辞退者アンケートを収集し、カテゴリ分けして改善に活かしているか?
✅経営層への報告:ダッシュボードやグラフで候補者体験KPIを可視化しているか?
✅改善アクション:KPIに基づいた具体的施策(面接官トレーニングやフォロー強化)を実行しているか?
✅長期的指標:承諾率だけでなく入社後の定着率まで測定しているか?
まとめ
候補者体験は「測れないもの」ではなく、採用KPIとして管理できる戦略指標です。
- 短期的にはレスポンスや面接満足度の改善で承諾率を押し上げる
- 中期的には内定後フォローや情報提供の一貫性で辞退を防止する
- 長期的には定着率や業績貢献度まで追跡し、採用ROIを最大化する
こうした取り組みを積み重ねることで、採用活動は「人数を確保するための業務」から「経営を支える投資活動」へと変わります。
まずは小さな一歩として、応募から初回返信までの時間を計測することや面接後アンケートを導入することから始めてみてください。その取り組みがやがてデータ基盤となり、候補者体験改善と承諾率向上の好循環を生み出します。
人事DXのお悩みはアクシアエージェンシーへ
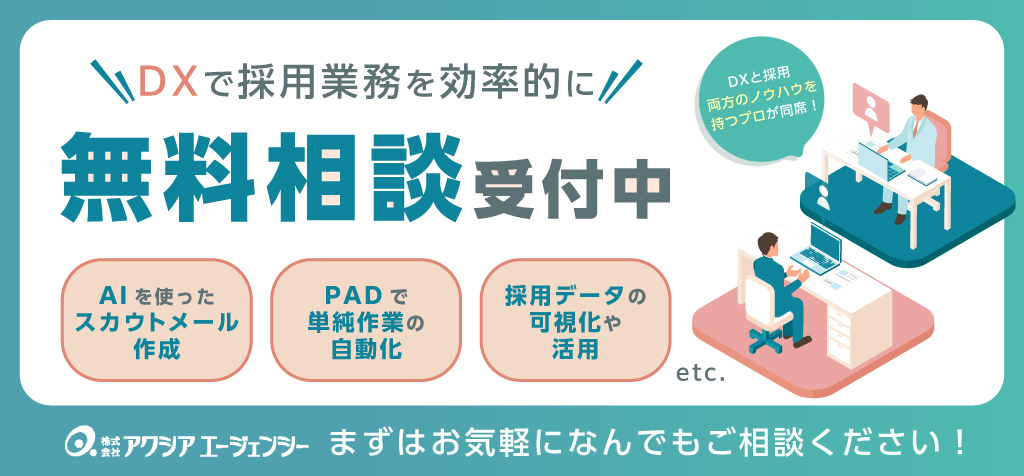
採用に関する総合コンサルティングを行っているアクシアエージェンシーでは、採用業務に関するDX化のお手伝いをしております。業務効率化だけではなく、母集団形成や採用コストの削減など、あらゆる観点での支援が可能です。

・面接調整や進捗管理に、毎日追われている
・スカウトや選考対応が、担当者に依存して属人化している
・採用データはあるのに、改善につながっていない
このようなお悩みをお抱えの企業様はぜひ一度、お話しをお聞かせ下さい。状況を整理し、問題・課題を把握する段階からはもちろんのこと、導入後もより良い採用活動に向けた効果改善などのサポートも行います。
アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴
.jpg)
企業のニーズや状況に合わせた
ツールのカスタマイズが可能
アクシアエージェンシーは、採用までのプロセスを一気通貫で支援。BIやATS、AI、RPA、API連携を活用し、企業ごとの課題に応じた運用設計も専任チームが柔軟に対応します。

データドリブンで
改善が“感覚”から“戦略”に変わる
属人的な採用活動を、KPIダッシュボードを活用してデータ起点の戦略型業務へ転換。リアルタイムで状況を可視化し、“なんとなく”の施策から脱却できます。

仕組みの“導入”だけで終わらない
伴走型パートナー
ツール導入で終わらせず、実務への落とし込みから運用定着までを伴走支援。業界や体制に応じて柔軟に設計し、“使われないDX”を防ぎます。
貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!

