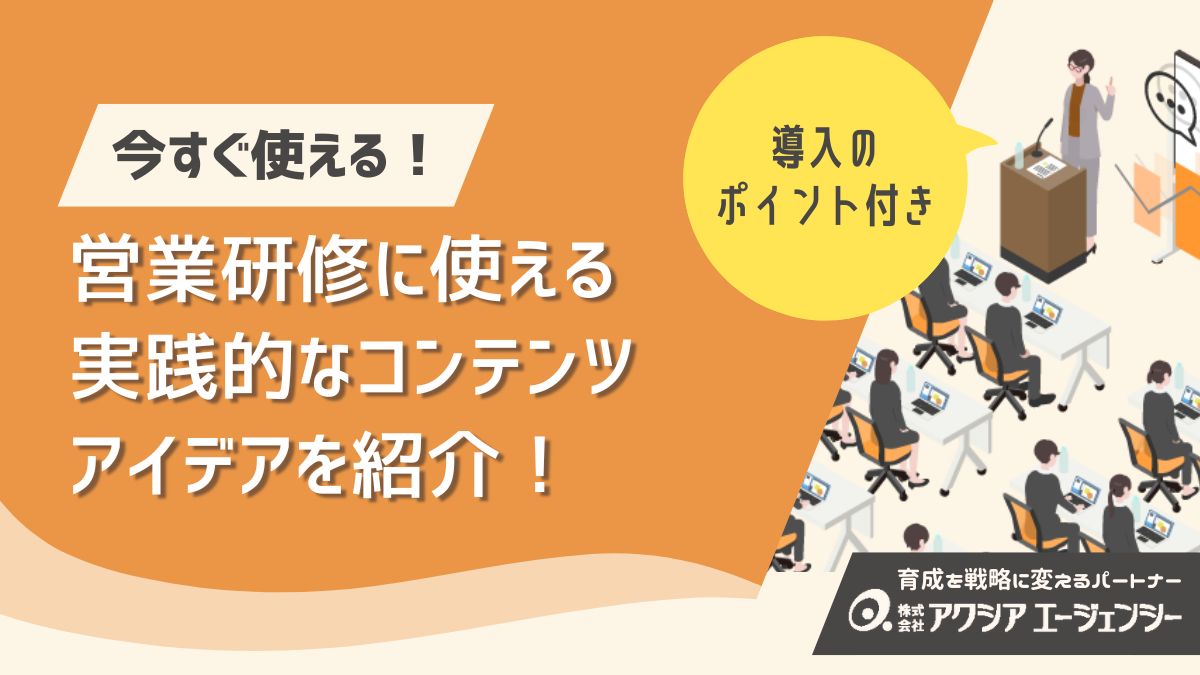営業パーソンのスキルや意識を底上げし、組織全体の営業力を強化するために欠かせないのが「営業研修」です。しかし、私がこれまで数百社以上の営業研修を担当してきた経験から言えるのは、研修の成否は、講師の話術や教材の質ではなく、「研修コンテンツ=中身の設計」にかかっているということです。
どれだけ華やかな資料を用意しても、優秀な講師が話しても、中身が現場とかけ離れていたり、受講者が受け身になってしまうような構成では、残念ながらほとんど成果にはつながりません。
この記事では、営業研修において「コンテンツ」が持つ意味と、効果的に設計するための考え方を、現場での具体的なエピソードや実践知も交えながらお伝えしていきます。
営業研修における「コンテンツ」の重要性とは?
なぜ営業研修の成果は「中身」で決まるのか
営業研修の現場に長年立ってきて実感するのは、研修の手応えと実務への効果は、どんなワークを取り入れるか、どんな体験をさせるかで大きく変わるという点です。
「教える」より「気づかせる」体験の設計
例えば、ある企業で「新人営業向けにプレゼン資料の作り方を教えてほしい」という依頼をいただいた際、私はあえて資料づくりではなく提案の聞かれ方に焦点をあてたワークショップを設計しました。受講者が実際に顧客役を演じ、同僚からのプレゼンを「受け手目線」で評価する時間を設けたのです。
この一見遠回りにも思えるアプローチが功を奏しました。「相手がどう感じるか」を体感することで、「伝えたいことを並べるだけではダメだ」と多くの受講者が自ら気づきました。これが数ヶ月後、営業資料の質だけでなく、商談でのヒアリング力の向上にもつながったという報告を受けたのです。
成果を生むのは中身の質と設計力
ここで言いたいのは、「どんな知識を与えるか」ではなく、「どう体験させ、どんな気づきを引き出すか」が重要だということ。つまり、営業研修において本当に成果を生むのは、中身(=コンテンツ)の質と設計力なのです。実際に多くの企業で起こっているのは、形式的にロールプレイをして終わってしまう、座学に偏って現場で再現性がない、というような「やった感」だけが残る研修です。こうしたケースでは、学びが受講者の中に深く根付かず、数週間後にはほとんどの内容が忘れ去られてしまう。
だからこそ、研修を設計する側は、「その時間で何を学ばせたいのか」「どんな行動変容を起こしたいのか」を明確にし、それに沿った体験型のコンテンツを用意する必要があります。実際に行動が変わったり、普段の営業スタイルを見直すような気づきを引き出すような中身でなければ、現場に効果は波及しません。
「ネタ」ではなく「戦略的コンテンツ」を選ぶ視点
営業研修に関してよく聞かれるのが、「何か面白いネタはありませんか?」という相談です。もちろん、参加者の緊張を和らげたり、場を盛り上げたりするネタが必要な場面もあります。しかし、講師として本当に大事にしているのは、「ネタ」ではなく戦略的に設計されたコンテンツを提供することです。
研修とは、エンタメではなく組織開発の一環です。だからこそ、研修のコンテンツは以下のような視点から逆算して選ぶ必要があります。
1. 研修の目的と営業課題を明確にする
まず第一に、「何のためにその研修をやるのか」を明確にすることが重要です。新規開拓のスキル向上が目的なのか、既存顧客との関係強化か、ヒアリング力か、提案スキルか。ゴールが明確でないまま、「とりあえず研修をやろう」と始めてしまうと、どんなネタを使っても期待する成果は得られません。
たとえば、「若手の主体性がない」という課題を持つ組織では、単なるトークスクリプトの練習よりも「自分で考えて答えを導くワーク」や「フィードバックをもとに自分を振り返る仕組み」の方が効果的です。
2. 受講者のレベル・属性に応じた構成
新入社員とベテラン営業では、当然ながら研修に求めることも、刺さるコンテンツもまったく異なります。
たとえば、新人向けには「基本行動を型として覚えるコンテンツ」、一方で中堅〜ベテランには「思考や判断の質を高めるディスカッション型」が有効です。
私が以前、同じ会社で役職別に分けて営業研修を実施した際、テーマは同じ「顧客ニーズの把握」でしたが、新人にはヒアリング項目を覚えるコンテンツを使い、ベテランには顧客心理を読み取るトレーニングを用意しました。これにより、それぞれの階層で「今の自分に必要なこと」が腑に落ち、行動に変化が見られたのです。
3. 「研修で終わらせない」設計
多くの企業で見落とされがちなのが、研修後のフォロー設計です。良い研修コンテンツは、「その場で終わらない」ことが条件です。具体的には、研修後に上司と1on1で実践内容を共有したり、同じチーム内で学んだ内容を実務で試すチャレンジの時間を設けたりする仕掛けが効果的です。
私は過去に、あるIT企業で、営業研修後の「成果報告ピッチ大会」を設けたことがあります。1ヶ月後に「研修で学んだことを活かして、どんな行動をし、どんな成果が出たか」をプレゼンする仕組みです。これが非常に効果的で、受講者全員のモチベーションが高まり、成果が可視化されることで社内の営業意識が大きく変わりました。
営業研修において成果を出すためには、どんなネタを使うかではなく、「誰に、何のために、どんな変化を期待して、どんな体験を提供するのか」を軸に戦略的にコンテンツを設計することが不可欠です。研修はやることが目的ではなく、変化を起こすことが目的。講師側も、企業側もその視点を持って取り組めば、営業組織の質は間違いなく変わっていきます。
【役職別】最適な営業研修コンテンツの考え方
営業研修の設計において、最も多くの企業が見落としがちなのが「役職別の設計」です。私も研修依頼をいただく際に、「全社員一括で同じ内容をお願いします」と言われることがありますが、それでは効果は薄いのが実情です。
営業のスキルやマインドは、年次やポジションによって求められるものがまったく異なります。にもかかわらず、全員一律のカリキュラムで実施してしまえば、「できる人には退屈」「初心者には難解」と、どちらにとっても中途半端な研修になってしまうのです。
ここでは、私が実際に多くの現場で設計・実施してきた知見をもとに、役職別に最適な研修コンテンツの考え方をお伝えします。
新入社員向け|営業の基礎を体得するスタートアップコンテンツ
新入社員に必要なのは、「成果を出す前提となる行動や思考の型を身体で覚えること」です。研修現場では、彼らが「何がわからないのかすらわからない」状態であることが多く、闇雲に知識を詰め込んでも、実務ではほとんど使いこなせません。私が重視しているのは、「知る」→「やってみる」→「振り返る」の繰り返しです。
おすすめのコンテンツ例
- 営業の基本フローをなぞるロールプレイ
まずは「挨拶・アイスブレイク」「ヒアリング」「提案」「クロージング」といった営業プロセスを、台本付きで反復練習します。初めは形でもよいので、流れに慣れることが重要です。 - ヒアリング力向上ワーク
商品知識よりも、顧客の話を「聞く姿勢」を育てることが先決です。ここでは、質問を使い分ける練習や、「お客様の言葉を深掘りするゲーム」などを通じて、聞く力を養います。 - 行動定着シートの活用
研修だけで終わらせないために、学んだことを日々の行動に落とし込むチェックシートを活用。上司との面談や1on1の中での活用を促します。
また、営業の本質だけでなく、「社会人としての基本マナー」「報連相のやり方」なども含めて設計すると、配属後の立ち上がりスピードが格段に上がります。
若手〜中堅向け|応用力・課題解決力を高める実践型トレーニング
入社3〜5年目あたりの営業パーソンは、「基本的な営業はできるが、成果に波がある」「提案に個性がない」といった課題を抱えていることが多い層です。
この層に必要なのは、自分の営業を客観視して改善できる力と、応用力・課題解決力です。この層向けの研修では、「正解を教える」のではなく、自分で考え、試し、フィードバックを受けて再構築する場を作ることが重要になります。
おすすめのコンテンツ例
- 自分の営業を分析する営業タイプ診断ワーク
「自分がどんなスタイルで営業しているのか」「どのスキルが強みで、どこに課題があるのか」を可視化。仲間同士で診断し合うと、学びが一段と深まります。 - 事例ディスカッション型ワークショップ
過去の実際の商談や失注例をもとに、グループで「なぜ失敗したのか」「どうすれば良かったのか」を検討。個人の成功体験だけでなく、他人の失敗からも学ぶスタイルです。 - ロープレ→フィードバック→再演習の徹底
単なるロープレではなく、「お客様役が本気で演じる」「研修講師が実際の商談目線でフィードバックする」「その場で改善して再挑戦する」という一連の流れが重要です。
この層に対しては、内容も少し難易度を上げつつ、「自分のスタイルを確立する」段階に導く設計が求められます。
マネージャー向け|育成・マネジメントスキルを養う研修
営業マネージャー向けの研修では、「自分が売れる営業になる」から、チームとして成果を出すマネジメントに視点を移すことが求められます。
実際、多くの現場で起きているのがプレイングマネージャーの限界です。自分が手を動かせば成果は出せるが、チームを育てるスキルが不足しているため、部下の成長が停滞してしまう。そんな課題を抱える組織は非常に多く存在します。
おすすめのコンテンツ例
- 営業同行で部下を育てる「観察とフィードバック」演習
部下の営業に同行しても、ただ一緒に商談するだけでは意味がありません。ここでは、「どう観察し、何に注目し、どんなフィードバックを返すべきか」をロールプレイで体験します。 - KPIマネジメントと育成のバランス設計ワーク
売上や訪問件数だけに注目せず、スキルやマインドの成長も管理するための視点を学びます。実際の数値と行動の相関を見ながら「伸ばすマネジメント」を設計します。 - 1on1面談の構造化トレーニング
マネージャーとして部下の本音を引き出し、成長意欲に火をつける面談スキルは必須です。「話しやすさ」「気づきを与える問い」「適切なフィードバック」の要素を徹底練習します。
この層の研修では、現場でありがちな「育成のつまずき」や「自分がやった方が早い病」と向き合いながら、チーム全体の営業力を上げる視点へのシフトチェンジを支援する必要があります。
営業研修は一律で設計するのではなく、それぞれの階層で「何が今、必要か?」に応じて設計することが、成果を最大化するカギです。新入社員には「型」、若手には「自走力」、マネージャーには「育成視点」。
こうした設計ができている企業ほど、研修が一過性で終わらず、現場の動きに変化が生まれます。
成果につながる!営業研修におすすめのコンテンツ7選
ここからは、私が実際に数多くの企業で導入して成果を出してきたおすすめの研修コンテンツをご紹介していきます。どれも単なる面白いネタではなく、営業の実務に直結し、行動変容を促す設計を重視したものです。

対象者の階層や研修目的に合わせて柔軟にカスタマイズできるので、社内研修でも外部講師のプログラムでも活用いただけるはずです。
1.ソーシャルスタイル診断 タイプ別アプローチ力を鍛える
営業において重要なのは自分らしさを貫くことではなく、相手に合わせて伝え方を変えられる柔軟性です。このワークでは、参加者が自身のコミュニケーションスタイルを4つのタイプに診断し、相手との相性やアプローチ方法の違いを理解していきます。
実施のポイント
- 事前に簡易診断を行い、当日はグループにタイプをばらけさせる
- ロープレで「異なるタイプの顧客に合わせた話し方」を練習
- 診断結果を営業戦略や顧客リストと結びつけると、実務への応用が加速
2.共通点発見ワーク 関係構築力の強化
営業のスタート地点は信頼関係です。共通点発見ワークでは、初対面の相手との短時間でのラポール構築(心の距離を縮める)を実践的に学びます。
参加者はペアになり、制限時間内に3つ以上の共通点を見つけ出すというシンプルなゲーム形式。ポイントは、「どう聞き出すか」「どう反応するか」を実体験できることです。
実施のポイント
- お題を事前に指定せず、自由な対話にすることで応用力がつく
- その後の振り返りで「共通点が見つかりやすい質問パターン」を共有する
- 実際の商談シーンへのつかみとして活用できるように紐づける
3.リアクション・ノーリアクション 提案時の反応対応トレーニング
提案の場面でよくあるのが、「お客様の反応が薄くて、手ごたえがない」と不安になるケース。
このワークでは、敢えてリアクションありと無反応の顧客役を用意し、営業側がどう対応を変えるかを体験させます。これにより、相手の非言語コミュニケーションを読む力や、こちらから空気を作る力が鍛えられます。
実施のポイント
- 顧客役にあらかじめリアクションの程度を設定しておく(無表情、うなずき多めなど)
- トレーニング後に、「自分の話し方にどんな変化が出たか」をグループで振り返る
- 管理職層がオブザーバー参加すると、客観的視点の気づきが深まる
4.グループディスカッション 論理的思考と傾聴力の養成
営業は、会話の中で相手の真意を読み取り、論理的に提案する力が求められます。このワークでは、テーマに対してグループで意見を出し合い、最終的に1つの結論を導くというプロセスを通じて、意見の整理・合意形成の力を鍛えます。
実施のポイント
- 「営業で最も重要なスキルとは?」「お客様のNOの本音とは?」など、実務に近いお題を出す
- 各グループでファシリテーター・書記・発表者を持ち回りにする
- 最後に全体で各結論を共有し、多様な考え方を学ぶ
5.ロールプレイマラソン 商談力の総合演習
ロールプレイを本気でやり抜くと、営業スキルは一気に底上げされます。このプログラムでは、複数の商談パターン(新規、既存、価格交渉など)を連続でロールプレイし、その都度フィードバックを受けて再演習します。反復によって、自分のクセや強みが浮き彫りになり、改善ポイントが明確になります。
実施のポイント
- 1回5〜10分の商談→3分のフィードバック→すぐに再実施、というテンポ感が大事
- 同じ商談でも相手役を変えると、視点が増える
- 終了後に「気づきマップ」を書かせると学習が定着しやすい
6.ヒアリングワークショップ 課題発見力を高める
「提案がズレてしまう」「お客様が真のニーズを話してくれない」といった悩みを持つ営業は多くいます。このワークショップでは、聞く力をテーマにした演習を行い、事実と感情の両方を掘り下げる質問力を鍛えます。
実施のポイント
- フィクションの商談ケースを用意し、顧客役からどこまで情報を引き出せるかを競う
- 質問の種類(オープン・クローズド)を意識的に使い分けさせる
- 振り返りでは、「聞けたこと」と「聞き漏らしたこと」を可視化し、全体共有
7.商品プレゼン対決 プレゼンテーションスキルの向上
営業の中でも「魅力的に伝える」力は成果を大きく左右します。このワークでは、同じ商品やサービスをテーマに、グループでプレゼンを作成。創造力、表現力、論理性を競うことで、自然とプレゼン力が鍛えられます。
実施のポイント
- 評価項目を「構成」「伝わりやすさ」「熱量」など多角的に設ける
- 対戦形式や投票を取り入れることで、楽しみながら学べる
- プレゼン後は、なぜ「伝わった/伝わらなかった」のかを全体でフィードバック
「体験型コンテンツ」が成果への最短ルート
今回ご紹介した7つの研修コンテンツは、いずれもやって終わりではなく、受講者の気づきと行動変容を生む設計を意識しています。
営業スキルは、教わるだけでは身につきません。体験し、試し、フィードバックをもらい、自分なりに解釈して実務に活かす——。その循環を生み出せるのが、優れた研修コンテンツの役割です。この中から、自社の課題や対象者に合ったものを選び、ぜひ現場で取り入れてみてください。
オンラインでも活用できる営業研修コンテンツ
コロナ禍を契機に、営業の現場だけでなく研修のスタイルも大きく変化しました。私自身も、2020年以降、対面からオンライン形式へのシフトを多くの企業とともに経験してきましたが、その中で強く感じたのは、「オンラインでも成果の出る営業研修は、設計次第で十分に実現可能」ということです。
ただし、従来の対面研修をそのままオンラインに置き換えるだけでは、効果は著しく落ちてしまいます。重要なのは、オンラインならではの「間」「仕掛け」「流れ」を踏まえた設計です。
ここでは、これまで実施してきた中でも特に反応のよかったオンライン研修のコンテンツ・実践手法をご紹介します。
- Zoom・Teamsでの双方向型演習
- 動画×ワークのハイブリッド設計
- オンライン営業に特化したロープレ研修
Zoom・Teamsでの双方向型研修
オンライン研修で最も多い失敗例が講義中心の一方通行になってしまうことです。対面であれば視線や雰囲気で場をつかめますが、画面越しでは受講者の集中力が切れるのも早く、気がつけば誰も発言しない、うなずきすら見えない…なんてことも少なくありません。そこで私が重視しているのが、双方向型の研修を組み込む設計です。
双方向型の研修の例
- ブレイクアウトルームでの2人組ロールプレイ
3〜5分で1ラウンド、交代して2ラウンド目。その後メインルームで全体フィードバック。短く、テンポよく、がコツです。 - チャットを活用したアイスブレイク&即レスワーク
「最近の商談で困ったことは?」「このセリフ、どう返す?」などを投げかけ、チャットで一斉回答 → 講師がリアルタイムで拾ってコメント。 - 簡易アンケート機能を使ったリアルタイム分析
Zoomの投票機能やGoogleフォームを使って、「提案に自信があるか」「顧客の沈黙が怖いか」などを可視化 → その場でディスカッションの材料にします。
このような設計を取り入れることで、参加者の集中が続き、参加している感覚を持たせることができます。
動画教材×ワークのハイブリッド構成
オンライン研修では、どうしても「一度に詰め込みすぎて疲れる」構成になりがちです。特に長時間の講義形式は、画面越しだと集中力が保ちません。そこでおすすめしたいのが、動画教材と実践ワークを組み合わせたハイブリッド型の構成です。
ハイブリット構成の例
- 事前にeラーニング動画を視聴してもらい、基礎知識をインプット
- 当日はその内容をベースにしたディスカッションやケーススタディを実施
- 学んだことを自分の業務にどう活かすかをペアやチームで共有
- 研修後は、動画を再視聴して学びを深める or 上司との振り返り面談をセットで設計
この形式なら、知識の定着と実務への接続を両立でき、また受講者自身の予習・復習の習慣化にもつながります。
私が担当したある企業では、動画視聴+実践ワーク+チーム発表という3段階で構成したところ、通常の集合研修よりも受講者の理解度・納得度が高まり、翌月の商談成約率が過去最高を記録したという成果も出ています。
オンライン特化のロープレ設計方法
オンライン営業が当たり前になった今、研修の中でもオンライン商談を想定したロープレが求められています。ただし、リアルのロープレをそのまま画面越しに行っても、効果は出ません。なぜなら、オンライン特有の「間の取り方」「資料の見せ方」「表情の伝わりづらさ」などに対応するスキルが別途必要だからです。
ロープレ時のポイント
- 事前に「Zoom営業でありがちな課題リスト」を共有
例:「リアクションが薄く不安」「お客様が画面オフ」「タイミングがつかめずクロージングできない」など - 講師が顧客役としてリアルに演じる
無表情・早口・遮るなど、実際にありそうなシチュエーションをリアルに再現。現場さながらの緊張感で学習効果が高まります。 - 録画→セルフレビュー→講師からのフィードバック
Zoomの録画機能を活用し、自分の話し方・表情・言い回しを確認。講師からは構成・テンポ・非言語の観点でアドバイスを行います。
このロープレ形式は非常に強力で、オンライン営業で苦戦していた若手社員が「自分の声のトーンが単調すぎた」「相手の表情をもっと見るべきだった」など、自発的に改善策を見出すケースが多くあります。
オンライン営業が一般化した今、研修の現場もまた柔軟な対応が求められます。重要なのは、単にオンラインでやることではなく、オンラインならではの強みと弱みを理解し、戦略的にコンテンツを設計することです。
これらを活用すれば、リアル研修に勝るとも劣らない成果を上げることが十分可能です。ぜひ、自社の営業組織に合った形で取り入れてみてください。
効果的な営業研修にするための実施ポイント
ここまで、営業研修の役職別コンテンツや実践的なアイデアをご紹介してきましたが、それらが真に効果を発揮するかどうかは、どう設計し、どう運営するかに大きく左右されます。
実際、まったく同じ内容・同じ講師でも、研修を行う企業や運営の仕方によって、受講者の反応や定着度に大きな差が出るのです。私自身も、年間で数十本以上の営業研修を行ってきましたが、「内容がよくても伝わらない」「熱量があっても現場に活かされない」――こうした失敗も数多く経験してきました。だからこそ、実施のポイントを抑えることが、営業研修の成否を決める要素であると確信しています。

以下に、効果を最大化するための4つの重要ポイントをご紹介します。
目的・ゴールを明確に設定する
研修において最も大事なのは、「なぜこの研修をやるのか?」という目的を、主催者・講師・受講者全員が共有していることです。目的が曖昧なまま実施された研修は、受講者にとっては「なんとなく呼ばれた」「とりあえず参加」という受け身の姿勢になりがちです。そうなると、せっかくの良い内容も届かず、「いい話だった」で終わってしまいます。
例えば、同じ「提案力強化」というテーマでも、以下のようにゴール設定を明確にすると、設計や進め方はまったく異なります。
- 【目的①】新規顧客へのアプローチ初期段階での提案スキルを向上させたい
- 【目的②】既存顧客の深掘り商談での課題解決型提案を磨きたい
- 【目的③】ロープレやフィードバックを通じて、自分の提案スタイルを確立したい
このように目的が定まると、「誰に」「どんな研修を」「どんな流れで」届けるべきかが明確になり、結果として効果の高い研修になります。
現場ニーズに合ったコンテンツ設計を行う
営業研修でありがちなのが、理想論に終始してしまうことです。理想像を語るだけでは、受講者の心は動きません。現場で本当に困っていること、葛藤していること、迷っていることに刺さる内容でなければ、行動変容にはつながらないのです。
私がよく行うのは、研修前に以下のようなヒアリングシートや簡易アンケートを実施することです。
- 最近の商談で、うまくいったこと・うまくいかなかったこと
- 顧客から言われて困ったセリフ
- 今の自分の営業スタイルで不安な点
- どんな営業になりたいか
こうしたリアルな声を拾った上で研修を設計すると、内容が受講者にフィットし、集中力も参加意欲も段違いになります。また、上司やマネージャーから事前に現場で起きている課題や受講後に期待する行動をヒアリングすることも非常に有効です。
参加型にするためのファシリテーション
営業パーソンは基本的にアクティブで、「聞くだけ」「読むだけ」の研修には耐性がありません。だからこそ、参加型・体験型の構成が非常に重要です。ただし、単にグループワークを入れればいいという話ではありません。参加型の設計には、以下のようなファシリテーションの工夫が求められます。
- アイスブレイクで心理的ハードルを下げ、発言しやすい空気を作る
- 正解のない問いを投げかけて、考える習慣を促す(例:「あなたなら、どうしますか?」)
- グループワーク後に「個人の気づき」に落とし込ませる問いを用意する
- 発表やシェアの場面では、否定せず多様な意見を歓迎する
「参加すること自体が学びになる」ように設計された研修は、受講者の姿勢を変えます。主体性が高まり、内発的なモチベーションへとつながっていきます。
実務への接続ポイントを明示する
研修が学びっぱなしで終わる最大の理由は、明日から何をすればいいかが曖昧だからです。受講者は講義やロールプレイの中で、なるほどと感じたり、自分に足りないものを理解します。しかし、その感覚が時間とともに薄れていくのは自然なこと。だからこそ、研修の最後に実務との接続ポイントをしっかり明示することが重要なのです。
- 「このヒアリングスキルを、来週の○○社との商談で試してみてください」
- 「今日気づいた話しすぎるクセを、1週間意識的にチェックしてみてください」
- 「次回の1on1で、上司とこのシートをもとに振り返ってください」
このように、何を・いつ・どの場面で実践するかを具体的に伝えることで、学びが日常業務に根づきます。
また、研修後に上司やマネージャーが伴走する仕組みを設けると、定着率が格段に上がります。たとえば、1on1で研修での学びをどう活かしたかを振り返る時間を設けると、行動変容のサイクルが回り始めます。
営業研修は学ぶ場ではなく、行動を変えるきっかけです。そのためには、目的の明確化・現場との接続・参加型の設計・実務へのブリッジが欠かせません。良いコンテンツを揃えるだけでは、成果にはつながりません。届け方と設計こそが、営業パーソンの行動を変え、結果を変えていく原動力になります。
オリジナルの研修コンテンツを作成する方法
市販の営業研修プログラムや外部の一般的な教材も便利ではありますが、企業が本気で営業組織を変えたいと考えたときには、やはり自社に最適化されたオリジナルコンテンツの存在が大きな力になります。私自身、長年にわたって営業研修を担当してきましたが、最も成果が出るのはやはり、現場とリンクした内容や自社文化に合った言葉やストーリーが盛り込まれたカスタム設計のプログラムです。
ここでは、実際に私がクライアント企業と一緒に進めてきたオリジナル研修コンテンツの作り方を、3つの視点からご紹介します。
1.自社の商品・業界特性を活かす
最初のステップは、自社の商品や業界の売り方のクセを可視化することです。営業という仕事の基本は共通していますが、業界によって顧客心理も商談プロセスもまったく異なります。
たとえば、医療機器の営業と、Web制作の営業とでは、提案スパンも、顧客が重要視するポイントも異なります。ですので、汎用的な研修だけではどうしても現場感が不足してしまう。だからこそ、自社の商品・サービスの販売プロセスをベースにした研修コンテンツが必要なのです。
自社の商品・業界特性を活かした例
- 商談でよく聞かれる質問を集め、「FAQロープレ」を作成
- 自社独自の提案フローをもとにした「営業プロセスマップ」を教材化
- 実際の提案書やプレゼン資料を用いて「リアルレビュー会」
こういった設計にすることで、受講者は「これは現場でそのまま使える」「自分に関係のあることだ」と実感でき、学習の定着が一気に進みます。
現場の「よくある失敗」からコンテンツ化
研修にリアリティと深さを与えるのが、現場で本当にあった失敗体験です。誰しも、自分の過去の失敗には目を背けたくなるものですが、組織全体で成長するにはその失敗を学びに変える仕掛けが必要です。私がよく取り入れるのは、失敗を題材にしたケーススタディ型のワークです。
- 過去に失注した商談の流れを、匿名で再現
- 「なぜ失注したのか?」「どうすれば防げたか?」をグループで分析
- 最後に、再提案するならどうする?をプレゼン形式で発表
この形式はとても効果的で、誰かの失敗が自分の学びになるだけでなく、失敗しても学びに変えられる文化が社内に根づきます。ポイントは、「失敗を責めない」「課題に対して前向きに向き合う」空気を作ること。マネージャーや講師のファシリテーションが重要になります。
また、失敗事例だけでなく、うまくいっているようで実は根本原因が不明確なグレーな成功も取り上げると、組織の営業力はより本質的に磨かれていきます。
トップ営業のノウハウを教材化する方法
どの組織にも成果を出しているベテラン営業がいます。彼らのノウハウや考え方を形式化して、研修コンテンツとして再現可能にすることが、営業組織の成長スピードを加速させます。
ただし、すごい営業=人に教えられる営業とは限りません。むしろ、無意識でやっているからこそ成果が出ている場合が多く、そのままではノウハウ化が難しいのが現実です。そこで有効なのが、ヒアリング+ロールプレイ分解法です。
ヒアリング+ロールプレイ分解法のやり方
- トップ営業に商談の流れを再現してもらう(録画・観察)
- その場で、「今なぜその質問をしたのか?」「なぜその表現を選んだのか?」を逐一インタビュー
- 講師がファシリテーションしながら、型や思考パターンを言語化
- 結果をもとに、ロープレ教材・シナリオ・チェックリストを作成
この手法により、「経験の属人化」を防ぎ、トップ人材の技術を組織全体に伝承できるようになります。さらに、本人にとっても「自分の営業を見直す機会」になり、モチベーションアップにもつながるという副次効果もあります。
その会社だからできる研修が、最大の武器になる
営業研修は、外部講師任せ・パッケージ任せでは本当の意味での変化を生み出しづらいものです。だからこそ、自社の商材や文化、営業現場のリアルを反映したオリジナルのコンテンツを開発・導入することが、営業組織の進化に直結します。
- 商品特性や業界のクセを反映した教材
- 現場の失敗や成功から生まれるリアルな学び
- トップ営業の技術を型にして伝えるしくみ
こうした設計ができれば、研修は単なるイベントではなく、成果を生み出す社内資産として長期的に機能していくでしょう。
営業研修でよくある失敗とその対策
営業研修の企画・運営に携わるご担当者様から、よくこんなご相談をいただきます。

「過去に研修は実施したものの、結局成果が見えなかった」
「その場では盛り上がるが、実務に活かされていない」
「なんとなく“やった感”はあるけれど、本当に意味があったのか分からない」
実はこれ、決して珍しい悩みではありません。私がこれまで関わってきた企業の中でも、多くの組織が似たような研修の落とし穴に陥っています。
このセクションでは、営業研修でよくある3つの失敗パターンを取り上げ、その原因と具体的な対策を講師視点で解説していきます。
形骸化した研修で終わってしまう
これは最も多いパターンです。年に一度、毎年恒例で実施している営業研修。とりあえず何かやらなきゃという動機で、内容を見直すことなく同じ研修を繰り返していませんか?一見継続しているように見えますが、実際の現場では以下のような状態に陥りがちです。

「またこの内容か…」「去年と同じ話だな…」
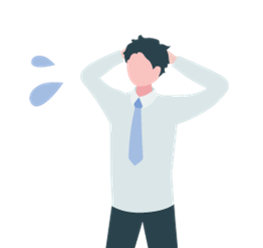
「どうせ一時的なもの」「現場は忙しくてそれどころじゃない」

「結果が出ているか見えないが、惰性で継続中…」
このように、目的や設計のない研修は形だけのものになり、誰の心にも行動にも残りません。これを防ぐには、以下のような対策をとりましょう。
- 研修ごとに「狙う成果」や「対象者の現状」を見直す
- 毎年“変える”ではなく“進化させる”という視点を持つ
- 研修設計の段階で、現場ヒアリングを実施する
たとえば、昨年は商談スキル強化だったが、今年はヒアリングに特化するなど、テーマの深掘りやズラしをすることで、継続性がある中でも新しい刺激を提供できます。
一方通行のレクチャー形式に偏る
これは講師としても痛感しているポイントですが、座学中心の講義形式だけでは、営業パーソンの学びは深まりません。特に営業という職種は、聞くより話す動くより考えるタイプが多いため、受け身の研修スタイルではエネルギーが落ちてしまいがちです。
- 講師が一方的に話し続け、参加者の発言がほとんどない
- ワークはあっても表面的で、発表やシェアが形だけ
- 受講者がメモを取っているが、質問が出ない
このような状況が起きていたら要注意。こうした静かな研修は、学びが浅く、記憶にも残りづらいのが実情です。
対策ポイント
- インタラクティブな仕掛け(問いかけ・グループワーク・ペアトーク)を意識的に挿入
- 45〜60分に1度は「参加者が話す時間」を設ける
- ロープレやケースディスカッションなど体験→振り返り型の設計を取り入れる
私の経験上、研修で一番学べたと感じた時間は、自分が話した時間であることがほとんどです。講師主導ではなく、場づくりに重点を置くことで、参加者のエンゲージメントが飛躍的に高まります。
研修後のフォローアップが不十分
研修は、あくまでスタート地点です。しかし実際には、やりっぱなし・振り返りなし・現場放置のまま終わってしまうケースが非常に多いです。その結果、受講者は学んだことを実務にどう活かせばいいのか分からず、研修の成果が不明瞭になってしまいます。
対策ポイント
- 研修の最後に「翌日から何をするか」具体的なアクション設定を行う
- 上司に対し、フォロー用の質問例や面談シートを提供する
- 1ヶ月後・3ヶ月後のチェックイン(簡易アンケート、レポート提出など)を実施
たとえば、研修の最後にMy Actionプランというシートを配布し、「この学びを活かして、○○社との次回商談で●●を試す」と書かせるだけでも、行動への落とし込みが一気に進みます。
さらに、上司やマネージャーと連動したフォロー体制があると、受講者の意識は格段に高まります。現場で見られている感覚があるだけで人は変わろうとするものです。
営業研修が成果につながらない要因は、中身だけではありません。形骸化、参加型設計の欠如、フォロー不足といった運営設計のゆるさが結果に直結しているケースがほとんどです。
逆に言えば、コンテンツ自体はそれほど派手でなくても、設計とフォローがしっかりしていれば、大きな成果を生み出すことができます。「なぜこの研修をやるのか」「誰が、何を、どう変えるためにやるのか」「その後、どうやって現場に定着させるのか」。これらを明確にし、関係者全員が同じゴールを見据えたとき、営業研修はただのイベントから、営業組織変革の起爆剤へと変わります。
営業研修を人と組織を動かす装置に
営業研修は、何かを教える場ではなく人と組織を動かす装置である——これは、私が長年研修に携わる中で、最も大切にしてきた信念です。
知識やスキルを教えるだけでなく、参加者自身が自分の限界やクセに気づき、仲間と語り合いながら視点を広げて明日からの行動を変えていく。その結果、数字が変わり、顧客の反応が変わり、やがて営業組織そのものの文化が変わっていく——。そんな研修を一社でも多く、ひとりでも多くの営業パーソンに届けたいと本気で思っています。
もし今、あなたの会社でも「営業研修を見直したい」「もっと現場に刺さる研修をつくりたい」とお考えなら、今回の記事でご紹介した内容を参考に、現場起点の実践型コンテンツから設計する営業研修にぜひ取り組んでみてください。
若手も管理職も、成長を実感できる研修を


「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」
「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」
「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」
若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。
アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。
アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴
- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供
- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走
- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決
- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供
研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
山田 忠利
株式会社リクルートフロム・エー(現リクルート)に16年勤めたのち、2003年ITアウトソーシングサービスの業界大手トランスコスモス株式会社に入社。WebマーケやEC事業の立ち上げ、営業本部長も歴任して後進指導にも携わる。2019年アクシアエージェンシーに入社し、人材開発室の立上げに参加。以降、自社の新卒育成及びお客様の新卒他中堅向けの研修講師と企画立案に従事。長年の営業、マネジメント経験を活かした新卒・育成担当者育成に強み。