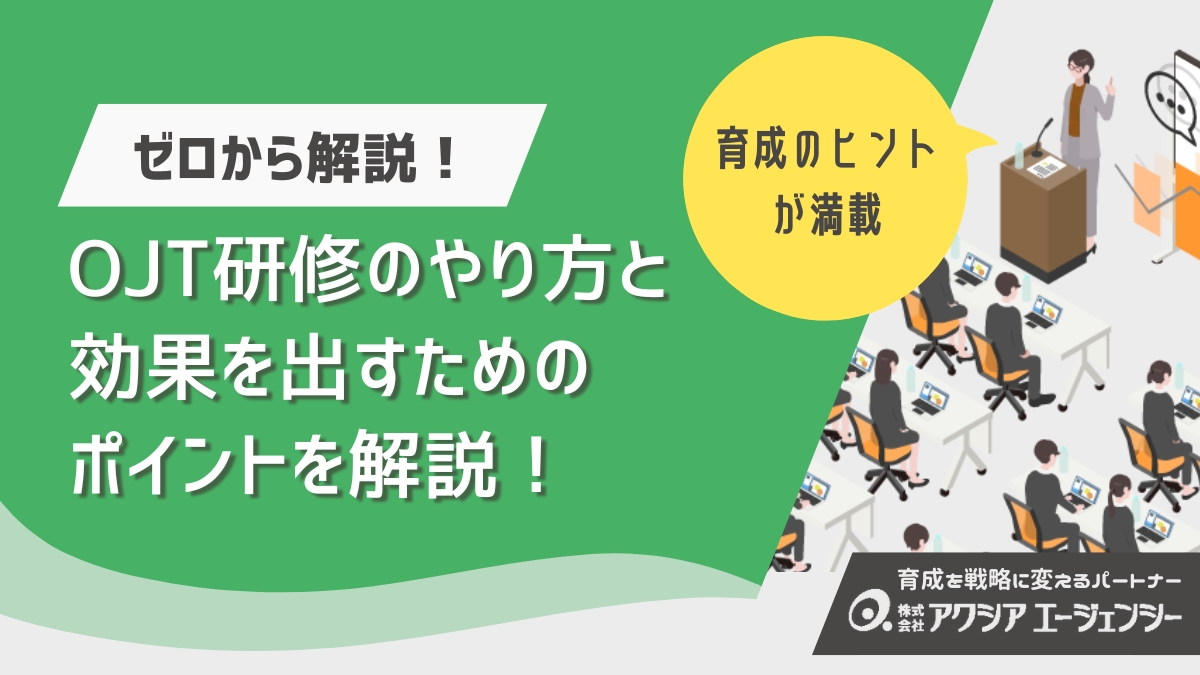OJT(On-the-Job Training)は、現場での実務を通して新入社員を育成する手法として、多くの企業で活用されています。しかし、「どう進めればよいかわからない」「効果が出ているのか判断が難しい」といった悩みを抱える人事担当者や現場のトレーナーも少なくありません。
この記事では、OJT研修の基本的な考え方から、効果を高めるための進め方、よくある課題への対応、デジタルツールの活用法、そして今後のOJTの展望まで、実践的にまとめています。新入社員の育成をより効果的に、そして無理なく進めるためのヒントをお届けします。
OJTとは
OJT(On-the-Job Training)とは、職場内で実際の業務を通じて行われる社員教育のことです。単なる知識の伝達ではなく、実務を通じた育成である点が特徴であり、特に新入社員や若手社員のオンボーディングにおいては重要な手法とされています。業務の流れや仕事の進め方を現場で学びながら、専門スキルや仕事への理解を深めることができます。
OJTを効果的に進めるには、まず目的を明確にし、新入社員がどのようなスキルや知識を得るのかを定義する必要があります。そのうえで、計画的な流れを設計し、トレーナーが「教えるだけでなく一緒に考える」姿勢を持つことが求められます。
近年では、オンラインでのOJT実施も増えており、自社に合った最新の手法を押さえることもポイントです。実施後にはフィードバックを行い、得られた成果や感じた課題をもとに次の改善に活かすことが重要です。
OJTとOFF-JTの違い
OJTが「実務の中で学ぶ教育」であるのに対し、OFF-JT(Off-the-Job Training)は職場を離れて行う座学や外部研修などを指します。OJTは現場に密着している分、即戦力の育成に適しており、個別の指導や実践が可能です。一方、OFF-JTでは専門的な知識や理論を体系的に学べるというメリットがあります。
それぞれの研修方法には異なる強みがあるため、目的や業務内容に応じて選ぶことが大切です。例えば、専門スキルの習得にはOJTが有効ですが、コンプライアンスやリーダーシップといった全社員共通のテーマはOFF-JTが適しています。両者をバランス良く活用することにより、研修のアウトプットを最大化し、離職率の低下や職場定着にもつながる可能性があります。
OJTの目的と得られる効果とは
OJT研修のの目的は、新入社員が業務を通じて職場に早く適応し、自立して行動できるようになることです。その過程では、トレーナーの役割が非常に重要で、実務を指導するだけでなく、定期的にフィードバックを与え、新入社員の成長を促す支援者としての立場が求められます。
また、OJTは単に目の前の業務を覚えるだけでなく、将来のキャリア形成にも影響を与える機会となります。自ら考え、行動し、結果を出す力を養うことができれば、それは異なる職種や業種でも活かせる「人的資産」として大きな価値を持ちます。
OJT研修のメリットとデメリット
OJTのメリット
実務に直結した学びが得られる
OJT研修の最大のメリットは、実際の業務を通じて学ぶことによって、理論だけでは得られない深い理解を得られる点です。職場においては、経験豊富なトレーナーからの直接的な指導があるため、学習の効率が非常に高まります。
応用力を実務で養いやすい
実務でのOJTは、新しい知識やスキルをすぐに業務に応用できる点が強みです。トレーナーの指導のもと、新入社員は日々の業務を通じて実践力を少しずつ身につけていくことができます。その積み重ねによって、徐々に即戦力としての基礎が形成されていきます。
すぐに結果が出るとは限らないものの、業務に直結した経験が得られる環境は、長期的に見て非常に有効です。
チーム全体のスキルアップにつながる
OJT研修により、職場全体のスキルアップが促進され、チーム全体のパフォーマンスが向上することにもつながります。OJTは、理論だけでなく実践的なスキルを養うために非常に有効な手法であり、トレーナーの役割が重要です。
OJTのデメリット
トレーナーの負担が大きい
OJTにはデメリットもあります。最も大きな課題の一つは、トレーナーの負担が増えることです。特に、指導内容が不十分であったり、経験豊富なトレーナーが不足している場合、研修の質が低下し、業務の効率にも影響を及ぼす可能性があります。
即戦力化までに時間がかかる
OJT研修の初期段階では、研修期間が長くなりがちで、新入社員が即戦力になるまで時間がかかることもあります。新しい社員が業務を理解し、結果を出すまでの時間が通常より長くなることもあるため、短期的には効率が落ちることがあります。
コストがかかる可能性がある
さらに、コストがかかることもデメリットの一つです。セミナーや外部研修を補完する形でOJTを行うと、コストが増える場合があります。トレーナーが指導のために時間やリソースを割くことは、会社にとって大きな負担になることもあります。
OJT研修を成功させるための準備
研修目標をしっかり設定する
OJT研修を効果的に行うためには、まず目的と目標を明確に設定することが基本です。目標は「スキルアップを図る」などの漠然とした表現ではなく、「3か月以内に報連相を自立して行えるようになる」など、具体的で測定可能な内容とすることが求められます。
また、トレーナーだけでなく、新入社員自身もその目標に共感し、何のために学ぶのかを理解できるようにすることが重要です。目標の意図や学習の方針を分かりやすく伝えるために、事前に目次やステップを明示することも効果的です。
さらに、研修の進捗を確認するための評価指標や振り返りのタイミングをあらかじめ設けておくことで、トレーナーと新入社員の双方が目標達成に向けて取り組みやすくなります。必要に応じて、eラーニングや学習シートなども併用し、学びの土台を整えることが大切です。
新入社員の状況を把握する大切さ
新入社員一人ひとりの現状を把握することは、OJTの設計や内容を最適化するうえで非常に重要です。そのためには、配属前や研修初期に面談の機会を設けることが効果的です。
面談では、新入社員が持っている知識やスキル、これまでの環境や経験、どのような不安を感じているのかといった背景や状態を丁寧にヒアリングしましょう。このステップによって、現場で求められる水準と、個々のスタート地点との差を明確にできます。
特に、業種や職種の違い、入社前の経験の有無によって、習得スピードや課題は異なります。画一的な指導ではなく、多様な状況を踏まえた柔軟な対応が求められるのです。現場での気づきや学びを深めるには、新入社員の“今”を知ることから始めるのが鉄則です。
適切なトレーナーの選び方
OJTの効果を左右する最大の要素のひとつがトレーナーの質です。トレーナーの選出にあたっては、まず業務や分野に対する専門性があることが前提となります。それに加えて、人材育成への理解や経験、コミュニケーション力も大切な要素です。
また、トレーナーの業務負担やタイミングも考慮しなければなりません。トレーニングに専念できる時間があるか、急ぎのプロジェクトと重なっていないかなど、適切なタイミングで任命することが重要です。
必要に応じて、トレーナー向けの事前セミナーやサポートツールの提供も検討しましょう。リーダーやメンターとしての役割を自ら理解し、トレーニングに前向きに取り組んでもらう体制を整えることで、より高い教育効果が期待できます。
OJT研修の基本的な4ステップ
①Show(やってみせる)
OJT研修の第一歩である「Show」は、トレーナーが実際に業務を行う姿を新入社員に見せるステップです。単なる説明だけでは伝わりづらい実務の流れや具体的な行動を、現場に合わせた実践的な方法で示すことが重要です。
この段階では、手順や作業内容だけでなく、仕事に取り組む姿勢や考え方など、見えにくい部分も自然と共有されます。「見せる」ことで伝わる情報の多さはOJTの大きなメリットの一つです。
また、トレーナーが一方的に動くだけでなく、途中で新入社員に任せて実行を促す場面を作ることも効果的です。自分の能力を発揮できる機会があることで、自信につながり、次のステップへのモチベーションも高まります。
②Tell(説明する)
「Tell」のステップでは、研修の目的や背景を丁寧に説明することが求められます。ただやり方を教えるだけではなく、なぜその業務が必要なのか、どんな意味があるのかまで伝えることで、理解が深まり、納得感をもって行動できるようになります。
ここでは、具体的な事例や実績の紹介を交えて説明するのが効果的です。業務にまつわる成功例や、他の社員がどう工夫しているかなどを紹介することで、理解が一層深まります。
また、Tellの場面では質問を歓迎し、丁寧に解説する姿勢が大切です。こうしたやり取りを通して、トレーナーと新入社員の間に信頼関係が生まれ、学びの質も高まります。
➂Do(やらせてみる)
「Do」の段階では、新入社員が実際に業務をやってみせましょう。トレーナーが見せて、説明した内容を踏まえて、自ら手を動かすことによって学びが定着していきます。
この時、いきなり複雑な業務を任せるのではなく、難易度の低いタスクから段階的に始めることがポイントです。小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけ、主体的に行動する姿勢が育まれます。
さらに、業務を行わせた後にはすぐにフィードバックを行うことが重要です。「何が良かったか」「どこを改善するとさらに良くなるか」を具体的に伝えることで、次の行動につながる学びが生まれます。
➃Check(評価・フィードバック)
最後の「Check」は、OJT研修全体の成果を確認し、今後に活かすための振り返りのステップです。定期的に新入社員のスキルや行動をチェックし、必要に応じて方向修正を行います。チェックは一度きりで終わるものではなく、一定期間ごとに継続して行うことが大切です。観察した情報はメモに残し、次回の研修や評価面談にも活用しましょう。
また、トレーナーからのフィードバックを通じて、本人が成長を実感できるようにすることが重要です。研修の効果がどれほど出ているか、どこを改善すべきかを踏まえて、次の目標や研修設計に反映することで、継続的な育成が可能になります。
評価を改善に活かすには
Checkのステップは評価だけで終わらせず、今後の改善につなげる視点を持つことが大切です。研修成果の確認と合わせてフィードバックを体系的に整理し、「どのステップが効果的だったか」「どこに改善の余地があるか」を洗い出しましょう。
こうしたフィードバックは、次回以降のOJT設計に活用できるほか、人事評価の参考にもなります。OJTを単発の取り組みではなく、継続的にブラッシュアップしていく仕組みとして整備することが、研修全体の質を高める鍵となります。
OJT研修をもっと効果的にするためのコツ
研修を計画的に進めるためのポイント
スキル習得に向けた計画設計
OJT研修を成果につなげるためには、事前の計画が何より重要です。まずは、どのスキルを新入社員に習得してもらうのかといった研修の目的と目標を明確に設定しましょう。その上で、目標に向けた段階的なプランを立て、戦略的に進めることが成功への近道です。
実施環境と体制の整備
プランの作成時には、各ステップで必要なスキルやタスクを整理し、プロセスごとの達成基準を明確にしておくと効果的です。
また、計画を実施するにあたっては、必要なシステムや環境を事前に整備し、トレーナーも含めた関係者全体の理解を促しておくことが大切です。
振り返りの仕組みづくり
研修が始まった後は、進捗を定期的に確認する仕組みを取り入れましょう。例えば、週次の振り返りやチェックリストによる進捗管理など、実施後の流れを見える化する施策が効果的です。企業として研修の質を高めていくには、こうした計画的な取り組みが欠かせません。
定期的なフォローアップを忘れずに
OJT研修は、初期の実施だけで終わらせてしまうと効果が一時的になりがちです。重要なのは、その後の継続的なフォローアップです。まずは、定期的に新入社員の習得状況を評価し、定着状況や課題を確認することが必要です。
そのうえで、適切なタイミングでサポートを行う体制を整えておきましょう。例えば、1か月後・3か月後といったフォロー面談の設定や、相談しやすい窓口の設置などが有効です。OJT中だけでなく、配属後の活躍を支援する仕組みがあることで、スキルの維持・向上にもつながります。
また、新入社員自身からのフィードバックを収集することも大切です。実際の体験から出てきた声を反映し、今後のOJT計画や施策改善に役立てることで、研修内容の質が継続的に高まります。フォローアップを「点」ではなく「流れ」として捉え、育成を推進していくことが成功のカギです。
コミュニケーションの重要性
OJT研修において、良好なコミュニケーションの構築は最も基本であり、最も重要な要素のひとつです。新入社員が不安を抱えずに成長していくためには、自由に質問できる、話しやすい雰囲気をトレーナーが意識的に作っていく必要があります。
特に、研修中の会話は単なるやりとり以上に意味があります。信頼関係が育まれることで、新入社員が自信を持って行動しやすくなり、業務への理解も深まります。これは、ビジネスマナーや社内ルールの定着にもつながる効果があります。
また、チームとしてのつながりや人間関係も意識したいポイントです。問題や課題が発生した際には、個人で抱え込むのではなく、対話を通じて協力して解決する姿勢が求められます。会社全体としてコミュニケーションの重要性を共有することが、OJT成功の土台を築きます。
OJT研修でよくある悩みとその解決策
育成対象者が指導を受け入れないときは?
関係づくりからはじめる
OJT研修の現場では、ときに新入社員が指導をうまく受け入れられない状況が生じることがあります。その背景には、不安やプレッシャー、あるいは指導方法とのミスマッチなど、さまざまな要因があるかもしれません。
まず大切なのは、トレーナーとの信頼関係を築くことです。信頼できる上司やリーダーからの指導であれば、内容を素直に受け入れやすくなります。そのためには、日々の声かけや丁寧な関わりが欠かせません。
フィードバックの伝え方と自分で学べる環境づくり
次に、フィードバックは曖昧ではなく具体的に伝えることが大切です。「もっと頑張って」ではなく、「報告時には結論から伝えるとより良くなるよ」といった、実践に役立つ言葉で伝えることで理解が深まります。
また、新入社員の自主性を引き出す環境を整えることも効果的です。過干渉にならず、自ら考える時間や場面を意識的に用意することで、トレーナーに依存せずに学びを進められるようになります。こうした対応によって、指導を拒絶するような状況の回避や早期の信頼構築につながります。
モチベーションが下がった時の対策
気持ちに寄り添うコミュニケーション
OJT研修中、モチベーションが下がってしまう新入社員は少なくありません。環境の変化や思ったように成果が出ない不安が原因になることが多く、早めの対処が大切です。
まずは、個別のニーズや悩みをしっかり把握することから始めましょう。形式的な面談だけでなく、日常のちょっとした会話から「何に困っているのか」「どんな気持ちか」を引き出す工夫が必要です。
前向きになれる声かけと将来イメージづくり
次に、努力を認めるポジティブなフィードバックを行うことが効果的です。たとえ成果が見えにくい時期であっても、「その工夫はとても良かったよ」などの言葉が安心感につながり、帰属意識の向上を促します。
さらに、将来のキャリアビジョンを一緒に描く場をつくることで、「今学んでいることは将来にどうつながるのか」が明確になります。キャリアへの理解と期待が深まれば、新入社員は前向きな気持ちを取り戻すことができます。
メンタルヘルスとストレス管理の重要性
OJT研修は、新入社員にとって業務・人間関係・職場環境のすべてが新しい状態の中で進むため、心理的負荷がかかりやすい状況です。しかし、多くの現場では業務遂行やスキルの評価に比重が偏りがちで、心のケアが後回しになるケースも見られます。
このような状況を防ぐには、研修期間中のメンタルヘルス対策を事前に設計しておくことが重要です。定期的なカウンセリングの実施や、心理的安全性を意識した声かけ、ストレスチェックなどの導入は、メンタル面の安定に大きく寄与します。
心理的安全性とは
心理的安全性とは、職場やチーム内で「自分の意見や気持ちを安心して表現できる」と感じられる状態のことを指します。たとえば、「こんなことを聞いたら怒られるかも」「間違えたら評価が下がるかも」といった不安がなく、質問・発言・相談・挑戦がしやすい環境が整っていることを意味します。
OJTの場面では、心理的安全性が高いと、新入社員が積極的に学ぼうとしたり、失敗を恐れずに実践を繰り返したりすることができます。トレーナー側も、日々の声かけやリアクションの工夫を通じて、「何を言っても大丈夫」と思える関係性を築いていくことが大切です。
また、トレーナー自身も精神的に余裕を持ち、必要に応じて上司や専門部署と連携できる体制を整えておくことが大切です。OJTは“育成”だけでなく、“守る”ことも含めた取り組みとして捉える必要があります。
トレーナーの負担を減らす方法
みんなで支える仕組みにする
OJTにおいては、トレーナーの負担が重くなりがちです。育成は業務の片手間でできるものではなく、時間とエネルギーを必要とする重要な役割です。そのため、負担を軽減する仕組みづくりが求められます。
まずは、役割分担を明確にすること。全てを一人に任せるのではなく、「実務の指導はAさん、評価の記録はBさん」といった具合に責任を分けることで、精神的・時間的負担を分散できます。
定期的な振り返りとつながりの維持
また、メンター制度を導入して複数人での支援体制を構築することもおすすめです。トレーナーが相談しやすい仲間を持つことは、継続的な育成の継続にもつながります。
さらに、定期的なチェックインを設定し、進捗や課題を可視化することで、先回りして支援ができるようになります。OJTを個人任せにせず、育成を組織で支援する取り組みとして考えることが重要です。
これからの時代に合った育成のヒント
OFF-JTとうまく組み合わせる方法
OJTをより効果的にするには、OFF-JTとの併用を前提とした設計が欠かせません。まずは、それぞれの役割を明確に理解しましょう。OJTは実務を通じてスキルを磨く場、OFF-JTは外部の研修や座学などを通じて基礎知識や視野を広げる場として機能します。
たとえば、OJTの中では補えない法令知識やビジネスマナーなどは、OFF-JTで体系的に学ぶと効果的です。そのうえで、職場の現場ではそれをどう使うかをOJTで身につけることで、学びの流れに一貫性が生まれます。
また、予算やリソースの配分も大切です。社内にノウハウがない分野は外部講師を活用するなど、目的に応じた組み合わせ方を考えることで、社員にとっても納得感のある研修環境をつくることができます。
デジタルツールを活用してみよう
近年では、OJTの中でもデジタルツールの活用が進んでいます。リモートワークの広がりを背景に、ツールをうまく取り入れることで、効率的かつ柔軟な研修が実現できます。
たとえば、オンラインマニュアルや操作動画を共有する仕組みを整えれば、業務の中で何度でも確認できる学習環境が作れます。実務に合わせたカスタマイズも可能で、新人にとっては自分のペースで学べる点も大きなメリットです。
変化する働き方に対応するOJT
働き方が多様化するなかで、OJTにも柔軟さが求められるようになってきました。かつては「現場で直接教える」ことが基本でしたが、今では業務内容に応じたカスタマイズが必要です。
まずは、現場で実際に求められるスキルや作業を反映した内容をOJTに取り入れることが重要です。マニュアル通りの育成ではなく、業務や役割に合わせて柔軟に設計することで、早期の戦力化につながります。
さらに、異なる業種・部門間でのナレッジ共有を活発にすることで、組織全体の育成力が高まります。社内コミュニケーションの活性化や、ビジネスの変化に対応した柔軟な教育体制が今後の鍵となります。
Z世代へのアプローチ方法
Z世代の新入社員は、個別性や柔軟性を重視する傾向があります。そのため、従来の一律的な研修スタイルではなく、彼らの特性に寄り添ったアプローチが求められます。
まず有効なのが、先輩社員とのメンター制度の導入です。年齢や考え方の近い存在が身近にいることで、相談しやすく安心感が生まれます。また、体系的な研修コンテンツを用意して、必要な情報を整理して提供することも重要です。
さらに、社会全体の価値観やトレンドを反映したテーマ(サステナビリティ、DXなど)を取り入れることで、「自分たちに合っている」と感じられる研修になります。こうした柔軟な対応によって、Z世代のエンゲージメント向上と早期離職の防止が期待できます。
まとめ
OJT研修は、新入社員に実践を通して学びを深めてもらう貴重な育成手段です。成功のカギは、目的とステップを明確にし、信頼関係のあるトレーナーによって丁寧に進めていくことにあります。
また、ただ実務を教えるだけでなく、モチベーションの低下やストレス、トレーナーの負担といった現場の悩みにも向き合いながら、企業全体でサポートできる仕組みを整えることが求められます。
この記事を参考に、御社らしいOJTの進め方を見直し、育成の力をさらに高めていくきっかけにしていただければ幸いです。
若手も管理職も、成長を実感できる研修を


「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」
「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」
「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」
若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。
アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。
アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴
- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供
- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走
- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決
- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供
研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。