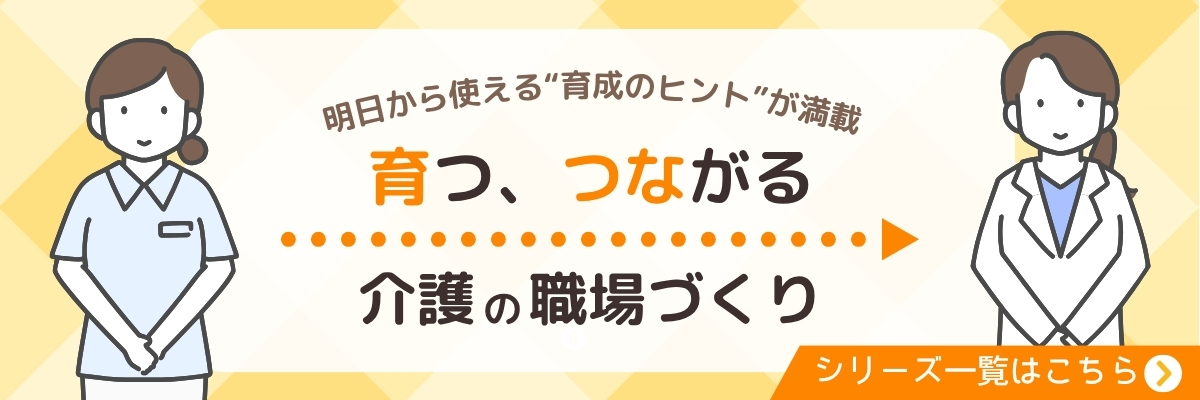介護現場で求められるのは、技術力だけではありません。利用者や家族との関わりの中で、安心感を与える「丁寧な対応」も、介護の質を左右する大切な要素です。しかし、「スタッフによって対応に差がある」「忙しいときほど言葉がきつくなる」など、現場の接遇力に課題を感じる施設は少なくありません。
利用者や家族から信頼を得るには、全員が同じ基準で心のこもった対応をできる職場づくりが欠かせません。そのために、接遇マナーを個人の感覚ではなく、職場の共通言語として共有することが重要です。
スタッフ一人ひとりの意識をそろえることで、利用者との信頼関係だけでなく、職員同士の関係もやわらぎ、自然と雰囲気のいい職場が生まれます。丁寧な対応は、職員が気持ちよく働ける環境づくりにもつながるのです。
【育つ、つながる、介護の職場づくり】第4回では、介護現場で信頼される対応を定着させるための考え方として、スタッフ教育の基本となる接遇マナー5原則を紹介します。「対応の質」をそろえ、利用者にも職員にも安心が広がる職場づくりのヒントにしてください。
接遇は「個人のスキル」ではなく「職場の文化」
介護現場では、同じような場面でも、職員によって対応の仕方が少しずつ違います。たとえば、朝のあいさつや声のかけ方ひとつをとっても、職員によって印象は大きく変わります。ある人は笑顔で声をかけ、ある人は黙々と業務を進める。利用者から見ると、そのちょっとした差が「居心地の良さ」や「安心感」に直結します。
実際、「あの人のときは安心するけど、別の人だと少し不安」という声を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?これは、スタッフ一人ひとりの印象の違いというより、職場としての接遇基準が共有されていないことが原因です。
介護はチームで成り立つ仕事です。だからこそ、誰が対応しても同じように安心できることが、施設全体の信頼を生みます。そのためには、接遇を「個人の意識」ではなく「職場の共通文化」として根づかせることが大切です。
新人やベテラン、パートや正社員――立場が違っても同じ基準で動ける。そんな環境をつくるために、接遇マナーの基本を共通言語として整理することが効果的です。
接遇マナー5原則で信頼される対応を育てる
職員一人ひとりの対応をそろえるうえで、まず大切なのが、接遇マナーの基本を共通認識として持つことです。
この5つの原則は、介護現場で信頼を得るための日々の行動の土台。難しいルールではなく、「どんな場面でも大切にしたい考え方」として全員で共有するのがポイントです。
① あいさつ ― 最初の3秒で信頼が決まる
介護現場では、1日の始まりのあいさつや、すれ違いざまの声かけが、そのまま施設の印象を決めます。
笑顔で「おはようございます」と声をかけるだけで、利用者も同僚も今日も安心して話せそうと感じられます。逆に、目も合わせずに通り過ぎるだけで、忙しそう話しかけにくいという印象を与えてしまうこともあります。
実践のポイント
- 相手の目を見て、名前を添えたあいさつを心がける
- 作業の手を止めて、体ごと相手の方を向く
- 表情が見えにくいときは声のトーンで笑顔を伝える
あいさつはマナーではなく、チームケアの始まりです。職員同士が明るく声を掛け合うだけで、利用者にも安心感が広がります。忙しい時間帯ほど誰にでも先に声をかける意識を共有し、新人やパートスタッフも自然に参加できる雰囲気をつくることが大切です。
朝礼での声かけ練習や「今日の一声」をテーマに話すなど、日常の中で意識づけを重ねていきましょう。
② 身だしなみ ― 清潔感は安心のメッセージ
介護職の「身だしなみ」は、単なる見た目の問題ではありません。それは、利用者にとって「この人なら安心して任せられる」と思えるかどうかのサインです。髪型や爪、制服の整え方、香水やアクセサリーの控え方など、清潔感の印象ひとつで、相手の受け取り方は大きく変わります。
清潔な身だしなみは、職員自身にとっても仕事のスイッチになります。鏡を見て身だしなみを整える行為は、利用者と向き合う心の準備でもあるのです。
実践のポイント
- 髪・爪・制服の清潔さを毎日セルフチェック
- 「相手がどう感じるか」を意識して身だしなみを選ぶ
- 制服にしわがない、靴が清潔、名札が見やすいなど、細部まで意識する
身だしなみは個人の自由ではなく職場の信頼に関わる部分です。チェックリストを用意して定期的に振り返る時間を設けると、「なんとなく気をつけている」から「意識的に整える」に変わります。
また、月1回の「身だしなみチェックデー」など、全員で確認する場をつくると意識が高まります。注意ではなく、褒めて共有する――それが長続きする文化をつくるコツです。
③ 表情 ― 言葉以上に安心を伝える
介護の現場では、言葉よりも先に伝わるのが表情です。マスク越しでも、目元や声のトーンには感情がにじみ出ています。
忙しいときほど表情が硬くなりがちですが、ほんの少しの笑顔が、利用者の不安をやわらげ、職員同士の空気もやさしく変えます。
実践のポイント
- 目で笑う意識をもつ(眉と目元を柔らかく)
- 声に「温度」を乗せる(トーンを少し高め、ゆっくり話す)
- 無表情で仕事をしない。話すときは相手に体を向ける
「笑顔でね」と言葉で伝えるだけでは浸透しません。朝礼での笑顔チェックや、ペアで表情を確認し合うなど、実際に「見て・感じて」共有する場を設けましょう。
また、管理者自身が穏やかな表情で話しかける姿勢を見せることが、新人や若手への一番の指導になります。笑顔は教えるものではなく、職場で育てるもの。互いの笑顔が連鎖していく環境づくりを意識しましょう。
➃ 言葉づかい ― 一言の添え方で印象が変わる
どんなに正しい内容でも、言葉の選び方ひとつで印象は大きく変わります。 命令口調よりも、お願いや感謝を添える表現が、相手に安心を与えます。
たとえば――
「待っててください」→「少しお時間いただけますか?」
「できません」→「別の方法を考えてみますね」
こうした小さな言い換えが、利用者にも家族にも丁寧に対応してもらえたという安心を残します。また、職員同士でも言葉づかいを整えることで、現場の雰囲気は驚くほど穏やかになります。
実践のポイント
- 否定ではなく代替案を添えて伝える
- 感謝・共感・気遣いの言葉を積極的に使う
- チーム全員で丁寧な伝え方を共有する
言葉づかいは、「注意」ではなく「習慣」で変えるのがコツです。まずは使いたい言葉をチームで決め、日常の中で良い言葉を見つけたら「今の言い方、素敵でしたね」と声をかけ合いましょう。
リーダーが率先して柔らかい言葉を使うことで、現場の空気全体が穏やかになり、クレーム防止にもつながります。
⑤ 態度・立ち居振る舞い ― 聴く姿勢が信頼をつくる
最後の原則は「態度」。介護の仕事では、話す力よりも聴く姿勢が信頼をつくります。忙しい中でも手を止めて、相手の目を見て話を聞く。そのたった数秒の丁寧さが、「きちんと向き合ってくれた」という印象につながります。
利用者や家族からの要望・意見・苦情を受けたときこそ、「まず聴く」「途中でさえぎらない」ことが大切です。落ち着いた所作と誠実な受け止め方が、どんな説明よりも信頼を生みます。
実践のポイント
- 感情的にならず、まずは「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と受け止める
- 相手の話を要約・復唱し、理解していることを伝える
- その場で判断できない場合は「確認してからご連絡します」と丁寧に返す
聴く姿勢はマニュアルでは身につきません。ロールプレイや事例共有の場を設け、「どんな言葉が相手に響いたか」をチームで話し合うことが効果的です。
また、上司やリーダーが率先して「まず聴く」を実践し、部下の話を遮らずに耳を傾けることで、聴く文化が自然と根づきます。言葉よりも態度で示すこと――それが一番の教育です。
接遇マナー5原則は、誰か一人のスキルを高めるためではなく、職員全員が同じ基準で信頼される対応を続けるための共通ルールです。あいさつ、身だしなみ、表情、言葉、態度――どれもすぐにできることばかりですが、その積み重ねが大きな安心を生みます。
小さな「丁寧さ」の連鎖が、利用者の満足度だけでなく、職員同士の関係性や職場の雰囲気まで変えていく。それが、信頼される介護の出発点です。
信頼を生む対応をチームで育てる。接遇・マナー研修の効果とは
接遇・マナー教育は、個人の印象改善だけでなく、チーム全体の空気を変える力があります。同じ基準を学ぶことで、言葉づかいや対応に一貫性が生まれ、施設全体の信頼感が高まります。
「ビジネスマナー・接遇研修」で学べる内容
- 第一印象を決める非言語コミュニケーションの使い方
- 利用者・家族への丁寧な言葉づかいと対応フレーズ
- 苦情対応・クレーム初期対応のロールプレイ
- チーム内コミュニケーションを円滑にする伝え方
- ストレスを溜めない聴く姿勢と感情コントロール
導入事例
ある企業でビジネスマナー研修を通じて見えてきたのは「当たり前のことほど、意識しなければすぐに形骸化してしまう」という現場の気づきでした。
受講者からは、「知っているつもりでも、いざ問われるとあやふやな部分が多かった」「仕事に慣れる中で、基本をおろそかにしていた」といった声が多く寄せられました。ビジネスマナーや接遇の基本を改めて学び直すことで、行動の一つひとつに意味を持って取り組む姿勢が芽生えています。
特に「初心を思い出した」「真摯に業務に向き合いたい」といった前向きな意識変化が見られ、マナー研修が型を覚える場から姿勢を整える場へと変化していることがうかがえます。
動画で学べる「ビジネスマナー研修」
現場研修だけでなく、動画で学べるオンデマンドコースもご用意しています。社会人の基礎となる「第一印象・身だしなみ」「あいさつ・お辞儀」「敬語・言葉づかい」「電話・メール応対」など、日常業務で欠かせない基本動作を体系的に学べる内容です。
オンライン形式なので、新人研修・内定者教育・マナーの再確認にも最適。現場を離れず、すき間時間で学習できるのが特長です。
ベテラン講師が研修を担当

長年、企業研修や接遇指導を手がける講師が、「感じがいい人」ではなく「信頼される社会人」をテーマに、OK/NG例を交えながら分かりやすく解説します。
「丁寧な対応」が当たり前になる職場へ
接遇やビジネスマナーは、個人の良し悪しではなく、職場全体で育てる「共通文化」です。今回整理した5原則(あいさつ/身だしなみ/表情/言葉づかい/立ち居振る舞い)は、明日から現場で実践できる土台づくりの考え方でした。
- そろえる
基準を言語化し、全員で共有する(朝礼での一言・チェックリスト・OK例の可視化)。 - 続ける
ロールプレイや振り返りの小さな場を定期化し、注意ではなく称賛で定着させる。 - 広げる
管理職・リーダーが日常の関わりで手本を見せ、「まず聴く」「柔らかく伝える」姿勢を連鎖させる。
この3つを回し続けることで、利用者・ご家族の安心感、職員同士の関係性、職場の雰囲気が着実に変わります。結果として、クレームの未然防止や離職抑制にもつながります。
もし「まずは基準を整えたい」「現場での伝え方を形にしたい」という段階であれば、接遇・マナー研修や、時間・場所を選ばず学べるオンデマンド型の基礎編をうまく組み合わせるのがおすすめです。小さな丁寧さの連鎖を、チーム全体の標準へ。今日から一歩ずつ進めていきましょう。
若手も管理職も、成長を実感できる研修を


「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」
「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」
「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」
若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。
アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。
アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴
- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供
- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走
- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決
- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供
研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。