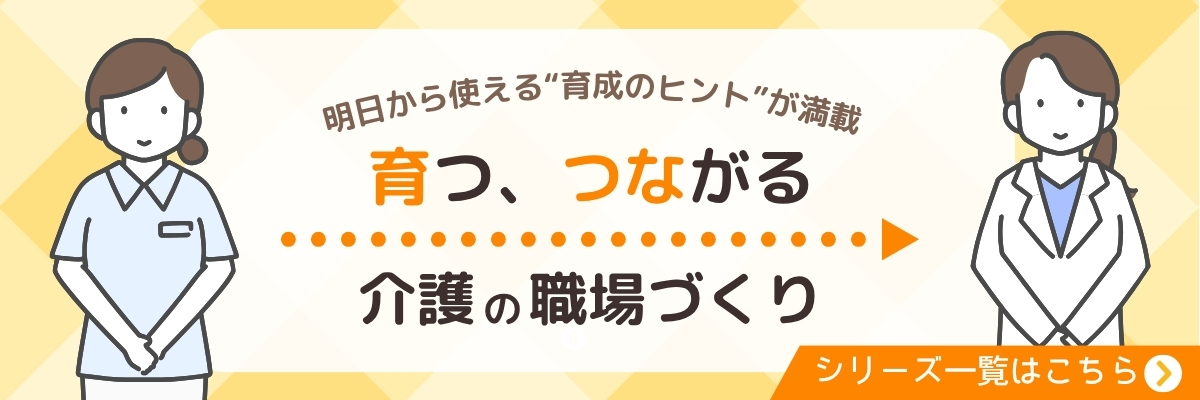介護の現場では、日々のコミュニケーションが仕事の質を左右します。しかし近年、「注意しただけなのにパワハラだと言われた」「きつい言い方をしてしまい後悔している」といった声も増え、 “指導”と“ハラスメント”の線引きに悩むケースが少なくありません。
一方で、「何か言うとトラブルになりそうで注意できない」「負担になりそうで上司にも相談しづらい」など、お互いが気を遣いすぎて、必要な対話が減ってしまう職場もあります。その結果、誤解や不信感が積み重なり、チームの関係性や職場の雰囲気に影響することも。
【育つ、つながる、介護の職場づくり】第3回では、「言いづらい」「伝わらない」といった現場のすれ違いをなくし、 上司・部下の双方が安心して話せる職場をつくるためのポイントを紹介します。
ハラスメント防止を守るためのルールではなく、関係を育てるコミュニケーションとして捉え直し、 介護現場に本当に必要な対話のあり方を考えていきます。
なぜ介護の現場では「言いづらさ」が生まれるのか
介護の現場では、日々の業務が密接に連携して行われる一方で、感情を伴う仕事であるがゆえに、ちょっとした言葉の行き違いが大きな誤解につながることがあります。人手不足や業務の多忙さから、伝え方が強くなってしまったり、忙しさゆえに十分な説明やフォローができず、意図せず相手を傷つけてしまうことも少なくありません。
公益財団法人介護労働安定センターの「令和6年度 介護労働実態調査」でも、直前の職場を辞めた理由として「職場の人間関係に問題があったため」と回答した人が24.7%で最も多く、 その内訳では、
- 上司や先輩からの指導や言動がきつかった・パワハラスメントがあった(49.1%)
- 上司の業務指示が不明確、リーダーシップがなかった(36.2%)
- 仕事の進め方に関する意思疎通がうまくいかなかった(35.5%)
と、上司・リーダーとの関係性に関する要因が中心を占めています。
つまり、ハラスメントの背景には悪意よりも、誤解や伝わらなさ、があるということです。また、「勤務先に仕事上の悩み事の相談ができなかった」と回答した人も3.0%おり、職場内で安心して話せる関係や相談体制が十分に機能していない実態も浮き彫りになっています。
介護現場は、他職種・多世代が協働する職場です。だからこそ、指導する側と受け取る側の価値観のズレが起きやすく、 「きつく言ったつもりはない」「悪気はなかった」という小さなズレが、相手には「人格を否定された」「相談できない」という大きな痛みとして残ることがあります。
この言いづらさの連鎖を断ち切るには、上司・部下のどちらか一方が変わるだけでは不十分です。 双方が伝え方と受け止め方を学び合い、同じ土台で理解し合える関係性を築くことが、ハラスメント防止の第一歩になります。
誤解を防ぐために必要なのは、伝え方・受け止め方・相談できる仕組みの3本柱
ハラスメントを防ぐというと、上司が気をつけることと考えられがちですが、実際には言う側と受け取る側の双方に理解とスキルが必要です。どちらか一方だけが意識しても、すれ違いは解消されません。
介護の現場で本当に求められているのは、お互いが安心して意見を伝え合える関係づくり。そのために欠かせないのが、
- 指導とパワハラの違いを正しく理解すること
- アサーティブコミュニケーションで伝え合うこと
- 相談できる仕組みを整えること
この3つの視点です。
① 「指導とパワハラの違い」を正しく理解する
「厳しく言ったつもりはない」「指導の一環だった」──そんな言葉が、結果的に職員を追い詰めてしまうことがあります。厚生労働省の定義によれば、パワーハラスメントとは、職場での優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、身体的・精神的な苦痛を与える行為。
つまり、目的と方法の両方が重要です。注意や指導そのものが悪いのではなく、その伝え方や頻度、場所、言葉の選び方が問題になるケースが多いのです。
現場で意識したいチェックポイント
- 「人前で叱る」ではなく、「落ち着いて話せる場を選んで伝える」
- 「何ができていないか」だけでなく、「どうすればできるか」を伝える
- 感情のままに話すのではなく、「事実」をもとにフィードバックする
“指導”と“パワハラ”の違いを理解し、伝え方を少し変えるだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。
② 感情を伝え合う「アサーティブコミュニケーション」を取り入れる
介護の現場では、立場や年齢の違いから伝えづらさが生まれやすいもの。そんな時に有効なのがアサーティブコミュニケーションです。
アサーティブとは、攻撃的でも受け身でもない、率直で誠実な伝え方のこと。たとえば「こうしてほしい」と言うときに、相手を責めるのではなく、「私はこう感じた」「こうしてもらえると助かる」と自分の思いを伝える形に変えるだけで、相手の受け取り方はやわらかくなります。
現場でできるアサーティブな関わり方
- 感情をそのままぶつけず、「事実→気持ち→希望」の順に話す
- 相手の話を最後まで聴き、「理解する姿勢」を示す
- 相手を否定せず、「どうすれば良くなるか」を一緒に考える
小さな言い換えの積み重ねが、職場全体のトーンを変えます。言い合える関係は、安心して働けるチームづくりの第一歩です。
③ 安心して話せる「相談の仕組み」をつくる
ハラスメントが深刻化する背景には、誰にも相談できなかったというケースが多くあります。トラブルを未然に防ぐためには、問題が起きる前に話せる仕組みが欠かせません。
たとえば、週1回のミニ面談や、月1回のフォロー面談を設定するだけでも、言いづらいことを話せる時間が確保されます。また、上司以外にも話せるサブ相談窓口を設けておくことで、「ここなら話せる」と思える安心感が生まれます。
現場でできる工夫
- 面談時に「最近どう?」と感情面にも触れる質問を取り入れる
- 日報や申し送りで“困りごと”を共有するスペースを設ける
- 相談を受けた際は“すぐに動く・報告する”ルールを整える
「言いづらい」をなくすには、相談を受ける側の姿勢も重要です。 どんな小さな声にも耳を傾けることが、ハラスメントを防ぎ、信頼を育てる第一歩になります。


上司・部下それぞれが学ぶ「ハラスメント防止研修」
ハラスメント防止は、誰かを責めるための取り組みではなく、お互いを理解し合い、働きやすい職場をつくるための学びです。
多くの職場では管理職だけを対象に研修を実施するケースが一般的ですが、実際には「受け取る側」である一般社員にも、正しい知識と伝え方を身につけることが欠かせません。指導の意図を理解し、自分の気持ちを伝える力を育てることで、言われっぱなし・言えないままというすれ違いを減らすことができます。
本研修では、上司と部下それぞれの立場からハラスメントの境界を理解し、適切なコミュニケーションを取れるようになることを目的に、管理職向け・一般社員向けの2種類のプログラムを実施します。
管理職向けプログラム
現場で起きやすい“グレーゾーン”を題材に、「指導」と「ハラスメント」の違いをケーススタディで学びます。
また、部下との1on1や注意場面で役立つ「アサーティブな伝え方」も実践形式で習得。感情を抑えるのではなく、冷静に伝えるスキルを身につけます。
主なテーマ
- 指導とパワハラの線引きを理解する
- 伝わる注意・叱り方のコツ
- フィードバックで相手を動かすコミュニケーション
導入事例
ある企業では、現場で声を荒げてしまう場面が課題となっており、管理職向けに「関係性を壊さない指導と対話」をテーマとした研修を実施。
受講者からは「育成とハラスメントの境界線が明確になった」「部下との信頼関係構築に活かしたい」との声が寄せられ、叱るから支えるへと意識が変わるきっかけになりました。
一般社員向けプログラム
ハラスメントを受けないための学びではなく、「どう受け止め、どう伝え返すか」に焦点を当てた内容です。上司への報告・相談の仕方や、誤解を防ぐ言葉の選び方を演習やロールプレイを通して学びます。
相手の意図を想像しながら、自分の考えを冷静に伝える力を養うことで、すれ違いや行き違いを防ぐ職場づくりにつなげます。
主なテーマ
- 「受け止め方」のクセを知る
- 違和感を感じた時の適切な伝え方
- 相談しやすいコミュニケーションの練習
導入事例
別の企業では、一般職向けにコミュニケーションを軸にした予防研修を実施。「ハラスメント以上に日常の言葉づかいが重要と気づいた」「相手の立場に立った言葉選びの必要性を実感した」との声が多く、日常業務での相互理解促進につながりました。
研修の特徴
- 上司・部下それぞれの立場に合わせた構成で、現場に即した学びを提供
- 実例ベースのシナリオで明日から使える実践型
- 研修後のフォローアップにより、学びの定着を支援
防止を目的とするだけではなく、 「どう関わればお互いが気持ちよく働けるか」を一緒に考えるのが、この研修のゴールです。上司と部下が同じ目線で話せる時間を持つことが、 職場の安心感と信頼関係を生み出していきます。
まとめ:関係を壊さず、育てるコミュニケーションへ
介護の現場では、日々の言葉ひとつがチームの空気を変えます。厳しく伝えたつもりが「冷たい」と受け取られたり、遠慮して言えなかったことが後になって誤解を生むこともあります。
大切なのは、完璧に伝えることではなく、相手を理解しようとする姿勢です。その一言に「相手を思う気持ち」があるかどうかが、職場の信頼を左右します。
ハラスメント防止とは、叱らない文化をつくることではありません。お互いが安心して意見を交わせる関係性を育て、「言っても大丈夫」「聞いても大丈夫」と思える職場をつくること。それが、定着と成長を支える土台になります。
【育つ、つながる、介護の職場づくり】シリーズの第3回では、 言いづらさをなくし、関係を育てるためのヒントを紹介しました。上司も部下も、同じ目線で対話する時間を持つことが、介護の現場をもっとあたたかく、働きやすい場所に変えていきます。言葉がけが変われば、職場が変わる。そしてその変化が、利用者にとっての安心にもつながっていきます。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
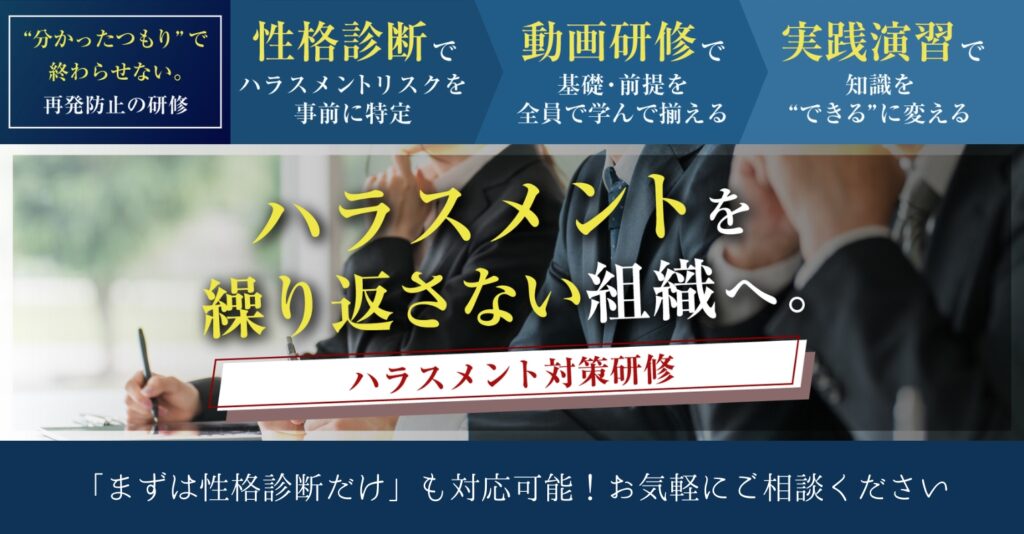

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。