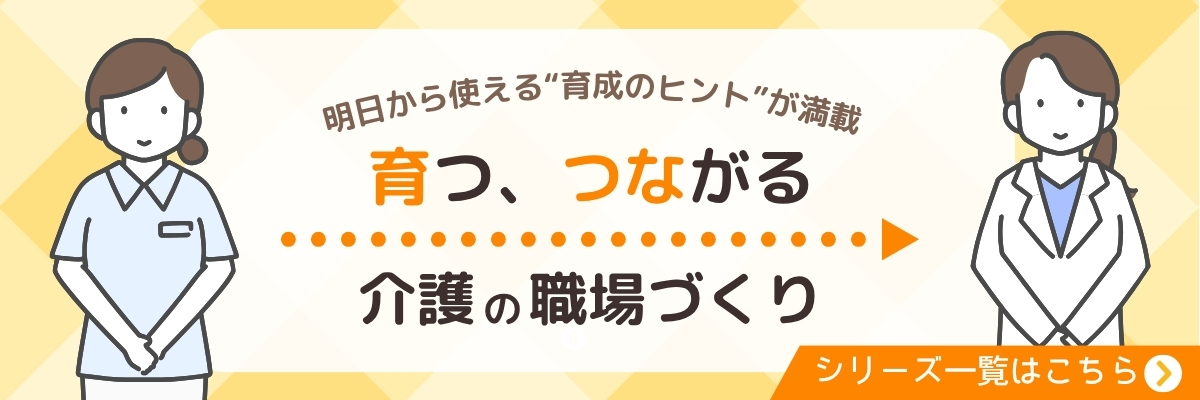介護リーダー(主任・サブリーダー・ユニットリーダーなど)に求められる役割は、年々変化しています。
以前のように「業務を管理し、指示する」だけでは、チームをまとめられない時代。今必要なのは、スタッフ一人ひとりに寄り添い、信頼関係を築きながら成果を出す“関係構築型リーダー”です。
【育つ、つながる、介護の職場づくり】第2回では、データから見る現場リーダーの課題と、 チームを支える1on1・チームビルディングの実践ポイントを紹介します。
なぜリーダーの関わり方が定着率を左右するのか
介護現場では、リーダーやサービス提供責任者が“人を支える側”として重要な役割を担っています。 しかし、現場の状況を見ると、リーダー自身が教育やフォローに十分な時間を取れないという課題が浮き彫りになっています。
公益財団法人介護労働安定センターの「令和6年度 介護労働実態調査」によると、「サービス提供責任者が担当業務に専念できる時間が足りない」と回答した事業所は60.3%、 「訪問介護員の指導・研修のための時間が確保できていない」という回答も30.8%にのぼります。
つまり、“人を育てたい”と思っていても、育てる時間や余力がない現実があるのです。
一方で、現場の離職要因を見てみると、「職場の人間関係に問題があったため」が24.7%と最も多く、その内訳では、
- 上司や先輩の指導や言動がきつかった・パワハラがあった(49.1%)
- 上司の業務指示が不明確、リーダーシップがなかった(36.2%)
- 仕事の進め方に関する意思疎通がうまくいかなかった(35.5%)
といった“上司・リーダーとの関係”に起因する要因が中心となっています。
つまり、リーダーの関わり方が、スタッフの定着を大きく左右しているということです。特に新人や若手ほど、日々の言葉かけやフィードバックの仕方に敏感に反応します。 リーダーが“支える姿勢”を持って関わるか、“指導する側”として距離を置くかで、「この職場に居続けたい」と思えるかどうかが変わってくるのです。
また、同調査では、 スタッフの仕事上の相談や指導を十分実施しているサービス提供責任者のもとでは、離職率が低い傾向が示されています。これは、コミュニケーションや相談体制の充実が離職防止に直結することを裏づけています。
さらに、事業所全体の取り組みとしても、 「職場定着に効果があった方策」として
- 人間関係が良好な職場づくり(29.5%)
- 職場内コミュニケーションの円滑化(30.9%)
が上位に挙げられています。
これらのデータが示すのは、介護現場の離職は“仕事のきつさ”ではなく、“人との関係の難しさ”から起きているという現実。 そして、その関係性を変える力を持っているのが、現場リーダーなのです。
リーダーが変わればチームが変わる―信頼を育む3つの実践法
リーダーが「支える力」を発揮できるようになると、チームの雰囲気は大きく変わります。とはいえ、いきなり関わり方を変えるのは簡単ではありません。
ここでは、現場ですぐに実践できる3つのステップを紹介します。小さな変化の積み重ねが、信頼と定着を生む第一歩になります。
① 指示型マネジメントから、伴走型マネジメントへ
スタッフに「こうして」「あれやって」と指示を出しても動かない――そんな時こそ、リーダーが変わるチャンスです。
伴走型マネジメントとは、相手と一緒に考え、動くリーダーシップ。スタッフに「どうしてできないの?」ではなく、 「どうしたらうまくいくと思う?」と問いかけることで、 本人の中に“自分で考えるスイッチ”が入ります。
現場でできる一工夫
- 新人や若手に仕事を任せるときは、「任せる前に一緒にやってみる」を1回入れる
- 注意を伝えるときは、「次にどうしたらいいか」を一緒に整理する
- 感情的に伝えず、「どんな状況だった?」と事実から話を始める
大切なのは、間違いを正すことよりも、次につなげること。「一緒に考えてくれる」と感じた瞬間、スタッフの心の距離はぐっと近づきます。
② 感情に寄り添いながら成果を出す「1on1の型」
介護現場では、業務の中でゆっくり話をする時間が取りにくいもの。だからこそ、短くても定期的な1on1(個別対話)が大切です。
たとえば、1人あたり月1回・15分だけでもOK。ポイントは、「評価」ではなく「雑談に近い安心の時間」にすることです。
1on1の実践例

「最近どう? 少し疲れてない?」
「この前の夜勤、大変だったでしょ。体調は大丈夫?」
「最近、新人さんのフォローもしてるけど、負担になってない?」
最初の数分は業務の話をしない時間として使うのがポイントです。仕事の調子よりも、「体調」「家庭」「趣味」「休日の過ごし方」など、相手が話しやすいテーマから入ることで、心の距離が縮まります。
目的は情報収集ではなく、安心して話せる空気をつくること。特に、疲れやストレスのサインを早めに拾う意識が大切です。

「それは大変だったね。あの時間帯、忙しかったもんね。」
「そっか…そう感じてたんだね。気づかなくてごめん。」
「ちゃんと頑張ってるの、分かってるよ。」
ここで大事なのは、共感のひとことを先に伝えること。アドバイスや改善の話は一旦置いて、まずは「大変だったね」「わかるよ」と感情を受け止めましょう。たったそれだけで、「この人は分かってくれる」と心が開きます。
沈黙があっても焦らず、うなずきながら聴いている姿勢を見せることが信頼につながります。

「次、同じような場面があったら、〇〇さんならどうしたいと思う?」
「何か私にできることある?」
「じゃあ、次のシフトのときに一緒にやってみようか。」
指示を出すよりも、問いかけで相手の考えを引き出すのがコツ。本人が自分の言葉で、次の一歩を口にした瞬間、主体性が育ちます。
うまく答えが出ないときは、「一緒に考えてみようか」「いくつか案を出してみよう」と並走するスタンスで。最後に「次の面談でまた様子を聞かせてね」と一言添えることで、継続的なフォローにつながります。
1on1で意識したい3つの姿勢
- 聴く: 話すより聴く時間を多く取る(7割聴く・3割話す)
- 認める: 小さな努力や変化にも「ありがとう」「助かってるよ」を言葉にする
- つなげる: 話した内容をメモに残し、次回「前回話してたあれ、どう?」と振り返る
たった15分の積み重ねでも、「気にかけてもらえている」という安心が、離職を防ぐ最大の力になります。
③ 離職率を下げる「チームビルディング」の実践例
チームづくりは、特別なイベントを開くことだけではありません。日常の中につながりをつくる工夫が、実は一番効果的です。
現場でできるチームづくりの工夫
- 毎朝の申し送りで「昨日助かったこと」を一言ずつ伝える
- 新人・ベテラン・パートなど立場の違う人をペアにして1日同行
- ミスが起きた時は「誰が悪いか」ではなく「どうすれば防げるか」を全員で話す
こうしたちょっとした共有の積み重ねが、「この職場は居心地がいい」という安心感を生み出します。
また、リーダー自身も「ありがとう」を口にする習慣をつけると、チーム全体のトーンが驚くほど変わります。
ポイント
- 感謝を伝えるリーダーがいると、チームの雰囲気は必ず良くなる
- 問題が起きたときほど、冷静に“仕組みで解決”を意識する
- 心理的安全性のあるチームでは、離職率が下がり、生産性も上がる
リーダー育成が、定着と現場改善のカギ
チームをまとめる立場にあるリーダーや管理職は、「どう指導するか」だけでなく、「どう関わるか」「どう聴くか」 が職場の安心感を左右します。
マネジメント&1on1研修では、部下との信頼関係を深め、チームの力を引き出すために、次のようなスキルや視点を実践的に学びます。
- 伴走型マネジメントへの転換
指示や命令に頼らず、部下と目線を合わせながら課題を解決する“伴走型”の関わり方を学びます。「自分で考え、行動できる人を育てる」ために、支援と期待のバランスを意識した対話の型を習得します。
- 感情に寄り添うフィードバックのスキルを磨く
部下の失敗や課題を責めるのではなく、前向きな行動を引き出す伝え方を体験的に学びます。成果だけでなく“努力”や“プロセス”を認めることで、心理的安全性を保ちながら成長を促すスキルを磨きます。
- 1on1ミーティングの型を身につける
「1on1=雑談」にならないよう、目的とゴールを明確にした構成で面談を行うコツを習得します。短時間でも効果的に“聴く・問いかける・共に考える”を実現する1on1の進め方を実践します。
- チームビルディングと関係構築の手法を学ぶ
職場全体の関係性を良くするために、メンバー間の相互理解を深めるワークを行います。立場や年次を超えて「安心して意見を言える関係性」を育むためのチームづくりの手法を体験します
実際の変化と受講者の声
ケース① 1on1を通じて、聴く姿勢が定着
ある企業では、若手の離職兆候を上司が拾えない課題を背景に、1on1の目的や進め方を学ぶ研修を実施しました。
受講後には「まずは聴くことが自分の役割だと気づいた」「話す時間より聴く時間を意識したい」との感想が多く、管理職層に“聴く文化”が広がるきっかけとなりました。
ケース② 心理的安全性の高いチームづくりへ
別の研修では、「自分との向き合い方」「他者との関わり方」をテーマにディスカッションを実施。まず自分の強みや価値観を振り返り、次にメンバーとの違いを認め合うことで、互いを理解し合う土台をつくりました。

「自己開示を通じて関係が近づいた」
「苦手な部分を補い合えるチームをつくりたい」
受講者からはこのような声があり、チーム全体で“支え合う意識”が芽生えたことが確認されました。
マネジメント&1on1研修は、「指導力」だけを高める研修ではありません。相手を理解し、関係を育てる力 を養うことで、メンバーが安心して意見を交わせる、信頼ベースの職場づくりを支援します。
一人ひとりが“話せる・頼れる・認め合える”チームをめざして、まずはリーダー自身の関わり方から見直してみませんか。
まとめ:関わり方ひとつで、現場は変わる
介護の現場では、日々の忙しさの中で、スタッフの声に耳を傾ける余裕がなくなってしまうことがあります。しかし、リーダーが少しだけ「関わり方」を変えるだけで、チーム全体の雰囲気は驚くほど変わります。
大切なのは、完璧に指導することではなく、相手を信じ、見守り、支える姿勢を持つこと。「うまくいかない時もあるけれど、一緒に考えよう」そんな言葉が、スタッフの安心と信頼を生み出します。
リーダーが変わると、現場が変わる。現場が変わると、スタッフが「続けたい」と思える職場になります。そしてその先にあるのは、利用者にとっても安心できる、あたたかな介護の現場です。
スタッフを支える“人を育てるリーダー”を増やすために。リーダーの関わり方を見直すきっかけとして、研修を活用してみてはいかがでしょうか。現場に寄り添う学びが、定着と安心を育てていきます。
若手も管理職も、成長を実感できる研修を


「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」
「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」
「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」
若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。
アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。
アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴
- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供
- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走
- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決
- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供
研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。