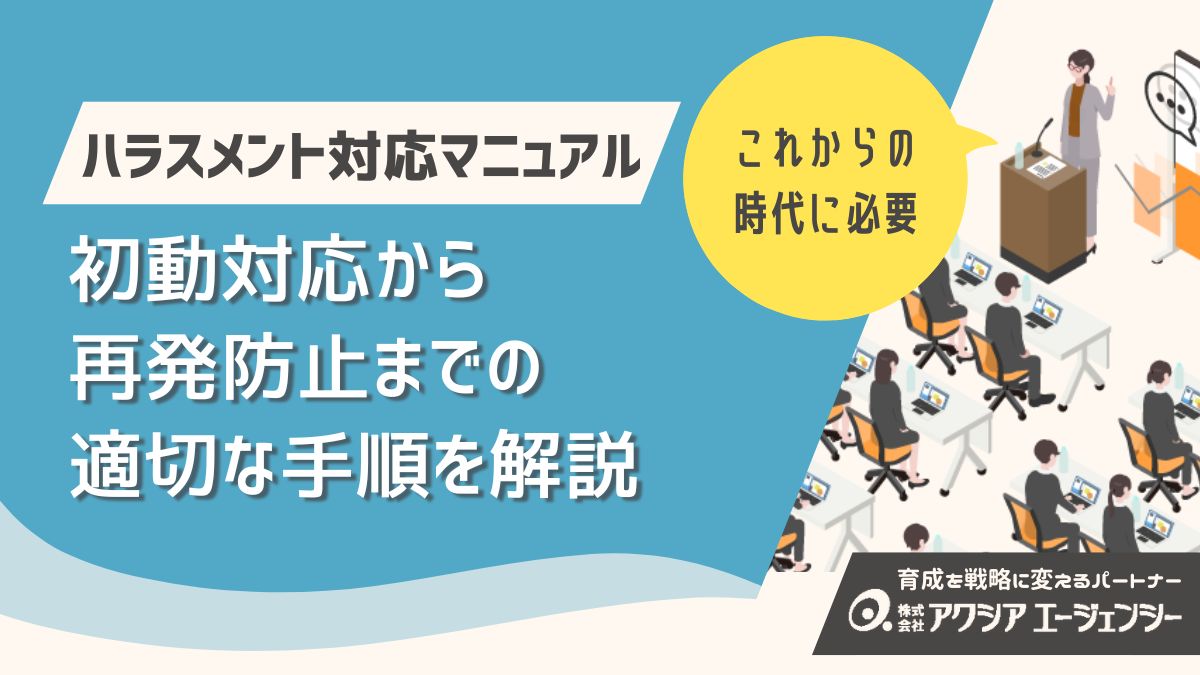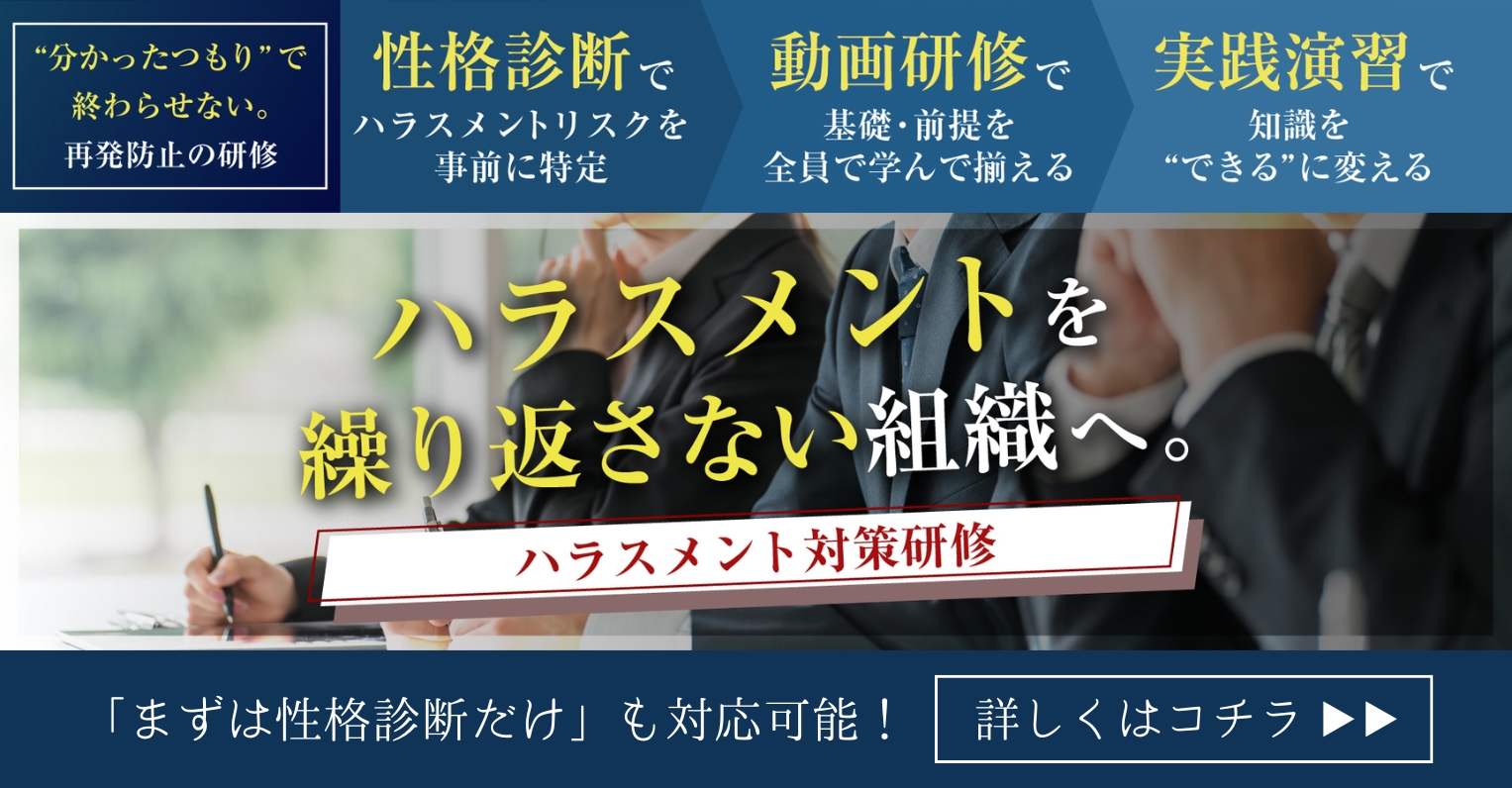近年、職場におけるハラスメントはますます多様化・複雑化しており、企業にとって深刻な経営リスクのひとつとなっています。パワハラやセクハラといった従来型の問題に加えて、リモートワークの普及や業務上のコミュニケーションツールの変化によって、より見えにくく、定義が曖昧なケースも増えています。そのため、「これは本当にハラスメントなのか?」「誰に、いつ、どのように対応をすればよいのか?」といった現場の戸惑いが後手に回り、深刻なトラブルや離職、訴訟に発展するケースが後を絶ちません。
とくに2022年4月からは、厚生労働省が定めたパワハラ防止措置が中小企業にも義務化され、社内ルールや相談体制の整備が強く求められるようになりました。人事部門や管理職は「法令遵守」という枠を超えて、職場で実際に起きうるハラスメントに対して即時に対応できる体制づくりと、社員が安心して相談できる環境の整備が必要不可欠な状況にあります。
しかし現実には、「相談窓口はあるが誰が対応するのか決まっていない」「ヒアリングをどう進めればよいか不明」「被害者と加害者の間でどこまで踏み込むべきかわからない」といった声が多く、人事担当者自身が“正解のない対応”に日々悩まされています。だからこそ今、多くの企業が注目しているのが、実務にすぐ使える『ハラスメント対応マニュアル』の整備と活用なのです。
本記事では、「ハラスメント 対応 マニュアル」という検索キーワードに込められた悩みや課題に応えるべく、企業が整備すべき対応の基本的なフローから、初動対応、事実確認、当事者ヒアリング、再発防止策まで、人事・管理部門が押さえるべき要点を体系的に解説していきます。
職場におけるハラスメントは、単なる一時的なトラブルにとどまらず、離職や退職、職場環境の悪化、ひいては企業そのものの信用低下にもつながる深刻な問題です。近年では、業務上のやりとりがきっかけで人間関係がこじれたり、対応の遅れが重大な結果を招いたりするケースも少なくありません。
人事担当者としては、「相談を受けたときに何から着手すればよいのか」「感情的になっている当事者にどう向き合うべきか」「制度としてルールは整備されているが、実際には機能していない」といった悩みに日々直面しているのではないでしょうか。
こうした状況を放置すれば、相談する側も対応する側も不安を抱えたままとなり、結果として問題が見過ごされたり、さらに複雑化してしまうおそれがあります。
だからこそ今、明確な手順と判断基準を持った“実務に使えるマニュアル”が必要とされています。ハラスメントを未然に防ぎ、相談や報告があった際にも落ち着いて対応できるよう、組織全体で備えておくことが、これからの企業に求められているのです。


なぜ今、企業に「ハラスメント対応マニュアル」が必要なのか?
職場のトラブルは“見えないところ”で進行している
職場におけるハラスメントのリスクは、企業規模や業種に関係なく、あらゆる組織に潜んでいます。従業員同士のコミュニケーションが複雑化し、価値観の多様化が進む中で、本人が悪意なく行った言動でも、受け手によっては深刻な被害と感じられるケースが少なくありません。
このようなトラブルは、相談として表面化しない限り把握が難しく、対応の遅れや判断ミスによって、問題が拡大するおそれがあります。特にハラスメントは、被害者が声を上げにくく、水面下で職場環境や人間関係を悪化させていることが多いのが現実です。
企業としては、早期発見と早期対応が不可欠であり、予防と事後対応の両面を見据えた仕組みを整えることが重要です。
制度があっても「現場で動けない」ことが最大の課題
多くの企業が、就業規則やハラスメント防止方針といった制度を整備しています。しかし、制度があることと、実際に問題が起きたときに正しく機能することは別問題です。
たとえば、相談が寄せられても「どこまで話を聞けばいいのか」「どう記録を残すべきか」「誰に報告し、どこまで共有すべきか」といった判断が、現場で属人的になってしまうことは少なくありません。その結果、対応が遅れたり、被害者・加害者の両方にとって不適切な対応となってしまい、企業にとって大きな損失を生む可能性があります。
制度と実務の“つなぎ目”を埋めるための仕組みとして、明確な対応マニュアルの必要性が高まっているのです。
ハラスメント対応は“企業リスク”のコントロールでもある
ハラスメントへの対応を誤ると、単に社内の問題にとどまらず、外部通報・訴訟・SNS炎上・離職・採用難など、さまざまな企業リスクへと発展する可能性があります。特に厚生労働省の指針に沿った対応が求められる中で、不十分な対応や曖昧な判断が露呈すると、行政指導や企業評価の低下にもつながります。
一方で、事前に標準化された対応手順を持ち、冷静かつ一貫した対応ができれば、企業への信頼性は高まり、職場の安定にも直結します。対応マニュアルは、法令遵守のためだけではなく、企業が自らを守り、従業員に安心を提供するためのリスクマネジメントツールでもあるのです。
組織全体で対応の質を“平準化”するために
属人的な対応に頼らない体制を整えることも、マニュアル導入の大きなメリットです。ハラスメント対応は、内容が複雑で精神的負荷も大きいため、担当者によって対応の質が大きく異なるリスクがあります。
対応マニュアルがあれば、誰が対応しても一定の水準を保つことができ、判断の軸が明確になり、個人の不安や負担を軽減することにもつながります。
また、相談者や関係者への配慮が組織的に担保されることで、職場全体に安心感と信頼感が広がり、ハラスメントが起きにくい職場環境の形成にもつながります。
「備えがある」ことが、組織の信頼をつくる
最後に重要なのは、対応マニュアルがあることで、企業としての姿勢を社内外に明確に示すことができるという点です。「私たちはハラスメントを決して見過ごさない」「何かあれば必ず対応する」という姿勢が、文書として、仕組みとして存在していることは、従業員のエンゲージメント向上にも直結します。
制度を整えるだけでなく、実際に動かせる体制をつくることこそが、これからの企業に求められる本質的な“対応力”なのです。
ハラスメント対応の前提として人事が押さえておくべき基本知識
ハラスメントの定義は「受け手の感じ方」が出発点
ハラスメントとは、特定の個人や集団に対する継続的または一時的な嫌がらせや不当な扱いを指しますが、その判断は常に「受け手の主観」が大きく影響します。つまり、発言や行動が“相手にどう受け取られたか”が基準となるため、加害者側に悪意や自覚がなくとも、成立してしまうことがあるのです。
この“受け手基準”の性質が、対応の難しさを増している要因でもあります。企業としては「意図がなければ問題ない」と判断するのではなく、相手が不快に感じる状況があったかどうかに注目して対応を考える必要があります。
パワハラ・セクハラ・マタハラなどの主な分類
人事が対応するうえでは、ハラスメントの分類ごとの特徴を理解しておくことが不可欠です。
- パワーハラスメント(パワハラ):職務上の地位や関係性を背景に、業務範囲を逸脱した叱責や無視、過大・過少な業務の強制など。
- セクシャルハラスメント(セクハラ):性的な言動や身体的接触、容姿や恋愛に関する不用意な発言など。
- マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠・出産・育児休業に関連する不利益な扱いや圧力。
- その他:SOGIハラ(性的指向・性自認)、ジェンハラ(性別役割に基づく偏見)、アルハラ(飲酒強要)など、多様な種類が存在します。
いずれも、行為そのものの「意図」や「文化的背景」ではなく、影響を受けた側の心理的・身体的負担が評価基準となるため、言動の背景を十分に精査する必要があります。
法的義務と企業に求められる対応の違い
2022年4月以降、厚生労働省の改正労働施策総合推進法により、中小企業も含めて「パワハラ防止措置の義務化」が適用されています。ただし、ここで誤解してはならないのは、義務化されたのは「教育研修の実施」ではなく、「相談体制の整備」や「再発防止のための措置」などの社内体制そのものだという点です。
つまり、制度や仕組みが形だけ整っていても、実際に相談があった際に対応できなければ、「義務を果たしていない」と評価される可能性もあるのです。その意味で、対応マニュアルの存在は「努力義務」ではなく、事実上の必須対応と言えるでしょう。
なぜ「制度だけ」では不十分なのか?
社内規定や指針の整備はハラスメント対策の第一歩ですが、それだけで職場環境が改善されるわけではありません。実際の相談対応や事後処理の場面で、担当者が迷わずに動けるかどうかが、制度の実効性を左右します。
また、ハラスメントの判断には常にグレーゾーンが存在します。行為者が善意だった場合や、双方に認識の違いがある場合など、対応のプロセスにおいて「納得感」や「公平性」をどう確保するかも人事にとって大きな課題です。そこで、制度を「生きた仕組み」として運用するためにも、定義・分類・リスク・対応原則といった基礎知識の共有が不可欠になります。
相談を受けたときの初動対応フローと注意点
初動対応で最も大切なのは「信頼の確保」
ハラスメント相談が寄せられたとき、人事担当者や窓口担当者がまず意識すべきは、相談者に安心感を与えることと、話を正しく受け止める姿勢を見せることです。初動の印象が悪いと、「この人に話しても意味がない」「会社は本気で対応しない」といった不信感が生まれ、真実の把握や対応の遅れ、職場全体の不安感に直結するリスクとなります。相談者の話を途中で遮ったり、先入観を持って判断を下したりすることは絶対に避け、一つひとつ丁寧に話を聞き、記録に残す姿勢が重要です。また、プライバシー保護を強調し、周囲に知られず対応されるということを明示することで、相談者の心理的なハードルを下げることができます。
事実確認は「公平性」を重視する
相談内容を受けたら、次に行うのが事実関係の確認作業です。ここでは、被害者だけでなく、加害者とされる側、さらには第三者の証言も含めて、複数の視点から冷静に情報を集めることがポイントです。
注意すべきは、あくまでも「事実」として確認できる内容に基づき判断を進めるということ。被害者の申し出だけで加害者を断定するような対応は、企業側のリスクになります。一方で、「聞き取りだけにとどまる」「何の処分も出さない」などの対応放棄も、被害者の不満や不信につながる可能性が高くなります。ここでのポイントは、情報を丁寧に収集し、記録に残しながら、公平性を保って進行することです。
社内関係者との情報連携は「最小限・最適化」が鉄則
事実確認の過程では、必要に応じて法務部門や顧問社労士、直属の上司などと連携を取る場面が出てきます。しかしこのとき、社内に不必要に情報を拡散してしまうと、関係者に心理的ストレスを与えたり、噂が広まって職場環境が悪化するリスクがあります。
連携はあくまで最小限に、かつ関係部署や担当者が適切に対応できる体制を整えることが求められます。マニュアルに関係者の範囲や役割分担を明記しておくことで、社内混乱を防ぐことができます。
相談内容の記録と管理は「証拠保全」の観点で対応を
相談内容やその後の対応については、必ず文書で記録に残すことが大原則です。曖昧な聞き取りやメモのない対応は、後になって「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。
また、記録には日時、場所、対応者、相談者の発言、対応経緯、関係者のヒアリング内容などをできるだけ詳細に記載し、保管方法やアクセス権限もマニュアルで定めておくことが必要です。企業としての説明責任を果たすためにも、この記録管理は極めて重要なステップとなります。
被害者・加害者それぞれに必要な配慮と対応の原則
被害者には「安心と尊重」を徹底する
ハラスメントの被害を訴えた従業員に対しては、まず安心感を与える対応が最優先です。訴えたことによって評価が下がったり、職場での立場が不利になることはないと明確に伝え、本人の尊厳を守る姿勢を示す必要があります。
被害者は、自分の発言や立場が組織にどう影響するか不安を感じていることが多く、対応の一つ一つに敏感に反応します。そのため、人事担当者は慎重に言葉を選び、非公開の場での面談・継続的なフォロー体制・柔軟な勤務対応(配置転換・休暇取得)などを通じて、状況に応じたケアを提供することが求められます。
また、被害者が精神的に不調をきたしているケースもあるため、産業医やカウンセラーとの連携も積極的に活用し、個別支援の方針をマニュアルに組み込んでおくことが重要です。
加害者とされる側にも「適正な手続き」を
一方で、加害者とされる従業員に対しても、無条件で加害認定を行うことは避けなければなりません。
被害申告があった段階では事実が確定しているわけではなく、企業としては中立の立場で調査を行い、公平な判断を下す義務があります。
加害者とされる側にも、言い分を述べる機会(弁明の機会)が保障されなければ、企業としての対応が不十分とみなされ、法的トラブルにつながるおそれがあります。そのため、ヒアリングや処分の検討にあたっては、事実確認に基づく根拠の明示・手続きの妥当性・懲戒基準の明文化が必要不可欠です。また、行為が認定された場合の対応においても、社内の処分基準に沿って過度・過小にならない判断を下すとともに、再教育や反省を促す機会を設けることが、組織としての成長にもつながります。
職場への影響を最小限に抑える配慮も不可欠
被害者・加害者双方への対応だけでなく、職場全体に対しても風評被害や分裂を招かないような配慮が必要です。特に、調査中の憶測や噂話が広がると、無関係の従業員にも不安や不信感を与え、職場環境そのものが悪化してしまいます。
こうした状況を防ぐためには、当事者のプライバシーを最大限守りながら、必要最小限の情報共有にとどめるとともに、必要に応じて管理職への対応方針の説明、部署内への落ち着いた説明を行うなど、社内広報的な視点も取り入れると効果的です。
また、職場内でハラスメントが起きた事実を重く受け止め、再発防止のための施策(教育・制度見直し・職場診断など)を速やかに実施する姿勢を示すことも信頼回復につながります。


再発防止に向けた教育と制度の整備、マニュアルの更新ポイント
教育・研修は“受けただけ”で終わらせない仕組みを
ハラスメントの再発防止には、形式的な教育ではなく「行動変容」を促す実践的な研修が欠かせません。年に一度の座学やeラーニングだけでは、職場内の価値観を変えるには不十分であり、従業員の理解度・態度・日常の行動にまで落とし込むには継続的かつ具体的な教育が求められます。
たとえば、加害者に悪意がないケースでは、「自分の行為がなぜ問題なのか」「なぜ相手が傷ついたのか」を理解できていない場合もあります。こうした誤解を防ぐには、ロールプレイやケーススタディを通じて“当事者の立場”を体感することが有効です。
また、管理職には「相談対応」「予兆への気づき」「部下同士の摩擦への介入」など、役割に応じた内容の研修を実施する必要があります。
制度は“使われること”を前提に設計する
ハラスメント防止における制度設計で陥りがちなのが、「相談窓口は設置しているが誰も利用していない」「対応フローがあるが現場では知られていない」といった“絵に描いた餅”状態です。これでは制度があっても、実際に役立たないばかりか、企業としての信頼も失われかねません。
そこで重要になるのが、制度の運用実態を定期的に点検し、「誰が見てもわかりやすい」構造に整えることです。たとえば、相談窓口の案内方法を社内イントラやポスターで周知したり、対応フローを図解で示して配布したりすることで、従業員が必要なときに迷わず利用できる環境を整えることができます。さらに、対応記録や相談件数などを分析し、制度が機能しているかを定期的に可視化する仕組みも有効です。
マニュアルは“作って終わり”ではない
ハラスメント対応マニュアルは、作成して終わりではなく、定期的な見直しとアップデートが必要です。職場の状況は常に変化し、新たなハラスメントの形態(SOGIハラ、オンラインハラスメントなど)や、厚労省の指針改定などへの対応も求められます。
見直しのタイミングとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 実際に相談やトラブルが発生したとき
- 法令やガイドラインの変更があったとき
- 職場環境や組織体制が変わったとき
- 年次評価や監査などの節目に合わせて
また、マニュアル改訂時には、対象部署や関係者に対する周知徹底・研修・説明会などもセットで実施することで、対応力の底上げにつながります。
外部の専門機関や社外リソースを上手に活用する方法
すべてを社内対応で完結しようとしない
ハラスメント対応は非常に繊細で複雑なケースが多く、人事担当者や管理職の判断だけで適切に進めるのは難しい場合もあります。特に、関係者の感情が高ぶっている場面や、対応によって訴訟リスクが高まるような局面では、社内だけで抱え込まず、早い段階で外部の専門家を巻き込むことが望ましいです。
自社内で処理しようと無理をすると、対応ミスや判断の偏りが起こりやすくなり、結果として企業としての信頼を大きく損なうリスクを抱えることになりかねません。
活用すべき外部リソースの例
以下のような外部リソースを、ハラスメント対応に組み込んでおくと、リスク回避だけでなく、社内の対応力強化にもつながります。
- 顧問社労士・弁護士:調査・ヒアリング内容の妥当性判断、懲戒処分に関する法的アドバイス、損害リスクの評価など。
- 外部相談窓口(EAP):従業員が匿名で専門家に相談できる体制を整備。心理的な障壁を下げ、社内に話しづらい内容の早期把握にもつながる。
- 産業医・カウンセラー:精神的ストレスの兆候や、継続的なメンタルケアが必要な場合に連携。安全配慮義務への対応にも有効。
- 第三者による調査代行サービス:客観性と中立性を担保したヒアリングや実態把握が可能。社内では判断が分かれがちなケースでも、信頼できる判断材料として活用できます。
社内制度に組み込むことで“仕組み化”する
外部リソースは「困ったときにスポットで使うもの」ではなく、社内制度やマニュアルの一部としてあらかじめ組み込んでおくことが大切です。たとえば、以下のような項目をマニュアルや相談対応フローに明記しておくと、現場での迷いを減らせます。
- 外部窓口の利用基準や連絡手順
- 外部専門家と社内との役割分担
- 相談者に外部相談先を提示する場面と方法
- トラブルの段階に応じた外部連携の判断基準
また、従業員にも「外部にも相談できる安心感」が伝わることで、内部通報制度の形骸化や“泣き寝入り”の防止にもつながります。
実務で役立つハラスメント対応マニュアルの具体例
ここでは、人事が日常業務で活用できるように、「マニュアルに書くべき具体的な文言」や「記載例」「テンプレート的な構成」を紹介します。相談を受けた瞬間から再発防止策の実行まで、対応の流れに沿って構成します。
1. 相談受付時の対応フロー(初動)
目的
安心して相談できる体制を整え、記録を正確に残す
記載例
- 相談者の不安を軽減する声かけ例:
→「お話いただきありがとうございます。内容は第三者に漏れないように厳密に管理いたします。」 - 対応者の姿勢に関する指針:
→ 否定・評価をせず、相談者の言葉をそのまま受け止め、遮らない。
→ 対応中は静かな個室で、可能であれば2名体制で対応する。 - 記録シート記入項目(テンプレ形式):
1. 相談者氏名/部署
2. 相談日・時間・場所
3. 相談内容(事実と感情を分けて)
4. 相手の氏名/関係性
5. 相談者の希望(処分希望/異動希望/記録のみ等)
6. 対応者氏名・記録者
2. 調査・ヒアリングの実施
目的
事実確認を中立的に行い、公平な判断材料を得る
記載例
- ヒアリング対象:
1. 相談者
2. 行為者(加害者とされる者)
3. 同席者・目撃者(第三者)
4. 上司など関係部署の責任者 - ヒアリング質問例(加害者向け):
→「この日、このような発言があったとされていますが、ご記憶はありますか?」
→「ご自身の発言・行動が、相手にどのように受け取られていたかお考えになったことはありますか?」 - 判断基準:
→ 「継続性があるか」「業務上の指導を逸脱していないか」「周囲の証言と整合性があるか」
3. 一時的対応・配慮措置(調査中)
目的
被害者・加害者ともに職場環境を一時的に安全に保つ
具体的対応例
- 加害者と被害者を業務的に隔離(可能であれば席替え・別部署への仮配置)
- 被害者の一時休職・在宅勤務措置(希望がある場合)
- 社内での接触制限通知(形式文例付き)
4. 処分の決定と実行
目的
社内ルールに基づき、行為の重大性に応じて対応する
記載例
- 処分検討時の材料:
→ 被害者の被害状況、加害者の反省の有無、過去の類似行為の有無、職場への影響 - 懲戒の種類(就業規則を引用):
→ 戒告、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇等 - 社内通知例(匿名・簡潔):
→「このたび、当社内においてハラスメント事案が発生し、就業規則に基づき適切な措置を講じました。」
5. 再発防止策の実施
目的
同様の事案を繰り返さないための仕組み作り
記載例
- 部署単位での研修実施(記録様式あり)
- 行為者への個別指導・再教育(内容と出席記録を保管)
- 全社員への周知活動(イントラ掲載/上司からのメッセージ配信)
- 職場風土改善のアンケート実施と対話型ミーティング
マニュアルの見直し・更新
更新タイミング例
- 対応事案が発生した後(必ず事後検証を行う)
- 年1回の制度点検時
- 法改正・ガイドライン変更時
- 顧問弁護士・社労士からの助言があったとき
更新履歴欄(例)
| 改訂日 | 内容 | 担当者 | 関係者共有済み |
| 2025/06/01 | ヒアリング項目追加 | 人事部K | ○ |
このように、マニュアルを具体的な記述・テンプレ・言葉の例まで整備すると、現場での迷いが減り、再現性の高い対応が全社で可能になります。
実践型研修を自社に導入するなら──信頼できる外部パートナーを選ぶことが鍵
ここまで、ハラスメント対応の重要性やマニュアル整備、職場文化改革の必要性について解説してきました。しかし、どれだけ制度やマニュアルが整っていても、「実際に職場の空気が変わる」ためには、人の行動が変わることが必要不可欠です。
そのためには、やはり「現場で起きていること」をリアルに捉え、当事者意識を持ちながら学べる“実践型”の研修プログラムの導入が効果的です。そして、それを形にするには、外部の信頼できるパートナーとの連携が非常に重要です。
アクシアエージェンシーのハラスメント研修は、実務に活かせる“行動定着型”
アクシアエージェンシーでは、【リアル集合研修】と【動画学習】を組み合わせたハイブリッド形式で、学びを職場での行動に落とし込むことに特化したハラスメント研修を提供しています。
- リアル研修では、ロールプレイやディスカッションを通じて、当事者視点と第三者視点の両方を体感
- 動画パートでは、繰り返し視聴できるコンテンツで基礎知識を定着
- 管理職と一般社員で異なるプログラム設計により、それぞれの立場に応じたリスク感度を育成
- 研修後のアンケートや実務チェックシートで“受けっぱなし”を防止
「社内では伝えづらい」「全社員に共通の理解を持たせたい」「行動に変化を起こしたい」──そうしたニーズにお応えできるプログラムです。
まずはお気軽にご相談ください
ハラスメント対応は、企業の信用・職場の安心・人材の定着に直結するテーマです。小さな不安や違和感を放置せず、外部の力を上手に活用しながら、今すぐできることから取り組んでみませんか?
アクシアエージェンシーでは、貴社の課題や業種・業態に合わせた最適な研修のご提案やお見積りのご相談を随時承っております。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
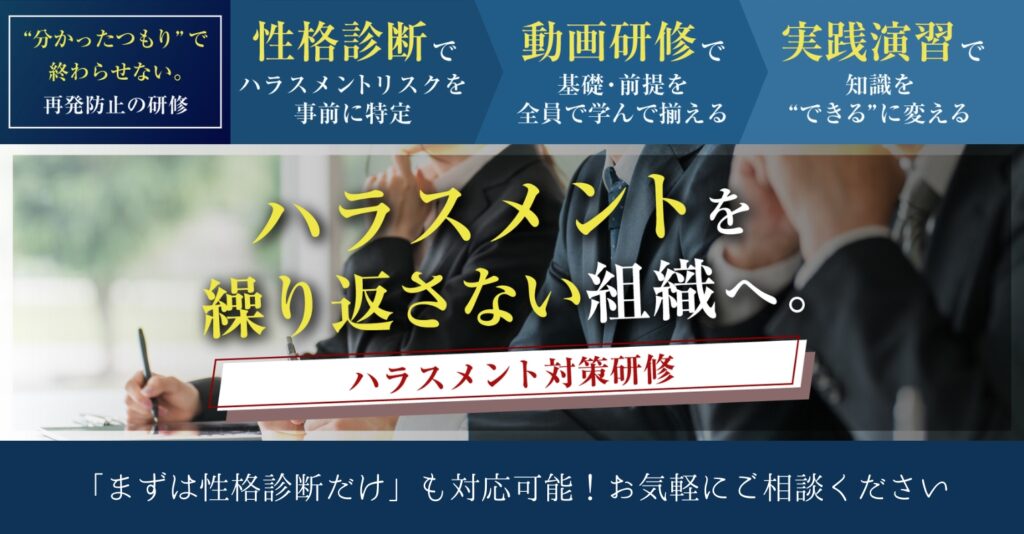

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。