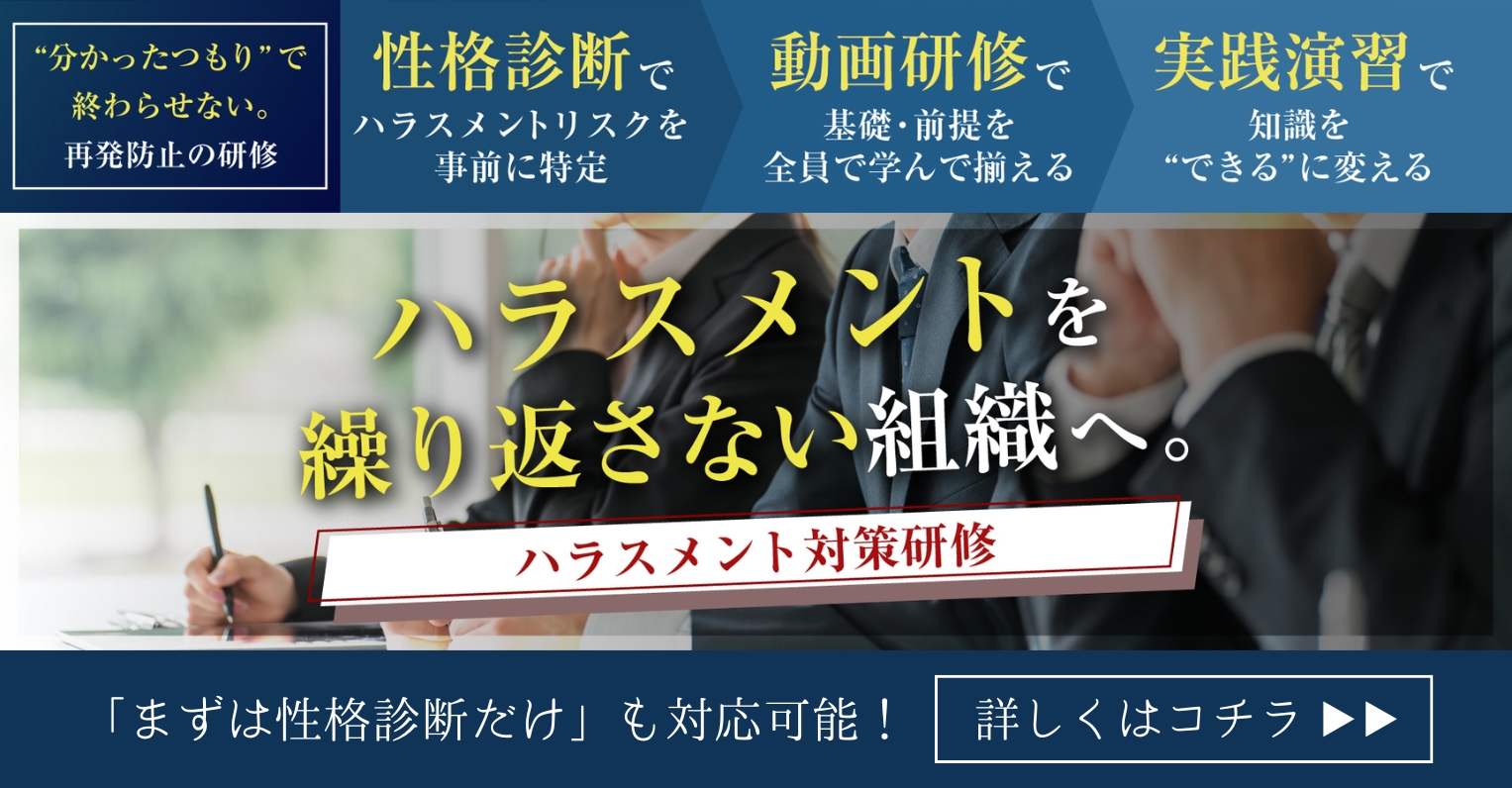多様な働き方が進み、世代・価値観・雇用形態が入り混じる現代の職場において、ハラスメントのリスクはより身近なものになっています。パワハラ(パワーハラスメント)やセクハラ(セクシュアルハラスメント)だけでなく、マタハラ(マタニティハラスメント)、カスハラ(カスタマーハラスメント)、SOGIハラ(性的指向や性自認に関するハラスメント)など、その種類は多岐にわたっており、企業としては「防止体制の構築」や「社内ルールの整備」といった制度面の対応に追われがちです。
そんな中、近年特に注目されているのが、講習や研修による“ハラスメント教育”の実効性です。法令対応として集合研修やeラーニングを導入していても、「本当に社員の意識は変わっているのか?」「現場の行動に落とし込まれているのか?」という疑問を抱く人事担当者は少なくありません。
実際、厚生労働省が定めるパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、企業には防止措置が義務付けられていますが、ハラスメント教育そのものは“努力義務”にとどまっています。にもかかわらず、実務上は明らかに講習の有無がトラブル防止に大きく影響しており、現場では「講習の質」「教育内容の設計」「社員の行動変容」が問われる時代に入ってきました。
特に問題となるのが、“やったこと”が目的になってしまう形式的な研修です。年に1度、義務感で参加するだけの座学講義や、マニュアルをなぞっただけの動画講習では、社員の記憶にも意識にも残りません。むしろ、「またこの内容か」とネガティブな印象を与えてしまい、結果として職場全体にハラスメントに対する“無関心”が広がる恐れさえあるのです。
さらに近年では、ハラスメントによる離職や職場不信から「退職代行サービス」を利用する若手社員が増えているという現象も見られます。ハラスメントが“相談しづらい空気”の中で放置されると、個の尊厳を傷つけるだけでなく、チームの信頼関係やエンゲージメント、生産性、企業のレピュテーションまでも損なわれてしまいます。
こうした背景から、人事担当者や教育部門にとっては「何を教えるか」だけでなく、「どう伝えるか」「どのように行動変容につなげるか」が求められています。つまり、ハラスメント教育は単なる情報提供ではなく、組織文化や職場環境、人間関係に深く関わる“組織開発”の一部であると言っても過言ではないのです。
本記事では、「ハラスメント教育で社員は本当に変わるのか?」という疑問に正面から向き合い、講習を“やって終わり”にしないための仕組み・手法・工夫について、多角的に解説していきます。実際に教育現場で成果を上げている企業の取り組みや、行動定着のポイント、管理職・若手社員それぞれに適したアプローチまでを具体的に紹介しながら、“意味のある教育”を実現するための考え方と実践例をお届けします。
「教育しているのにトラブルが減らない」「研修を受けさせたのに現場が変わらない」と感じている企業担当者にこそ読んでほしい、実践重視のハラスメント対策ガイドです。


なぜ今、ハラスメント教育の“実効性”が問われているのか?
講習を受けただけで意識は変わらない
ハラスメント研修や講習を実施している企業は多くあります。とくにパワーハラスメント防止措置の義務化以降、eラーニングや集合研修、外部講師を招いたセミナーなど、何らかの形で教育に取り組んでいる企業が増えました。しかし、「一通りやっているのにトラブルは減っていない」「相談件数は横ばい、もしくは増加傾向にある」と感じている人事担当者も少なくありません。
多くの場合、社員の行動や職場の雰囲気が変わらない理由は明確です。それは、受けた研修が“行動変容”につながっていないからです。たとえ法的な定義や類型、罰則の内容を覚えたとしても、現場でのコミュニケーション、部下指導、会議での発言などに反映されなければ、意味がありません。社員が自分ごととして捉えず、単なる“法令対応”と受け止めているようでは、教育効果は一過性にとどまってしまいます。
こうした形式的な研修が常態化すると、「また受けなきゃいけないのか」「今年もあの資料か」といった倦怠感が職場全体に広がり、ハラスメントに対する無関心、もしくは反発を生むリスクさえあるのです。
人事・管理職の多くが抱える「やっても変わらない」課題
人事担当者や管理職からよく聞かれるのが、「やっても変わらない」という声です。年1回の座学講習や動画視聴で形式的には教育を済ませているのに、職場での“空気”が変わらない。部下への指導や雑談の中に、今なおグレーな発言が残っている。相談窓口を設けても、報告はわずか。こうした状況が何年も続いている企業は少なくありません。
根本の問題は、教育の目的が“受講させること”になってしまっていることです。本来であれば、ハラスメント教育は社員の意識を変え、職場のコミュニケーションの質を高め、風通しの良い組織をつくる手段であるはずです。にもかかわらず、実務では「法令対応として済ませたい」「社内コンプライアンスとしての記録がほしい」といった“事務手続き的な発想”に流れてしまうことが多いのです。
また、研修の内容や形式が「社員に合わせたものになっていない」ことも、実効性を低下させる要因のひとつです。たとえば管理職にはマネジメントにおける言葉選びや叱責の境界線を伝える必要がありますし、新卒・若手社員には受け手としての感受性や相談の方法を教える必要があります。階層別・職種別のアプローチをせず、一律のコンテンツを全社に配信しているだけでは、行動にはつながりません。
「形だけの研修」が招く逆効果とは
さらに問題なのは、ハラスメント教育が「形だけ」になってしまうことで、逆効果を招くこともあるという点です。社員が「どうせ毎年やるだけの儀式」と感じてしまえば、研修そのものへの信頼が失われます。そしてそれは、本来重要であるはずの“職場での配慮”や“相談する勇気”を奪ってしまうことにもつながります。
たとえば、講習の冒頭で「この研修は義務なので参加してください」と言われただけで、参加者の意識は下がります。あるいは、相談事例が「どこか他人事」でリアリティに欠けていれば、自分の職場とは関係ないと感じてしまうでしょう。これでは、研修を通じて社員の行動を変えるどころか、“やっているから大丈夫”という錯覚を生み、実態の改善を遠ざけてしまうのです。
ハラスメント防止において最も重要なのは、「あの人が悪い」ではなく「どうすれば未然に防げるか」という全体視点です。これは社員一人ひとりの意識だけではなく、組織の価値観や制度、上司のマネジメント姿勢にも深く関わります。教育は、その価値観や姿勢を共有し、文化として浸透させる起点であるべきなのです。
だからこそ、ハラスメント教育の実効性を高めるには、ただ教えるだけでなく、社員が“体験し、気づき、行動する”ための設計が求められるのです。
教育で行動が変わる仕組みとは?心理・行動科学から考える
「知識の習得」だけで人は動かない理由
多くの企業が行うハラスメント研修では、まず法律の定義や6類型、懲戒規定といった“知識のインプット”に重点が置かれがちです。もちろんこれらは教育の基礎として不可欠ですが、知識だけでは行動は変わらないということを理解しておく必要があります。
人の行動変容には、「知識・理解」→「気づき・納得」→「習慣化・実践」というプロセスがあり、単なる情報提供では、この中の最初のステップしか踏めていません。心理学や行動科学の視点では、人がある行動を自発的に変えるためには、その行動の必要性と自分との関係性に“納得感”を得ることが不可欠だとされます。
たとえば、「威圧的な口調はパワハラにあたる場合がある」と講義で学んだだけでは、「でも、部下がだらしないときは強く言わないといけない」と正当化してしまう人もいます。このように、知識と現場の実感とのギャップがあると、行動変容は生まれません。知識が“自分ごと化”され、初めて変化の第一歩が始まるのです。
「行動の定着」に必要な3つの条件(理解・納得・習慣化)
行動科学の研究からは、ハラスメントのような“意識を変える”教育を成功させるには、以下の3つの要素が必要だとされています。
- 理解:法律や制度、リスク、背景を正しく知る
- 納得:自分の経験や職場の状況と結びつけて「なるほど」と思える
- 習慣化:現場で繰り返し意識し、日々のコミュニケーションで実践できる
この3つがすべて満たされたとき、初めて“教育が定着した”と言えます。逆に、理解はしていても納得していなかったり、納得していても実践の機会がなかったりすれば、教育の成果は可視化されません。
たとえば、研修で「相手の感じ方がハラスメントかどうかを左右する」と学んでも、それを意識する場面が職場で設定されていなければ、「知っているけど、何を変えればいいのか分からない」となってしまいます。現場で“行動に落とし込む仕組み”が必要なのです。
教育を職場文化につなげるために必要なこと
行動変容が個人にとどまると、教育効果は一時的になります。重要なのは、学んだことが“職場全体の文化”として定着するかどうかです。ここでカギを握るのが、「研修の内容が職場の日常に結びついているか」という点です。
たとえば、研修後に上司が部下との1on1で「最近、職場で困っていることある?」と話を振る、朝礼で「ハラスメント防止のためにこういう発言に注意してみよう」と共有する、などの**行動の促進装置(ナッジ)**が組織全体で仕掛けられるかが、文化として根づくか否かを左右します。
また、制度としても「相談できる窓口」「記録を残せるフロー」「匿名報告の選択肢」など、教育後に実際に社員が動きやすくなるインフラ整備が求められます。研修と制度が連動していなければ、教育は一時的なイベントにとどまり、期待される効果は得られません。
さらに、「なぜこの教育をするのか」という企業側のメッセージ性・スタンスも非常に重要です。社員は講師の話だけでなく、企業の姿勢をよく見ています。理念や経営者の言葉にハラスメントに対する明確な意思表示があれば、それが全体への浸透を強く後押しするのです。
講習を“やりっぱなし”にしない、行動定着の実践アイデア
動画×集合のハイブリッド型で反転学習を促す
近年、多くの企業で導入されているのが「ハイブリッド型研修」です。これは、講義形式のインプットを動画やeラーニングで事前に行い、集合研修ではケースディスカッションやロールプレイなどアウトプットを中心に実施する形式です。いわゆる“反転学習型”の設計であり、知識を理解したうえで、行動への橋渡しを行うスタイルとして注目されています。
この形式の利点は、参加者があらかじめハラスメントに関する定義や分類、法的な位置づけなどを把握してから集合研修に臨むため、限られた時間の中で実践に近いテーマを扱えることです。管理職には「指導とパワハラの境界線をどこで引くべきか」、一般社員には「どんなときに相談すべきか、何を気にするべきか」など、役割に応じたディスカッションが可能になります。
また、動画は研修後も繰り返し視聴できるため、復習や他社員への波及にも活用でき、学習の定着と組織内展開の両方を担保できる点でも有効です。とくに多拠点・シフト制の職場では、全員を同じタイミングで集合させることが難しいため、この柔軟性は大きな武器になります。
ケース討議・ロールプレイによる内省と対話の促進
知識だけでなく“気づき”や“納得”を引き出すためには、実際の職場に近いシチュエーションをもとにしたケース討議やロールプレイが欠かせません。とくに管理職研修では、「この発言はパワハラか?指導か?」といったグレーゾーンの対応を扱うと、参加者から活発な意見が出やすく、実務の悩みに直結します。
ロールプレイでは、上司役・部下役・観察者といった立場を体験しながら、自分の言葉がどう受け止められるか、相手の立場でどう感じるかといった視点の転換と共感の促進が図られます。これにより、「そんなつもりはなかった」が、「そう受け止められるかもしれない」に変わり、内省が深まる設計になります。
また、事例をただ見て判断するだけでなく、「自社の文化ではどう扱われるのか」「自分のチームでは何が課題か」といった、参加者自身の文脈で考えるワークを取り入れることで、汎用的な理解から実践的な行動へとつなげることが可能です。
受講後のフォローアップと現場マネジメントとの連携
ハラスメント講習を“やりっぱなし”にせず、行動定着を図るためには、受講後のフォローアップ設計が極めて重要です。たとえば、研修後1ヶ月以内に「振り返りワークシート」を提出させる、上司が1on1で感想をヒアリングする、チェックリスト形式の自己評価を共有するなど、行動を再認識する場を設けることで、記憶と行動の定着率は大きく向上します。
また、現場のマネジメント層が「学んだ内容を言語化して再発信する」ことも有効です。たとえば朝礼やチームミーティングで、「昨日のハラスメント研修で印象に残ったのはこのポイントでした。だから今後こうします」と語るだけでも、チーム内の“学びの空気”が共有されやすくなります。
このように、人事部門だけでなく、マネージャーやリーダー層が研修内容を自分の言葉で扱うことが、行動変容を“個人の努力”にとどめず、職場単位での文化形成へと押し上げる鍵になります。
さらに、中長期的には「定期的なセルフチェック」「相談窓口の利用状況の確認」「研修受講後の変化に関するアンケート」などを通じて、教育効果の測定と改善サイクルの運用も取り入れることが望ましいでしょう。


管理職・若手・中堅…層別で変える、ハラスメント教育の戦略
管理職には「指導とパワハラの違い」を体感させる
ハラスメント防止教育において、最も重点的に対応が必要な層の一つが「管理職」です。管理職は日常的に部下を評価し、指導し、時には注意や叱責も行う立場にあります。そのため、“適切なマネジメント”と“パワハラ”の境界線が曖昧になりやすいという特性を持ちます。
とくに成果主義・目標管理が重視される企業文化では、「結果を出すために多少厳しい言い方をしても仕方ない」と考える管理職もいます。しかし、その言動が相手にとっては人格否定と受け取られたり、継続的な圧力と感じさせてしまう可能性があるのです。
したがって、管理職向けの研修では、「自分の行動がどう受け止められるか」という“受け手視点”を疑似体験できるプログラムが不可欠です。ロールプレイやケース討議を通じて、「部下の立場ではどう感じるか」を内省する機会を設けることで、これまで気づけなかった自分の言動に変化が生まれます。
また、指導の仕方ひとつでも、事実を淡々と伝えるのか、人格を否定する言い方になるのかで、相手の受け止め方は大きく異なります。研修の中では、言葉の選び方・タイミング・場面の設定など具体的なマネジメントスキルにまで踏み込むことで、「ハラスメントにならない指導の型」を習得できるようにするのが効果的です。
若手には「受け手としての感性」を育てる
若手社員の研修では、加害者としての視点だけでなく、被害者・受け手としての意識形成が重要です。というのも、社会人経験が浅い若手は、「これはハラスメントなのか?」「相談してもよいのか?」という判断がつかず、我慢したり、自分が悪いと思い込んでしまう傾向が強いためです。
また、近年では「指導されること=ハラスメント」と過度に感じてしまう若手も存在します。こうした認識のズレは、職場の信頼関係を損ない、不要な誤解や対立を招くことにもつながります。だからこそ、若手社員には「どんな言動が不適切なのか」を知るだけでなく、「相談してもよい」「話してよい」という安心感と判断基準を育む教育が必要です。
そのためには、単なる情報提供ではなく、ケーススタディや先輩社員の実体験を用いた対話型の研修が効果的です。また、相談窓口の仕組みや、社内における相談事例などを共有することで、「困ったら動いていい」「動ける場所がある」という意識づけができます。さらに、SNSやチャットなど非対面コミュニケーションでのトラブルが増える現代において、テキストコミュニケーションにおける配慮や感情のズレについても扱うことで、より実践的な理解を深めることができるでしょう。
中堅層には「組織の潤滑油としての対話力」を磨く
中堅社員は、組織において上からも下からも期待される“潤滑油”のような存在です。しかし、立場のあいまいさゆえに、上司と部下の板挟みになったり、現場のハラスメントに気づいても動けないことがあります。だからこそ、中堅層には「気づき・介入・橋渡し」のスキルと意識を高める教育が求められます。
ハラスメントの兆候を早期に察知し、上司や人事に相談できる“つなぎ役”になれるかどうかで、職場の安全性は大きく変わります。また、問題が起きた後ではなく、起きる前の雰囲気を察知して“対話”で関係性を整える力が、ハラスメント予防のカギとなるのです。
この層には、「どうすれば声をあげやすい場を作れるか」「仲介するときの立ち振る舞い」など、実際のケースに即した実践的な対処法を伝えることで、職場の“潤滑剤”としての役割を発揮しやすくなります。
さらに、チームリーダーやプロジェクトマネージャーとして部下を持つ立場になるケースも多いため、管理職研修のエッセンスも段階的に含めていくことが効果的です。こうすることで、将来的なマネジメント層としての意識も育ち、継続的なハラスメント予防文化の構築につながります。
ハラスメントを放置することのリスク
ハラスメントは“業務上の重大リスク”である
ハラスメントの問題は、単に「個人間の感情トラブル」ではありません。見逃したり、対応が遅れたりした場合、業務の停滞・退職の連鎖・組織の機能不全にまで発展する深刻なリスクです。実際、パワハラを受けた社員が心身の不調を訴え、長期休職や退職に至るケースは多く、企業としての損失は計り知れません。
また、近年では“制度的な放置”も問題視されており、「規定があるだけ」「相談窓口が形だけ」で、実質的に機能していない企業も少なくありません。厚生労働省の指針では、ハラスメントに関する社内ルールの整備、周知・啓発、相談体制の構築、再発防止措置などを講じることが求められており、形式だけでなく実効性が問われる時代になっているのです。
業務上のリスク管理としても、ハラスメントは重大な要因です。トラブルが起これば、社内調査や人事対応、場合によっては訴訟や労働基準監督署への対応など、多くのリソースが割かれることになります。加えて、その間の業務は停滞し、チームのパフォーマンスや士気にも大きな影響を及ぼします。
職場環境の悪化は、同僚・関係者全体に波及する
ハラスメントの被害者はもちろん、その周囲にいる同僚や関係者にまで悪影響が及ぶ点も重要です。たとえば、ある管理職の威圧的な発言を日常的に目にするだけで、「あの人には何も言えない」「自分も怒鳴られたらどうしよう」といった心理的不安が広がります。これにより、意見が出なくなる・報連相が減る・新しい提案が出なくなるといった“沈黙の職場”が生まれてしまうのです。
また、見て見ぬふりをしてしまう職場では、やがて「この会社は社員を守ってくれない」という不信感が蔓延します。この状態が続くと、表面上は穏やかでも“心理的安全性”が失われた職場が出来上がり、人間関係は希薄化し、エンゲージメントは著しく低下します。
さらに、人間関係の悪化によって情報共有の質が下がったり、連携ミスが増えたりと、本来の業務遂行にまで影響が及ぶのです。職場環境の健全さは、組織の生産性に直結しているという点を軽視すべきではありません。
退職・転職・退職代行サービスの増加につながる
最も分かりやすく、そして取り返しのつかないダメージが「社員の退職」です。ハラスメントを受けた社員が、職場に相談できる環境がなかったり、対応が不十分だった場合、自ら“退職”という選択を取る可能性が高まります。しかも、それが「自己都合退職」として処理されてしまうケースも多く、企業としての責任が見えにくくなるという問題があります。
こうした状況を放置すると、「社員が辞める理由が見えない」「採用しても定着しない」「若手が育たない」といった連鎖が起き、企業の人材戦略そのものが崩れてしまいます。
近年では、ハラスメント被害を理由に退職代行サービスを利用する社員も増えており、社内での対話が不可能と判断された職場は、今後の採用活動やブランディングにも影響を及ぼす恐れがあります。SNSや口コミサイトによって「人を大事にしない会社」と拡散されれば、優秀な人材の確保も困難になりかねません。
このように、ハラスメントを放置することは、制度・人事・経営・風土といったあらゆる観点で企業にとっての大きなリスクになるのです。早期の発見・対応はもちろんのこと、「そもそも起きない状態をつくる」ための教育と組織づくりが欠かせません。


アクシアエージェンシーのハラスメント研修とは?
ハラスメントのない職場づくりは、制度や通報窓口だけで実現できるものではありません。何より重要なのは、社員一人ひとりの意識と行動を変えていく教育設計です。そうした中、アクシアエージェンシーでは、実践的かつ継続的な行動変容を目的とした「ハラスメント研修プログラム」を提供しています。
本研修は、一般的な知識習得型の講習とは異なり、「インプットとアウトプットを繰り返す構成」「現場課題に合わせたシナリオ」「講師によるフィードバック」によって、受講者自身が“気づき・納得・実践”へと進んでいける設計になっています。研修形式も動画学習+集合研修のハイブリッド型で、各層の働き方やスケジュールにも柔軟に対応可能です。
たとえば動画では、パワハラ・セクハラなど6類型の法的定義や最新の相談事例を短時間でインプットし、集合研修ではその内容を前提に、職場で起きうるグレーな場面をもとにしたディスカッション・ロールプレイを実施。これにより、「わかる」から「できる」へと理解が深まり、職場での具体的な行動変化につながります。
また、対象者も管理職・若手・中堅と階層別に設計されており、それぞれの立場や役割に応じたテーマが扱われます。たとえば管理職向けでは「指導とハラスメントの違い」、若手向けには「相談する力と気づき」、中堅社員には「つなぎ役としての対話力」など、実務に即したテーマを重視しています。
さらに研修後には、受講者アンケートや行動宣言ワークなどを通じたフォローアップ体制も整っており、単発の研修で終わらせず、職場全体への浸透を促す設計になっています。研修担当者には、受講者の反応をまとめた報告書や、改善提案もフィードバックされるため、継続的な施策立案にもつながります。
「研修をやっても現場が変わらない」と悩んでいる企業や、「社員が真剣に向き合う研修がしたい」と考えているご担当者の方は、ぜひアクシアエージェンシーのハラスメント研修をご検討ください。知識ではなく行動を変える研修で、安心と信頼のある職場づくりを一緒に実現していきましょう。
まとめ:行動が変わるハラスメント教育が、職場の未来を変える
ハラスメントは、企業にとって避けては通れない課題でありながら、対応が後手に回りがちなテーマでもあります。「研修はしているが現場は変わらない」「相談件数が減らない」「退職者が出てから気づいた」といった声に象徴されるように、制度の整備や講習だけでは実効性が伴わない現実があります。
しかし、この記事で紹介してきたように、ハラスメント教育は“知識の伝達”で終わるものではなく、社員の意識と行動を変えるための、戦略的な組織開発の一部としてとらえることが重要です。そのためには、反転学習や実践型ワーク、階層別設計、フォローアップなどを取り入れた、「行動定着」を目的とする設計思想が欠かせません。
また、ハラスメントを放置することで企業が抱えるリスク(業務への支障、職場環境の悪化、人間関係の崩壊、退職・離職の増加、ブランドイメージの低下など)は、想像以上に広範かつ深刻です。“あってはならない”ではなく、“起こさない仕組みをつくる”ことが今、求められています。
アクシアエージェンシーでは、こうした課題意識に基づいた、実践型のハラスメント研修を提供しています。「伝える」ではなく「変える」を軸にした研修設計で、企業の未来を支える“安全で風通しのよい職場づくり”をサポートしています。
人事として、社員の安心・定着・成長を実現したい方、制度だけでなく“人の行動そのもの”に向き合いたい方は、ぜひこの機会に研修のあり方を見直してみてください。行動が変われば、職場が変わります。そして職場が変われば、組織の未来は確実に良くなります。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
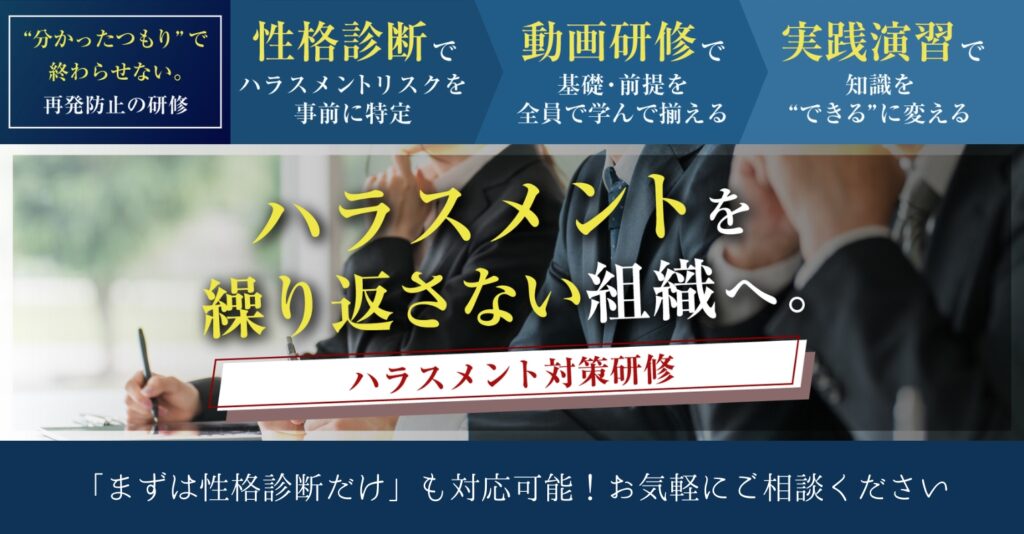

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。