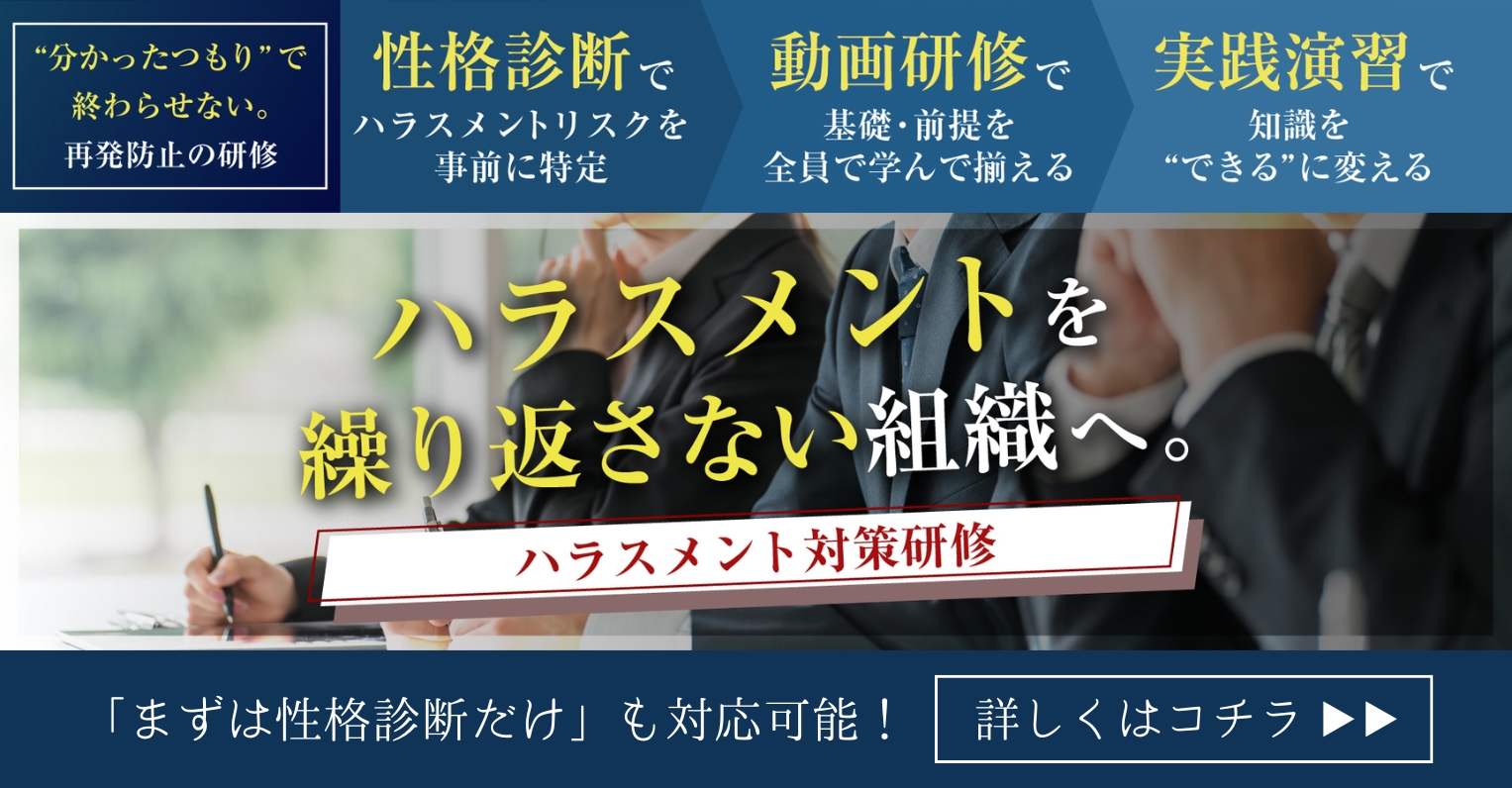職場におけるハラスメントは、働く労働者の心身の健康を損なうだけでなく、会社全体の信頼性や生産性にも深刻な影響を及ぼします。近年、法改正や社会的な関心の高まりを背景に、企業としてハラスメント防止への取り組みがますます不可欠となっています。しかし、制度の整備だけでは、事実関係に基づいた適正な対応ができるとは限りません。
重要なのは、組織文化やコミュニケーションの在り方を見直し、従業員一人ひとりが安心して働ける環境を実現することです。本記事では、ハラスメントの定義や発生要因、会社として実行可能な防止策、関連する事業の法的枠組み、外部リソースの活用法などを紹介し、具体的な解決のヒントをお届けします。人事担当者をはじめとする企業関係者にとって、実務に役立つ実践的なガイドとなることを目指しています。


なぜ今「ハラスメント防止」が重要なのか
職場におけるハラスメントは、個人の尊厳を傷つけるだけにとどまらず、職場環境や組織のパフォーマンス全体にも深刻な影響を与えます。特に、近年は働き方の多様化や価値観の変化が進み、ほんの少しのすれ違いや無意識の言動が、大きな問題へと発展するリスクが高まっています。
こうした状況の中、企業がハラスメント防止に向けた取り組みを強化することは、もはや選択肢ではなく「当然の責務」となりつつあります。本章では、なぜいまハラスメント防止がこれほどまでに重要視されているのか、その背景や企業が直面する課題について、より深く掘り下げていきます。
労働環境の変化と法改正の背景
現代の日本社会では、労働環境が急速に変化しています。少子高齢化に伴う労働人口の減少は避けられない現実であり、企業にとっては、限られた人材をいかに確保し、定着・活躍させるかが経営の最重要課題となっています。また、働き方改革やダイバーシティの推進により、年齢、性別、価値観の異なる多様な人材が共に働く機会が増え、職場のコミュニケーションや人間関係に対する配慮も一層求められるようになっています。
このような状況のなか、職場におけるハラスメントの問題が大きく取り沙汰されるようになりました。ハラスメントは、被害者の尊厳を傷つけるだけでなく、業務上の支障を引き起こし、企業の信頼やブランド価値にまで影響を与えかねません。さらに、SNSなどで職場の内情が外部に拡散されるリスクもあるため、以前よりもはるかに迅速かつ的確な対応が求められる時代となっています。
こうした社会的背景を受け、2020年に施行された改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)では、事業主に対してパワーハラスメント防止措置を講じることが義務化されました。2022年4月からは中小企業も対象に含まれ、もはや「規模が小さいから」「うちには関係ない」という言い訳は通用しません。企業がこの法的義務を怠った場合、被害者から損害賠償を求められるだけでなく、行政指導の対象にもなり得ます。つまり、ハラスメント防止は「企業が主体的に取り組むべき社会的責任」であると同時に、「法令遵守の一環」としても強く位置づけられているのです。
若手社員の育成に与える影響
職場でハラスメントが発生すると、被害を受けた社員が受けるダメージは計り知れません。中でも深刻なのは、成長途中にある若手社員に与える影響です。彼らはまだ社会人経験が浅く、上司や先輩からの言葉や態度を敏感に受け止めがちです。何気ない発言が傷つけてしまうこともあり、ハラスメントを受けたと感じると強い不信感を抱き、仕事へのモチベーションを著しく損ないます。
たとえば、仕事のミスに対する厳しい叱責がパワハラと受け取られた結果、本人が体調を崩して休職に至った、という事例も少なくありません。また、マタハラやSOGIハラスメントといった、個人のライフステージや属性に関わる言動は、当事者に深い精神的苦痛を与えるばかりでなく、周囲の社員にも「この職場は安全ではない」という印象を与えることになります。
このような悪循環が生じれば、職場の雰囲気は悪化し、離職者が相次ぎ、組織の知見やノウハウが蓄積されないという状態に陥ってしまいます。育成どころか、継続的な組織運営さえ難しくなるのです。企業が将来にわたって人材を育て、競争力を維持していくためには、ハラスメントのない安心・安全な職場環境を整えることが不可欠です。
管理職が抱える“指導できない”問題
一方で、ハラスメントを「してはいけない」という意識が高まるにつれ、現場の管理職が抱える新たな課題も浮き彫りになっています。それは、「どこまでが適切な指導で、どこからがハラスメントになるのかが分からない」という戸惑いです。実際、部下の成長を願って厳しく指導したつもりが、結果としてパワハラと受け取られ、社内トラブルに発展するケースも存在します。
このような状況に陥ると、管理職は「言わない方が無難だ」と育成に消極的になりがちです。部下からの信頼を失いたくないがために、注意を避けるようになり、結果として育成機会が失われてしまいます。この“指導できない”というジレンマは、個人の育成だけでなく、組織全体のマネジメント力を低下させる大きな要因となります。
管理職が安心して育成に関われるようにするには、組織として明確な指導の基準や行動ガイドラインを整備することが求められます。さらに、指導とハラスメントの違いを丁寧に理解できる研修や、相談できる仕組みを整えることで、「ハラスメントを恐れて関わらない」から「適切に関わる」への意識変革を促すことが可能です。
職場におけるハラスメントの定義と種類
職場で発生するハラスメントにはさまざまな種類があり、その定義や特徴を正しく理解することが防止の第一歩です。ハラスメントは、単に不快な言動だけでなく、相手に精神的・身体的な苦痛を与え、職場環境を悪化させる重大な行為です。特に近年は、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに加えて、妊娠・出産に関わるマタニティハラスメントや、顧客からの不当な言動によるカスタマーハラスメントなど、新たな形態にも注目が集まっています。
この章では、それぞれのハラスメントの定義と具体例を通じて、どのような行為が該当し、どのような影響を及ぼすのかを明らかにします。
セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場において性的な言動により相手に不快感や不利益を与える行為のことを指します。性別を問わず、当事者が性的な対象として扱われることによって、職場内での人間関係や業務に悪影響を及ぼす点が特徴です。
たとえば、身体的特徴に対する発言、恋愛や結婚に関する私的な質問、性的な冗談やからかい、不必要な身体接触などが挙げられます。実際には、上司が「今日は色っぽいね」といった言葉を繰り返したことで、部下が強いストレスを感じて体調を崩したというような事例もあります。また、社内SNSやチャットツールを通じて性的な画像や動画を送るといった行為も、業務外であってもセクハラに該当するケースがあります。
このような行為は、単なる不快感だけでなく、被害者のメンタルヘルスに深刻なダメージを与え、場合によっては仕事への支障や離職といった結果を引き起こします。さらに、職場全体の雰囲気が悪化し、他の社員にも悪影響が及ぶことも少なくありません。セクシュアルハラスメントは、個人の尊厳を傷つける重大な行為であると同時に、職場の健全性を損なう要因であるという理解が必要です。
パワーハラスメント
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場における地位や人間関係の優位性を背景にした言動によって、相手に身体的または精神的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為を指します。加害者はしばしば「業務指導の一環」と主張するものの、実際には業務上の適切な指導を逸脱しており、相手の尊厳や意欲を著しく損なう点に特徴があります。
具体的な行為としては、部下に対して「能力がない」「こんなこともできないのか」といった暴言を繰り返す、業務に支障をきたすほどの過剰な仕事を押し付ける、あえて仕事を与えずに孤立させる、あるいは業務とは無関係な私用を強制するなど、多岐にわたります。これらの行為は、単発であってもその内容や状況によってはパワハラと認定される場合があります。
たとえば、ある中堅企業では、上司が部下に対してミスを執拗に責め続け、昼休みにも呼び出して叱責した結果、部下が出社できなくなるほどの精神的ダメージを受けたという事例がありました。このように、パワハラは被害者の心身に深刻な影響を及ぼし、長期の休職や退職につながることも少なくありません。
さらに、パワハラが職場に蔓延していると、周囲の社員も委縮し、自由な意見交換やチームワークが損なわれる恐れがあります。結果として職場全体の雰囲気が悪化し、業務効率や生産性の低下、優秀な人材の流出など、組織にとっても大きな損失となります。だからこそ、パワーハラスメントは「個人間の問題」として放置せず、組織として早期に気付き、適切な対応をとることが求められるのです。
マタニティ・カスタマーハラスメントなど
マタニティハラスメントは、妊娠・出産・育児休業といったライフイベントに関連して、職場で不利益な扱いや嫌がらせを受ける問題です。被害の実態としては、妊娠を理由に重要な業務から外されたり、体調不良による欠勤に対して冷たい態度を取られるといった事例が多く見られます。なかには「育休を取るなんて甘えだ」「戦力外になるのだから当然」といった心ない言葉を投げかけられ、精神的に大きなダメージを受けた女性もいます。
こうした行為は、被害を受けた本人の就業継続意欲や自己肯定感を著しく低下させるだけでなく、周囲の社員にも悪影響を与える可能性があります。また、背景には「妊娠や出産は個人の問題」という根強い価値観や、働く女性への無理解があることも見逃せません。企業にとっては、こうした無意識の偏見をいかに是正するかが、今後の組織づくりにおいて重要な課題となります。
一方、近年注目を集めているのが、カスタマーハラスメント(カスハラ)です。これは、顧客や取引先からの過度な要求や暴言、威圧的な態度により、従業員が精神的苦痛を受けるという問題です。実際には、「こんなサービスじゃ満足できない」「責任者を出せ」といった暴言を繰り返したり、SNSでの晒し行為を通じて企業や個人を攻撃するといったケースが報告されています。
こうしたカスハラは、従業員のメンタルヘルスを著しく害し、仕事への意欲を低下させるだけでなく、離職や労災申請といった事態に発展することもあります。問題を軽視して放置すれば、企業全体の士気が下がり、職場環境の悪化を招くおそれがあるため、組織的な周知と明確な対応方針が不可欠です。
これらのハラスメント問題に共通するのは、被害者が声を上げにくい構造と、社会的な理解の遅れです。企業は実態を正しく認識し、制度や方針を整えるだけでなく、社員一人ひとりの意識を変えていく取り組みが求められます。
ハラスメントの主な発生要因
ハラスメントを防止するためには、まずその発生原因を正しく理解することが欠かせません。問題の根本には、個人の価値観や認識のズレ、そして職場全体の風土やマネジメント体制の未整備といった、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。これらの要因は表面的には見えにくく、気づかないうちにハラスメントを誘発していることもあります。
この章では、ハラスメントがどのような背景で発生するのかを、個人と組織の両面から掘り下げていきます。それぞれの視点から原因を把握することで、より効果的な防止策の設計につながります。
個人要因:価値観・認識のズレ
ハラスメントが発生する背景には、個人の心理的な要因が大きく関与しています。特に価値観や認識のズレは、職場での人間関係における誤解やトラブルの温床となりやすく、何気ない言動が深刻な問題を引き起こす原因となります。たとえば、「昔からこうだった」「自分も同じようにされてきた」といった考えが、無意識のうちに相手を傷つけているケースは少なくありません。
こうした行為の背景には、加害者自身の経験や環境によって形成された思考のクセ、自分本位な価値観、そして他者への共感力の欠如が見受けられます。特に、一定の経験を積んできた世代や管理職層においては、自分のやり方や過去の常識を押し通してしまう傾向があり、「これはハラスメントにあたるのか」という基本的な認識すら欠けていることもあります。
また、業務の多忙さやプレッシャー、評価への不安などが重なることで、精神的に余裕を失い、言葉遣いや態度に注意を払うことが難しくなる場面もあります。4月などの新年度や異動の時期には、ストレスや新しい人間関係が重なり、このような状況が表面化しやすくなります。
このように、個人の認識や意識の低下は、日々の職場の中で自然に起こり得るものです。しかし、だからこそ、一人ひとりが「自分の言動が相手にどう受け止められるか」を常に意識し、ハラスメントに対する感度を高めておくことが、未然にトラブルを防ぐ鍵になります。
織要因:風土やマネジメントの未整備
ハラスメントの発生には、個人の要因だけでなく、組織文化やマネジメントの仕組みが整っていないことも大きな要因となります。特に、「長時間労働は当然」「成果さえ出せば多少の厳しさは問題にならない」といった価値観が暗黙のうちに共有されている職場では、ハラスメントが日常的に見過ごされがちです。
こうした職場では、従業員が違和感を覚えても声を上げられず、問題が表面化しにくくなります。また、「指導」と称して強圧的な言動を取ることが正当化されていたり、相談しても「それくらいは我慢すべき」と軽視されたりすることが続くと、職場全体が沈黙と諦めに覆われ、ハラスメントが慢性化してしまいます。
この背景には、マネジメントの不在や、人事部門がハラスメント問題に対して十分な対応体制を持っていないことが挙げられます。組織としてのルールや相談制度があっても、周知や運用が不十分であれば、実効性は担保されません。特に中小企業では、専任の人事担当がいないケースも多く、問題の対応が後手に回りがちです。
こうした状況を改善するためには、まず組織文化そのものを客観的に評価し、ハラスメントを助長している要因を洗い出すことが不可欠です。そして、労働組合や外部の専門家と連携しながら、職場全体で共通の価値観を育む取り組みが求められます。小さな違和感にも耳を傾け、誰もが安心して働ける環境を整備することが、健全な職場づくりへの第一歩となります。
企業に求められる基本的な防止対策
ハラスメントを防ぐためには、感情的な対処だけでは限界があります。組織としての明確な方針と仕組みを整備し、すべての従業員が安心して働ける環境を作ることが求められます。そのためには、誰もが理解できるルールの整備、実効性のある教育・研修、そして気軽に相談できる体制づくりが欠かせません。
この章では、企業にとっての基本的かつ最も重要なハラスメント防止の取り組みとして、「社内ルール・ポリシーの明文化」「教育・研修の実施と継続」「相談窓口・対応フローの整備」の3つの観点から、具体的な対策とその効果について解説していきます。
社内ルール・ポリシーの明文化
ハラスメント防止に向けた企業の第一歩は、明確な社内ポリシーの策定とその周知です。ポリシーとは単なる取り決めではなく、組織としての姿勢と価値観を示す重要なメッセージです。「当社はハラスメントを許容しない」という意思表示を明文化することで、従業員の行動指針が明確になります。
具体的には、禁止行為の定義、対象となる範囲、相談・通報の方法、事実確認のフロー、処分の基準、そして被害者・加害者双方の権利と責任について、漏れなく記載する必要があります。特に、よくあるグレーゾーンの事例についても、どこが問題でどう判断するかを明示することで、現場の迷いや不安を減らすことができます。
ポリシーは紙媒体のパンフレットやPDFにまとめ、入社時のオリエンテーションや年次研修で配布するだけでなく、社内ポータルや掲示板などにも常時掲載しておくことで、全従業員に継続的に意識づけを図れます。また、ハラスメントに関する相談対応においては、個人情報保護が極めて重要です。相談者や関係者の情報は厳重に管理し、不適切な開示や扱いがないよう、記載内容に明確なルールと運用体制を整備しておきましょう。
このように、社内ポリシーを具体的に記述し、それを実効性のある形で周知・活用することが、ハラスメントを防止し、職場の信頼関係を構築する土台となります。
教育・研修の実施と継続
社内ポリシーを制度として整備しただけでは、実際の現場で防止につなげるには不十分です。従業員一人ひとりがその内容を理解し、日々の行動に反映させられるようにするには、教育・研修の実施が不可欠です。しかも、単発的な研修ではなく、継続的かつ多層的なアプローチが求められます。
研修の第一の目的は、単なる法令遵守ではありません。「言う側・言われる側」双方がハラスメントについて正しく理解し、相互の信頼関係を損なわないコミュニケーションのあり方を学ぶことが重要です。そのため、研修内容は現場の実態に即して具体化し、よくあるハラスメントの例やグレーゾーンについてケーススタディを通じて考える構成が効果的です。
対象者の立場に応じた内容設計も欠かせません。管理職には、「育成とハラスメントの境界」を見極める判断軸を持たせ、過剰な配慮による指導の放棄ではなく、信頼に基づいた的確なマネジメントができるよう促します。一方、若手社員には、「これは叱責か“期待”か」を正しく捉える視点を養うことで、過度な自己防衛や誤解による不信感を減らし、建設的な関係を築く素地を作ることができます。
研修の講師には、現場経験が豊富な人事担当や、育児・介護など多様なライフステージを経験した講師を起用すると、受講者との距離が縮まりやすく、より実感のこもった学びを提供できます。また、eラーニングや小テスト、参加者同士の対話型ワークを組み合わせることで、知識の定着と実践的な活用を後押しすることができます。
研修は一度実施して終わりではありません。年に一度以上の頻度で計画的に実施し、受講後のアンケートや評価をもとに内容を改善していくことが、ハラスメントに強い職場づくりに不可欠です。研修等を通じて、「注意されるから控える」といった外からの圧力による行動ではなく、「自分自身が正しくあろうとする意識」に基づいた行動を促すことこそが、ハラスメント防止教育の本質です。
相談窓口・対応フローの整備
ハラスメントを早期に把握し、適切に対処するには、社員が安心して相談できる体制を整えることが欠かせません。その中心となるのが、相談窓口の設置と運用です。窓口は単なる“連絡先”ではなく、職場全体の信頼を支えるインフラであり、その整備の質が企業の姿勢を映し出します。
相談窓口は、社内の人事やコンプライアンス部門に加え、外部の第三者窓口を設けることで、多様な相談ニーズに応えることができます。特に、匿名での相談が可能な体制を構築すれば、報復や評価への不安から沈黙していた社員が声を上げやすくなり、潜在的な問題の早期発見にもつながります。
相談手段も重要です。電話・メール・オンラインフォーム・チャットツールなど複数の選択肢を用意し、従業員が「今すぐ」「簡単に」アクセスできるようにしておくことが理想です。特にリモート勤務が広がる中で、物理的な距離を超えて相談できる仕組みは、ますます求められています。
加えて、相談対応後のフローも明確に整備しておく必要があります。事実確認の方法、関係者への対応、報告・処分の手順、再発防止策までを一連の流れとして社内で共有し、必要に応じてマニュアル化しておきましょう。定期的に運用状況を見直し、改善点を洗い出して対策を講じるサイクルを確立することが、信頼される相談窓口の維持に不可欠です。
コミュニケーションと風土改善の取り組み
ハラスメントを未然に防ぐためには、制度やルールの整備だけでは不十分です。職場の日常に根付いたコミュニケーションのあり方や、組織全体の風土こそが、トラブルの芽を早期に見つけ、健全な関係を育てる基盤になります。この章では、心理的安全性を高める社内風土の特徴や、オープンな対話を促すマネジメント手法、そして管理職と若手社員それぞれへの効果的なアプローチについて解説します。人と人との信頼が築かれる職場環境づくりの第一歩を、一緒に考えていきましょう。
心理的安全性を高める社内風土とは
心理的安全性とは、職場で自分の意見や疑問を自由に話しても非難されない、間違いや失敗をしても人格を否定されないという安心感のある状態を意味します。この安全性が担保されている環境では、従業員が積極的に意見を出し合い、問題の早期発見やチームの創造性向上が期待できます。逆に、心理的安全性が低い職場では、社員は沈黙を選び、表面的な協力関係しか築けず、組織の停滞を招く恐れがあります。
まず、こうした風土をつくるためには、「意見が歓迎される場」を日常の中に組み込むことが欠かせません。たとえば、定例会議の冒頭に「今週の気づきや困りごと」を共有する時間を設ける、少人数グループでの対話の時間を月に数回設定するなど、発言しやすい仕組みを整えることが効果的です。誰かが発言したら否定せずにまずは「聞く」ことを全員で意識するだけでも、場の空気は大きく変わります。
また、管理職自身が日頃からオープンな姿勢でいることも心理的安全性の基盤となります。たとえば、上司が自分の業務の悩みや失敗談を率直に語ることで、部下も「話していいんだ」という安心感を得ることができます。このように、肩書きに関係なく誰もが尊重されるというメッセージが組織に根付けば、社員同士の信頼関係も強まり、ハラスメントを遠ざける効果が期待できるのです。
さらに、定期的なアンケートで社員の感じている安心度や不安要素を把握し、改善につなげることも重要です。心理的安全性のある社内風土は、一朝一夕には築けませんが、日々の積み重ねが確実に大きな変化を生むのです。
オープンな対話を促すマネジメント
ハラスメントを防ぐためには、制度やルールの整備に加えて、日常の「コミュニケーションの質」が重要です。なかでも、上司と部下が対等に意見を交わせる「オープンな対話」は、信頼を基盤とする職場づくりに不可欠です。
このような対話を実現するには、まず上司が「聞く姿勢」を明確に持つことが求められます。業務報告にとどまらず、感情や背景を含めた話を聞く時間を意図的につくることで、部下は自分の気持ちを安心して伝えられるようになります。週1回の1on1ミーティングや、月1回のキャリア面談など、形式にとらわれず「話せる場」の定着を目指しましょう。
また、組織としての「声を吸い上げる仕組み」も重要です。匿名意見箱、オンラインアンケート、SlackやTeamsなどのチャットツールでの意見募集など、形式は多様で構いません。大切なのは、出された声に対して「聞いたままにしない」という姿勢です。対応状況を可視化し、改善策が検討・実行されていることをオープンにすることで、従業員は「発言が意味を持つ」と感じられます。
さらに、対話の促進は一部の管理職だけの取り組みではなく、組織全体のカルチャーにしていく必要があります。そのために、対話の重要性をテーマにした社内研修や、優れた対話を実践しているリーダーのインタビュー記事を社内報で紹介するなど、「対話が価値である」という意識づけを図ることも有効です。
オープンな対話が日常的に行われるようになれば、ハラスメントの芽は早い段階で察知され、未然に防ぐことが可能になります。何より、社員一人ひとりが職場に安心して居られるようになり、その安心感が組織全体の活力へとつながっていくのです。
管理職と若手へのアプローチの違い
管理職と若手社員では、職場で求められるコミュニケーションのスタイルや意識が大きく異なります。その違いを踏まえたアプローチが、ハラスメント予防にはとても効果的です。
管理職向け
管理職はチームの雰囲気やメンバーの状態を把握し、適切にマネジメントする必要があります。そのためには、「信頼関係の構築」と「育成とハラスメントの境界を見極める判断力」がキーワードです。具体的には、部下に対して定期的に1on1で対話する習慣を持ち、「指導」と「叱責」の違いや、部下のモチベーションを下げずに改善を促す言い方を身につけてもらいます。また、部下の成長を後押しする言い回しや、問題が見つかったときの声かけやフィードバックの方法をケーススタディを通じて学ぶ場を設けることも有効です。
若手社員向け
若手社員はまだ経験が浅いため、「自身が受ける指導が正当なものなのか」「それともハラスメントに該当するのか」を見極める視点を身につける必要があります。したがって研修では、よくある叱責と期待の違いを取り上げたケーススタディを交え、自分が受けた言葉がどう感じられるのか内省する機会を作ります。さらに、問題を感じたときに自分で相談窓口へ連絡できる体験的なトレーニングや、相談スクリプトの演習なども有効です。
このように、立場によって異なるニーズを捉えた研修やコミュニケーション支援を行うことで、組織全体の理解レベルが底上げされ、ハラスメントの芽を早期に摘み取れるようになるのです。
ハラスメント防止に関連する法令
ハラスメント防止において、企業が適切な対応を取るためには、関連する法令の理解と遵守が不可欠です。法令は単に規制の枠組みではなく、職場での公正性を確保し、従業員の安心・安全を守るための土台です。この章では、ハラスメントに関係する主要な法令の概要と、それらが企業活動に与える影響について解説します。就業規則との関連性や、法令遵守の意義についても詳しく触れながら、企業が取るべき体制づくりのポイントを整理します。
関連法令の概要
ハラスメント防止に関する取り組みを進めるにあたって、まず押さえておきたいのが、関係する法令の存在です。これらの法令は、従業員の権利を守り、職場における公平性と安全性を確保するために定められています。企業が自社のルールや方針を策定するうえでも、これらの法律の内容をしっかり理解しておく必要があります。
たとえば、男女雇用機会均等法は、職場での性別を理由とした差別やセクシュアルハラスメントの防止を定めた法律です。この法律により、企業にはハラスメントを防ぐための必要な措置を講じる義務が課されています。
また、育児・介護休業法では、妊娠・出産・育児・介護に関連するハラスメント、いわゆるマタハラ・ケアハラへの対応が義務付けられています。これらの法令により、育児休業の取得を理由とした不利益取り扱いの禁止や、職場復帰支援の義務などが企業に課されています。
さらに、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)では、パワーハラスメントの防止措置がすべての企業に義務付けられました。とくに2022年4月以降は中小企業も対象となっており、体制整備が求められています。
これらの法令は、就業規則や社内ポリシーの整備にも直結します。たとえば、ハラスメント行為の定義や禁止規定、違反時の処分、相談対応の体制などを就業規則に明文化することは、組織としての取り組みを示すうえでも非常に重要です。
法律の知識を深めることは、単なる義務の遂行にとどまらず、働くすべての人の安心と信頼を築く基盤になります。
法令遵守の重要性
ハラスメント防止において、関連法令を理解するだけでなく、実際にそれを社内に根付かせ、遵守する体制を整えることが極めて重要です。法令遵守は単なる「義務」ではなく、企業が信頼を維持し、持続的に発展していくための土台といえます。
まず、法令を守ることで、企業には信頼性の向上という大きなメリットがあります。従業員や求職者にとって、ハラスメントのない安心できる職場環境は、企業選びの重要な判断基準となっています。法令をしっかりと守り、その取り組みを社内外に発信することで、企業イメージの向上にもつながります。
また、組織の体制整備という点でも、法令遵守は不可欠です。具体的には、就業規則への反映、相談窓口の設置、教育・研修の実施、記録や対応フローの文書化などが求められます。こうした体制が整っていないと、たとえ問題が起きたときに誠実な対応をしたとしても、「仕組みがなかった」として企業の責任が問われる可能性があります。
さらに、法令遵守は従業員のプライバシー保護にも直結します。ハラスメントに関する相談や調査においては、被害者や関係者のプライバシーに十分配慮する必要があります。これを怠ると、被害が拡大するだけでなく、企業に対する信頼も大きく損なわれかねません。
最後に、法令遵守は「守らなければ罰せられる」という消極的な姿勢ではなく、「社員全員の安全と尊厳を守るための積極的な取り組み」として捉えることが大切です。そのためにも、制度やマニュアルだけでなく、日々の業務の中での意識づけや対話を通じて、組織全体で遵守の文化を醸成していくことが求められます。


研修・制度以外の支援リソース
ハラスメント防止の取り組みを効果的に進めるには、社内だけで完結せず、外部の支援資源を上手に活用することが重要です。近年では、ハラスメントに関する知識や経験を持つ専門家のアドバイスを受けたり、信頼性の高い関連団体やポータルサイトから最新情報を得たりすることで、より実践的な対策が可能になります。この章では、外部専門家の選定や連携のポイント、さらに有用な情報源として活用できる団体やオンラインリソースについて、具体的にご紹介します。
外部専門家の活用
ハラスメント防止の取り組みを企業内だけで完結させるのは限界があります。そこで、専門知見を持つ外部専門家と連携することは非常に効果的です。まず、どの分野の専門家を選ぶか―選定基準を明確にすることが重要です。たとえば、法的対応を強化するには労働法やハラスメント法規に詳しい弁護士を、被害者支援や心理ケアを重視するなら臨床心理士・産業カウンセラーを選ぶとよいでしょう。特に、被害者や加害者への心理的サポートが求められる場面では、今後のメンタルヘルスを見据えたケアが可能なカウンセラーの存在が大きな支えとなります。
次に、業務内容や社風に応じた専門家選定のポイントについても考慮が必要です。たとえば製造業のように、安全管理や労働負荷が高い職場では、職場特有のストレスや身体的負担に起因する問題が発生しやすくなります。こうした環境では、産業医や安全衛生の専門家と連携し、ハラスメントの発生要因になり得る過重労働や人間関係のストレスに早期に対処する体制を構築することが求められます。長時間労働や危険作業が続く職場では、緊張感が高まり、感情の衝突や誤解からハラスメントが生じるリスクも上昇します。このような状況に対応するために、産業医が定期的に従業員の健康状態やストレス状況を把握し、予兆を捉えて早めに介入する仕組みが有効です。
導入後には、単に支援を依頼するだけでなく、定期的に評価とフィードバックを行うことも重要です。たとえば、半年ごとに研修や相談件数に対する専門家の所見をヒアリングし、実際の職場での活用度や課題点を報告書として共有します。これにより、「せっかく導入したが活用されていない」「形式的な実施にとどまっている」といった問題を早期に発見し、改善につなげることができます。
さらに、専門家との連携は一過性で終わらせず、長期的なパートナーシップとして育むことが理想的です。定期的な研修プログラムの共同設計、相談窓口への継続的な関与、職場風土改善に向けた共同評価など、企業と専門家の関係が「共成長」できる仕組みを構築することで、ハラスメント防止の組織力が倍化します。
関連団体やポータルサイトの紹介
ハラスメント防止に取り組む企業にとって、信頼できる外部リソースを日常的に活用できる体制は重要です。ここでは、関連団体やポータルサイトの紹介とその活用法について詳しくまとめます。
信頼性の高い団体・サイトの選定
まず、情報源として信頼性のある団体やポータルサイトを選ぶことが前提です。たとえば、厚生労働省が提供する「職場のいじめ・嫌がらせ防止に関するガイドライン」や、都道府県労働局のハラスメント相談窓口紹介ページなど、行政の資料は法的根拠に基づいた確かな情報源です。他にも業界団体(例:日本産業カウンセラー協会、日本労務学会など)が提供する調査報告や実績レポート、企業向け資料は、実務へのヒントとして活用できます。
定期的な情報の更新と紹介方法
Webコンテンツは時間とともに情報が陳腐化する可能性があります。そのため、定期的にサイト内容を確認し、更新の有無や改訂情報をチェックすることが不可欠です。具体的には、年に数回のリストレビュー会議を行い、新たに推奨する団体や情報源の追加・削除を検討します。社内イントラやポータルに掲載する際にも、「最終更新日」「おすすめする理由」などを明示し、利用者に安心感を与えましょう。
利用者の声の収集と反映
ただ情報を掲載するだけでは活用にはつながりません。情報提供後に従業員からの利用者の声を収集し、情報の質や有用性を検証することが重要です。たとえば、「○○相談窓口を利用してキャリアに関する悩みが解消された」「法令解説に具体的な事例が役立った」などの経験談を、社内報やイントラ記事として紹介すると、他の社員にとっても利用のハードルが下がります。また、アンケートで「次はこの情報がほしい」などの要望を募り、定期的な改善や追加更新に活用します。
他企業との連携としての活用
さらに、業界横断で情報交換できる場を設けるのも効果的です。例えば、近隣の企業や業界団体と、「ハラスメント対策情報共有会」を定期開催することで、自社では取り入れにくい取り組みや最新手法などを共有し合えます。こうしたネットワークを活かすことで、社外の有益なサポートリソースを広く活用することが可能です。
継続的な評価と改善の仕組みづくり
ハラスメント防止の取り組みは、一度制度や施策を整えたからといって終わりではありません。継続的に職場の実態を把握し、必要に応じて見直しを行うことが、持続可能で効果的な対策につながります。そのためには、定期的な評価の実施と、フィードバックを通じた改善の仕組みづくりが欠かせません。この章では、評価の方法やポイント、フィードバック文化の醸成による好循環の生み出し方について解説します。
実態調査・匿名アンケートの活用
ハラスメント防止に向けた取り組みを機能させるためには、実態を正確に把握することが欠かせません。そのための有効な手段が、実態調査や匿名アンケートの活用です。これにより、表面化しにくい職場内の課題を掘り起こし、改善の糸口をつかむことができます。
まず、匿名性のある調査を導入することは、回答者の心理的なハードルを下げ、より率直な意見や感情が集まりやすくなります。特にハラスメントに関する内容は、加害者・被害者の関係性や周囲の目が気になり、直接声を上げにくい場合が多いため、匿名形式は信頼を得やすい方法といえるでしょう。
調査項目には、職場の雰囲気や管理職との関係、過去に違和感を覚えた言動の有無など、定性的な情報も取り入れると効果的です。あわせて、研修の受講後アンケートや定期的な意識調査も行うことで、対策の成果や変化の兆しを捉えることができます。
また、集まった結果は単に集計するだけでなく、傾向分析を行い、部署や職種ごとの課題に応じた対策を検討することが重要です。可能であれば年1回程度、定期的に同様の調査を実施し、時系列での変化を追う体制を整えましょう。
実態調査と匿名アンケートは、職場の「見えない課題」に気づくための大切な窓口です。この情報を的確に活用することが、ハラスメントを未然に防ぎ、健全な職場づくりに寄与します。
定期的な研修評価とフィードバック
ハラスメント防止のために実施される研修は、単発で終わるものではなく、定期的に内容と効果を評価し、改善を重ねていくことが求められます。研修が実際に職場の行動変容や意識改革につながっているかを確認するには、継続的なフォローとフィードバックが不可欠です。
まず重要なのは、研修終了後に参加者からのフィードバックを収集する仕組みです。具体的には、理解度、納得感、実務への活用イメージといった項目を中心にアンケートを実施し、自由記述欄を設けて意見や要望を把握します。このような声は、次回以降の研修内容の見直しや、現場に即した事例の追加に活かすことができます。
加えて、フィードバックを基にした改善活動を定例化し、必要に応じて資料の更新や進行方法の再設計を行うことが大切です。特に「伝わったか」ではなく「行動が変わったか」という観点から研修の効果を測ることで、本質的な変化を捉えることができます。
例えば、「部下に対して感情的にならず、一度言葉を選ぶようにした」「注意する前に相手の意図を確認する習慣がついた」「部下の話を最後まで聞いた上でフィードバックするようになった」といった変化は、研修がもたらす具体的な成果として評価できます。こうした行動変容の兆しをキャッチし、組織全体で共有することで、研修の意義がより明確になります。
また、研修担当者と人事部門、現場マネージャーが連携し、職場での実践状況を共有する機会を設けると、学びの定着が一層進みます。管理職やリーダー層には、部下との対話の中で気づいた変化や課題をフィードバックしてもらい、それを研修設計に反映させる流れを整備しましょう。
定期的な研修評価とフィードバックを通じて、「伝える」研修から「変わる」研修へと質を高めていくことが、ハラスメントのない職場づくりのカギとなります。
これからの職場づくり
ハラスメント防止に取り組むうえで、重要なのは一時的な施策ではなく、職場全体での継続的な意識と行動の積み重ねです。多様な価値観を持つ従業員が互いに尊重し合い、安全に働ける環境を維持するためには、企業としての姿勢を明確にし、組織文化の中に予防の意識を根付かせる必要があります。この章では、そうした「ハラスメントを起こさない文化」を醸成するための考え方と、管理職・従業員それぞれが主体的に学び合う組織づくりの視点についてご紹介します。
ハラスメントの“予防文化”の醸成へ
ハラスメントを防ぐための制度やルールが整っていても、職場の文化として定着していなければ、真の防止にはつながりません。重要なのは、職場全体に「ハラスメントはあってはならないこと」という価値観が根付き、日々の業務の中で自然と予防行動が取れるような風土をつくることです。
そのためには、まず定期的な研修や啓発活動を通じて、全従業員がハラスメントの本質や影響について理解を深める必要があります。法令の知識や防止策だけでなく、実際に起こり得る事例や、どのような言動が誤解を招くのかといった具体的な情報を共有することで、予防意識を高めることができます。
また、相談窓口や匿名アンケートなどを活用し、実際に従業員が安心して声を上げられる環境づくりも欠かせません。これにより、問題の早期発見や改善につなげることができ、職場全体の安全性が保たれます。
さらに、企業のリーダー層が率先してハラスメントのない職場づくりに取り組む姿勢を示すことも、予防文化を根付かせるために重要です。経営層や管理職が「見過ごさない」「指摘する」「対話する」といった行動を実践することで、職場の空気は確実に変わっていきます。
予防文化の醸成は一朝一夕には実現しませんが、継続的な取り組みによって、誰もが安心して働ける職場を築くことが可能です。
管理職と従業員がともに学び合う組織へ
ハラスメント防止の取り組みを実効性のあるものにするには、管理職と一般従業員が互いに学び合い、成長する組織文化を育むことが必要です。特定の役職や立場の人だけが学ぶのではなく、全員が当事者意識を持って取り組むことで、より強固な予防体制が築かれます。
管理職には、ハラスメントに対する法的知識や対応力だけでなく、部下との信頼関係を築きながら指導する力が求められます。一方、従業員側も、組織のルールや期待される言動を理解し、自らの行動を省みる視点が欠かせません。こうした相互の理解と協力が、健全な職場づくりを支える土台となります。
また、双方向の学びを促進するためには、研修やワークショップでの意見交換やロールプレイなど、実践的な学習の機会を設けることが効果的です。実際の職場で起こり得るシナリオを共有し、対応策を一緒に考えることで、学びは深まり、現場で活かせる知識となります。
最終的に、管理職と従業員がそれぞれの立場を理解し合い、共通の目的に向かって行動できる職場こそが、ハラスメントのない健全な職場づくりを実現する鍵となるのです。
まとめ
ハラスメント防止は、単なる義務の遂行ではなく、会社としての持続的な事業運営に不可欠な課題です。法令順守や制度整備に加え、職場風土の改善や、労働者同士のコミュニケーションの質向上がカギを握ります。特に管理職や経営層がリーダーシップを発揮することで、現場での意識と行動に変化が生まれます。
また、ハラスメントは一人の問題ではなく、組織全体の責任です。従業員が事実関係を正確に把握し、自ら適正な判断と行動をとることが、職場全体の信頼を高め、根本的な解決につながります。研修や制度だけにとどまらず、対話と共感を重ねることで、予防文化が社内に根づいていくでしょう。
本記事が、より良い労働環境づくりへの一助となることを願っています。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
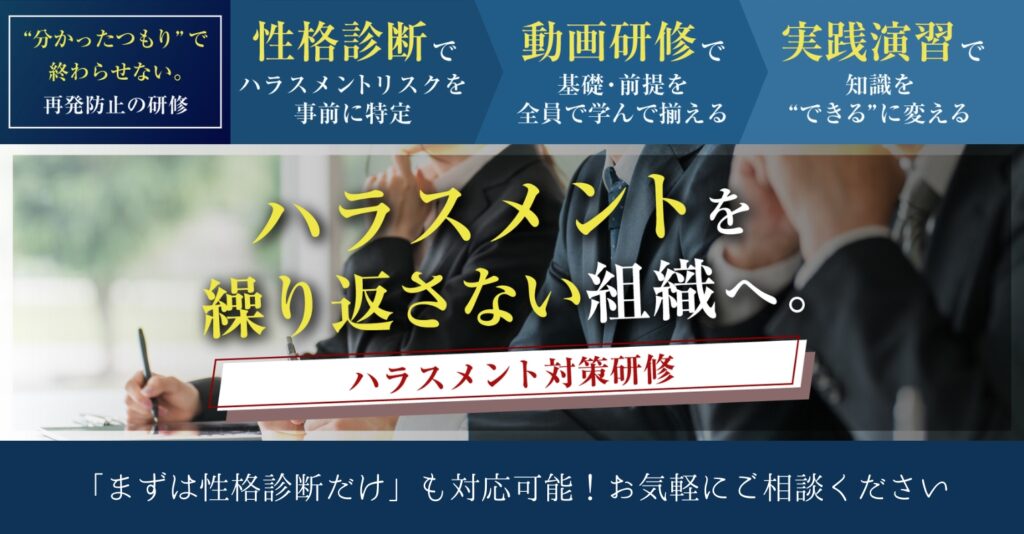

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。