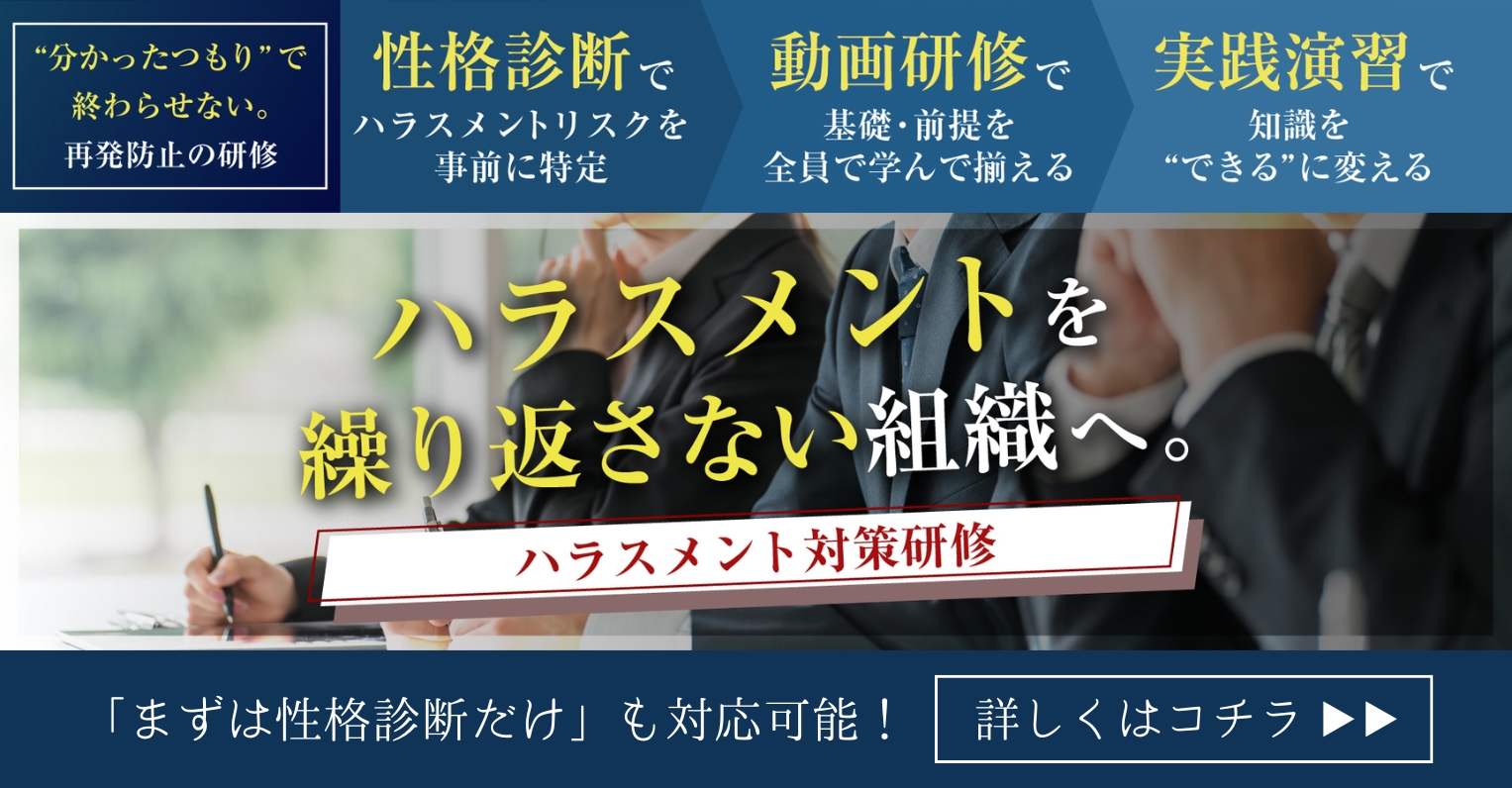ハラスメント問題は、今や企業規模を問わず、すべての職場で避けて通れない重要課題です。被害者の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、組織全体の信頼性や業績にも大きな影響を及ぼします。特に中小企業においては、限られた人員・体制の中で、どのように実効性のある対策を講じていくかが問われています。
本記事では、ハラスメントの種類や発生要因を整理したうえで、予防と対応のための実践的な取り組み、研修や体制整備のポイントまでを詳しく解説します。法的リスクを回避し、社員が安心して働ける職場づくりのヒントを提供します。


ハラスメント対策の必要性と企業への影響
ハラスメントは単なる職場のトラブルではなく、企業経営に深刻な影響を与えるリスク要因です。放置すれば従業員の離職や信頼性の低下を招き、業績にも大きなマイナスとなります。ここでは、ハラスメントが企業に及ぼす具体的な影響と、その背景にある法令や社会的評価との関係について解説します。
ハラスメントが企業活動に与えるダメージ
ハラスメントが職場で発生した場合、企業活動にはさまざまな悪影響が及びます。まず最も大きな問題は、従業員の働く意欲や信頼関係の崩壊です。加害者だけでなく、周囲の社員にも心理的な緊張や不安を与えるため、職場全体に重苦しい雰囲気が漂い、日常業務のパフォーマンスが著しく低下することになります。被害者が業務に集中できなくなるのはもちろん、傍観者となった社員も「自分もいつ被害者になるか分からない」と感じ、チームワークや協働に支障が出るようになります。
このような状況が続けば、従業員の離職率が高まり、人材の流出が止まらなくなるという悪循環に陥ります。特に中小企業にとっては、ひとりの社員が担っている業務領域が広いため、突然の離職によって業務の継続そのものが困難になるリスクもあります。さらに、新たな採用や教育には時間とコストがかかるため、経営資源への負担が一層増してしまいます。
また、ハラスメントが重大な事案として認定された場合、企業は損害賠償責任を負うこともあります。例えば、長期間にわたるパワーハラスメントの結果、被害者がうつ病を発症し、訴訟に発展。数百万円規模の慰謝料や未払い賃金、治療費の支払いを命じられた例もあります。こうした損失は金銭的な問題にとどまらず、企業名が報道されることで社会的信用の低下を招き、取引停止や業績悪化につながるケースも見られます。
ハラスメントは一見、個別の人間関係の問題に見えますが、実際には企業全体の信頼・成長・持続可能性を揺るがす重大な経営リスクであることを強く認識しなければなりません。
法令対応と企業イメージの関係
ハラスメント対策において、企業が果たすべき法的責任は年々強化されており、その対応姿勢が企業の社会的評価にも大きく関わってきます。とくに2022年4月から中小企業にも適用されたパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)は、職場におけるハラスメントを「防止・相談・再発防止」の観点から総合的に取り組むことを義務付けています。この法律の施行により、就業規則への明記や相談窓口の設置、被害者と加害者への適切な対応が企業に求められるようになりました。
こうした法令に対応していない場合、指導・勧告・企業名の公表などの行政処分を受ける可能性があります。それだけでなく、社員や求職者、取引先から「コンプライアンスに消極的な会社」と見なされることで、信頼や期待が損なわれ、企業の成長機会を失う結果にもつながりかねません。近年では、SNSや口コミサイトなどを通じて職場内の情報が拡散しやすく、法令違反やハラスメント問題が瞬時に社会問題化することもあります。
一方で、法令に基づいた明確なハラスメント対策を講じている企業は、社会的信頼の獲得や社員の定着率向上など、ポジティブな評価を得ることができます。たとえば、就職情報サイトなどでは「コンプライアンス重視」や「安心して働ける職場」といった企業イメージが若年層の志望動機に強く影響する傾向が見られます。法令対応は単なる義務ではなく、企業ブランドを高める投資であると捉えることが、これからの経営には必要です。
職場におけるハラスメントの種類と具体例
ハラスメントと一口に言っても、その形態は多岐にわたり、それぞれに特徴的な背景や発生状況があります。対策を検討するうえでは、どのような種類のハラスメントがあるのか、具体的な事例を通じて正しく理解することが欠かせません。ここでは代表的な4つのハラスメントについて、実際に起こり得る言動を交えて紹介します。
セクシュアルハラスメントの定義と事例
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動によって相手に不快感を与えたり、就業環境を害したりする行為を指します。典型的な例としては、見た目や服装に関する不適切なコメント、プライベートな性的な話題への言及、身体への不必要な接触などがあります。
たとえば、上司が女性社員に対し「今日はずいぶん色っぽい格好だね」「独身なんだから、飲みに付き合ってよ」などと発言するケースは、業務上の必要性を超えた過剰な関心とみなされ、明確なセクハラに該当します。また、仕事の成果を「俺と食事に行ったら評価してやるよ」といった形で評価と結びつけるような言動も、業務上の権限を利用した悪質なハラスメントです。
これらの行為は、たとえ発言者に悪意がなかったとしても、受け手が不快に感じ、就業環境が害されればセクハラとして成立します。男女雇用機会均等法では、事業主に対し、セクハラを防止するための体制整備を義務づけています。社内ルールとしても、何が「性的な言動」にあたるかを具体的に明文化することが、防止策として有効です。
パワーハラスメントの定義と事例
パワーハラスメント(パワハラ)は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた言動によって他者に精神的・身体的苦痛を与える行為です。上司から部下に対する暴言や無視、不当な業務命令などが典型的な例に挙げられます。
たとえば、上司が特定の社員にだけ厳しい口調で叱責を繰り返し、「お前には能力がない」「辞めた方が会社のためだ」と日常的に言い続けるケースや、実現不可能な目標を押しつけ、達成できなければ評価を下げるといった対応は、いずれもパワハラとみなされます。これにより、被害者は職場での居場所を失い、精神的な健康を損なうこともあります。
パワハラの防止には、上司自身が自分の言動の影響力を認識し、適切なコミュニケーションを心がけるとともに、企業としても明確な基準を設けることが重要です。パワーハラスメント対策は、労働施策総合推進法によって事業主に義務付けられており、企業規模にかかわらず対応が求められます。
マタニティ・カスタマーハラスメントなどの事例
職場で問題となるハラスメントの中でも、マタニティハラスメント(マタハラ)とカスタマーハラスメント(カスハラ)は、従業員が業務を遂行するうえで重大なストレス要因となっています。それぞれの特徴と具体例、そして企業としての対応のあり方を整理しておきましょう。
マタハラは、妊娠・出産・育児を理由とした不当な扱いや発言を指し、育児休業制度の利用を妨げたり、業務の縮小や昇進機会の剥奪といった形で現れることがあります。たとえば、妊娠を報告した社員に「このタイミングで妊娠するなんて迷惑だ」「育休を取るならその分の穴埋めは自分で考えて」といった発言があると、法令違反となる可能性があります。男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、こうした不利益取扱いを明確に禁止しており、企業には体制整備と管理職教育が求められます。
一方、カスハラは、顧客や取引先からの理不尽な要求や暴言を受けることにより、従業員の精神的負担が増大する問題です。たとえば、「土下座しろ」「何時間でも待ってやるから謝罪しろ」「無料にしないならSNSに悪評を書く」など、過度な言動が該当します。近年では、正当なクレームとハラスメントの境界線が注目されるようになっており、企業には対応基準やマニュアルの整備が求められています。
この2つに共通して言えるのは、被害を受ける側が自ら声を上げにくいという点です。そのため、企業は「何がハラスメントに該当するのか」を明確に定義し、社内に共有するとともに、被害を受けた場合に安心して相談できる窓口や体制を整えておくことが重要です。マタハラ・カスハラを未然に防ぐとともに、発生時の迅速な対応が、職場の健全性を保つ鍵となります。
ハラスメントが起こる根本要因
ハラスメントが職場で発生する背景には、表面的なやりとりや態度だけでなく、より深いところにある心理的な動機や職場全体の空気・価値観といった根本要因が潜んでいます。単に加害者個人の問題と捉えるのではなく、職場という組織の構造や文化、そして当人の認識・心理状態に目を向けることが、根本的な対策を講じる上で欠かせません。
この章では、「個人」と「組織」の2つの視点から、ハラスメントがなぜ起こるのか、その土台となる構造について深掘りしていきます。
個人の認識・心理的要因
ハラスメントの根本には、加害者個人の心理状態や価値観、認識のズレといった要素が大きく関係しています。特に、自身の考えや行動に対する客観性が欠如している人は、相手の感情や状況に無自覚なまま、不適切な言動を取りがちです。「指導の一環」「冗談のつもり」と思っていても、それが他者にとっては侮辱や威圧として受け取られることも少なくありません。
また、職場におけるストレスやプレッシャーも、心理的なゆがみを引き起こす要因になります。上司が過大な目標を背負い、自身の焦りや不安を部下にぶつけることで、感情的な発言や高圧的な指導につながってしまうケースは多く見られます。こうした状況は、本人が意識しないまま繰り返され、結果的にハラスメントへと発展していくのです。
さらに、「拒絶されることへの強い恐れ」「評価されないことへの不安」など、自己肯定感の低さや対人関係への不信感が行動の背景にあることもあります。例えば、部下や後輩からの否定的な反応に過敏になり、「自分の立場を守るために先に支配しよう」といった心理が働く場合もあります。このような防衛的な行動が、権限の濫用や強要として現れ、知らぬ間に加害者となってしまうのです。
個人の認識や心理的傾向は、日常的な対話や研修だけでは変わりにくい側面もありますが、組織として「自身の言動を省みる機会」を提供することが重要です。たとえば、管理職に対するハラスメント研修や定期的な自己チェック、メンタルヘルス面談などを通じて、無自覚な加害行為を防ぐ意識を育むことが、再発防止につながります。
組織文化・職場風土の影響
ハラスメントが起こる背景には、組織全体の価値観や人間関係、コミュニケーションの風土が密接に関係しています。たとえば、「昔ながらの体育会系文化が根強く残っている」「上司の言うことは絶対」「反論は許されない」といった価値観が根付いている職場では、たとえ不適切な言動があっても誰も指摘せず、問題が放置されやすくなります。
また、組織内でのハラスメント防止に関するルールや指針があっても、それが形骸化していると効果は薄くなります。マニュアルが存在するだけでは不十分であり、日々の業務や人間関係の中で「ハラスメントは許されない」という意識がどれだけ根づいているかが重要です。たとえば、定期的な教育や啓発ポスター、管理職への継続的な指導などによって、風土として根づかせていく必要があります。
特に管理職の存在は、職場の空気を大きく左右します。管理職が感情的な言動を見せたり、部下に対して高圧的な態度をとっていたりすると、その姿が模範となって組織全体に波及してしまいます。逆に、冷静でフェアな対応をとる管理職がいる職場では、自然と健全なコミュニケーションが根づきやすくなります。
さらに、労働組合や人事部門などが、従業員の声をしっかり拾い上げる体制を持っていることも大切です。たとえば、匿名で意見を出せる仕組みや、外部の相談窓口との連携などにより、組織に対する信頼感が高まり、問題が早期に可視化されるようになります。
健全な組織文化を育むには、制度設計や規則だけでなく、「日々の働き方」や「社内の対話」の質を見直していくことが欠かせません。ハラスメントを起こさない、起こさせないための土壌づくりこそが、企業の持続的な成長につながるのです。
ハラスメント防止策の基本と実施例
ハラスメント対策において重要なのは、理念やルールを掲げるだけでなく、それを実際に社内で機能させていく具体的な手段を講じることです。ここでは、ハラスメント防止に取り組む企業がまず実践すべき基本的な対策と、現実的な実施例について詳しく解説します。
方針の策定と社内周知の進め方
ハラスメント対策を推進するうえで最も重要なのは、企業としての明確な姿勢を「方針」として打ち出すことです。これは単なる理念にとどまらず、実際の行動指針として機能するものでなければなりません。どのような行為がハラスメントに該当するか、どのような対応を行うか、企業としてどの程度の責任を負うのかなどを具体的に明文化し、社員全員が共通の認識を持てるようにすることが第一歩となります。
この方針は、文書化された状態で全社員に配布するのが理想です。ハンドブック、パンフレット、社内ポータルサイトへの掲載、あるいは定期的な研修資料への組み込みなど、複数の手段を併用することで、社員の記憶に残りやすくなります。また、研修やミーティングを通じて繰り返し伝えることで、理解を深める機会が増え、社内文化として定着しやすくなります。
さらに、ハラスメントに対する企業の姿勢を明確に伝えるためには、経営層が積極的に関与することも大切です。トップメッセージとして方針を語ってもらうことで、「この会社は本気で取り組んでいる」という印象を社員に与えることができます。社員から信頼を得るためには、こうした具体的な姿勢が非常に効果的です。
また、策定した方針は一度きりで終わらせるのではなく、法改正や社会的な価値観の変化に応じて定期的に見直すことが不可欠です。たとえば、テレワークやSNSにおける新たなハラスメントの形態に対応するためには、最新の実情を踏まえた更新が求められます。これにより、常に現実に即した対応が可能となり、形骸化を防ぐことができます。
相談窓口の設置と運用ポイント
相談窓口は、ハラスメントの早期発見と解決のために欠かせない仕組みです。しかし単に設置するだけでは十分ではなく、実際に機能し、利用されるものでなければなりません。そのためには、社員にとって「信頼できる」「話しやすい」と感じられる体制づくりが必要です。
まずは、誰が相談を受けるのか、どのように相談できるのかを明確にし、社内で広く周知する必要があります。相談手段は対面、電話、メール、Webフォームなど複数用意し、使いやすさを重視することが求められます。特に中小企業では、「社内の人には言いづらい」という声もあるため、外部相談窓口を設けることで心理的ハードルを下げる工夫が有効です。
また、相談内容が外部に漏れたり、本人に不利益が及んだりしないよう、プライバシー保護には万全の体制が必要です。相談を受ける担当者には守秘義務を課すとともに、対応記録や面談内容の管理方法も明確に定めておくことが大切です。これにより、相談者が安心して話せる環境が整います。
加えて、窓口の設置後も、運用の見直しを継続的に行うことが求められます。実際の相談件数や対応事例をもとに、改善点を洗い出し、マニュアルや対応手順をアップデートしていくことが、相談体制の質を高めるポイントです。また、相談窓口の存在が周知されていないケースもあるため、定期的な社内告知や研修でリマインドすることも効果的です。
相談窓口は、単なる制度ではなく、「助けを求める声を確実に拾い上げる」ための企業の姿勢そのものを示すものです。形だけにせず、実効性を伴った運用を目指すことが、社員からの信頼と組織全体の安心感につながります。
防止のためのルール整備と周囲の支援
ハラスメントを未然に防ぐためには、明確なルールを整備し、それを組織全体に浸透させる仕組みが必要です。ハラスメントを「しない・させない」ための基準や禁止事項を明文化し、全社員が行動の指針として理解できるようにすることが基本です。これは、万が一トラブルが発生した際の対応にも活用でき、企業としてのリスク管理にもつながります。
まず行うべきは、ハラスメントに該当する言動の具体例と、それに対する処分の方針を明記した社内ルールの策定です。社内規定や就業規則の中に明示的に盛り込むことで、形式的な位置づけにとどまらず、実効性のある規律となります。禁止事項だけでなく、「こうすれば防げる」といった推奨行動をあわせて示すことで、社員が前向きに行動しやすくなります。
加えて、ルールを社内で機能させるには、周囲の支援体制の構築が重要です。ハラスメントは、加害者と被害者だけの問題ではなく、周囲の無関心や黙認が状況を悪化させる要因にもなります。そのため、「見て見ぬふりをしない」「気づいたら声をかける」など、第三者としての役割についても意識づけを行うことが効果的です。
このような姿勢を定着させるためには、定期的な社内研修やロールプレイ、グループディスカッションの実施が有効です。特に管理職に対しては、部下からの相談を受けた際の対応や、組織内の雰囲気づくりについて深く学ぶ機会を設けることが望まれます。また、制度としては通報者保護のルールを明確にし、声を上げた人が不利益を受けない環境を整えることも忘れてはなりません。
組織としてのルールが整い、周囲の協力体制が機能することで、社員一人ひとりがハラスメント防止の担い手となる職場が実現します。それは結果的に、安心して働ける風通しのよい職場づくりへとつながっていきます。
中小企業における現実的な対策方法
中小企業においては、ハラスメント対策の必要性を感じていても、大企業のような専門部署や人材、予算を確保するのが難しいという現実があります。限られたリソースの中で実行可能な対策を講じることが求められるため、「できる範囲で、確実に機能する対策」を設計することがポイントです。
まず取り組むべきは、経営者や管理職が主導して、ハラスメントを許容しない姿勢を明確に示すことです。トップが関与して「うちの会社はハラスメントを見過ごさない」という意思表示を行うだけでも、職場全体の空気は大きく変わります。掲示板や朝礼での定期的なメッセージ発信など、費用をかけずに実施できる方法を活用しましょう。
次に、社員全員がハラスメントの基本を理解できるよう、簡単なチェックリストや社内資料を配布することが効果的です。例えば、「これってハラスメント?」といった具体的な例を紹介した1枚紙の資料を作成して配布するだけでも、行動の指針になります。人事担当者や管理職が社員に対して短時間の説明会を実施することも、理解を深めるうえで有効です。
また、外部リソースの活用も中小企業にとって重要な選択肢です。地方自治体や商工会議所が提供している相談窓口や研修コンテンツを活用することで、自社内に専門知識がなくても一定水準の対策を講じることができます。厚生労働省の「あかるい職場応援団」など、公的な無料資料やガイドラインも有効に活用しましょう。
さらに、相談窓口や対応体制がない場合でも、まずは「誰に話せばいいか」を明確にし、1名でも窓口担当を設定するだけで、大きな一歩となります。形式にとらわれず、「社員の声に耳を傾ける場」をつくることが重要です。小さな工夫を積み重ねることで、ハラスメント防止の取り組みは確実に社内へと根づいていきます。
低コストで実施できる相談体制の作り方
中小企業がハラスメント相談体制を構築する際に直面するのが、コストや人的リソースの制約です。しかし、限られた環境下でも工夫次第で信頼性の高い相談体制を築くことは可能です。重要なのは、形式ではなく「社員が安心して相談できる環境」を整えることです。
まず取りかかりやすいのが、担当者の明確化です。人事担当や管理職、信頼のおける社員など、社内で相談対応ができる人物をあらかじめ指定し、その名前と連絡手段を掲示しておきます。電話やメールなど、簡単にアクセスできる手段を用意し、「いつでも話せる」と感じられる雰囲気をつくることが肝心です。
特に重要なのがプライバシーへの配慮です。社内の小規模な組織では、匿名性を保つのが難しいと感じる社員も多いため、相談者が不利益を被らないよう「守秘義務の徹底」や「不利益取扱い禁止」を明記した文書を配布すると安心感につながります。また、Googleフォームや匿名チャットツールを活用することで、簡易ながら匿名性の高い仕組みも導入可能です。
さらに、外部の無料相談窓口を紹介することも現実的な方法です。たとえば、厚生労働省の「あかるい職場応援団」や地域の労働相談センターなどを案内し、社外にも相談できる場があることを伝えるだけでも、相談のハードルは大きく下がります。
継続的に相談体制を機能させるには、定期的な見直しと社内への周知が欠かせません。年1回程度のアンケートや意識調査を行い、制度が機能しているかをチェックしつつ、必要に応じて改善を加えていく姿勢が信頼を育みます。
コストをかけずに相談体制を整えることは、創意工夫次第で十分に可能です。社員の声を拾い上げる小さな仕組みが、企業全体の信頼性と健全な職場環境づくりに大きく貢献します。
自社でできる簡易研修の進め方
ハラスメント防止のためには、社員一人ひとりの意識を高めることが欠かせません。ただし、外部講師を招いたり、高額なeラーニングを導入したりする方法は、すべての企業にとって現実的とは限りません。業務とのバランスや体制上の制約から、実施方法に工夫が求められる場面も多くあります。そのような状況下でも取り組みやすい簡易的な研修を導入しつつ、可能な範囲で専門家の支援を受けるなど、段階的な整備を進めることが大切です。
まず取り入れやすいのが、厚生労働省や自治体が無料で提供している資料や動画を活用した社内勉強会です。「あかるい職場応援団」などのポータルサイトには、具体的な事例や対応方法を紹介するわかりやすいコンテンツが用意されており、短時間でも効果的な研修が可能です。パワーポイント資料を印刷して配布し、10~15分ほどの説明を加えるだけでも、ハラスメントへの意識づけに役立ちます。
また、社内事例や想定シナリオを用いたロールプレイ形式の研修も効果的です。たとえば、「これはハラスメントになる?」「上司としてどう対応する?」といった具体的な場面を提示し、グループで意見交換を行うことで、理解が深まると同時に当事者意識も育まれます。こうした形式は費用がかからず、参加者同士の対話を通じて職場全体の雰囲気改善にもつながります。
さらに、管理職やリーダー層に向けた簡易マニュアルを作成し、相談対応や日常的な声かけのポイントを伝えることも重要です。対応が属人的にならないよう、「こういうときはこうする」という具体的な指針を共有することで、現場対応の質を底上げできます。
研修を年1回の行事で終わらせるのではなく、朝礼や社内SNSなどを活用して定期的に注意喚起を行うことも効果的です。短くても頻度を高めることで、ハラスメント防止の意識が継続的に社内に根づいていきます。
自社でできる範囲からでも、工夫を凝らした簡易研修は十分に実施可能です。大切なのは「やらない理由」ではなく、「できる方法」を見つける姿勢。小さな取り組みの積み重ねが、大きな防止力を生み出すのです。
効果的なハラスメント防止研修の設計
ハラスメント防止に向けた取り組みの中でも、社内研修は社員一人ひとりの意識を高め、具体的な行動変容を促すために欠かせない要素です。しかし、単に知識を伝えるだけでは、職場の実情に即した行動にはつながりません。効果的な研修を行うには、受講者の役割や立場に応じたカリキュラムを設計し、実務に活かせる内容に落とし込むことが重要です。この章では、目的別・対象別の研修設計と、効果を高めるための工夫について詳しく解説します。
研修の目的・対象ごとのカリキュラム例
ハラスメント防止研修を設計する際、最も重要なのは「何のために実施するのか」という目的を明確にすることです。研修は単なる知識の伝達にとどまらず、職場における行動変容を促すことが求められます。全社員が安心して働ける環境をつくるためには、全員が共通の理解を持ち、それぞれの立場に応じた対応力を身につける必要があります。
まず管理職を対象とした研修では、部下の行動への適切なフィードバック方法や、相談対応の初期ステップ、指導とハラスメントの違いを理解させることが中心となります。特に「パワハラにならない注意の仕方」や「問題発生時の初動対応」など、現場での判断が問われる内容を重点的に扱うと効果的です。
一方、一般社員向けには、日常業務の中で遭遇するかもしれない場面を想定し、「これはハラスメントか否か」を自ら判断できるようになる内容が求められます。また、被害を受けた場合の相談方法や、同僚が困っている場合にどのようにサポートするかなど、実践的な視点を盛り込むと理解が深まります。
経営層や役員クラス向けには、ハラスメントが企業に与える経営的リスクや、社会からの信頼・企業イメージに直結することを強調しましょう。法的責任や社会的信用への影響を具体的に示し、対策が経営戦略の一環であることを理解させる内容が効果的です。
このように、立場や職務に応じて内容を調整することで、全社的に一貫した理解と対応力が育まれ、ハラスメント防止の取り組みに深みが出ます。
研修を機能させるための工夫と継続支援
研修の効果を持続させ、職場全体の行動変化につなげていくには、内容の工夫と継続的な支援体制が不可欠です。最初の一歩として有効なのが、事前アンケートやヒアリングを通じた参加者のニーズ把握です。受講者の関心や不安を事前に把握し、それに即したコンテンツを組み込むことで、研修の「当事者感」が高まり、学びが深まります。
演習形式の導入も効果的です。例えば、部下の言動に違和感を覚えたときの対応方法、顧客からの無理な要求への対処法など、実際の職場で起こりうる場面を取り上げたロールプレイやディスカッションを行うことで、理解が深まり行動にも結びつきやすくなります。
また、研修後のフォローアップも重要な要素です。受講者への振り返りアンケートやミニテストを通じて、理解度を測定するとともに、未理解な箇所を補完できるようにします。社内ポータルサイトや社内SNSを活用して定期的に情報を発信し、日常業務の中でも学びを継続できる仕掛けを整えると、研修効果が組織に定着しやすくなります。
さらに、数か月に一度のフォローアップ研修や、1on1面談での確認など、小さなステップを積み重ねていくことが肝心です。こうした継続的な取り組みによって、ハラスメントのない職場文化が徐々に浸透していきます。
ハラスメント発生時の正しい対応フロー
ハラスメントが発生した際、企業が適切な対応を取れるかどうかは、職場の信頼性を保つ上で極めて重要です。被害者が安心して声を上げられる環境を整え、加害者に対しては事実に基づいた公正な判断を下す必要があります。また、同様の事態を繰り返さないために、再発防止の仕組みを構築し、組織全体での対応力を高めていくことも欠かせません。この章では、対応の流れと社内体制整備のポイントについて解説します。
被害者・加害者への適切な対応
ハラスメントが発生した際には、被害者と加害者の両者に対し、迅速かつ公正な対応を行うことが重要です。まず、被害者には安心して話ができる環境を整え、心身の安全を確保することが優先されます。被害内容についての事実関係を正確に把握し、本人の言葉に丁寧に耳を傾けることが信頼関係の構築につながります。加えて、必要に応じて医療機関や弁護士、外部の相談機関との連携を図ることで、被害者が適切な支援を受けられる体制を整えましょう。
一方で、加害者に対しては、感情的な対応を避け、客観的な事実確認に基づいて処分を検討する姿勢が求められます。調査は関係者からの聞き取りなどを通じて公正に実施し、その結果に基づいた措置を講じる必要があります。内容によっては厳正な懲戒処分も検討されるべきですが、同時に加害者が自らの行為を理解し、再発防止につながる教育的支援を受けられる仕組みを設けることも有効です。
また、職場全体における対応として、周囲の人々ができるサポートも見逃せません。被害者の感情に寄り添い、安心して相談できるような雰囲気を作るとともに、適切な情報提供や相談先の紹介など、具体的な支援行動を職場全体で共有していくことが、再発防止にもつながっていきます。
再発防止に向けた記録と社内体制の整備
ハラスメント対応において、事後の対応を適切に行うとともに、同様の事態が再び起こらないようにするための体制整備が不可欠です。その第一歩が、発生した事案に関する記録の作成です。日時、関係者、内容、対応状況などを漏れなく記録し、必要に応じて関係部署と共有することで、再発防止に向けた課題の抽出が可能になります。こうした記録は、外部機関からの問い合わせや、万が一の法的対応の際にも重要な資料となります。
加えて、ハラスメント対応を一過性のものにせず、継続的に管理するための社内体制の整備が求められます。具体的には、ハラスメント対策委員会や外部の専門家を含む第三者委員会の設置、社内通報制度の充実、関係部署との連携体制の構築などが考えられます。体制が明確であればあるほど、社員は安心して相談や報告を行うことができ、結果としてハラスメントの早期発見・解決につながります。
さらに、社内での共有だけでなく、事案の傾向や対応実績を定期的に集計・分析し、方針や研修内容の見直しに反映させることも重要です。こうしたPDCAサイクルの実行により、組織としての対応力が高まり、ハラスメントを未然に防ぐ土壌を育てることができます。


ハラスメント対策の評価と改善サイクル
ハラスメント対策は、一度実施したら終わりというものではありません。対策の効果を適切に評価し、必要に応じて見直しを行うことが、職場全体の信頼性を高めるためには不可欠です。とくに、研修や制度を「やったこと」ではなく、「効果があったかどうか」で判断する姿勢が、組織の健全な成長につながります。この章では、効果測定の具体的な方法や、フィードバックを活かした制度の改善について解説します。
効果測定の指標と手法
ハラスメント対策において、研修や方針策定を行うことは重要ですが、それ自体が目的になってしまっては本質的な改善にはつながりません。実施後の効果を正確に把握し、継続的な改善へとつなげる評価サイクルこそが、対策の定着と職場環境の向上に欠かせない要素です。
効果測定を行うには、まず明確な評価指標と手法を設定する必要があります。定期的に行う匿名アンケートやヒアリング、研修前後の比較調査などを通じて、従業員の意識や職場の空気感にどのような変化があったかを把握します。また、研修内容の理解度や、その後の実践状況を確認するフォローアップテストや簡易評価フォームも、定量的な把握に役立ちます。
これらの情報を部署別・階層別に分析することで、組織の中でも特にリスクの高いエリアや、対策が浸透していない層を明確にすることができます。特に管理職の理解度や実践度を重点的に測ることで、リーダー層の姿勢が職場全体にどのような影響を及ぼしているかも見えてくるでしょう。
研修や対策の有無に満足するのではなく、その“後”にどんな変化があったのか、どの施策が実効性を持ったのかを検証し続ける姿勢が、継続的な改善につながります。
フィードバックの活用と制度の見直し
ハラスメント対策をより実効性あるものにするためには、現場の声を起点としたフィードバックの活用が欠かせません。社員が実際にどのような課題を感じているのか、どのような制度が機能していないのかを把握することが、制度改善の第一歩になります。
フィードバックの収集は、定期的なアンケートや意見募集、研修後の感想記入など、日常的に取り組める方法で継続することが重要です。とりわけ、自由記述の声や少数意見にこそ、見逃されがちな問題の芽が潜んでいることがあります。そうした意見を無視せず、丁寧に分析して対応する姿勢が、組織の信頼性を高めます。
また、集まったフィードバックを制度見直しにどう反映するかも大切な視点です。通報制度の使い勝手やプライバシー保護の運用、研修の頻度や内容の調整、相談窓口の対応体制の強化など、具体的な改善点を洗い出し、順次実施に移していきましょう。
さらに、自社内だけで完結せず、外部専門家の意見や他社の成功事例を参考にすることで、自社の対策の客観性と信頼性が向上します。こうしたサイクルを回すことにより、ハラスメント対策は一過性の取り組みではなく、企業文化として根付いていくのです。
ハラスメント防止の実践事例と企業の取り組み
ハラスメント対策は、制度やルールの整備だけでは完結しません。実際に職場で何が起きているのかを見つめ、どのような場面でリスクが顕在化するのかを理解することが大切です。ここでは、ある企業が直面した実際のトラブルをきっかけに、どのようにハラスメント防止に取り組んだのか、そのプロセスを事例としてご紹介します。
現場で起きた事案から学ぶ:ハラスメント防止研修の事例
ある情報システム関連企業では、業務系システムの開発・保守に携わるエンジニアを中心に、プロジェクト単位で顧客先に常駐する業務スタイルが一般的です。プロジェクトごとに他社と合同でチームを組むことも多く、顧客や外部パートナーと協働する場面が日常的に存在します。
そうした中、外部チームとの協業プロジェクトにおいて、メンバー間のコミュニケーションがうまくいかず、顧客から対応に対する懸念が示される出来事がありました。社内で確認したところ、事実関係は明らかになったものの、当該社員自身や周囲の組織には、ハラスメント防止に関する十分な理解や教育の機会が不足していたことが判明しました。
このような背景を受けて、経営陣が組織的な課題として認識し、リーダー層を対象とした研修の必要性を明確化。30名弱のメンバーを対象に、現場で起こり得るハラスメントのリスクや、その防止に向けた実践的なスキルの習得を目的とする研修が設計されました。
研修では、ハラスメントの定義や法的なリスクを押さえた上で、実際に起こり得る事案に近いケースをもとにグループディスカッションを実施。さらに、相手の受け取り方を踏まえた伝え方をロールプレイ形式で学ぶなど、業務現場での実践を想定した内容とすることで、受講者の理解と納得を促進しました。現在では他部門にも展開が進められ、組織全体での再発防止意識の醸成につながっています。
この事例は、ハラスメント防止に取り組む際、法令や社内ルールを学ぶだけでは不十分であることを改めて気づかせてくれます。現場での実践に必要なのは、相手との関わり方や伝え方といった、日常的なコミュニケーションの質を高めることです。受け取り方の違いや立場の差に配慮した接し方を学ぶことで、ハラスメントの芽を早期に摘み取る感覚を育てることができるのです。
よくある質問と対応のヒント
ハラスメント対策を進める中で、現場の担当者や管理職から寄せられる疑問や不安は少なくありません。とくに相談窓口の運営方法や、社員への伝え方、管理職が現場でどう対応すべきかといった実務面の悩みは、対策の実効性を左右する重要な要素です。この章では、よくある質問に対する実践的なヒントを紹介しながら、現場で迷わず対応できるようになるためのポイントを解説します。
相談窓口運営のポイント
職場内でハラスメント問題が発生した際、最初に相談が寄せられる場所となるのが相談窓口です。従業員が安心して相談できる環境を整備することは、対策の根幹をなす取り組みと言えます。相談窓口を適切に機能させるためには、まず対応を担当する職員に専門的な知識とスキルを備えさせることが重要です。ハラスメントに関する基礎知識だけでなく、対応時の言葉遣いや聞き取り方、感情の扱い方までを含めた教育が必要です。
相談内容に関しては、機密性を確保することが絶対条件です。相談者のプライバシーが守られていないと感じれば、声を上げることにためらいが生じてしまい、問題の発見が遅れて深刻化する恐れもあります。記録の取り扱いや情報共有の範囲について明確なルールを設け、関係者以外に情報が漏れない体制を築きましょう。
また、相談に対して迅速に対応する姿勢も信頼構築に不可欠です。初期対応が遅れれば、相談者の不安が増し、事態が悪化する可能性があります。相談受付から初動対応までの流れをマニュアル化し、社内で共有しておくことで、属人的な対応のばらつきを防ぎます。さらに、定期的な運営状況の確認や改善も行いながら、相談窓口を常に信頼できる存在として維持することが求められます。
管理職の対応時に注意すべきこと
管理職は、組織内でハラスメント対策を実行する上で、極めて重要な役割を担います。部下からの相談を受けた際には、まず相手の話に真摯に耳を傾け、丁寧に対応する姿勢が求められます。相談を受けた段階での無理解や軽視、あるいは不用意な発言は、被害者に二次被害を与える恐れがあります。
また、ハラスメントの申し立てがあった場合には、すぐに事実確認を行う準備を始めることが大切です。ヒアリングの手順や記録の取り方についても、あらかじめトレーニングを受けておくと、対応に迷いが生じにくくなります。同時に、加害者とされる人物への対応にも配慮が必要です。事実が確定していない段階で一方的な判断をせず、公平性を保った形で話を聞くことが求められます。
さらに、社内のハラスメント方針や相談体制について日頃から部下に伝えておくことも、管理職としての大切な責任です。万が一問題が起こった際に、どう対応するかを組織として共有しておくことで、混乱や情報の錯綜を防ぐことができます。管理職自身が率先して対策に取り組むことで、職場全体の意識向上にもつながります。
社員向け説明時に伝えるべき内容
ハラスメント対策を社内に浸透させるためには、社員一人ひとりへの丁寧な説明が欠かせません。ただ制度を設けるだけではなく、なぜその制度が必要なのか、企業としてどのような姿勢をとっているのかを、具体的な事例や言葉を用いて伝える必要があります。
社員説明の際には、まず「ハラスメントとは何か」という基本的な定義と、職場における該当例を具体的に紹介しましょう。何がセクハラに該当するのか、どのような言動がパワハラと見なされるのかを明確にすることで、社員自身の言動を見直すきっかけにもなります。また、相談窓口の利用方法や、相談時に守られるプライバシーについても丁寧に説明することが、実際の利用促進につながります。
加えて、社員には「傍観者にならない」意識を持ってもらうことも大切です。職場で問題を目にしたとき、どのような対応が適切なのか、周囲の支援や通報のあり方も含めて共有しましょう。こうした啓発は一度きりではなく、定期的に行うことが効果的です。説明会のほか、社内報やポスター、オンラインツールなどを活用し、繰り返し伝えることで理解が定着していきます。
まとめ
ハラスメント対策は、法令に則った制度整備だけでは十分とは言えません。重要なのは、社員一人ひとりが正しい知識を持ち、互いに尊重し合う関係性を築くことです。特に現場で日々行われるコミュニケーションの中に、無意識のハラスメントの芽が潜んでいることも少なくありません。
だからこそ、単なるルールの周知にとどまらず、日々の業務に即した事例やロールプレイを通じた研修を取り入れることが、効果的な対策につながります。企業としての信頼性を高め、働きやすい職場を実現するために、今できる一歩から始めてみましょう。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
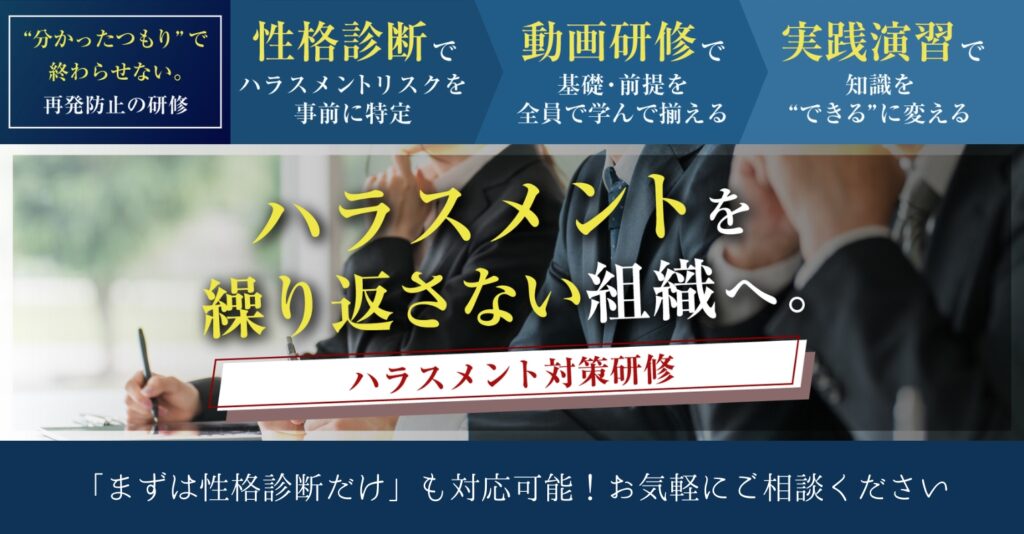

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。