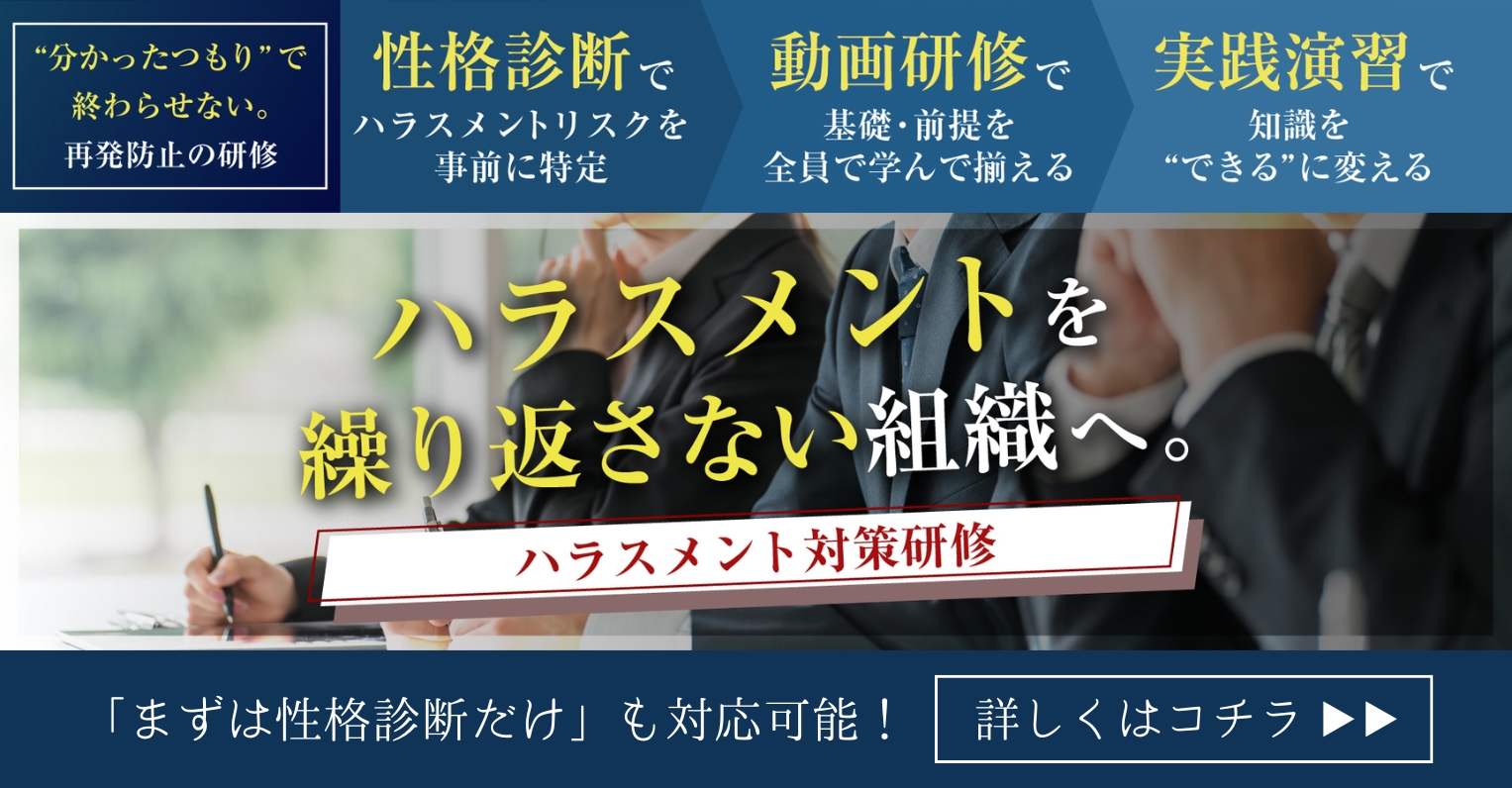近年、ハラスメントに対する社会の目は一層厳しくなり、企業に求められる責任も大きく変化しています。パワハラやセクハラといった明確な行為だけでなく、日常のなにげない言動や関係性の中にも、ハラスメントの火種が潜んでいる時代です。
本質的なハラスメント対策とは、単に法令を守ることにとどまりません。働く人が安心して声を上げられ、自分らしく力を発揮できる職場づくりを通じて、組織全体の信頼と生産性を高めていくこと。そのためには、個人の意識だけでなく、組織としての仕組みや文化、そして日々のコミュニケーションのあり方を見直す必要があります。
本記事では、ハラスメントが起きにくい職場に共通する特徴から、企業が取り組むべき具体的な対策、現場での実践事例、そして社員一人ひとりの意識を変えるためのアプローチまで、包括的に解説します。
制度や研修で“やったつもり”で終わらせないために。本質的な改善のヒントを、貴社の取り組みにぜひお役立てください。




なぜ今、企業に「ハラスメント対策」が求められているのか
近年、企業を取り巻く労働環境や社会の価値観は大きく変化しています。職場でのハラスメントに対する社会的関心も年々高まっており、これまで以上に企業としての対策が強く求められるようになりました。
この章では、なぜ今「ハラスメント対策」が必要とされているのかを明らかにし、職場に与える影響や、企業が果たすべき社会的責任について解説します。単なる法令順守にとどまらず、従業員が安心して働ける環境を整えることの重要性を、さまざまな角度から考えていきます。
なぜ今「ハラスメント対策」が必要なのか
ハラスメント対策が企業に求められる理由は、単に法令への対応という枠に収まりません。近年、社会全体の人権意識の高まりや、メディア・SNSの影響により、ハラスメント問題は企業活動に直結する重要なテーマとして扱われるようになっています。
とくに働き方改革や多様性の推進が進む中で、異なる価値観を持つ人が一緒に働く機会が増え、これまで当たり前とされていた言動が、ハラスメントと受け止められることも少なくありません。価値観のすれ違いによってトラブルが生まれやすくなっている今だからこそ、企業としての明確な姿勢が求められています。
対策に取り組む企業では、風通しが良く、従業員が安心して働ける環境づくりが進み、結果として生産性の向上や人材の定着につながっています。ハラスメントを未然に防ぎ、誰もが能力を発揮できる職場を実現することは、持続的な成長のための土台でもあります。
職場に与える影響と放置するリスク
ハラスメントが放置された職場では、従業員同士の信頼関係が損なわれ、チームワークの低下や業務効率の悪化が起こります。相談できない雰囲気や、「見て見ぬふり」が当たり前になることで、心理的な安全性が失われ、従業員の定着率にも悪影響を及ぼします。
また、社内だけでなく、社外への影響も見逃せません。パワハラやセクハラなどの問題が表面化した場合、SNS等での拡散により企業の信用が一気に失われるリスクもあります。ひとたび問題が発覚すれば、採用活動への影響や取引先からの評価低下、さらには訴訟リスクや行政指導といった事態に発展する可能性もあります。
これらのリスクは、明確な対策を講じていれば未然に防げたかもしれないものです。「自分の会社には関係ない」と見過ごすことこそが、もっとも大きなリスクと言えるでしょう。
社会的責任としての重要性
ハラスメント防止は、企業の「社会的責任」として取り組むべきテーマです。特に、2020年のパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)によって、企業はハラスメントを防ぐための措置を講じることが義務付けられました。これは企業規模を問わず、すべての職場に適用される法的義務です。
この法律は、企業に相談窓口の設置や、再発防止措置、社内方針の明確化などを求めるもので、形式的な取り組みだけでは不十分とされています。実効性のある体制を構築し、社員一人ひとりが「ここなら安心して働ける」と感じられる環境を整えることが、今後ますます重要になっていきます。
ハラスメントのない職場を目指すことは、単に問題を防ぐためではなく、企業が社会から信頼され続けるための基本姿勢とも言えます。取引先や求職者、地域社会から見て、安心して関わることができる会社であるかどうか。その判断材料として、ハラスメント対策の有無が大きな影響を与える時代になってきているのです。
ハラスメントが起きない職場に共通する3つの特徴
ハラスメントが発生しやすい職場には、共通して「人間関係の断絶」や「コミュニケーション不足」が見られることが少なくありません。逆に言えば、信頼関係や安心感のある職場では、問題が深刻化する前に対話が生まれやすく、ハラスメントが発生しにくい土壌が育まれています。
この章では、実際にハラスメントの起きにくい職場に共通する3つの特徴を取り上げます。心理的安全性、対話と指導のバランス、多様性への理解と尊重。それぞれの要素が、働く人々の安心感と信頼を支え、トラブルの未然防止につながっている理由を詳しく解説します。
心理的安全性が保たれている
ハラスメントが起きにくい職場に共通するもっとも重要な特徴の一つが、「心理的安全性」が確保されていることです。心理的安全性とは、職場の中で自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態を指し、上司や同僚から否定されたり、評価を下げられたりする不安を感じることなく、率直に対話できる関係性が築かれている環境を意味します。
このような職場では、従業員がミスを恐れずに挑戦できるため、業務改善や創造的な提案も生まれやすくなります。そして、違和感や不満も早い段階で共有されるため、ハラスメントの芽を未然に摘むことが可能になります。たとえば、ある言動が「少し嫌だ」と感じたときに、それを気軽に伝えられる雰囲気があれば、誤解やすれ違いが大きな問題に発展する前に解消されやすくなるのです。
また、心理的安全性が保たれている職場では、上司と部下、同僚同士のあいだに信頼があり、感情や意見を表に出すことが組織の成長にとってプラスになると捉えられています。反対に、誰もが「何も言わないほうが安全」と感じてしまうような環境では、表面的には静かでも水面下で不満や緊張が積み重なり、ある日突然、ハラスメントとして噴き出すリスクもあります。
心理的安全性は、個人の意識だけでなく、組織としての姿勢やマネジメントのあり方にも深く関係しています。上司が自ら率先して意見を歓迎し、失敗を責めない態度を取ること、否定せずに受け止める姿勢を示すことが、チーム全体に安心感を広げる土台となります。
安心して声を上げられる職場こそが、ハラスメントのない組織づくりの第一歩です。心理的安全性は目に見えにくいものですが、だからこそ意識的に育てていく必要があるのです。
指導と対話のバランスが取れている
職場において上司が部下を指導する場面は避けて通れません。しかし、その指導が一方通行であったり、相手の人格を否定するような言葉になっていたりすると、たとえ意図していなくても、ハラスメントと受け取られてしまう可能性があります。そこで重要になるのが、「指導」と「対話」のバランスです。
ハラスメントが起きにくい職場では、厳しさだけでなく、相手とのコミュニケーションを重視する姿勢が根付いています。業務上の課題やミスに対して注意を促すことは必要ですが、それを伝える際に「なぜそれが必要なのか」「どうすれば改善できるのか」といった説明や、相手の理解度に応じた声かけを意識することで、受け止め方が大きく変わります。
たとえば、単に「この資料はダメだ、作り直して」と言われるのと、「目的に合った提案にするには、こういう観点を追加するともっと良くなると思うよ」と伝えられるのとでは、相手の受け取り方も納得感もまったく異なります。こうしたコミュニケーションの積み重ねが、指導を「成長の機会」として受け入れやすくし、関係性の信頼を深めていきます。
また、対話のある職場では、部下から上司へも意見を伝えやすい空気があります。自分の考えや感じたことを率直に話せる環境があるからこそ、上司も自身の指導方法を見直したり、誤解を早期に修正したりすることができるのです。
「厳しく言えば育つ」という時代は、すでに過去のものになりつつあります。今求められているのは、相手を尊重しながらも、必要なことをしっかり伝える“伝え方の質”です。丁寧な言葉選び、相手の受け取り方への配慮、感情的ではなく論理的な説明。こうした工夫が、ハラスメントリスクの低減につながり、同時に育成の質も高めてくれるのです。
適切な指導と、信頼に基づいた対話が両立している職場は、メンバーが安心して成長できる環境であり、結果として組織全体の健全な発展にもつながります。
多様性と相互理解が尊重されている
近年、企業のあらゆる場面で「多様性(ダイバーシティ)」という言葉が広く使われるようになりました。性別や年齢、国籍だけでなく、価値観、働き方、ライフスタイル、経験、障がいの有無など、多様な背景を持つ人が共に働く時代において、多様性を前提としたコミュニケーションが極めて重要になっています。
ハラスメントが起きにくい職場では、この「違い」に対して寛容で、相互理解を深めようとする姿勢が文化として根づいています。誰かの発言や行動に対して、「自分の常識と違う」と感じたときにすぐに否定するのではなく、「なぜそう感じるのか」「背景にはどんな考え方があるのか」と、一歩踏み込んで理解しようとする姿勢があるのです。
たとえば、ある社員が残業を断ったとき、「やる気がない」と捉えるのではなく、「家庭の事情があるのかもしれない」「仕事の進め方を工夫しているのかもしれない」と、多様な事情を想像することが、誤解や偏見を防ぐ第一歩になります。
また、価値観が違うからこそ起こるすれ違いや摩擦を、「個人の問題」ではなく「文化の違い」として捉える視点も重要です。自分とは異なる背景や視点を持つ人と働くには、お互いの理解を深める対話が欠かせません。研修やワークショップでの交流、異文化理解の機会づくり、心理的安全性を土台にしたチームミーティングなど、仕組みとして対話を生む工夫も効果的です。
このように、個人が“違い”を受け入れるだけでなく、組織としても「多様性を活かす」方針や制度があることで、安心して働ける風土が醸成されていきます。その結果として、ハラスメントの芽は早期に見つかり、トラブルが大きくなる前に防止できるのです。
多様性と相互理解が尊重される職場は、単にハラスメントを防ぐだけではありません。社員一人ひとりが「自分らしく働ける」感覚を持つことで、エンゲージメントが高まり、生産性や定着率にも好影響をもたらします。つまり、ハラスメント対策と組織の成長は切り離せない関係にあるのです。
ハラスメントが生まれる背景と原因
ハラスメントを防ぐためには、個人の問題として片づけるのではなく、それが生まれてしまう職場の土壌や仕組みに目を向けることが大切です。多くの職場で、「それくらい仕方ない」「どこにでもあること」と見過ごされてきたような環境や関係性が、実はハラスメントの温床となっていることも少なくありません。
この章では、ハラスメントの背景にある3つの要素──「コミュニケーションの不足」「職場風土や価値観のズレ」「権限や上下関係の構造的な問題」──に注目します。どれもすぐに変えることは難しいかもしれませんが、小さな見直しや工夫によって、職場の空気を大きく変えるきっかけになります。自社の状況に照らしながら、どこにリスクが潜んでいるかを見つめ直す視点として活用してください。
コミュニケーション不足が招く誤解
日常のコミュニケーションが不足している職場では、小さなすれ違いや誤解がそのまま放置され、大きな問題へと発展してしまうことがあります。特に、相手の意図がわからないまま受け取った一言や行動は、「無神経な言動だった」「馬鹿にされた」といったネガティブな印象に変わりやすく、ハラスメントの火種となります。
近年は、業務の効率化や柔軟な働き方の浸透により、やり取りが簡潔になったり、オンライン上での会話が中心になったりするケースも増えています。こうした働き方には大きなメリットがある一方で、雑談やちょっとした声かけのような“非公式なコミュニケーション”が減り、相手の背景や感情を読み取る機会が少なくなることもあります。その結果、意図しないすれ違いや誤解が生まれやすくなるのです。
また、指導や評価の場面では、フィードバックの伝え方によって受け止め方が大きく変わります。丁寧な言葉選びや、相手の理解度に応じた説明がないと、「一方的に責められた」と感じられてしまうことも少なくありません。そうした誤解が積み重なると、不信感やストレスにつながり、関係性の悪化を招く可能性があります。
ハラスメントを防ぐためには、日常的な信頼関係の構築が欠かせません。形式にこだわらず、雑談や1on1ミーティング、チャットでの気軽な声かけなど、組織に合った方法で“対話のきっかけ”を意識的につくることが大切です。さらに、ポジティブなフィードバックを交えた双方向のコミュニケーションを心がけることで、相互理解と安心感が生まれやすくなります。
職場風土や価値観のズレ
ハラスメントが発生しやすい職場には、その組織特有の風土や価値観の偏りが影響しているケースが少なくありません。たとえば、「結果を出すことがすべて」といった価値観が極端に優先される環境では、プロセスや人間関係への配慮が後回しになりがちです。その結果として、強引な指導や無理な働きかけが正当化され、当事者が不快に感じても「指導の一環」として片づけられてしまうことがあります。
また、長年同じメンバーで構成されている組織では、暗黙のルールや空気感が根付いていることがあります。「これくらい言っても大丈夫」「うちの職場では普通」といった考え方が、外部の視点から見ればハラスメントに該当するケースでも、内部では問題とされないまま放置されることがあるのです。
こうしたズレがあると、新しく入った社員や若手社員が違和感を抱えても声を上げにくく、問題が見えにくいまま蓄積されていきます。多様な価値観が共存する今の時代において、過去の常識や慣習に固執してしまうことは、無自覚のうちに誰かを傷つけたり、排除してしまうリスクにもつながります。
ハラスメントを防ぐ職場づくりの第一歩は、「自分たちの価値観がすべてではない」と認識することです。多様な考え方を受け入れ、柔軟に見直す姿勢を組織として持つことが大切です。そのためには、研修や対話の場を通じて、互いの違いを前向きに捉え、理解し合う文化を育んでいく必要があります。
職場全体が“相手の感じ方”を尊重する土壌を持っていれば、たとえ言葉や態度にズレがあったとしても、気づいた段階で軌道修正することができます。価値観の違いを受け入れ合える風土こそが、ハラスメントの予防につながる大きな力になるのです。
権限・上下関係の構造的問題
企業や組織において、ある程度の上下関係や役割分担は必要不可欠です。しかし、その「上下関係」が適切に機能していないと、権限の行使が一方的になり、ハラスメントにつながるリスクが高まります。
特に、日本の職場文化では、上司に対して異を唱えにくい空気や、「年次が上=発言力が強い」といった価値観が根強く残っている職場も少なくありません。このような状況では、指導の名のもとに過度な叱責や押しつけがましい言動が起きても、それを疑問視する声が上がりにくく、結果として“構造的にハラスメントが黙認されやすい状態”になってしまいます。
また、近年は多様な雇用形態が一般的になり、正社員と契約社員、派遣社員、業務委託など、立場の異なるメンバーが同じ職場で働くことが増えています。その分、権限の違いや影響力の格差も大きくなりやすく、無意識のうちに「立場を利用した圧力」が生じる場面も少なくありません。
こうした構造的な問題に対処するには、まず「何がハラスメントにあたるのか」という共通認識を職場全体で持つことが重要です。そして、上下関係のある場面でも“言いやすさ”や“相談しやすさ”を確保する取り組みが求められます。たとえば、上司と部下の間に定期的な1on1を設けたり、匿名で意見を伝えられる制度を導入することで、力関係に偏らない健全な関係性を保つことができます。
さらに、組織として「権限の乱用を許さない」というメッセージを明確に打ち出し、行動規範として示すことも効果的です。ルールと責任を明文化し、違反時の対応を明確にすることで、誰もが安心して働ける環境に近づいていきます。
上下関係や権限の存在そのものが問題なのではなく、それが適切に運用されているかどうかが問われています。立場にかかわらず、誰もが尊重される職場をつくることが、ハラスメントを防ぐ土台になるのです。
ハラスメントを防ぎ、再発させないための仕組みづくり
ハラスメントをなくすためには、個人の意識や言動だけでなく、組織としての仕組みや環境づくりが不可欠です。誰もが安心して働ける職場を実現するには、発生を未然に防ぐ予防策と、万が一発生した際の適切な対応、そして再発を防ぐための継続的な取り組みが求められます。
この章では、ハラスメント対策を制度として機能させるために必要な「社内ポリシーの策定」「相談窓口や通報体制の整備」、そして「効果的な研修の導入と運用」について解説します。さらに、ハラスメントが発生した際の対応と再発防止策についても触れ、一過性の対処に終わらない、継続的な職場改善の視点をお伝えします。
明確な社内ポリシーの策定
ハラスメント防止の土台となるのが、組織としての明確なポリシーの策定です。これは単なるルールの掲示ではなく、職場全体に「ハラスメントを容認しない」という明確な姿勢を示す重要なメッセージでもあります。ポリシーがあることで、どのような行為がハラスメントに該当し、どのように対処されるかを全従業員が理解しやすくなり、未然防止に大きな効果を発揮します。
ポリシーを策定する際には、抽象的な表現にとどまらず、具体的なケースを交えてわかりやすく記述することが求められます。たとえば「上司による叱責」や「私的な質問の強要」など、曖昧になりがちなグレーゾーンについても明記しておくと、現場での判断がしやすくなります。
また、作成したポリシーは策定して終わりではなく、全従業員への周知と定着が不可欠です。イントラネットや研修、ポスターなど、複数の手段を使って繰り返し伝えることで、日常業務の中に自然と組み込まれていきます。さらに、法改正や社会の動向をふまえて定期的に見直しを行い、常に最新の内容に保つことも重要です。
このように、企業としての姿勢を明文化し、従業員一人ひとりが自分ごととして理解・実践できる状態を目指すことが、ハラスメントの起きにくい職場づくりの第一歩となります。
相談窓口と通報体制の整備
ハラスメントの早期発見と適切な対処には、相談窓口と通報体制の整備が欠かせません。問題が発生しても、安心して声を上げられる仕組みがなければ、事態は見えないまま深刻化してしまいます。
信頼される相談体制を構築するためには、まず相談者の匿名性とプライバシーの保護を徹底することが基本です。誰にも知られずに相談できることが明示されていれば、被害を受けた人はもちろん、周囲で気づいた人も行動に移しやすくなります。また、相談対応にあたる担当者は、社内の人間関係に左右されないよう、外部の専門機関や第三者を活用する方法も効果的です。
さらに、寄せられた相談には迅速かつ丁寧な対応が求められます。対応が遅れたり、形式的な受け答えに終始したりすれば、相談者の不信感を招き、制度そのものの形骸化につながってしまいます。相談後の対応フローや改善措置の説明などを明確にし、相談者が「きちんと受け止めてもらえた」と感じられるようにすることが大切です。
相談窓口は、単なる「設置すべきもの」ではなく、職場の信頼関係を築く重要なインフラです。運用のあり方を定期的に見直しながら、社員が安心して声を上げられる環境づくりを目指していきましょう。
ハラスメント研修の導入と実施
制度や仕組みを整えるだけでなく、従業員一人ひとりの意識と行動を変えていくためには、ハラスメント研修の実施が欠かせません。日常の中で無意識に行っている言動が、実は相手にとって負担や苦痛になっている可能性があることを学ぶことで、ハラスメントの“予防”につながります。
研修は一度きりで終わらせず、定期的に実施することが重要です。繰り返し学ぶことで認識が深まり、意識が習慣として根づいていきます。また、座学だけでなく、実際の事例をもとにしたディスカッションやロールプレイなど、参加者が主体的に取り組める内容にすることで、より実践的な学びが得られます。
さらに、受講者の理解度や反応を確認するために、研修後のアンケートや意見交換の場を設けることも効果的です。フィードバックを受けて内容をブラッシュアップし続けることで、現場の実態に即した研修へと進化させていくことができます。
ハラスメント対策を実効性のあるものにするには、組織としての仕組みと並行して、「学びを続ける文化」を根づかせることが鍵となります。
管理職・リーダー層向けのポイント
管理職やリーダー層は、組織の風土や人間関係に大きな影響を与える存在です。そのため、ハラスメント研修では一般社員以上に「組織を導く立場」としての責任と行動が求められます。
この層に向けた研修では、ハラスメントの定義や事例を学ぶだけでなく、部下への指導の仕方やフィードバックの伝え方など、日常業務での言動を見直す視点を取り入れることが重要です。また、問題が発生した際の対応フローや、相談を受けた際の初動対応についても具体的に学べる内容にすることで、実践力が高まります。
「知らなかった」「悪気はなかった」が通用しない立場であるからこそ、意識的にアップデートを重ね、部下の信頼を得ることがハラスメント防止の大きな力になります。
一般社員向けのポイント
一般社員に向けたハラスメント研修では、「加害者にも被害者にもならないためにどうすればよいか」という視点に加えて、ハラスメントと適切な指導の違いを正しく理解することが大きなテーマとなります。日常的なコミュニケーションの中で、自分の発言や態度が相手にどう伝わるのかを意識することは、予防の第一歩です。
研修では、ハラスメントの定義や具体的な事例を学ぶとともに、「これは指導?それともハラスメント?」といったグレーゾーンについて考えるワークを取り入れると、理解が深まります。特に、上司からの指摘や注意を、感情的にハラスメントと受け取ってしまわないようにするためにも、指導の意図や職場での役割を整理しながら、受け手側としての理解力や受け止め方にも目を向けることが大切です。
また、「見て見ぬふりをしない」「違和感を言葉にする」といった、第三者としての行動も研修の中で取り上げることで、職場全体でハラスメントを防止する空気づくりにつながります。個人の意識とスキルを高めることが、働きやすい環境の基盤となるのです。
研修後のフォローアップ体制
どれほど質の高い研修を行っても、学びを職場に持ち帰って行動に移せなければ意味がありません。そのため、研修後のフォローアップ体制を整えることは極めて重要です。
具体的には、定期的な振り返りの機会を設ける、管理職による1on1の場での確認、職場内でのミニワークショップの実施など、研修内容を継続的に活用できる仕掛けが求められます。また、研修で得た学びが業務や人間関係の中でどう活かされているかを共有し合う文化を育てることも、定着に向けた一歩になります。
こうした継続的な取り組みによって、単なる「受けっぱなし」ではない、行動変容につながる研修が実現します。
ハラスメント発生時の対応と再発防止策
万が一ハラスメントが発生してしまった場合、企業には迅速かつ適切な対応が求められます。対応の遅れや不十分な対処は、被害者の心身の状態を悪化させるだけでなく、職場全体の信頼を損なうリスクをはらんでいます。発生を「なかったこと」にせず、真摯に向き合う姿勢こそが、再発を防ぐ第一歩です。
まず大切なのは、被害者の声に耳を傾け、配慮ある対応を徹底することです。心理的な安全性を確保し、必要に応じて専門機関と連携したサポート体制を整えることで、被害者の安心感を支えることができます。特に、二次被害の防止にも注意が必要です。被害者が周囲の視線を気にすることなく働き続けられる環境を整えることが、信頼回復の鍵となります。
次に、事実確認と加害者への対応です。感情的な判断に流されることなく、証言や記録を基に冷静かつ公平な調査を行いましょう。加害者には適切な処分を講じるとともに、ハラスメントの再発を防ぐための教育的な措置を検討することが重要です。懲罰だけで終わらせるのではなく、組織としての学びや改善にどうつなげるかが問われます。
最後に、再発防止の視点を忘れてはなりません。事案の背景や職場環境を見直し、組織としてどのような改善が必要かを明確にすることが求められます。場合によっては、職場の風土やコミュニケーションのあり方、ルールの運用などに踏み込んだ見直しが必要になることもあります。
発生後の対応を「点」で終わらせず、「線」や「面」として組織全体に展開していくことで、同じことを繰り返さない強い職場づくりへとつながっていきます。
現場で取り組まれているハラスメント対策の実例
ハラスメント対策は「やるべきこと」として語られることが多い一方で、実際にどのように取り組めばよいのか、社内にどう定着させるかに悩む声も少なくありません。そこで本章では、実際の企業における取り組みをもとに、研修導入の背景や現場の課題、成果につながった工夫や定着の工夫について紹介します。
制度を形だけで終わらせず、社員の行動や職場の空気を変えていくために、どのような視点や設計が有効なのか。実践に根ざした事例から、貴社の取り組みに活かせるヒントを見つけていただければと思います。
ハラスメント防止に向けた研修導入の背景と狙い
ある企業では、現場において一部の職員が感情的な言動に陥る場面が散見され、ハラスメントに発展するリスクが懸念されていました。さらに、社員同士のコミュニケーション不足が影響し、個人プレーが強まり業務の偏りが生じるなど、チーム全体のパフォーマンスにも影を落としていたのです。組織の中心を担う世代が40代以上に偏っていることから、若手社員の育成体制にも課題があり、組織としての成長基盤を見直す必要性が高まっていました。
こうした背景を踏まえ、「ハラスメント防止」というテーマを切り口にしつつも、単なる法令順守にとどまらない、コミュニケーションを軸に据えた予防的アプローチに焦点を当てた研修が企画されました。研修では、ハラスメントの定義や法的リスクといった基本知識の理解に加えて、実際の現場で起こり得る事例を題材としたディスカッションやロールプレイングなどを取り入れ、参加者が自らの言動を振り返りながら、より良い関係性を築くスキルを実践的に学べる構成としました。
管理職向けには、「伝える力」や「信頼を築く関わり方」に重点を置いた内容とし、一般社員向けには、ハラスメントを正しく理解し、必要な場面で適切に対処・相談できるようになるための基本スキルを扱いました。
研修後には、「ただ避けるだけでなく、適切なコミュニケーションによってハラスメントを未然に防ぐことが大切だと気づいた」「アドバイスではなく、相手の思いを引き出す関わりを意識したい」など、参加者の意識変化が見られました。加えて、「全社的に取り組むべき内容」「上位層も含めて共通理解が必要」といった声も寄せられ、組織全体での意識改革につながる研修となりました。
ハラスメント研修を効果的にするための工夫ポイント
ハラスメント研修を実施しても、「一方通行の座学で終わってしまう」「受け身のまま参加している人が多い」といった声が出ることもあります。効果的な研修にするためには、設計段階から“主体的な学び”を促す工夫が必要です。
まず、研修の冒頭では、参加者に「なぜこの研修を受けるのか」を丁寧に伝えることが重要です。ハラスメント対策は誰かのためではなく、自分や仲間を守るための知識でありスキルであるという意識を持ってもらうことで、理解の深まりや行動の変化が期待できます。
また、具体的な事例を使ったディスカッションやロールプレイは、参加者が「自分だったらどうするか」を考えるきっかけになります。指導とハラスメントの境界線を考えるワークなどを通じて、正解が一つではない難しさと向き合う経験は、日常での判断力にもつながります。
さらに、管理職と一般職で求められる役割は異なるため、階層別にテーマや進行方法を変えることで、それぞれが納得感を持って学べる内容になります。研修を「受けさせられるもの」ではなく、「自分の仕事に役立つもの」と感じてもらえるかどうかが、研修の成否を大きく左右するのです。
社内定着を促すフォローアップ施策
一度の研修で得た学びを職場に根づかせるには、継続的なフォローアップが不可欠です。知識や意識があっても、日々の業務に流される中で学んだ内容が薄れてしまうのは自然なこと。だからこそ、学びを定着させる仕組みが重要です。
たとえば、研修後の振り返りシートやアンケートの実施は、参加者自身が学んだことを整理する機会になります。加えて、チーム単位で「どう活かすか」を話し合う場を設けると、職場全体の意識が高まり、日常の行動にも変化が見られるようになります。
定期的なミニ勉強会やリマインド資料の配信も効果的です。「この前の研修、覚えてますか?」という一言とともに配られるチェックリストや事例紹介は、忘れかけていた学びを呼び起こし、職場の会話のきっかけにもなります。
また、相談窓口の周知や、職場でのフィードバック文化の醸成など、研修の内容とつながる取り組みを日常業務の中に散りばめていくことで、ハラスメントを“自分たちの問題”として捉える空気が育ちます。
学びを一過性にしないこと。それが、ハラスメントのない職場づくりにつながる本当のスタートラインです。
社員の意識と行動を変えるためにできること
現場で意識変容を促すためのアプローチ
ハラスメントを防ぐには、正しい知識を持つだけでなく、日々の言動や他者への接し方に変化が生まれること=意識変容と行動変容が何より重要です。そのためには、個々の気づきに任せるだけでは不十分で、組織として意識変容を“促す仕掛け”をつくる必要があります。
たとえば、次のようなアプローチが有効です:
具体的な問いを投げかける場をつくる
日々のチームミーティングや研修後の振り返りで、「相手の立場だったらどう感じるか?」「これは適切な伝え方だったか?」などの問いを投げかけることで、自分の言動を客観視する習慣が生まれます。
小さな“気づき”を言語化する文化を育てる
ちょっとした声かけや、気持ちよく伝えられたことなど、日常の中にある“良い関わり”を称賛し、共有する仕組みをつくることで、「こういう関係性が良いよね」という価値観が可視化されていきます。
感情や背景をすり合わせる時間を設ける
定例の1on1や対話の場で、「どんな気持ちだったか」「なぜその対応をしたのか」といった背景を共有する機会をつくることで、誤解やすれ違いの芽を早期に摘むことができます。
ロールプレイやケーススタディを通じて実践する
知識で終わらせず、「どんな伝え方が良いか」「どう反応するか」を体験できる機会を設けると、理解が深まり、実際の職場での言動に反映されやすくなります。
大切なのは、「こうした方が良い」と分かっていても、実際に“やってみる”場をつくり、継続的に働きかけることです。意識は一度の研修や声かけで変わるものではありません。現場で自然とリフレクション(内省)できる風土や、行動を促す仕掛けが整ってはじめて、ハラスメントを防ぐ職場文化が根付き始めます。
自身の言動を見直すきっかけづくり
ハラスメントを防ぐための第一歩は、自分自身の言動を見直すことです。ただし、「見直すべき」と頭では分かっていても、日々の忙しさの中でそれを自然に実行できる人は多くありません。だからこそ、職場として、社員一人ひとりが“自分の言動を振り返る”ためのきっかけを意識的につくることが重要です。
たとえば、1on1やチーム内でのフィードバックの場で「相手にどう伝わっていたか」を確認したり、研修後の振り返りの時間に「自分の発言や態度がどうだったか」を見つめ直す問いかけを用意したりと、日常の中に小さな“立ち止まり”を組み込むことで、自分の言動を客観視する視点が育ちます。また、ロールプレイや動画教材を活用して、他人のやりとりを外から見る体験を通じて「自分も気をつけよう」と思える機会をつくるのも効果的です。
重要なのは、「これは適切な指導だっただろうか」「相手の立場で受け取ったらどう感じるか」と、自らの言葉や態度を一歩引いて見られる力を少しずつ高めていくこと。行動を変えるには、まず“気づくこと”が必要です。そしてその気づきを得るための環境や問いかけが、意識を変える土台となります。個人任せにせず、職場として「考えるきっかけ」を意図的に設計することで、言動の質は着実に変わっていきます。
ハラスメントを“見て見ぬふり”させない職場風土
ハラスメントを根本的になくしていくためには、加害者と被害者の関係だけに注目するのではなく、「その場にいた周囲の人がどう行動するか」が非常に重要です。どんなに対策を講じても、誰も声を上げず、見て見ぬふりが当たり前の風土がある限り、ハラスメントは組織に根を張り続けてしまいます。
人は、目の前で問題が起きていても、「自分には関係ない」「余計なことは言わない方がいい」と判断しがちです。特に上下関係が強い職場や、同調圧力のある環境ではその傾向が強くなります。しかし、黙認され続けたハラスメントはやがて組織全体の信頼を損ない、優秀な人材の離職や企業イメージの悪化につながります。
だからこそ、「おかしいと思ったら声を上げていい」「気づいたことは共有する」という文化を根づかせることが大切です。たとえば、「注意喚起は必ずしも告発ではない」というスタンスを明確にしたり、匿名で意見を伝えられる手段を整えることで、声を上げることに対する心理的なハードルを下げていく必要があります。
また、誰かが勇気を出して行動したときに、それを否定せず肯定的に受け止める組織の姿勢も不可欠です。「言ってくれてありがとう」「早く気づけてよかった」というフィードバックがあるだけで、次に声を上げる人が出やすくなります。小さなアラートに耳を傾けられる職場こそが、ハラスメントを未然に防げる強い組織と言えるでしょう。
まとめ
ハラスメントを防ぐ取り組みは、特別な何かを導入することではなく、日々のコミュニケーションや関係性を見つめ直すことから始まります。一人ひとりの意識が変わり、組織としての仕組みが整い、職場の空気が少しずつ変わっていく——その積み重ねこそが、ハラスメントのない職場づくりの原動力です。
「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、学びを続け、対話を重ね、違和感をそのままにしない文化を育てていくことが求められています。誰もが尊重され、安心して働ける環境は、企業にとって最大の財産です。
本記事で紹介した視点や事例が、貴社のこれからの取り組みのヒントとなり、働く人すべてにとってよりよい職場づくりにつながることを願っています。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
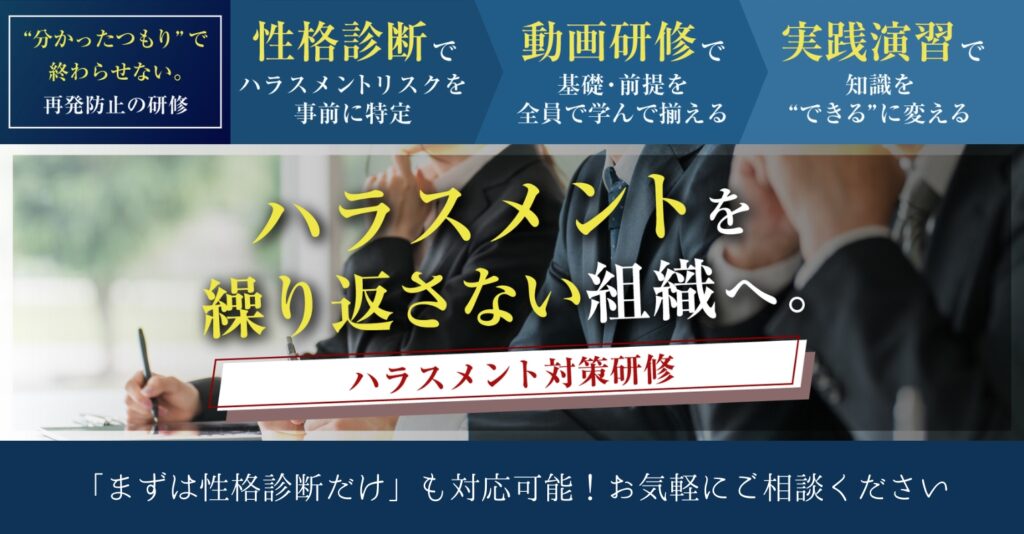

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。