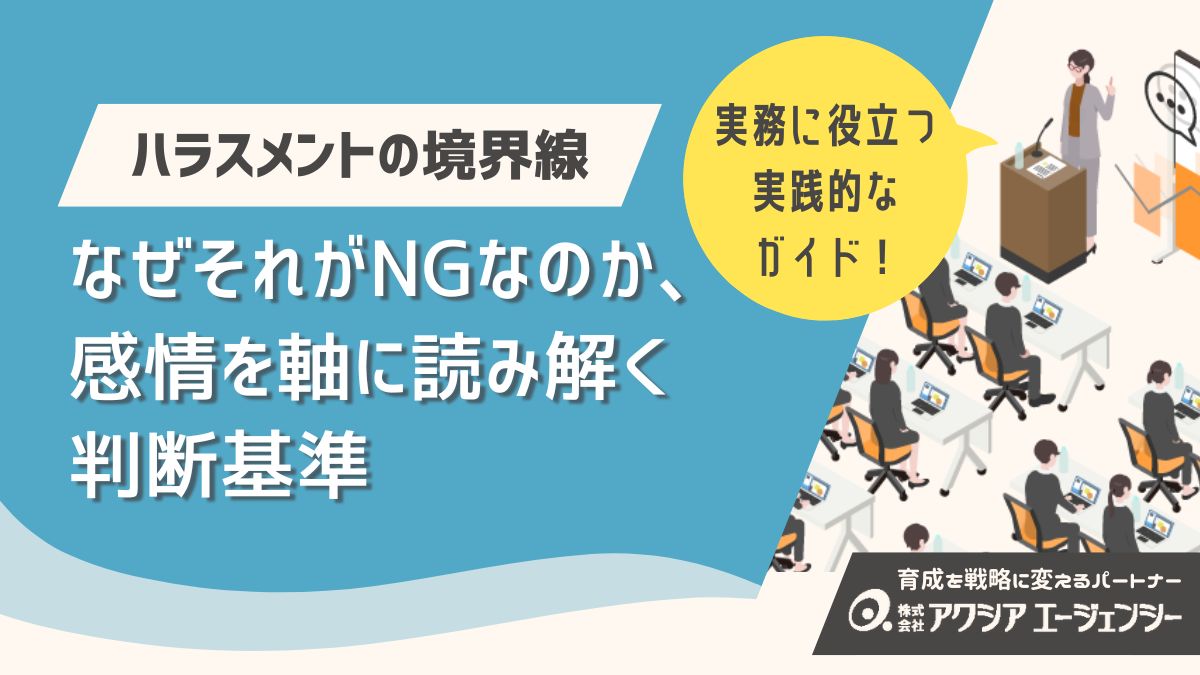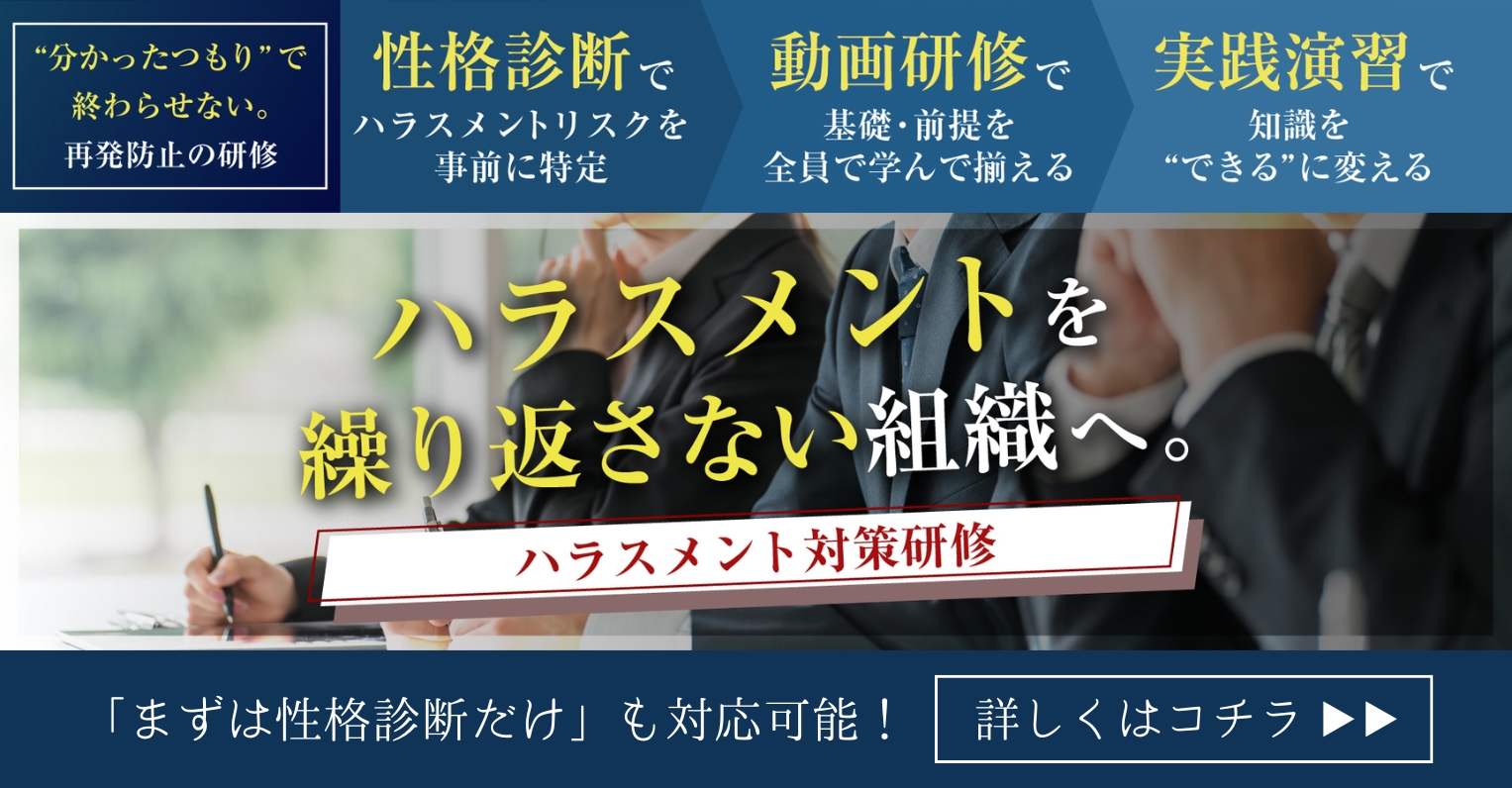職場で「これは指導?それともハラスメント?」と迷う場面は少なくありません。
部下から「人格を否定された気がする」と訴えられることもあれば、逆に上司が「誤解されるのでは」と不安を抱き、指導そのものをためらってしまうケースもあります。こうした 指導と嫌がらせ等の境界線 があいまいな状況では、仕事の効率や人材育成に重大な支障を及ぼします。
特に近年の雇用環境では、多様性の尊重やプライバシーの保護が求められ、徹底したハラスメント防止対策を講じることが不可欠です。指導の際には、精神的な影響や身体的な侵害リスク まで含まれる可能性があるため、単なる言葉選び以上に、能力開発や職場文化のあり方が問われています。
さらに、上司・同僚・部下といった立場の違いが「どの程度までが適切か」という認識のズレを生みやすく、場所や時間、状況に応じて判断が難しくなる要素も多く存在します。その結果、社員が安心して遂行すべき仕事に集中できず、雇用の安定や組織の成長が阻害される恐れがあります。
本記事では、ハラスメントの定義や気を付けるべき行為の整理から、企業が作成すべき方針や体制、実施すべき研修、相談窓口の取扱い方法まで幅広く紹介します。誤解のない環境を整備することは、人材の定着を満たすだけでなく、組織の持続的成長を支える経営戦略 です。 “誤解のない職場”を実現するヒントを、一緒に探っていきましょう。


ハラスメントとは何か?現場で起きる”線引きの難しさ”
ハラスメントという言葉は、多くの企業で耳にするようになりましたが、現場では「どこからがハラスメントにあたるのか」と迷う場面が依然として多くあります。たとえば、上司による注意が「指導」なのか「パワハラ」なのか、その線引きが分からず、指導をためらう管理職の声もよく聞かれます。
ハラスメントの定義は一見すると明確なようでありながら、実際の現場では関係性や文脈、受け手の感じ方によって判断が分かれることが少なくありません。この章では、基本的な定義や種類を整理したうえで、判断が難しくなる背景や現場で起こりがちなズレについて解説します。企業として共通の認識を持つことが、対応の第一歩となります。
そもそもハラスメントとは?定義と種類
ハラスメントとは、相手に対して不快感や苦痛を与える言動を指し、その多くが職場における人間関係や力関係の中で生じます。厚生労働省の指針などにおいても、ハラスメント行為は「相手の人格や尊厳を害し、就業環境に支障を生じさせるもの」と定められています。
ハラスメントにはさまざまな類型があり、代表的な種類として以下が挙げられます。
- パワーハラスメント(パワハラ):職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、不適切な指導や叱責が行われるケース。
- セクシュアルハラスメント(セクハラ):性的な言動や身体的接触、性的な話題の強要などによって相手を不快にさせる行為。
- マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠・出産・育児を理由に不利益な扱いをする言動。
- モラルハラスメント(モラハラ):侮辱や無視など精神的な攻撃によって、相手に継続的な苦痛を与える行為。
- カスタマーハラスメント(カスハラ):顧客など外部からの不適切な言動により、従業員が心理的に害されるケース。
これらはすべて、加害者に明確な「悪意」がなくても成立する場合がある点が重要です。
ハラスメントかどうかの判断には、行為の目的や内容、状況などを踏まえた客観的な評価が必要とされます。特にパワハラのように、職場における優位性を背景とした言動では、受け手がどう感じたかに加え、その言動が業務上の適正な範囲を超えているかどうかという視点が重視されます。
つまり、受け手が不快に感じたこと自体は大切なサインであるものの、それだけで直ちにハラスメントと決まるわけではありません。あくまで、個別の状況を踏まえて総合的に判断されます。
また、同じ言動であっても、集団の中で行われるか、個別の関係性の中で起きるかによっても影響の大きさが異なることがあります。そうした意味で、ハラスメントは非常に多様かつ曖昧な性質を持ち、単純な「種類分け」では把握しきれない難しさがあるのです。
なぜ、どこからがハラスメントなのか?が分かりづらいのか
ハラスメントの線引きが難しい理由のひとつは、人によって感じ方や価値観が異なるという点にあります。特に職場では、上下関係や文化、年齢差、性別の違いなど、さまざまな要因が複雑に絡み合っており、同じ発言でも受け手によって「冗談」と取られることもあれば「侮辱」と感じられることもあります。
さらに、加害者自身が「悪気はなかった」「正当な指導のつもりだった」と思っている場合でも、相手にとっては精神的苦痛や萎縮を生む結果になることがあります。このような「意図と受け取り方のズレ」が、判断を一層難しくしているのです。
加えて、ハラスメントの定義自体が法的にすべて明確に定められているわけではないことも、現場の混乱を招く原因のひとつです。たとえばパワハラ防止法では、パワハラの「類型」が提示されてはいますが、実際の言動がどの類型に該当するかの判断は非常にケースバイケースであり、明確なラインを引くのが難しいのが実情です。こうした背景から、現場では「これはハラスメントなのか、単なる注意なのか」「この言い方はどこまで許されるのか」といった悩みが常につきまといます。職場でのトラブルや人材の定着に影響するリスクを考えると、明確な“共通認識”を組織内で持つことの重要性はますます高まっていると言えるでしょう。
「どこからがハラスメント?」曖昧な境界線と現場の声
ハラスメントに対する意識が高まるなかで、「どこからがハラスメントに該当するのか分からない」と悩む声が多く聞かれます。
特に管理職の立場にある人にとっては、「これは指導の一環なのか、それとも不適切な言動なのか」と、日々のコミュニケーションに迷いを感じる場面も増えているのではないでしょうか。
一方で、部下や従業員側からは、「あの発言、なんだかモヤモヤするけど、ハラスメントって言えるほどではない気もする…」といった、“グレーゾーン”への不安が見られます。
こうした現場の戸惑いの背景には、「立場や価値観、世代によって“感じ方”が異なる」という難しさがあります。
この章では、管理職が直面する判断の悩みや、よくあるグレーな言動、そして上司と部下の感じ方のズレについて、具体的な事例を交えながら読み解いていきます。
管理職が戸惑う「指導とハラスメントの境界」
「この注意は指導?それともパワハラになるのでは…」
そう戸惑う管理職の声は、今や決して珍しいものではありません。業務上の注意や改善指導を行うたびに、「言い方に気をつけないと」「相手にどう伝わるかが怖い」と感じている管理職は少なくないでしょう。
特にパワハラの問題は、指導との線引きがあいまいな“グレーゾーン”が多い点が現場の悩みを深めています。
厚生労働省の定義では、パワーハラスメントは「職場における優越的な関係を背景に」「業務上必要かつ相当な範囲を超えて」「身体的・精神的な苦痛を与える行為」とされています。
この“必要かつ相当な範囲を超えて”という表現こそが、多くの現場での迷いの原因です。
たとえば――
- 注意内容は正当でも、「人前で叱責する」「繰り返し同じ言い方で責める」
- 説明不足のまま、「結果だけで評価して否定する」
- 本人の性格やプライベートにまで言及してしまう
といったケースは、業務上の注意であっても、精神的な苦痛や萎縮を与えると判断される可能性があります。
一方で、職場のパフォーマンスを維持するために、指導や注意が必要であることも事実です。「ハラスメントが怖くて、指導そのものを避けてしまう」という状態は、組織の健全な成長を妨げます。
そこで重要なのが、「指導の目的・手段・受け止め方」を見直す視点です。
- その注意は業務上必要な目的に沿っているか
- 言い方やタイミングは冷静かつ具体的か
- 相手の人格ではなく行動・結果に焦点を当てているか
こうした点を意識することで、ハラスメントのリスクを避けつつ、信頼関係を壊さない伝え方が可能になります。
また、組織としては、「ここまでが適正な指導、ここからが不適切」というラインを共通言語として可視化しておくことが、管理職の不安を軽減し、指導力を支える基盤になります。
「これはハラスメント?」よくあるグレーな言動
職場で交わされる何気ない一言が、時にハラスメントと受け取られてしまう――。
そうした「グレーゾーン」の言動は、発言者に悪意がない場合ほど、対応が遅れて問題が深刻化することがあります。
たとえば、以下のような発言が挙げられます。
「この資料、なんかピンとこないな」
→ 発言自体は業務上のフィードバックであるものの、言い方や場面によっては“否定された”と感じられやすく、人格批判と受け止められるリスクがあります。
「〇〇さんってほんとマイペースだよね」
→ 性格的な特徴を指摘したつもりでも、繰り返されると“レッテル貼り”や“揶揄”と感じられ、職場での孤立や自己否定感につながる可能性があります。
「若いんだからもっとしっかりしないと」
→ 年齢に基づく発言は、意図せず世代間の差別や価値観の押し付けと受け取られることがあり、職場に不公平感を生むこともあります。
「産休入るなら、前倒しで仕上げてね」
→ 業務調整の意図があっても、配慮のない言い方や押し付けがあると、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)とみなされる可能性があります。
このような発言で注意すべきは、言った本人に悪気がなかったとしても、相手にとっては精神的な負担になっている可能性がある点です。特に、日常的に繰り返されることでストレスが蓄積され、ある日突然「ハラスメントだ」と表面化することもあります。
また、こうしたグレーゾーンの言動は、職場の文化や人間関係、上下関係などの影響を強く受けます。発言者にとっては当たり前だった表現が、相手にとっては「否定された」「嫌味に聞こえた」と受け取られることは少なくありません。
だからこそ、重要なのは「これは問題発言か?」ではなく、「どう受け取られる可能性があるか?」という視点を持つことです。そして、その違和感を相談しやすい雰囲気や、早期に対処できる体制を整えておくことが、組織全体のリスク管理にもつながります。
グレーな言動は、放置すれば関係性の悪化や退職、法的トラブルにも発展しかねません。日常の中でこそ、丁寧なコミュニケーションを意識することが、ハラスメント防止の第一歩となります。
上司と部下、感じ方のギャップとは
ハラスメントをめぐるトラブルの多くは、「そんなつもりじゃなかった」という言葉から始まります。
指導する側とされる側で、発言や行動の受け取り方が大きく異なる。その背景には、単なるコミュニケーションのすれ違いではなく、育ってきた環境や時代背景の違いが影響しているケースが多くあります。
育った時代・価値観の違い:当たり前が違うだけ
育った時代・価値観の違い=当たり前が違うだけ
今の管理職世代と若手世代とでは、「当たり前」の基準が大きく異なります。
管理職は「上下関係が明確な組織文化」「厳しさも教育のうち」といった価値観の中でキャリアを積んできた一方で、若い世代は「多様性が尊重される社会」で育ち、対等な関係性や感情面の配慮が重視される環境に慣れています。
その結果、上司が「当然の指導」と捉えている言動が、部下にとっては「感情を無視された」「一方的に押し付けられた」と感じられることがあります。
また、言葉の使い方や伝え方においても、SNSやチャット文化に慣れた世代は、短くフラットなコミュニケーションを好む傾向があり、ベテラン世代との間で表現のズレが起こりやすいのです。
つまり、双方に悪意があるわけではなく、「前提としている世界が違う」ことによってギャップが生まれているのです。
組織風土と人間関係:信頼関係の有無が感じ方を左右する
さらに、職場の雰囲気や人間関係も、感じ方に大きく影響します。
たとえば、普段から意見を言いやすい職場であれば、多少厳しい指摘でも建設的に受け止められることが多いです。
一方で、上下関係が強すぎたり、心理的な安全性が担保されていない職場では、少しの言動でも「攻撃された」と感じてしまう空気感が生まれやすくなります。
また、リモートワークの普及により、表情やトーンといった非言語の情報が伝わりにくくなったことも、誤解やすれ違いを助長する要因の一つです。
こうしたギャップの根底には、それぞれが育ってきた社会や職場文化の違いがあります。
だからこそ、「自分の常識は相手の常識とは限らない」という前提に立つことが、ハラスメント防止において重要な姿勢です。
上司は、「自分がされても気にしない」は通用しないことを理解し、部下は「自分が嫌だったから即ハラスメント」と決めつける前に、背景や意図を冷静に見つめ直す余白を持つ必要があります。
そして何より、すれ違いに気づいたときに、対話で確認し合える関係性を築いていくことが、ハラスメントを生まない職場環境づくりの土台になります。
ハラスメントが起きる背景と加害者心理を知る
ハラスメント問題を考えるとき、多くの人が被害者のつらさや職場への影響に注目します。もちろんそれは非常に重要ですが、再発防止を考える上では「なぜ加害者がそのような行動を取るのか」という背景に目を向けることも欠かせません。
加害者を単に「悪意のある人」として切り捨てるのではなく、心理的要因や組織の構造がどのように影響しているのかを理解することで、より効果的な防止策につなげることができます。
加害行動の裏にある心理的要因とは
ハラスメント加害者と聞くと、強い立場を利用して相手を攻撃する「悪意のある人」を思い浮かべるかもしれません。もちろん、意図的に相手を傷つけたり、権力を誇示するような言動は明らかに問題です。
しかし実際には、必ずしも「加害者=100%悪」という単純な構図ではないケースも多く見られます。むしろ、本人に自覚がないまま心理的要因に押し流され、結果として加害行動につながってしまう場合があるのです。
たとえば――
不安や焦りから強く当たってしまう
目標達成や納期に追われてストレスが高まると、普段なら冷静に伝えられることも、つい感情的な言葉で表現してしまうことがあります。
自分のやり方こそが正しいという思い込み
「昔はこうだった」「自分も厳しくされて成長した」という経験が、知らず知らずのうちに他者への押し付けにつながることがあります。
承認欲求や優越感を満たしたい気持ち
職場での存在感を確かめたい、部下に頼られたいという気持ちが、過剰な支配的態度に変化することもあります。
これらは必ずしも“悪意”から生じるわけではありません。
むしろ、「チームのため」「本人の成長のため」と信じていたり、自分のストレスに気づかないまま行動している場合が多いのです。
その結果、本人の意図と受け手の感じ方が大きくズレてしまい、ハラスメントと受け止められることがあります。
このように考えると、加害行動の背景には、個人の性格や一時的な感情だけでなく、心理的な要因と組織の状況が複雑に絡み合っていることが分かります。
だからこそ、ハラスメント防止を考えるときには、「加害者を責めること」にとどまらず、なぜそのような行動に至ったのかという背景理解が欠かせないのです。
ストレス・思い込み・組織文化が影響するケース
加害行動の背景には、個人の心理的要因だけでなく、職場という環境そのものが影響しているケースも少なくありません。むしろ、多くのハラスメントは「その人が特別に攻撃的だから」ではなく、過剰なストレスや組織のあり方が引き金となって表面化するのです。
納期のプレッシャー、人員不足、成果重視の評価制度――こうした状況が続くと、人は冷静な判断力を失いがちです。
本来なら建設的に伝えられることも、短気になったり、強い口調で相手を追い込む行動に出やすくなります。
また、自分が過度にストレスを抱えているときほど、周囲の小さなミスや遅れが目につきやすくなり、それが攻撃的な発言につながることもあります。
もうひとつ見逃せないのが、「これは当然」「こうすべき」という思い込みです。
「自分も昔は厳しくされて育ったから、このやり方が正しい」
「多少厳しく言わないと部下は育たない」
こうした価値観は、本人にとっては善意や経験則に基づいたものでも、相手にとっては精神的な圧力になりかねません。
特に世代間で価値観が異なる職場では、この「思い込み」がすれ違いを生みやすく、加害者が“悪気なく”ハラスメントに至ってしまう温床となります。
さらに大きな要因となるのが、職場全体の文化です。
上下関係が強く「上司の言うことは絶対」とされる風土、失敗を許容しない成果主義、過去の慣習をそのまま続ける体質――こうした文化は、強い言葉や威圧的な態度を「当たり前」と思わせる土壌になります。
たとえ一人の管理職に問題がなくても、職場全体が「厳しさこそ正義」といった雰囲気を持っていれば、その空気に飲まれ、誰もが加害者になり得るのです。
このように、ストレス・思い込み・組織文化はいずれも、本人の意識とは関係なく行動に影響を与えます。
つまり、ハラスメント対策を考えるうえで重要なのは、「加害者個人の資質」だけに注目するのではなく、環境や組織構造を見直す視点です。
過度な負荷を和らげ、対話を重視する文化を育てることこそが、加害行為を防ぎ、健全な職場をつくる土台となります。
「自分は正しい」という誤認とその危うさ
ハラスメントの加害行動の中で見逃せないのが、「これは指導の一環だ」「相手のためを思って言っている」と本人が信じてしまっているケースです。
このような誤認は、本人の意図と受け手の感じ方の間に大きなギャップを生み、結果としてハラスメントと判断される可能性があります。
問題なのは、この状態では本人に強い悪意がないために、「改善の必要がある」という自覚を持ちにくいことです。むしろ「自分は正しいのだから、相手が敏感すぎる」と考えてしまい、改善のきっかけが得られないまま、同じ行動を繰り返してしまうリスクがあります。
しかし、受け手が精神的な苦痛を感じている以上、悪意の有無にかかわらずハラスメントに該当し得ます。ここで大切なのは、「自分はどういう意図で言ったか」だけでなく、「相手にどう受け取られたか」に目を向ける姿勢です。
企業としては、このような誤認を防ぐために、単に禁止事項を伝えるだけでは不十分です。
「どこまでが適切な指導で、どこからが不適切な行為なのか」を明文化し、具体的なケースを共有することで共通認識を持たせることが必要です。
さらに、研修や面談を通じて、管理職自身が自分の言動を振り返り、気づきを得られる機会を持つことが、再発防止につながります。こうして誤認を修正し、行動を見直す仕組みを整えることで、上司・部下の双方が安心して意見を交わせる職場環境へと近づけるのです。
なぜ”認識のズレ”が職場を危険にするのか
ハラスメントの難しさは、「加害者の意図」と「被害者の受け取り方」が必ずしも一致しないことにあります。
「これは指導のつもりだった」「いや、人格を否定されたと感じた」――こうした認識のズレは、誰の職場でも起こり得るものです。
一見小さなすれ違いに思えるかもしれませんが、このズレが積み重なると、育成の停滞や離職の増加、マネジメント層の指導回避、さらには心理的安全性の低下といった深刻な課題へとつながります。やがて企業の信頼や競争力にまで影響を及ぼす可能性も否定できません。
この章では、認識のズレがもたらす実態を多角的に整理しながら、そのリスクと、企業が取り組むべき視点について考えていきます。
育成が止まり、離職が進む現場の実態
認識のズレは、人材育成の根幹を揺るがします。
上司が「指導のつもりだった」と言っても、部下が「人格を否定された」と感じれば萎縮してしまい、新しい挑戦を避けるようになります。
一方で、上司が伝えた改善点を部下が「これは大したことではない」「単なる小言だ」と軽視してしまえば、行動は変わらず、改善のチャンスを逃します。
改善が行われないということは、同じ失敗や非効率が繰り返されるということです。こうした積み重ねが、本人の成長を妨げるだけでなく、チーム全体の成果やモチベーション低下にもつながります。
結果として、組織に「学び合う文化」が育たず、成長のスピードが鈍化してしまうのです。さらに、こうした環境に失望した社員は「ここではキャリアを積めない」と感じ、転職を選択するケースも増えていきます。
離職者が続出すれば、採用コストや教育コストが膨らみ、残された社員の負担は一層大きくなり、悪循環が加速していくのです。
指導を避けるマネジメント層の心理とリスク
「これは指導?それともパワハラ?」と迷う管理職は少なくありません。
特に近年はハラスメントに対する意識が高まっており、指導が誤解されることを恐れて、**必要なフィードバックを避ける“萎縮型マネジメント”**に陥るケースが見られます。
指導を避けると、一時的にはトラブルを防げるかもしれません。しかし長期的には、部下が改善の機会を失い、チーム全体のパフォーマンス低下につながります。さらに、放置された問題が積み重なることで、結果的に大きな失敗や組織の混乱を招くリスクが高まります。
つまり、マネジメント層にとって「言えない」状況は、企業の競争力そのものを損なうリスクにつながるのです。
被害者の心理的影響とセルフケアの重要性
認識のズレが放置されると、実際にハラスメントを受けた社員は深刻な心理的ダメージを抱えます。
「自分は役に立たないのでは」「この職場には居場所がない」という自己否定感や不安は、不眠や体調不良を引き起こし、やがて休職や退職につながることも少なくありません。
さらに問題なのは、周囲の社員がその姿を目にすることです。
「ここで声を上げても守られないのでは」「自分も同じように攻撃されるかもしれない」という不安が広がると、心理的安全性が失われていきます。
心理的安全性が低下すると、社員は萎縮して発言を控えるようになります。
その結果、ミスやリスクが報告されなくなり、チーム内での情報共有や改善のスピードが落ちてしまいます。新しいアイデアも生まれにくくなり、イノベーションの停滞にも直結します。
つまり、心理的安全性を欠いた職場は、個人の健康問題にとどまらず、組織の生産性や競争力を大きく損なうのです。
こうしたリスクを防ぐためには、企業が支援の仕組みを整えることが不可欠です。
たとえば、体調や気分の変化に気づけるよう定期的な面談を設けること、信頼できる社内外の相談窓口を案内すること、外部のカウンセリングや専門機関を利用しやすい制度を用意することなどです。
こうしたサポート体制があることで、従業員は「守られている」と感じ、心理的安全性が高まります。結果として、組織全体の健全性を守ることにもつながるのです。
企業としての責任と信頼の失墜リスク
認識のズレを軽視すると、企業は法的責任や社会的信頼の失墜といったリスクに直面します。裁判や労務トラブルに発展すれば多額の賠償が発生するだけでなく、管理体制の不備として世間の注目を浴びることになります。SNSやメディアを通じた情報拡散が加速する時代においては、「ハラスメントを軽視する会社」という印象が一度広がれば、人材採用や取引にも影響が及びます。
しかしここで強調すべきは、「ハラスメント対策=防御のためのコスト」という発想にとどまらないという点です。
従業員が安心して声を上げられる環境を整えることは、人材の定着や成長を促し、組織全体の生産性や創造性を高める投資でもあります。心理的安全性が確保されれば、社員同士が率直に意見を交わし、失敗を恐れず挑戦する文化が根づきます。それは結果的に企業の競争力を強め、持続的な成長へとつながります。
つまり、ハラスメント対策は「問題を起こさないための防御」ではなく、人材・組織・企業の未来を支える経営課題なのです。
企業がとるべき「ハラスメント防止」の具体策
ハラスメントの問題は、もはや個人の振る舞いだけで解決できるものではありません。法改正によって企業に防止措置が義務付けられたことからも分かるように、組織全体で仕組みを整えることが不可欠になっています。
大切なのは「法律に従うから仕方なく」ではなく、社員が安心して働ける職場をつくるために、どのような仕組みを整えるべきかを考えることです。
ここでは、防止法の概要と企業に求められる措置を確認したうえで、社内の認識をそろえる体制づくり、相談窓口や通報制度の整備など、実務で取り入れるべきポイントを整理します。
防止法の概要と企業に求められる措置
2020年6月に施行された「労働施策総合推進法」(いわゆるパワハラ防止法)は、職場でのパワーハラスメントを防止するために制定されました。
法律ではパワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するもの」と定義しています。
企業には以下の措置が義務付けられています。
- 防止方針の明確化と周知(社内規程やガイドラインの整備)
- 相談窓口の設置(迅速かつ適切な対応体制の構築)
- 再発防止措置(調査後の対応や教育・研修)
大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月から義務化され、違反すれば厚生労働省による指導や企業名公表の可能性もあります。つまり、今やハラスメント防止は企業経営に直結する必須課題となっているのです。
社内で認識をそろえるために必要な体制づくり
法律で義務付けられた対応を整えるだけでは、ハラスメントはなくなりません。職場の一人ひとりが同じ基準を共有し、「どこからが不適切なのか」を共通の認識として持つことが大切です。そのために必要なのが、社内での体制づくりです。
まずは、ハラスメントに関するルールや約束事をはっきり示すことです。難しく言えば「ポリシー策定」ですが、要は「こういう言動はやめよう」「困ったときはここに相談できる」といったガイドラインをわかりやすく示し、全社員に周知することです。
次に欠かせないのが研修や教育の機会です。
ハラスメントの境界を理解することは、管理職だけでなく一般社員にとっても重要です。
- 管理職は、境界を知ったうえで「どう伝えれば適切な指導になるのか」を学ぶ。
- 一般社員は、境界を知ったうえで「どう受け止め、必要ならどう伝えるのか」を学ぶ。
この両方があってこそ、職場全体で誤解やすれ違いを防ぐことができます。そして共通して大切なのは、お互いの立場を尊重しながら、率直に話し合えるコミュニケーションスキルを磨くことです。
そして忘れてはいけないのが、経営層からの後押しです。ハラスメント対策を現場に任せきりにするのではなく、経営層自ら「安心して働ける環境をつくろう」というメッセージを示すことが大切です。トップが積極的に働きかけることで、「もし困ったことがあっても会社がきちんと向き合ってくれる」という安心感が広がり、全体として取り組みが定着していきます。
相談窓口や内部通報制度の整備ポイント
ハラスメントを未然に防ぐためには、社員が「困ったときに声を上げられる」と感じられる環境が欠かせません。その中核となるのが、相談窓口や内部通報制度の整備です。
整備にあたっては、以下の点がポイントとなります。
- 複数の窓口を用意する(人事部だけでなく、外部の専門窓口なども選択肢にする)
- 匿名性や秘密保持を担保する(相談したことで不利益が生じない仕組みを明示)
- 相談の流れをわかりやすく示す(どこに連絡し、どのように対応されるのかを事前に周知)
こうした制度は、利用件数の多さで評価されるものではありません。むしろ大切なのは、「いざという時には相談できる仕組みが整っている」という安心感を全社員に共有することです。
社員が「もし何かあっても会社が守ってくれる」と感じられるだけで、職場の心理的安全性は大きく高まります。
「一度やって終わり」では意味がない理由
多くの企業がハラスメント防止研修を導入していますが、「一度やったから大丈夫」と単発で終わってしまうケースも少なくありません。
しかし実際には、ハラスメント防止の意識やスキルは一度の受講で身につくものではなく、継続的な学びとトレーニングを通じて初めて定着するものです。
背景には、職場環境の変化があります。
価値観の多様化によって「どこからが不快か」の基準は人によって異なり、世代やバックグラウンドの違いがすれ違いを生む場面も増えています。さらに、リモートワークの普及などによって、日常的なコミュニケーションが希薄になり、相手の表情や意図が伝わりにくいこともハラスメントの温床となっています。
こうした状況を解消するには、法律やルールを守らせるだけでは不十分です。
「相手をどう理解するか」「どう伝えれば誤解なく届くか」 といったコミュニケーションスキルを磨き、良好な関係性を築けるようになることが欠かせません。定期的な研修は、こうしたスキルをアップデートし、日常の行動に落とし込むためのトレーニングの場として機能します。
一度きりの形式的な研修では「知っている」に留まりますが、定期的に体験し続けることで「できる」に変わっていきます。
つまり、研修は“義務”ではなく、職場をより健全で前向きな環境へと変えていくための継続的な投資なのです。
伝え方・受け止め方を学ぶ体験型研修とは
ハラスメントのグレーゾーンを減らすためには、「これはハラスメントに当たるかどうか」という知識を知っているだけでは不十分です。実際の職場では、同じ言葉でも伝え方ひとつ、受け止め方ひとつで意味が大きく変わるからです。
そこで効果を発揮するのが、体験型の研修です。
例えば、ロールプレイで「部下へのフィードバック」を実際に演じてみると、上司は「指導のつもり」で伝えた言葉が、部下には「強い否定」として響いてしまうことに気づきます。逆に部下の立場を体験することで、「自分ならどう感じるか」を肌で理解できます。
また、ケーススタディを通じて「どこからが不適切か」をグループで議論すれば、感じ方の違いを知ることができます。これにより、日常のコミュニケーションでも「相手の立場に立って考える」視点が自然に育ちます。
体験型研修の大きな特徴は、管理職と一般社員の両方にメリットがあることです。
- 管理職にとっては、「どう伝えれば適切な指導になるのか」を実践的に学べる。
- 一般社員にとっては、「どう受け止めれば意図を理解できるか」「不安を感じたときにどう伝えればいいか」を学べる。
こうした双方の理解が深まることで、単なる知識の共有ではなく、お互いに安心して意見を交わせる関係性づくりにつながります。
研修導入事例:現場の変化・受講者の声
体験型のハラスメント研修受講者からは、「単に知識を得ただけでなく、新しい視点に気づけた」という声が多く寄せられています。
ある管理職は「ハラスメントかどうかを見極めること以上に、日常のコミュニケーションの積み重ねが大事だと気づいた」と振り返ります。別の参加者は「相手の立場に立った言葉選びの必要性を実感した」と語っています。
さらに、「自分がハラスメントをしないという考え方だけでなく、部下や周囲の関係をどうサポートするかという視点を改めて意識できた」という感想もありました。
また、「ハラスメントを避けるだけでなく、むしろ適切な方法で積極的にコミュニケーションを取るべきだと気づけた」という声も上がっています。
研修は「今すぐ結果を出すもの」ではなく、こうした小さな気づきを積み重ねていくことで、やがて職場の空気や人間関係に変化をもたらしていきます。
”誤解のない職場”が、人材の定着と成長を生む
ハラスメントの線引きが曖昧なままでは、育成が滞り、社員が安心して働ける環境は育ちません。
一方で、誤解の少ないコミュニケーションが根づけば、社員は力を発揮しやすくなり、組織には挑戦や成長が積み重なっていきます。
最後に、企業が目指すべき方向性を整理します。
企業に必要なのは「安心して育てられる」環境
人材育成の場で最も重要なのは、「厳しくも適切に指導できる環境」と「社員が安心して学べる環境」が両立していることです。
ハラスメントを恐れて指導を避けてしまえば、成長の機会を奪います。しかし、配慮なく指導を行えば、信頼を損ない離職につながります。
必要なのは、上司が安心して育てられ、部下が安心して成長できる職場です。
そのためには、誤解を減らす明確な基準づくりと、相互理解を深めるコミュニケーションの実践が不可欠です。これが「安心して育てられる環境」を支える土台になります。
社内での振り返り+外部の視点で見える改善のヒント
ハラスメント防止の取り組みを進めるうえで大切なのは、最初の一歩を明確にすることです。
まずは、自社の現状を振り返り、どのような場面で認識のズレやグレーゾーンが生じやすいのかを整理することから始めましょう。これは社内のアンケートやヒアリングなど、自分たちで進めることも十分に可能です。
一方で、どうしても社内だけでは気づきにくい課題や、改善のための具体的な工夫が見えづらいこともあります。そんなときには、外部の専門的な視点を取り入れることも有効な選択肢です。
第三者の立場から現状を客観的に分析してもらうことで、新しい気づきや解決策が見えてくることも少なくありません。
つまり、「まずは自社で整理してみる」「必要に応じて外部の知見を活用する」——この二つを柔軟に組み合わせることが、誤解のない職場づくりへの確実な一歩になるのです。
まとめ
ハラスメントの線引きは、単純な「白か黒か」では判断できません。
感じ方の違いや育ってきた背景の違いが、誤解や摩擦を生み、それが職場全体の停滞や離職へとつながることがあります。
だからこそ企業に必要なのは、「安心して育てられる」環境づくりです。
法令対応という守りの姿勢にとどまらず、社員一人ひとりが安心して声を上げ、互いに学び合える土壌を整えること。
その積み重ねが、定着率の向上や生産性アップ、そして持続的な企業成長につながります。
まずは、自社の現状を整理することから始めてみてください。自社だけで進めるもよし、外部の専門的な視点を取り入れるもよし。大切なのは「職場をより良くしよう」という第一歩です。
“誤解のない職場”こそが、人材の定着と成長を生み出す最大の基盤となるのです。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
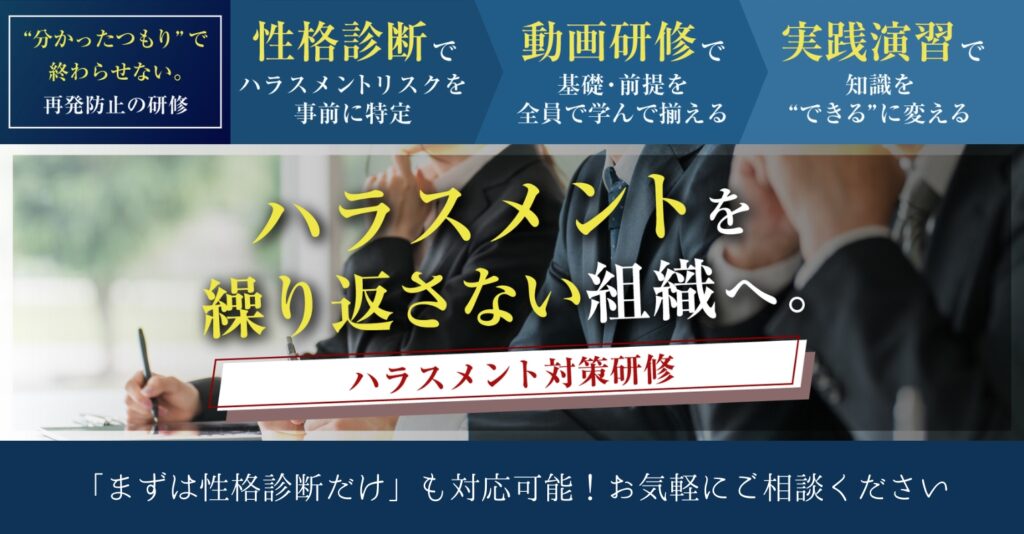

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。