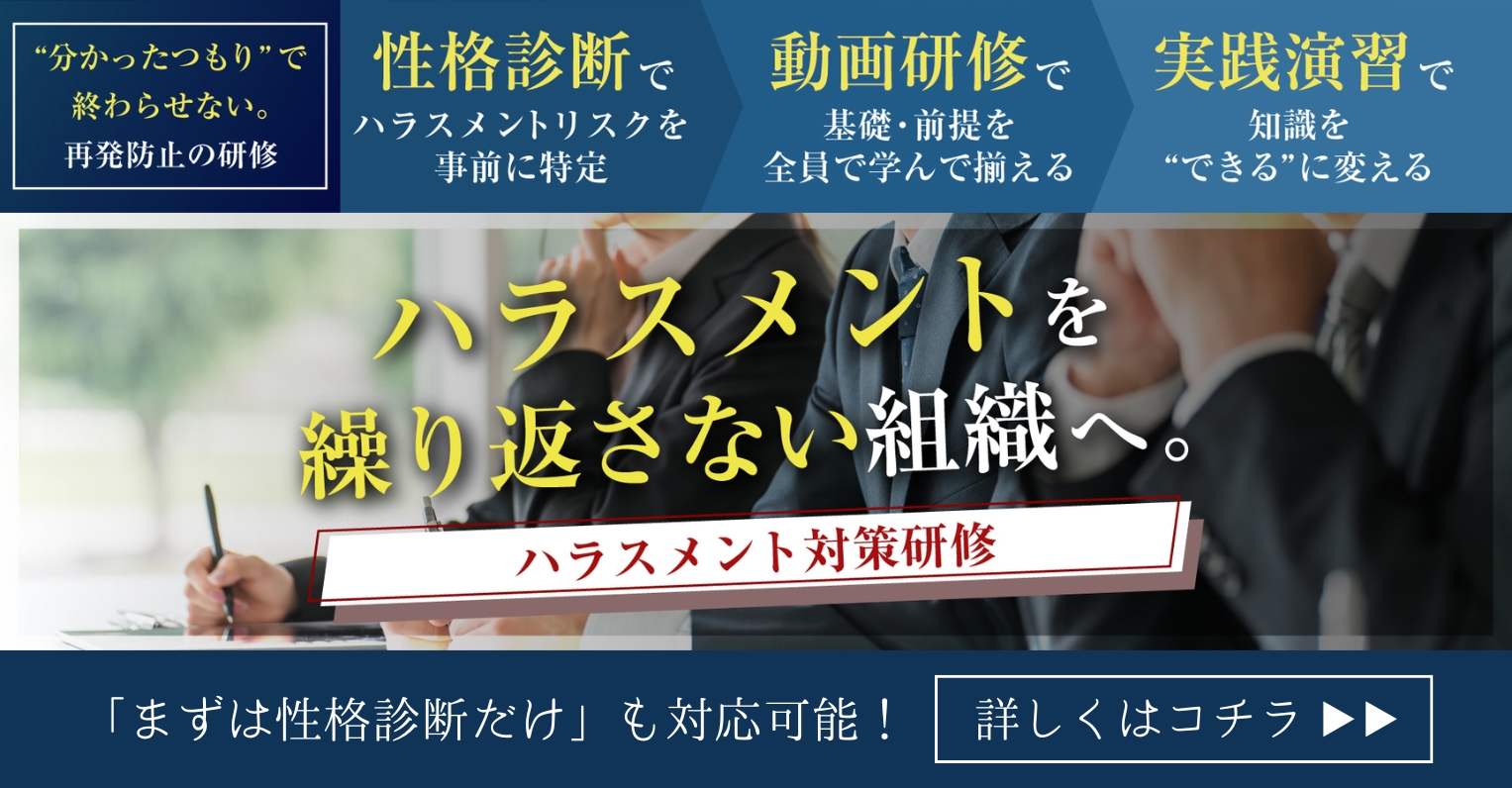ハラスメントの線引きは、かつてないほど難しくなっています。価値観の多様化や働き方の変化が進むなか、同じ言動でも受け取り方が大きく分かれ、指導とハラスメントの境界が見えにくくなっているためです。特に労働現場では、採用時の面接や入社後の指示・評価など、さまざまな場面で問題が生じやすく、対応を誤れば人材流出や生産性の低下、企業方針への不信感、さらには事業主の法的責任に直結するリスクも高まっています。
本記事では、まず「なぜ判断が難しいのか」という背景を共有し、迷いやすいケースの共通点と認識ギャップがもたらす問題を整理します。続いて、パワハラ・セクハラ・マタハラ・カスハラ等の種類ごとの判断基準を解説し、組織が講ずべき施策や管理体制の概要を示します。要点は、ルールや規程の作成だけに頼らず、第三者視点を交えた客観的な判断と、信頼関係・コミュニケーションを基盤にした職場づくりです。人事・管理職・事業主向けに、参考になる実務的な手段を整理しました。


ハラスメントの線引きはなぜ難しいのか?
現代の職場では、ハラスメントの線引きがますます難しくなっています。その背景には、急速な社会の変化や価値観の多様化、そして個人の尊重が重視される時代の流れがあります。これまで当たり前とされていた言動が、今では問題行動とみなされるケースも少なくありません。
かつては上下関係を強調したマネジメントが一般的でしたが、現在では部下との信頼関係を重視したコミュニケーションが求められています。こうした価値観の転換により、意図せずして相手に不快感を与え、トラブルや信頼関係の損失につながる事例が増えているのです。
感じ方・受け取り方の個人差
ハラスメントの判断が難しい理由の一つに、受け手によって感じ方が異なるという「個人差」があります。たとえば、上司が部下の業務改善を願ってかけた一言が、励ましとして受け取られる場合もあれば、逆に「嫌がらせ」や「人格否定」として受け止められてしまうこともあります。
人はそれぞれ、育ってきた環境やこれまでの仕事経験、労務環境、従業員としての立場が異なります。そのため、言葉や態度に対する受け止め方も多様であることを前提にする必要があります。
とはいえ、上司や先輩が必要な指導や業務上の指示を行うこと自体は、組織として当然の義務でもあります。そのため、発言を避けるのではなく、「相手にどう伝わるか」を考えたうえで表現を工夫することが大切です。受け手側もまた、全てをハラスメントと捉えるのではなく、まずはその経緯や目的を確認する姿勢が求められます。
判断を迷わせる「グレーゾーン」
ハラスメントの判断が特に難しくなるのは、「グレーゾーン」と呼ばれる領域です。これは、行為そのものが明確に法的に違法とは言い切れないが、受け手の心理や状況によっては問題になる可能性がある場面のことです。
たとえば、成績不振の社員に対して厳しくフィードバックをする場合、それが業務上の適正な指導であれば問題はありません。しかし、その伝え方が感情的だったり、時間外に繰り返されたりすると、受け手は精神的な負担を強く感じ、ハラスメントと捉えることがあります。
また、日常会話の中での冗談や軽口も、対象や時の状況によっては、無意識のうちに「嫌がらせ」と取られる場合があります。顧客や社内の従業員が関連する会話であれば、損害賠償など大きなリスクにもつながる可能性があります。
こうした「線引きの曖昧さ」が残る以上、完全に明らかにするのは困難です。そのため、組織としては第三者によるヒアリングやチェック体制を設け、客観的に参照できる情報を基づく判断基準を整備することが求められます。
そのため、全てをルール化するのではなく、日頃からの信頼関係や職場風土も含めて、相手にどう伝わるかを意識したコミュニケーションを重ねることが重要です。上司・部下の双方が不安や誤解なく関われるよう、感情面への配慮と、組織としての共通認識の育成が求められます。
管理職と若手で異なる価値観
世代間での価値観の違いも、ハラスメントが生じやすくなる一因です。管理職世代が「当たり前」と考えてきた慣行や規定に基づく働き方が、若手従業員にはストレス源となることがあります。たとえば、飲み会への強制的な誘いは過去には「慣習」とされていましたが、現在はパワハラ防止法の観点から問題視されることがあります。
一方で、若手側が上司の取扱いを誤解し、必要な指導や評価を「ハラスメントだ」と訴え、逆に組織を混乱させるケースも見られます。若手側が必要な指導や業務上の指摘を拒んだり、過剰に反発したりするケースは逆ハラスメントとも呼ばれ、法的リスクを高めかねません。大切なのは、双方が歩み寄り、相手の立場を理解する努力を怠らないことです。企業は雇用管理の一環として、世代間のギャップを埋める施策や研修を講ずる必要があります。どちらか一方が正しい・間違っていると決めつけるのではなく、お互いの価値観を尊重しながら、職場全体で健全なコミュニケーションの土台を築くことが、ハラスメントを防ぐ第一歩になります。
これはハラスメント?迷いやすい判断基準のポイント
ハラスメントの難しさは、「これは業務上の適正な指導なのか、それとも行き過ぎた言動なのか」という線引きにあります。特に、現場では判断を迷うケースが多く、当事者の意図や立場の違いがギャップを生み出し、トラブルにつながることが少なくありません。ここでは、迷いやすいポイントと公式な判断基準について整理します。
判断を迷うケースの共通点
ハラスメントかどうか判断に迷う場面には、いくつかの典型的な共通点があります。第一に多いのは「業務上の指導」と「人格攻撃」が混同されやすいケースです。たとえば、部下の成果を改善するために厳しいフィードバックを行うことは、適正な業務指導の一環です。しかし、その伝え方が感情的であったり、人前で繰り返されたりすると、受け手は自尊心を傷つけられたと感じ、ハラスメントに近いものとして受け取ります。
第二に、「本人の意図」と「受け手の受け取り方」がずれる場面もよく見られます。上司が「期待しているよ」と声をかけたつもりでも、部下にとっては「過度なプレッシャー」として響くことがあるのです。このように、同じ言動が状況や人によって全く異なる意味を持ってしまうことが、判断を難しくしています。
こうしたケースが迷いを生む根本的な理由は、「明確なルールを適用しにくい」という点にあります。同じ発言や行動でも、状況や人間関係、受け手の心理状態によって意味合いが変わってしまうため、客観的な基準に当てはめるだけでは判断がつかないことが多いのです。そのため、現場だけで結論を出そうとすると「指導なのかハラスメントなのか」が堂々巡りになりやすいのが実情です。こうしたときに重要なのが、相談窓口や外部の専門機関など、第三者の視点を交えて客観的に評価することです。
被害者と加害者の「ギャップ」が生む問題
被害者と加害者の認識のギャップは、ハラスメント問題を長期化・複雑化させる大きな要因です。加害者とされる側は「業務上必要な指導だった」と考えている一方で、被害者は「人格を否定された」「精神的苦痛を受けた」と感じている。このギャップが埋まらないまま放置されると、両者の間に不信感が積み重なり、職場全体の人間関係の悪化やチームの機能不全へとつながっていきます。
さらに問題なのは、周囲の従業員にもその緊張感が伝わることです。第三者がどちらの言い分を信じるべきか分からず、職場に派閥や沈黙が生じ、心理的安全性が低下します。結果として、業務効率の低下や離職といった深刻な悪影響をもたらす可能性があります。また、ギャップが解消されないままSNSなどで一方的な情報が拡散されれば、企業の評判や信用を損なう事態にも発展しかねません。
このようなギャップを解消するには、どちらか一方が「正しい」「間違っている」と決めつけるのではなく、相手の立場に立って理解しようとする姿勢が不可欠です。加害者とされる側は、受け手の感じ方に耳を傾けることが求められますし、被害者とされる側もまた、相手に業務上の意図があった可能性を考えることが大切です。最終的には、双方が歩み寄り、共に健全な職場づくりを目指す姿勢こそが、ギャップによる問題を乗り越えるための鍵となります。
厚労省などが示す判断基準の考え方
厚生労働省は、2025年4月施行の「職場のパワーハラスメント防止指針」において、パワハラの判断基準を以下のように整理しています。
- 優越的な関係に基づいて行われること
- 業務の適正な範囲を超えること
- 就業環境を害する程度の影響があること
この3要件を満たす場合にハラスメントと判断されます。これらの定めは中小企業を含むすべての事業主に適用され、雇用の安定や従業員の心身の健康を守るための基本的な方針とされています。たとえば、部下を繰り返し叱責し、健康を害するほどの精神的苦痛を与えた場合は、業務指導の域を超えていると評価されます。
これらの基準の意義は、判断の曖昧さを少しでも減らし、企業や従業員が共通の認識を持てるようにすることにあります。ただし、現実の現場ではケースごとに背景や人間関係が異なり、「線引きが難しい」ことに変わりはありません。そのため、厚労省の定義を基礎としつつ、企業ごとに就業規則や相談体制を整備し、適正な対応を取れる仕組みを構築することが重要です。
ハラスメントの種類ごとの判断基準
ハラスメントは一言でまとめられがちですが、種類ごとに性質や態様、判断基準は大きく異なります。ここでは代表的な4つのハラスメントを取り上げ、それぞれの定義や具体例、そして判断基準のポイントを整理します。
パワーハラスメント|指導とパワハラの違い、6類型の基準
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて行われる言動を指します。厚生労働省の指針では「優越的な関係を背景に」「業務の適正な範囲を超えて」「就業環境を害する」3要件を満たす場合にパワハラと認定されます。
代表的な事例には、過度な叱責や暴言、必要以上に長時間立たせる、無視や隔離といった行為が挙げられます。本人は「部下を育てるため」と考えていても、度を超えれば人格を否定する行為として受け止められます。
厚労省はさらに、行為を6つの類型に整理しています。
- 身体的な攻撃(殴る、物を投げるなど)
- 精神的な攻撃(暴言、侮辱的な発言など)
- 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外れ)
- 過大な要求(能力を大きく超える業務の強要)
- 過小な要求(本来の職務から外れた単純作業のみを割り当てる)
- 個の侵害(私的な情報に過度に立ち入る)
指導とパワハラの違いは「合理性」と「必要性」の有無にあります。業務遂行に必要な範囲で、適切な言葉と方法で行う指導はパワハラに該当しません。一方で、感情的な発言や行き過ぎた方法は、職場環境に支障をきたし、懲戒処分や解雇といった重大なリスクにつながる可能性があります。
セクシュアルハラスメント|性的な言動の線引きと受け取り方
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動によって相手に不快感や精神的苦痛を与える行為です。厚労省の定義では、①相手の意に反する性的言動が行われること、②その結果、就業環境が害されることが基準となります。
具体例としては、容姿や服装についての発言、身体的接触、私生活に関する性的な冗談や質問、SNSを通じた過度なメッセージなどがあります。行為者側に「軽い気持ち」や「冗談」の意識があっても、受け手が不快に感じればセクハラに該当する可能性があります。
セクハラの判断基準で重要なのは、被害者の視点と社会的文脈です。同じ発言でも、職場の立場や関係性によって受け止め方は大きく異なります。たとえば、上司からの容姿に関する発言は部下にとって強いプレッシャーとなり得ます。社会全体でジェンダー平等が推進される中、性別や関係性を軽視した言動は「時代に合わない行為」として厳しく見られる傾向にあります。
セクハラは「気をつければ避けられる行為」であり、特に管理職やリーダー層は自分の発言や態度がどのように受け取られるかを常に意識することが必要です。
マタニティハラスメント|妊娠・出産に関する配慮と制約
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、妊娠・出産・育児などを理由として従業員が不利益な取り扱いを受けることを指します。たとえば、妊娠を理由に業務から外す、育児休業を理由に昇進機会を奪う、体調を考慮せずに過度な勤務を強いるなどが代表例です。
マタハラは、被害者本人に大きな心理的負担を与えるだけでなく、家族や職場全体にも悪影響を及ぼします。「妊娠したらキャリアが止まる」という雰囲気が広がれば、女性だけでなく男性も含めた従業員全体の安心感が低下します。
判断基準としては、労働基準法や男女雇用機会均等法に基づき、「妊娠・出産・育児を理由とした不利益な取り扱いは一切禁止」とされています。解雇・降格・減給などの措置は明確に違法となる可能性があります。企業が配慮の範囲を逸脱して従業員に負担を強いた場合、法的責任を問われることもあります。
マタハラを防ぐには、就業規則やマニュアルに明記するだけでなく、上司・同僚が正しい知識を持ち、実務で適切に配慮する文化を育むことが欠かせません。
カスタマーハラスメント|顧客対応と社員保護の両立
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などからの暴言・脅迫・過剰な要求など、従業員に不当な負担や精神的苦痛を与える行為を指します。サービス業や接客業を中心に、近年大きな社会問題として取り上げられています。
具体例としては、「土下座を要求する」「営業時間外に繰り返し電話をかける」「従業員を人格否定する暴言を浴びせる」などがあります。これらは労働者の尊厳を害し、職場全体の雰囲気を悪化させる要因となります。
厚労省はカスハラについても指針を出しており、判断基準としては「要求の適正性」「態度の妥当性」「従業員の就業環境に与える影響」などが挙げられます。たとえ顧客であっても、社会通念上許容される範囲を超える要求や暴言は認められません。
企業が注意すべきなのは、「顧客第一」を理由に従業員を守らない体制が続くと、離職やメンタル不調が相次ぎ、結果的にサービスの質も低下してしまう点です。顧客対応と社員保護を両立させるためには、対応マニュアルを整備し、必要に応じて毅然とした対応を取る姿勢が求められます。
組織として取り組むべき、ハラスメント対策の重要性
ハラスメント問題は、個人の意識や行動に起因する部分が大きいと考えられがちですが、実際には「組織の仕組みや風土」がその背景を大きく左右しています。個々の従業員の努力だけに頼るのではなく、組織全体で一貫したルールとサポート体制を整備することが、職場における予防と早期解決の鍵となります。ここでは、なぜ組織としての取り組みが不可欠なのか、その理由を具体的に見ていきます。
判断基準の浸透が進まない理由
厚生労働省のガイドラインや企業の就業規則では、パワハラやセクハラの定義、禁止事項が明確に示されています。しかし、現場で実際に運用される段階になると、必ずしもルールが浸透しているとは言えません。その背景には、ハラスメントの線引きが「状況や相手の受け止め方」によって大きく変わるという特徴があります。
たとえば、文面で「過度な叱責は禁止」と書かれていても、何が「過度」なのかはケースごとに異なります。本人の性格や体調、職場の雰囲気、発言のタイミングなど、多くの要素が影響し、現場の従業員が一律に判断できるものではありません。
さらに、企業側が「規則を周知したから大丈夫」と捉えてしまうと、従業員は実際の場面で迷ったときに相談できず、結果として見て見ぬふりをする傾向が強まります。判断基準を真に浸透させるためには、条文やマニュアルの提示だけでなく、現場に即した具体例を交えた研修や、従業員同士が意見交換できる場が欠かせません。こうした「生きた知識」として伝える仕組みが整っていないことが、浸透を妨げる大きな理由となっています。
管理職・従業員間のすれ違いと不安
ハラスメント対応を難しくしているもう一つの要因が、管理職と従業員の間で生じる認識のすれ違いです。管理職は、成果を上げるために一定のプレッシャーをかけることが必要だと感じる場面があります。一方で従業員は、そのプレッシャーを過剰に受け止め、精神的な負担として捉えてしまうことがあります。
このようなすれ違いは、単なる「意見の違い」ではなく、職場の雰囲気や信頼関係に影響を与えます。たとえば、管理職が「もっと頑張ってほしい」という意図で与えた課題が、従業員には「無理を強いられている」と映ると、双方の間に不信感が積み重なります。逆に、従業員が本音を伝えられず、表面的には従っているように見えても、内心では不安や不満を抱えている場合もあります。こうした感情のギャップが解消されないまま積み重なれば、組織全体の協力体制が弱まり、モチベーションの低下や離職につながることも少なくありません。
また、管理職自身にも不安があります。「厳しく指導するとパワハラと言われてしまうのではないか」「一方で放置すれば評価責任を問われるのではないか」といった板挟みの状況です。必要な指導を避けるようになれば、部下の成長機会を奪うだけでなく、組織の成果にも影響が及びます。こうした不安や誤解を減らすには、両者が共通の理解を持ち、互いの考えを安心して共有できる対話の場が必要です。
個人任せでは限界がある組織課題
「ハラスメントは一人ひとりが気を付ければ防げる」という考え方は、一見もっともらしく聞こえますが、現実には大きな限界があります。なぜなら、従業員一人ひとりの経験や価値観は異なり、同じ状況でも判断や対応の仕方がバラバラになるからです。ある人にとっては問題にならない行為が、別の人にとっては耐えがたい苦痛になることもあり、その差を個人の努力だけで埋めるのは困難です。
さらに、組織文化そのものがハラスメントを助長する場合があります。過度な成果主義や「長時間働くことが美徳」という価値観が残っている職場では、従業員が互いに無理を強い合う構造が生まれやすくなります。このような環境では、個人がどれだけ気を付けても、根本的な改善にはつながりません。
だからこそ、ハラスメントは「組織課題」として取り組む必要があります。企業として就業規則や相談窓口を整備することはもちろん、経営層から現場まで一貫した姿勢を示すことが重要です。従業員が「ここでは安心して働ける」と感じられる環境を整えることが、離職防止や人材定着、ひいては企業全体の持続的な成長に直結します。
効果的なハラスメント対策の進め方
ハラスメント防止は「規則を作って終わり」ではなく、実際に機能する仕組みを整えることが重要です。そのためには、社内ルールの明確化、教育や情報提供の仕組みづくり、そして継続的なフォロー体制を組み合わせて取り組む必要があります。ここでは、効果的に進めるための具体的なステップを紹介します。
社内ルールや相談窓口の整備
まず基盤となるのは、社内で共有される明確なルールの策定です。パワハラやセクハラなどの定義を就業規則や社内規程に明記し、どのような言動が禁止されるのかを従業員全員が理解できる形にしておく必要があります。そのうえで、違反があった場合の対応や懲戒の基準も明確化しておくと、組織としての姿勢が示されます。
さらに、従業員が安心して声を上げられる相談窓口の設置も不可欠です。窓口は人事部門だけでなく、外部の専門機関を利用できる仕組みを併用すると、相談者の心理的なハードルを下げられます。相談があった場合には、プライバシーを尊重しつつ迅速に対応し、再発防止策を講じることが重要です。相談窓口の存在は「会社が従業員を守る姿勢を持っている」ことを示すシグナルにもなります。
ハラスメントに関する教育・情報提供の仕組みづくり
ルールを整備しても、従業員一人ひとりが正しく理解していなければ実効性は伴いません。そのため、定期的な教育・研修の実施が欠かせません。研修では、一般的な定義や法律だけでなく、実際に起こり得る具体的なケースをシナリオ形式で提示し、どう対応すべきかを考える実践的な内容にすると効果的です。
また、従業員からの疑問や意見を研修に反映させることで、「自分ごと」として理解が深まります。たとえば、ロールプレイ形式で上司と部下の立場を入れ替えて体験することで、受け取り方の違いを実感できる機会を設けると、相互理解につながります。
さらに、研修だけでなく、イントラネットや社内報、eラーニングなどを活用して継続的に情報を発信する仕組みを整えると、学んだ内容が日常業務の中で定着しやすくなります。
継続的なフォロー体制の構築
ハラスメント対策は「一度の研修や周知」で終わらせてはいけません。対策の効果を維持し続けるためには、継続的なフォロー体制が必要です。
まず、研修後のアンケートや意見収集を行い、従業員が実際に職場で活かせているかを確認します。その結果をもとに、研修内容や社内規程を定期的に見直し、改善を重ねることで制度が形骸化するのを防げます。
また、相談件数や職場環境アンケートの結果をモニタリングし、課題を早期に把握することも大切です。特定の部署や業務に偏りが見られる場合は、追加のフォローや重点的な教育を実施することで、リスクを未然に防ぐことができます。
継続的なフォローは「企業が真剣にハラスメント防止に取り組んでいる」という安心感を従業員に与えます。その積み重ねが信頼関係を強化し、健全で働きやすい職場づくりにつながります。
ハラスメントを未然に防ぐ組織づくりとは
ハラスメント防止は、起きてしまった事案に対応すること以上に、「そもそも発生させない仕組み」を整えることが重要です。そのためにはルールや規程の整備だけでなく、組織の文化や日常の関係性が大きく影響します。特に、従業員同士が信頼関係を築き、安心してコミュニケーションを取れる風土を育むことが、未然防止の最大の鍵となります。ここでは、そのために必要な3つの視点を整理します。
心理的安全性を高める風土
心理的安全性とは「自分の考えや気持ちを表明しても拒否されない」「失敗しても人格を否定されない」と感じられる状態を指します。この安心感があることで、従業員は困ったことや違和感を早めに共有でき、トラブルを水面下で抱え込まずに解決へつなげられます。逆に、心理的安全性が低い環境では、声を上げることがリスクと感じられ、ハラスメントが表面化せず深刻化する危険があります。
心理的安全性を高めるためには、管理職が率先して耳を傾け、否定せずに意見を受け止める姿勢を見せることが不可欠です。日常的に「どんな意見も大切にされる」と感じられる場をつくることで、従業員は互いに助け合い、信頼を育むことができます。また、失敗を責めるのではなく「次の成長につなげる学び」として扱う文化を根付かせることも、安心できる土壌をつくる重要な要素です。こうした風土は、自然とハラスメントを寄せつけない組織体質を形成します。
管理職と従業員双方の意識変革
ハラスメントを未然に防ぐためには、管理職と従業員がそれぞれの立場から意識を変えることが求められます。管理職は、成果を追求するあまり強い言葉を使ったり、一方的に業務を押しつけたりするのではなく、相手がどのように受け取るかを意識しながら指導を行う必要があります。一方、従業員もまた、上司の言動をすぐに「ハラスメントだ」と断定するのではなく、まずは業務上の意図や背景を理解しようとする姿勢が求められます。
この双方の歩み寄りがなければ、どちらか一方に不満や不安が積み重なり、信頼関係が崩れていきます。反対に、双方が「自分の立場だけでなく相手の視点でも考える」ことを意識できれば、不要な摩擦は大きく減少します。研修やワークショップを通じて、お互いの立場を体験する仕組みを導入するのも有効です。こうした取り組みが、指導とサポートが調和する健全な職場環境を生み出す基盤となります。
安心して育てあえる職場の実現
究極的に目指すべきは、従業員同士が安心して育て合える職場の実現です。そこでは、上司が部下を一方的に評価するのではなく、互いにフィードバックを交わし合い、学び合う関係性が築かれます。信頼関係があるからこそ、指摘も前向きに受け止められ、感謝や承認の言葉が自然に飛び交う環境になります。
このような文化が育まれると、否定や攻撃といった言動は少なくなり、代わりに「どうすればもっとよくできるか」を建設的に考える空気が職場全体に広がります。結果として、ハラスメントが発生しにくいだけでなく、従業員のエンゲージメントや定着率が高まり、企業の長期的な成長につながります。
安心して育て合える職場をつくることは、単なるハラスメント対策にとどまらず、組織の未来を支える投資です。コミュニケーションと信頼を基盤にした文化を築くことこそが、未然防止において最も効果的なアプローチなのです。
まとめ
ハラスメントの判断を難しくしているのは、価値観や受け取り方の個人差、状況依存の強さ、そして当事者間の認識ギャップです。だからこそ、条文の周知だけでは限界があり、第三者の視点を取り入れた客観的な評価と、日常的なコミュニケーションの質を高める取り組みが欠かせません。
本記事で確認したとおり、未然防止の施策は以下の三点に集約されます。
1つ目は、社内ルールと相談窓口の整備です。パワハラ等の禁止事項や懲戒の基準を就業規則に明記し、どの程度の行為が対象になるのかを具体的に示す必要があります。
2つ目は、教育・情報提供の仕組みづくりです。研修では実際の事例や業務関連のケースを用い、管理職・従業員が相互に立場を理解できるような内容を作成することが重要です。
3つ目は、継続的なフォロー体制です。アンケートや相談件数のモニタリングを行い、改善施策を講ずる手段を明確化することで、形骸化を防ぎます。
最終的な目的は、安心して育て合える職場を実現することです。心理的安全性を重視し、事業主が責任を持って方針を示すことで、従業員一人ひとりが安心して働ける環境が整います。信頼関係とコミュニケーションを基盤に、ルール・教育・管理施策を連動させる。これこそが、企業が相当の労力を投じる価値のある取り組みであり、持続的な成長につながる道筋です。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
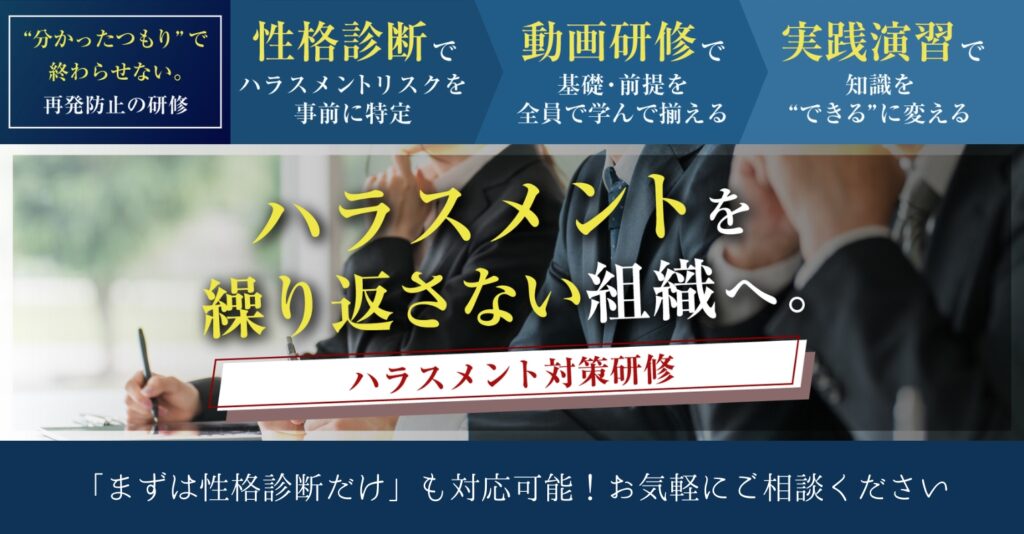

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。