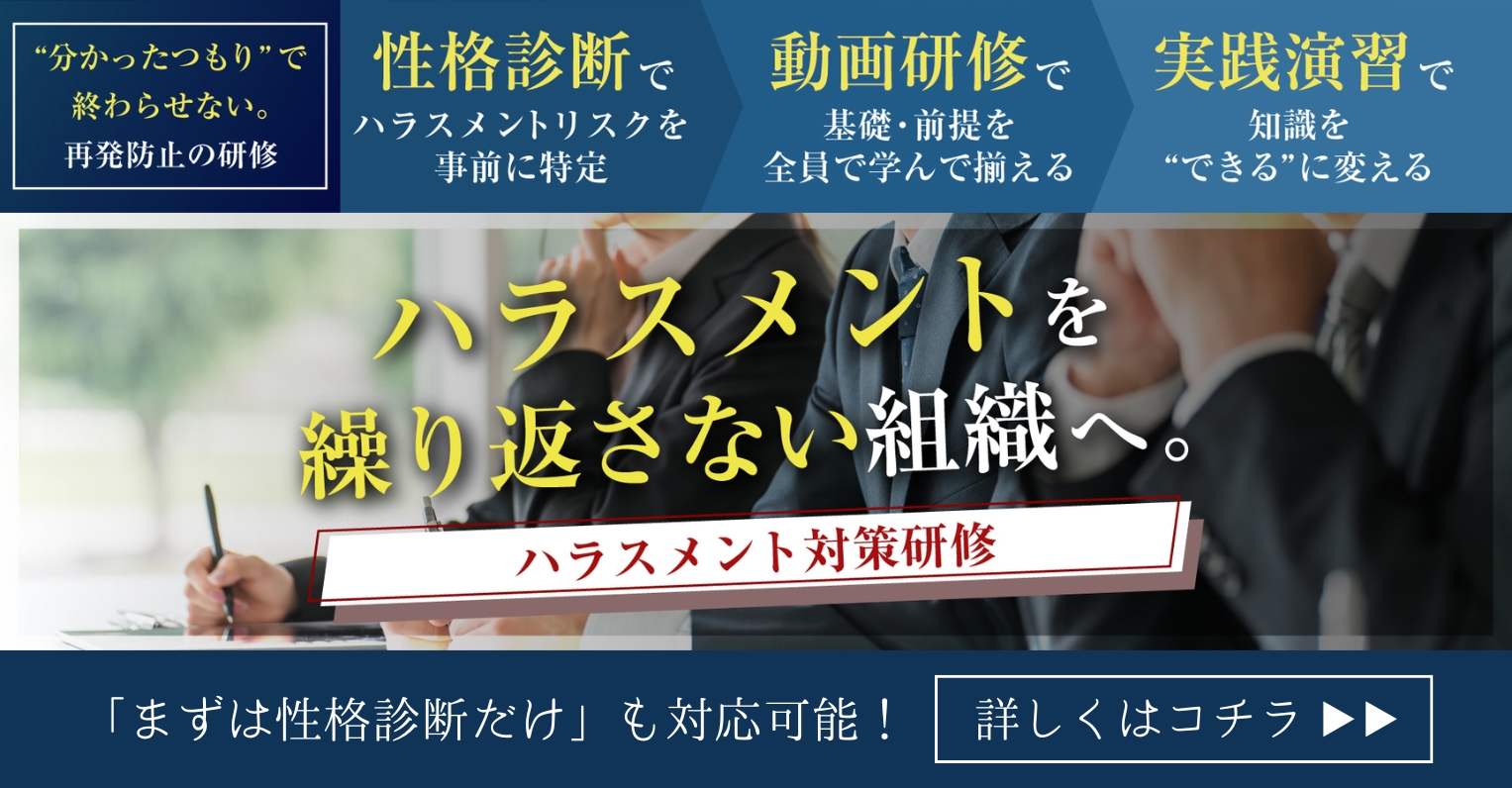働く現場では近年、「ハラスメント」という言葉を耳にする機会が急増しています。社会全体でその認知は進んでいるものの、実際にどのような行為が該当するのか、なぜ発生するのか、どうすれば防げるのかを正しく理解している人は、まだ多くないのが現実です。
ハラスメントは単なる個人の問題ではなく、職場の文化やマネジメント、さらには一人ひとりの価値観や無意識の偏見とも深く関わっています。そして、放置すれば職場環境の悪化、メンタルヘルス不調、人材流出、法的リスクといった深刻な影響を及ぼしかねません。
本記事では、職場でハラスメントが起きる原因や背景を多角的に分析し、企業が取るべき実践的な対策について、現場目線でわかりやすく解説します。ハラスメントを「自分には関係ないこと」とせず、誰もが安心して働ける職場をつくるために、今できることを一緒に考えていきましょう。


ハラスメントとは何か
ハラスメントという言葉は広く知られるようになりましたが、その定義や具体的な内容については十分に理解されていないケースも多くあります。特に職場におけるハラスメントは、本人の自覚がないままに加害行為となってしまうことも少なくありません。
この章では、ハラスメントとは何か、その定義や種類について整理し、どのような言動が該当するのかを明らかにしていきます。
ハラスメントの定義と種類
ハラスメントとは、相手の人格や尊厳を傷つける行為や発言、態度のことを指します。職場においては、上下関係や業務の指示といった正当な業務の範囲を逸脱し、相手に精神的または身体的苦痛を与える行為が含まれます。
法律上では、厚生労働省によって定められた指針やルールに基づき、「パワーハラスメント(パワハラ)」「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」「マタニティハラスメント(マタハラ)」などが明確に定義されています。それぞれの種類ごとに、加害者側の意図の有無にかかわらず、受け手が苦痛を感じたかどうかが判断基準となるのが一般的です。
たとえば、厳しい叱責や無視、仕事を与えないといった言動が、パワハラに該当するケースもあります。これらのハラスメント行為は、その場の空気や組織の文化、言葉の使い方などによっても異なり、ルールに則った適切な判断が求められます。
ハラスメントは非常に多様で、定義が曖昧なままにされやすい問題です。だからこそ、それぞれの行為が何を指し、どのように取り扱うべきかを明確に理解することが重要です。具体的な事例とともに整理することで、読者にとっての理解をより深めることができます。
ハラスメントの社会的影響
ハラスメント行為は、個人だけでなく、組織全体や社会にも大きな影響を与えます。特に職場で発生した場合は、従業員のモチベーション低下や生産性の著しい減退、人材流出といった深刻な結果を招きかねません。
たとえば、上司からの継続的な叱責によりメンタルヘルスを崩し、長期休職に至ったケースは少なくありません。こうした迷惑行為は、本人だけでなくチーム全体の士気にも影響を与え、組織の健全な成長を妨げる要因となります。
また、ハラスメントを放置する企業は、社会的信用を失う可能性もあります。SNSなどでの情報拡散が容易になった現代においては、企業の対応姿勢そのものがブランド価値に直結するため、気軽な対応は許されません。
一方で、ハラスメントの背景には、個人の過去の経験や価値観、さらには企業文化の偏りといった要素が関係していることも多く、単純に個人の問題として片付けるのは適切ではありません。今後の組織づくりにおいては、こうした現状を正しく把握し、再発防止と予防の仕組みを実現していく姿勢が求められます。
職場でのハラスメントの現状
企業がハラスメント対策に取り組むうえで、まず現状を正確に把握することは欠かせません。職場では今、どのようなハラスメントが起きているのか、相談件数はどのように推移しているのか。さらに、職場環境や人間関係がハラスメントの発生にどう影響しているのかを知ることは、対策を講じる上での第一歩となります。
この章では、相談件数の動向や職場環境との関係性に注目し、ハラスメントの現状を読み解いていきます。
ハラスメント相談件数の推移
職場におけるハラスメントへの関心は年々高まっており、それに伴い相談件数も増加傾向にあります。厚生労働省が公表している雇用環境・均等局への相談件数によると、令和4年度の職場におけるハラスメント関連の相談件数は約8万件を超えており、10年前と比較しておよそ1.5倍以上に増加しています。
特に「パワーハラスメント」に関する相談が多く、全体の過半数を占めています。また、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント、SOGIハラスメントといった新しい類型の相談も登録件数として徐々に増えており、ハラスメントの多様化が進んでいることがわかります。
性別による傾向にも違いが見られ、女性からの相談が圧倒的に多いものの、男性からの相談件数も年々増えているのが特徴です。近年は「男性も被害者になる」ことへの理解が進み、誰もが当事者になりうる問題であるという意識が社会全体に広まりつつあります。相談件数の増加は、被害が増えているという一面もありますが、同時に「声を上げやすくなった環境が整備されてきた」とも捉えることができます。企業が取り組むべき次の課題は、これらの声に対して適切に対応し、再発を防止する仕組みを確実に運用していくことにあります。
職場環境とハラスメントの関係
ハラスメントが発生する背景には、職場の物理的・心理的環境が大きく関係しています。たとえば、閉鎖的な組織文化や上下関係が強く意見を言いにくい風土では、上司からの一方的な言動がエスカレートしやすく、結果的にパワハラに発展するケースが多く見られます。
また、職場内の人間関係が希薄である場合、部下や同僚との感情的なすれ違いや誤解が起こりやすくなります。こうした関係性の悪化がストレスを誘発し、ハラスメントにつながるリスクが高まるのです。
職場におけるハラスメント対策は、単なる言動の制限にとどまらず、信頼関係を築ける就業環境の整備が重要です。職場全体が安心して感情や意見を表現できる場であれば、問題が大きくなる前に質問や相談がしやすくなるため、未然に防止することができます。
加えて、「男女雇用機会均等法」は、性別にかかわらず働きやすい環境を整えるための法的枠組みとして、ハラスメント防止にも大きな役割を果たしています。企業はこの法律の趣旨を理解し、自社の対策にきちんと落とし込むことが求められます。
ハラスメントは職場環境に起因する問題であり、個人の資質だけに責任を負わせるものではありません。職場全体の雰囲気や制度のあり方を見直すことで、より安心して働ける職場づくりにつながっていきます。
多様性とハラスメント:新たな職場の課題
近年、企業ではダイバーシティ推進が加速し、性別や年齢、国籍、価値観の異なる人材が共に働く環境が当たり前になってきました。しかし、多様性を受け入れることは同時に、異なる背景を持つ人同士のコミュニケーションの難しさや価値観のズレと向き合うことも意味します。
この章では、多様性の進展が新たなハラスメントのリスクをどう生み出しているのかを見つめ、今の職場に必要な配慮や対策について考えていきます。
ダイバーシティ推進がもたらす新たな摩擦
ダイバーシティの推進により、性別や年齢、国籍、宗教、働き方などが異なる人々が、同じ職場で共に働く場面が増えてきました。これは企業にとって非常に重要な取り組みであり、創造性や問題解決力の向上など、多くのメリットをもたらします。しかしその一方で、価値観や文化的背景の違いが、職場に新たな摩擦や誤解を生む温床となっていることも見逃せません。
たとえば、ジェンダーに関する無意識の偏見や、外国籍社員に対する配慮の欠如、年代の違いによるコミュニケーションギャップなどが、日常の業務の中で小さな軋轢を生むことがあります。本人にとっては何気ない一言や冗談でも、相手にとっては差別的・排他的な印象を与えてしまい、結果としてハラスメントと捉えられる可能性があるのです。
「当たり前」のズレと理解不足が生むリスク
職場での「当たり前」が人によって異なることが前提となるため、従来のような画一的なマナーやルールだけでは対応が難しくなっている現実もあります。例えば、日本では比較的当たり前とされる上下関係の意識や敬語の使い方も、他国や世代によっては違和感を覚えることがあるでしょう。このようなギャップは、特にチームでの連携や指導の場面で、互いにストレスや誤解を生む原因となり得ます。
さらに、SOGI(性的指向・性自認)や障がいの有無といったテーマに関する知識や理解が不十分なまま、配慮のない発言をしてしまうことで、本人の意図に反して「傷つけられた」と受け止められることもあります。重要なのは、加害の意図がなくても、受け手が被害を感じればハラスメントになり得るという点です。
相互理解を深める仕組みと組織の姿勢
このように、多様性が進むことで、職場におけるコミュニケーションの難易度は高まり、「何がハラスメントにあたるのか」という基準もより複雑化しています。企業がこの課題に取り組むためには、まず価値観の多様性を前提とした対話の土壌を整えることが不可欠です。形式的な研修にとどまらず、日常の中で相互理解を深める時間や、気づきを促す仕掛けが求められます。
たとえば、異文化理解やアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に関する研修の実施、異なる背景を持つ社員との座談会や意見交換会の場づくりなどが効果的です。多様性が活きる職場は、単に個性を尊重するだけでなく、違いを認識し合い、それを前向きに捉える風土が育っている職場でもあります。
そして何よりも大切なのは、企業として「多様性を大切にすること」と「その違いによって孤立させないこと」を両立する姿勢です。誰もが安心して働ける環境づくりの一歩は、「違いがあることを前提に、どう向き合うか」をチーム全体で考えることから始まります。
このような背景を踏まえると、ハラスメントは単なる個人の問題ではなく、職場という共同体がどうありたいかという組織全体の姿勢が問われる課題でもあることがわかります。次章では、こうした多様性の中で、なぜハラスメントが発生してしまうのか、その原因をさらに掘り下げていきます。
ハラスメントが発生する原因
ハラスメントは突発的に起こるものではなく、職場や個人に潜むさまざまな要因が複雑に絡み合う中で生まれます。特に、コミュニケーションの断絶や組織風土の問題、個人の価値観や思い込みなど、日常的に見過ごされがちな要素が、その背景に存在しています。
この章では、ハラスメントの根本的な原因を多角的に捉え、職場に潜む課題とその構造を明らかにします。企業として予防や改善に取り組むためには、まず「なぜ起きるのか」を理解することが出発点です。一つひとつの要因を丁寧にひも解くことで、より実効性のある対策へとつなげていきましょう。
コミュニケーションの不足
職場でのハラスメントの背景には、日常的なコミュニケーションの不足が大きく影響しています。業務に追われ対話の時間が減ると、相手の考えや感情を理解する機会が失われ、些細なすれ違いが摩擦に発展しやすくなります。
たとえば、定期的なフィードバックが行われず不満が蓄積されると、無視や感情的な態度などが発生しやすくなり、それがハラスメントと受け止められる可能性があります。これを防ぐには、日頃からの情報共有や意見交換の場の整備が不可欠です。共通のルールや判断基準を職場全体で共有することで、行き違いによる不快感やトラブルを減らすことができます。
職場文化と風土の影響
ハラスメントが根づきやすい職場には、同調圧力や上下関係の強さが表面化しにくい文化が見られます。「昔からのやり方」や「上司に逆らいにくい雰囲気」が無意識のうちにストレスや緊張を生み、問題を表出しにくくしています。
特に、「雰囲気を乱さないこと」が優先されがちな職場では、違和感を口にできず、不満や違和感が蓄積されやすくなります。こうした風土を変えていくには、多様な意見や価値観を受け入れる姿勢を共有することが重要です。評価や会話の中で「違いを認め合う」ことを促し、ハラスメントが起こりにくい職場づくりにつなげましょう。
個人の意識と無意識の偏見
ハラスメントの背景には、加害者本人が気づいていない無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)が潜んでいることも少なくありません。自分では正しいと思っていた言動が、相手にとっては不快な経験になっていたというケースは多く見られます。
たとえば、「若手は叱って育てるもの」「女性には配慮が必要」など、一見好意的に思える言動でも、相手の個人性を無視した対応は、時に苦痛を生むことがあります。これは、無意識に根付いた価値観や過去の経験からくる判断によって起こるものです。
そのため、自分自身の偏った意識に気づくことが、ハラスメント防止の第一歩です。意識改革のための研修やワークショップを実施し、「お互いを理解するための視点」を育てることが有効です。また、日常的な周知活動を通じて、自分と異なる意見や感情を尊重する風土を築くことが大切です。偏見は、個人の内面に深く根ざしているからこそ、意識しなければ変えられません。その意識に光を当てることが、職場全体の安全性と信頼性を高める第一歩になります。
マネジメントの欠如
ハラスメントが組織内で深刻化する背景には、マネジメントの不在や機能不全があります。管理職が部下の状態に気づけず、問題を放置してしまうケースや、適切な指導ができずに信頼関係が崩れるケースも見受けられます。
特に、指導とハラスメントの線引きが曖昧な場面では、「何を言ってもパワハラと受け取られる」と感じた管理職が指導を避けるようになり、組織の活力が失われてしまうこともあります。これは、マネジメントの不安や自信のなさが原因となっている場合が多いです。
こうした課題に対応するには、管理職のマネジメント能力を高める研修の実施が有効です。具体的には、対話の仕方、フィードバックの技術、感情のコントロールなど、現場で使えるスキルを実践的に学ぶ機会を設ける必要があります。また、従業員の声を定期的に吸い上げる仕組みの導入や、外部の専門家によるサポート体制の活用も、管理職の負担を軽減し、組織全体のマネジメントレベルの底上げにつながります。
家庭環境や育成背景の影響
職場でのハラスメント行動には、個人が育ってきた環境や価値観の形成過程が無意識のうちに影響していることがあります。たとえば、厳格な家庭で育ち、叱責が当たり前だった人は、同じような態度を職場でも無自覚に取ってしまう傾向があります。
また、学校や部活動での上下関係や、教師との関係の中で身につけた「強くあるべき」という価値観が、大人になっても残り続けることがあります。これらは、本人が意識していなくても、部下や後輩に対して過度な指導や無理な要求として表れることがあります。
このような背景を持つ人に対して、「行動そのもの」だけでなく「なぜその行動を取ってしまうのか」という視点で捉えることも、組織としての対応において重要です。ハラスメントを個人の問題に矮小化せず、背景への理解を持ちつつ是正する視点が求められます。さらに、家庭や教育現場でも価値観の多様性を育む教育が進むことで、長期的には職場のハラスメント防止にもつながっていくでしょう。企業内での研修だけでなく、社会全体での意識改革が、根本的な解決につながる鍵となるのです。
業界別に見るハラスメントの構造と対策
ハラスメントの発生要因は職場全体に共通するものも多くありますが、業界ごとの業務特性や文化、慣習の違いによってもその傾向は大きく異なります。長時間労働が常態化している業界、上下関係が厳しい業界、成果主義が強くプレッシャーの大きい業界など、それぞれの構造がハラスメントの温床となるケースが少なくありません。
この章では、代表的な業界をいくつか取り上げ、どのような背景がハラスメントを引き起こしやすくしているのか、そしてその課題にどのように対応していくべきかを整理します。自社の業界特性と照らし合わせながら、より実践的な対策のヒントを見つけていきましょう。
製造業:上下関係の強さと現場の沈黙
製造業では、安全管理や作業手順の厳格な運用が求められることから、上下関係が明確であることが多く、上司の言葉が絶対という風土が根づいている職場も少なくありません。そのため、指導のつもりでの発言が一方的に受け取られ、部下にとっては強い圧力や恐怖となってしまうケースがあります。
また、現場作業に集中している時間が長く、感情を言葉にする機会が少ないことも、誤解や不満が蓄積する原因となります。対策としては、現場リーダー層に対してコミュニケーション技術やフィードバックの方法を習得する研修を実施することが有効です。また、「報連相」にとどまらず、「対話」を促す職場づくりが求められます。
IT業界:プロジェクト型業務とメンタル負荷
IT業界はスピード感と成果が重視され、プロジェクト単位でのプレッシャーが大きくなりがちです。納期の厳守やトラブル対応によるストレスが高まり、感情のコントロールが難しくなる状況が発生しやすい構造にあります。
特にチーム内での役割分担や進捗管理が曖昧な場合、責任の押しつけや過剰な要求が起きやすく、それがハラスメントにつながるリスクがあります。このような環境では、マネージャーのメンタルヘルスケアに加え、感情マネジメントやチームビルディング研修の導入が効果的です。リモートワークが多い職場では、日常的なコミュニケーションの意識的な設計も重要です。
医療・福祉業界:使命感と慢性的な人手不足の狭間で
医療や福祉の現場では、命や生活に直結する仕事であるがゆえに、強い責任感や緊張感のある環境で働いています。その一方で、人手不足や過重労働が常態化しており、精神的・肉体的な余裕を持ちづらい職場になっていることも多いです。
その結果、イライラや疲労がハラスメント行動として現れることがあります。また、指導と称して威圧的な言動が日常化しやすい職場文化も、見過ごせない要因の一つです。
このような環境では、職場の心理的安全性を確保する取り組みが不可欠です。管理職やリーダーに対して、感情の扱い方やストレスマネジメントを中心とした研修を実施し、職場全体の対話力を高めることが求められます。
飲食・サービス業界:属人的な指導と過剰な慣習
飲食やサービス業界では、業務が忙しくスピード重視になりやすい分、新人教育が属人的になりがちです。ベテランの「背中を見て覚えろ」的な指導が残っているケースでは、言語化されないルールや理不尽な指摘がハラスメントと捉えられる可能性があります。
さらに、長時間労働や休日の少なさ、体育会系の上下関係など、業界特有の慣習がハラスメントの温床になることもあります。こうした業界では、まずマニュアルや育成指針の整備が重要です。育成のスタンダードを明確にすることで、指導における主観や感情の入り込みを減らし、全員にとって安心できる教育環境を整えることができます。
業界特性を踏まえた対策の重要性
ハラスメント対策は、どの業界にも共通する基礎的な取り組みだけでは不十分です。業界ごとの構造や風土に合わせて、最もリスクが高くなりやすい場面を特定し、重点的に対策を講じることが必要です。
また、社内の声を丁寧に拾い上げ、現場で起きている「小さな違和感」に目を向ける姿勢が求められます。業界特性に即した具体的な行動指針を示すことで、現場にとってリアルで実践的なハラスメント防止が可能になります。
ハラスメントの種類と具体例
一口にハラスメントと言っても、その内容や発生の背景はさまざまです。職場におけるハラスメントは、明らかな暴言・暴力だけではなく、無意識の言動や習慣化された態度からも発生することがあります。そして、それぞれの種類によって、受け手に与える影響や必要な対応策も異なります。
この章では、職場で特に注意すべき代表的なハラスメントの種類を取り上げ、どのような行動が該当するのか、どのようなリスクを生むのかを具体例を交えて解説します。自分や職場が無自覚に加害側になっていないかを見直すきっかけとして、正しい知識を身につけましょう。
上司と部下の力関係が生むパワハラの構造
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場における優越的な立場を利用して、業務の適正な範囲を超えて他者に精神的・身体的苦痛を与える行為を指します。上司から部下への行為に限らず、経験年数や役職の差を背景にしたものも含まれます。
厚生労働省の定義では、パワハラには以下の3つの要素が含まれます。
- 優越的な関係に基づいて行われること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
- 就業環境を害すること
具体的な発言例としては、
- 「何度言えばわかるんだ」
- 「そんなこともできないのか」
- 「お前なんて必要ない」
といった人格否定につながる言葉が挙げられます。
パワハラは、怒鳴る・叱責するだけでなく、無視や仕事を与えないといった行為も含まれることがあります。つまり、目に見える攻撃だけでなく、見えにくい圧力も対象となるのです。その範囲は非常に広く、「正当な指導」との境界が曖昧になりやすいため、職場では行為の目的や言い方、頻度、相手の受け止め方を考慮した配慮が求められます。
セクハラとされる発言や行動、その受け止め方
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、相手の意に反する性的な言動により、不快感や屈辱感を与える行為を指します。相手の性別や年齢、立場にかかわらず、受け手が不快に感じるかどうかが重要な判断基準となります。
たとえば、以下のようなケースが問題となります。
- 服装や体型に関する発言を繰り返す
- プライベートな恋愛や結婚について執拗に質問する
- 飲み会などで身体的な接触を試みる
これらの行動は、受け手の感じ方によっては業務に支障をきたすほどの心理的負担を与えることがあり、深刻な人間関係の悪化や離職にもつながります。セクハラの影響は、単なる迷惑行為にとどまらず、職場全体の信頼関係や組織文化にまで悪影響を及ぼすという点でも重要です。被害者が声を上げにくい構造を見直し、事前に未然に防ぐ体制の整備が求められます。
モラハラが引き起こす心のダメージと職場への影響
モラルハラスメント(モラハラ)は、言葉や態度によって相手の人格や尊厳を継続的に傷つける精神的な嫌がらせを意味します。暴力や大声などの明らかな行為ではなく、表面上は穏やかに見えても、言外の圧力や軽視が繰り返される点が特徴です。
代表的な行動としては、
- 相手の意見を無視し続ける
- 皮肉や否定的な言い回しを多用する
- 他の社員の前で繰り返し恥をかかせる
こうした行動は、被害者の価値観や自己肯定感に深刻な影響を与え、強いストレスや抑うつ状態を引き起こす原因となります。いじめのように集団で行われるケースもあり、エスカレートすれば職場全体の雰囲気が悪化するリスクも高まります。モラハラは「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、記録や周囲の認識の共有が対処には不可欠です。また、管理職は日常的に職場の空気を観察し、異変の兆候に気づける感受性を持つことが重要です。
リモートワーク時代に生まれた新しいハラスメントの形
近年の働き方の多様化により増加しているのが、リモート環境で発生する「リモートハラスメント(リモハラ)」です。これは、オンライン上で行われる嫌がらせや圧力的な言動を指し、リモートワークの普及に伴って新たな課題として注目されています。
たとえば、
- Web会議で必要以上に監視される、プライベート空間を非難される
- チャットでの言葉遣いが一方的で冷たい
- オンラインでの無視、返信の遅延による心理的な圧迫
といった行為が、リモハラと認識されることがあります。特にテキストコミュニケーションは、表情や声のトーンが伝わらないため誤解が生まれやすく、意図せずに不快感を与えることもあります。リモートハラスメントの影響は、孤立感の増加やメンタル不調につながりやすく、対処が遅れると深刻化する可能性があります。そのため、定期的な1on1や感情共有の機会を設けるなど、リモート前提での新しいコミュニケーション設計が必要です。
ハラスメントの影響とリスク
ハラスメントは、単なる人間関係のトラブルではなく、企業活動全体に深刻な影響を及ぼすリスクをはらんでいます。被害を受けた従業員のメンタルヘルスへの影響はもちろん、職場の雰囲気の悪化、生産性の低下、さらには企業の社会的信用を損なう法的リスクにもつながります。
この章では、ハラスメントがもたらす影響を3つの視点から整理します。法的責任、職場環境への悪影響、そして個人の心身へのダメージ。どれも見過ごすことのできない重要なリスクであり、企業として真剣に向き合うべき課題です。
法的責任と企業に求められる対応
ハラスメントを放置した場合、企業は大きな法的リスクを抱えることになります。厚生労働省の指針に基づき、企業(事業主)にはハラスメント防止に関する措置義務が課されており、対応を怠ると損害賠償や行政指導の対象となる可能性もあります。
特に、パワーハラスメントに関しては、2020年6月より大企業に義務化され、2022年4月からは中小企業にも適用が拡大されました。適切な対応が行われなかった場合、訴訟リスクや企業イメージの毀損、不利益な評判の拡散といった影響が生じかねません。
こうしたリスクを回避するためには、まずハラスメントに関する法律の理解を全社的に深めることが重要です。その上で、企業は社内規定やガイドラインの整備を行い、どのような行為が該当し、どう対処すべきかを明文化する必要があります。加えて、リスク管理体制の強化として、人事部門の対応プロトコルや外部機関との連携体制を構築しておくことが推奨されます。社員教育も欠かせない要素であり、定期的な研修を通じて「どこからがハラスメントか」を理解し、問題が起こる前に防止できる意識を育てることが求められます。
職場の雰囲気と生産性への悪影響
ハラスメントは、個人だけでなく職場全体の雰囲気や生産性にも大きな影響を及ぼします。不安や不信感が蔓延した職場では、従業員が自由に意見を言いにくくなり、チーム全体のパフォーマンスが著しく低下することがあります。
また、ハラスメントが横行する環境では、上司と部下の信頼関係が崩れやすくなります。問題を指摘しにくい空気が広がると、現場の課題が表面化せず、改善の機会が失われてしまいます。出産や育児などライフステージに応じた配慮がなされない場合、働きにくい職場と見なされ、優秀な人材の流出にもつながります。
このような悪化を防ぐためには、日常的なコミュニケーションの改善が欠かせません。具体的には、1on1ミーティングの導入や、雑談も含めた気軽な対話の場づくりが効果的です。また、フィードバックを自然に行える文化を育てることにより、早期に問題点を発見し、チームで共有・解決する風土が生まれます。加えて、チームビルディング活動や部署を超えた交流の機会を通じて、従業員同士の関係性を強化することも重要です。職場環境を整えることで、ハラスメントの温床を根本から断つことができるのです。
心の健康に及ぼす深刻な影響
ハラスメントの被害を受けた従業員は、精神的なストレスや不安、抑うつ状態などのメンタルヘルス不調を抱えるリスクが非常に高くなります。特に、長期間にわたり苦痛を受け続けた場合には、仕事への意欲を失い、最終的には離職や休職につながるケースも少なくありません。
厚生労働省も、メンタルヘルス対策の導入を企業に強く推奨しており、ハラスメントによる心理的影響を未然に防ぐことは、人事や労務管理の観点からも極めて重要な課題とされています。
有効な対策としては、社内に相談窓口を設けることがまず挙げられます。従業員が気軽に悩みを打ち明けられる体制を整えることで、早期に問題を把握し、対応を講じることが可能になります。また、産業医や外部のメンタルヘルスサービスとの連携も、支援体制の強化に有効です。
さらに、定期的なメンタルチェックの実施によって、心理的な負荷の兆候を早期にキャッチすることも求められます。特にストレスが高まりやすい繁忙期や人事異動のタイミングなどには、個別のフォローを強化するなどの工夫が必要です。従業員の心の健康は、企業の健全な運営の土台です。心理的安全性を高める職場づくりが、ハラスメント防止だけでなく、組織の持続的な成長にもつながっていくのです。
ハラスメント対策の重要性
ハラスメントを防止するためには、問題が発生してから対処するのではなく、日常的に予防する体制と意識を職場全体で共有することが何よりも重要です。企業には、従業員が安心して働ける環境を整備する責任があり、それは単なる道義的責任にとどまらず、法律上の義務として明確に求められています。
この章では、企業が果たすべき責任と法的な義務、そしてハラスメントを未然に防ぐための教育の重要性について解説します。適切な対応体制と継続的な教育の両輪によって、組織全体の信頼性と働きやすさを高めていくことができます。
組織としての責任と法的義務の明確化
企業がハラスメントを未然に防ぐためには、まず組織としての責任と業務上の義務を正しく理解することが求められます。ハラスメントは一個人の問題として片付けられるものではなく、会社全体の風土や対応体制が問われる問題でもあります。
厚生労働省のガイドラインでは、事業主はハラスメント防止のために「雇用管理上必要な措置を講じること」が義務づけられており、これを怠った場合には、労働局などからの指導や是正勧告を受ける可能性があります。中小企業であっても、2022年4月以降はパワハラ防止法の対象となり、すべての企業に責任が課されています。
企業はまず、業務上の対策として、ハラスメントに関する方針を明確に打ち出すことが重要です。たとえば、社内規程に禁止行為や報告ルートを記載し、社員に周知徹底する必要があります。そして、担当者や窓口を明確に設定し、迅速かつ公平に対応できる体制を整備しましょう。また、コンプライアンス(法令遵守)を徹底する姿勢は、社外への信頼性向上にもつながります。 ハラスメントの予防は「問題が起きたら対応する」という後手の姿勢ではなく、企業文化そのものに根付いた取り組みであるべきです。
教育による予防と意識向上の取り組み
ハラスメントの防止には、教育による予防的なアプローチが不可欠です。社員一人ひとりが、何がハラスメントに該当するのかを正しく理解し、自分自身の言動を振り返るきっかけを持つことが、安全な職場づくりへの第一歩となります。
特に近年では、「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳が通用しない社会的環境になっており、パワハラ防止法などの法令を参考にした教育プログラムの導入が強く求められています。単なる座学ではなく、ケーススタディやロールプレイングなどを通じて、自分事として受け止められる工夫が必要です。
教育は形式的に実施するだけでなく、従業員への配慮を忘れず、心理的な安全性を確保したうえで行うことが重要です。たとえば、個別相談の場を設けたり、匿名で質問できる仕組みを取り入れたりすることで、理解が深まりやすくなります。
また、教育は一度きりの研修で終わらせるのではなく、継続的にアップデートしていく姿勢が大切です。社会情勢や法改正に合わせて内容を見直し、常に現場に即した情報を提供し続けることで、実効性のある防止策として機能します。
教育を通じてハラスメントの知識を「与える」だけでなく、相手への配慮や職場の空気を察する力を育てることこそが、本当の意味でのハラスメント対策につながります。
職場でのハラスメント対策
ハラスメントの発生を防ぐためには、制度やルールだけでなく、日々の職場の在り方そのものを見直すことが欠かせません。個人の意識改革とともに、組織としての働きかけや職場文化の整備が求められます。
この章では、具体的な対策として、コミュニケーション環境の改善や相談体制の構築、継続的な教育の推進など、職場内で取り組むべき施策を紹介します。どれもすぐに始められる現実的な方法ばかりです。予防と対応の両面から、安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。
オープンな職場をつくるコミュニケーションの土台づくり
ハラスメントの防止には、日頃から風通しの良い職場環境を構築することが欠かせません。従業員同士が立場を超えて意見を交わせる環境が整っていれば、不安や不満が蓄積する前に対話によって解消され、問題が表面化しにくくなります。
具体的には、オープンなコミュニケーションを促進する制度や仕組みを整えることがポイントです。定例の1on1ミーティング、自由に話せる場の設置、匿名での意見箱など、小さな仕組みの積み重ねが大きな効果を生みます。
また、互いの意見を尊重する文化を醸成することも重要です。相手の立場や考えを否定せず、「違いがあって当たり前」とする意識を持つことで、上下関係に関わらず安心して話せる環境が生まれます。さらに、定期的なフィードバックの実施は、社員の声を反映しやすい制度の一つです。職場の改善は「誰かの不満」から始まることも多く、意見が活かされるという実感が信頼関係の構築につながります。周囲との優位性ではなく、対等な関係の存在感を意識することが鍵となります。
無自覚なハラスメントに気づく仕組みづくり
多くのハラスメントは、本人が悪意を持たず、無自覚に行っているケースが少なくありません。だからこそ、予防の第一歩は、ハラスメントの定義や事例を丁寧に周知することです。
たとえば、「これくらい冗談の範囲だと思っていた」「上司として当然の指導だと考えていた」といった行動が、相手にとっては苦痛や屈辱となっていたケースは多くあります。これらを防ぐには、定期的な研修やワークショップを通じて、自らの言動を見直す機会を提供することが重要です。
また、ハラスメントが発生した場合には、誰が・どう対応するのかを明確にしておくことが必要です。トップメッセージや社内イントラでのガイドライン配信など、無視できない存在感を持った「周知の仕組み」をつくることで、組織全体が予防意識を持つようになります。
もちろん、対応策は内容に応じて柔軟に設定する必要があります。対話による早期解決、必要に応じた懲戒処分など、「対応の取り扱い」が一律でないことも理解しておくべきポイントです。
相談しやすい窓口の設置と運用
ハラスメント対策において、相談窓口の設置は中核的な取り組みです。問題の早期発見と対応を実現するためには、窓口の存在と内容を明確に周知することが出発点となります。
相談窓口の運営で特に重要なのが、匿名での相談を可能にする仕組みです。特に2024年、2025年といったハラスメント意識が高まる中で、従業員が安心して声を上げられる仕組みを整備しておくことが、企業の信頼性にも直結します。
また、窓口の設置がゴールではなく、その運用状況を定期的に見直すことも大切です。たとえば、相談対応の質、受付件数の傾向、相談者の満足度などを点検し、必要があれば外部の専門家や新たな対処制度の導入も検討しましょう。公開されているだけの窓口では意味がありません。従業員が「ここに相談すれば大丈夫だ」と感じられる体験をどう設計するかが、制度の効果を左右します。
継続的な研修と啓発で職場の意識を高める
ハラスメント防止に向けた対策は、一度きりの研修で終わらせては効果が限定的です。定期的な研修と継続的な啓発活動によって、職場全体の意識を維持・向上させることが求められます。
研修では、専門家を招いた講義や最新の事例に基づいた学習コンテンツを活用し、従業員が自らの行動を振り返るきっかけを提供します。また、人材育成と並行して実施することで、ハラスメント防止と指導力強化の相乗効果も期待できます。
啓発活動としては、社内報やポスター、eラーニングなどでの継続的な発信が有効です。異動や新入社員の受け入れ時など、節目ごとの周知も欠かせません。特に言動が注目されやすい管理職には、より高度な対応力が求められます。研修によってリーダーとしての振る舞いや指導法を強化することは、ハラスメントを未然に防ぎ、職場の健康な文化形成にもつながります。
ハラスメントが発生した場合の対応
どれほど対策を講じていても、ハラスメントを完全に防ぐことは難しく、実際に問題が発生した際の対応力が企業の信頼を左右します。被害者への配慮を欠いた対応や、曖昧な処理を行えば、事態が深刻化し、職場全体の士気にも影響を及ぼします。
この章では、ハラスメントが発覚した際に企業が取るべき対応の流れと、被害者に対して求められる支援体制について解説します。迅速かつ誠実な対応が、問題の拡大防止と再発予防の鍵となります。
迅速な対応で被害の拡大を防ぐ
ハラスメントが職場で発生した際には、スピード感のある対応が最も重要なポイントです。対応が遅れると、被害者の苦痛が深まるだけでなく、組織全体の信頼性にも大きく影響します。特に近年は、SNSなどを通じて情報が拡散しやすくなっており、企業にとって迅速かつ適切な初動対応はリスク管理上の最優先事項です。
まずは、問題を早期に特定し、状況を正確に把握することが第一歩です。「何が起きたのか」「いつ・どこで・誰が関与していたのか」といった基本情報を押さえ、冷静に事実関係を洗い出します。曖昧な情報のまま動くと誤解が生じやすく、加害者・被害者双方にとって不利益な結果を生む可能性があります。
次に、適切な情報を収集し、必要に応じて第三者的な立場からの確認も行いましょう。人事や労務担当、場合によっては社外の弁護士や社労士との連携も有効です。特に内容が複雑な場合や加害者側との利害関係があるときには、客観性を担保するための外部連携が役立ちます。
そして、関係者との連携を密にしながら、事態に応じた対策を講じることが求められます。注意・警告・配置転換・懲戒処分といった対応策は、状況の深刻さと組織内規定に応じて適切に選定する必要があります。感情ではなくルールと証拠に基づいた対応が、結果として信頼回復にもつながります。「小さな問題」に見えても、見過ごすことなく早期に対応する姿勢が、ハラスメントの再発防止と健全な職場の維持に大きく役立ちます。
被害者の声に寄り添った支援体制の構築
ハラスメント対応において、被害者へのサポート体制の整備は、問題解決の柱となります。適切な支援を受けられない状況は、当事者にとって二次被害となり、心理的な負担をさらに増大させることにもなりかねません。
まず重要なのは、支援の種類を整理し、被害者が何を必要としているのかを理解することです。たとえば、メンタル面のサポート、業務内容の見直し、勤務時間の調整、他部署への異動希望など、支援のかたちは一律ではありません。本人の状況や希望に応じて、柔軟に対応することが求められます。
その際に大切なのは、被害者の声を尊重する姿勢です。事実確認や対応を進める中で、「相手が悪いかどうか」だけに焦点を当てると、被害者が置き去りにされてしまう可能性があります。あくまで当事者の意向に耳を傾け、納得のいく形でサポートを提供することが、安心と信頼の回復につながります。
さらに、必要なリソースを確実に提供する体制づくりも欠かせません。具体的には、産業医やカウンセラーの紹介、休職・復職の制度説明、社外の相談窓口の案内などが挙げられます。社内での対応が難しい場合は、外部サービスの活用も積極的に検討しましょう。支援体制は「用意しているだけ」では意味がありません。必要な時に、安心して、利用できるかどうかが重要です。そのためにも、制度の存在を日常的に周知し、誰もが活用しやすい環境を整えることが、ハラスメント防止の後方支援として非常に重要です。
ハラスメントを生まない企業文化と環境の整え方
ハラスメント対策は、単なる制度の整備や教育の実施だけでは十分とは言えません。本質的な防止に向けては、職場全体に根づく文化や価値観そのものを見直す必要があります。 一人ひとりが安心して働ける環境をつくるには、日常のコミュニケーション、相互の信頼、そして多様性を受け入れる姿勢が欠かせません。
この章では、ハラスメントを生まないために企業が取り組むべき具体的な対策や文化改善の視点について整理します。制度と風土の両面から職場を見直し、誰にとっても働きやすい環境づくりを実現していきましょう。
ハラスメント防止のために必要なこと
ハラスメントを防止するためには、まず職場全体での明確な対策とルールの整備が欠かせません。社内のガイドラインや手続きの流れを明文化し、すべての社員に理解・周知させることで、「何がハラスメントに該当するのか」を組織全体で共有できます。
また、定期的な社員教育の実施も重要です。知識としての理解だけでなく、行動にまで落とし込むためには、ケーススタディやロールプレイなど実践的な研修を組み込むと効果的です。社員一人ひとりが、自分の言動を振り返るきっかけを持つことが、予防の第一歩になります。
さらに、相談窓口の設置と運用の見直しを行い、従業員が安心して相談できる体制を整えることも必要です。形式的に存在するだけでなく、適切な対応が取られると信頼される窓口であることが、職場の安全性を高めます。こうした具体的な方法を講じることで、ハラスメントの未然防止と早期対応が可能になります。目的は単にトラブルを避けることではなく、従業員が安心して働ける職場環境を持続的に整えることにあります。
企業文化の見直しと改善
ハラスメント対策は、制度や教育だけでは不十分であり、根本的には企業文化そのものを見直すことが求められます。 まずは、ハラスメントに対する認識を全社員で共有し、誰もが当事者意識を持てる環境をつくることが出発点です。
次に、フィードバックを重視する風土を整えることも重要です。評価の場だけでなく、日常的に意見や提案が受け入れられる仕組みを作ることで、職場の課題が早期に顕在化し、改善につながりやすくなります。
また、多様な背景や価値観を尊重することは、ハラスメントを減らすだけでなく、社員一人ひとりの力を活かす土壌を築くことにもつながります。 多様性を受け入れる文化が育てば、互いを尊重し、認め合う関係性が自然に根づきやすくなります。
企業が成長し続けるためには、「働きやすい職場」としての信頼性を高めていく必要があります。ハラスメントのない環境は、企業価値の向上と人材の定着・育成にも直結する大切な土台であると言えるでしょう。
まとめ
ハラスメント対策は、単なる制度や研修の導入にとどまるものではありません。企業が本当に取り組むべきは、職場の文化や環境そのものを見直し、従業員一人ひとりが安心して働ける土台を整えることです。
本記事では、ハラスメントの定義や種類、発生の原因、業界ごとの構造的な課題まで、多角的な視点で整理してきました。そして、法的な責任、組織としての対応、教育・相談体制の構築といった、実務に即した取り組みについても具体的に紹介しました。
これらの内容はすべて、「誰もが尊重され、力を発揮できる職場」をつくるための指針です。ハラスメントは未然に防ぐことができ、適切に対応すれば職場の信頼も取り戻すことができます。今この瞬間から、職場をより良くする一歩を踏み出すことができるのは、組織をつくる私たち一人ひとりです。
ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか
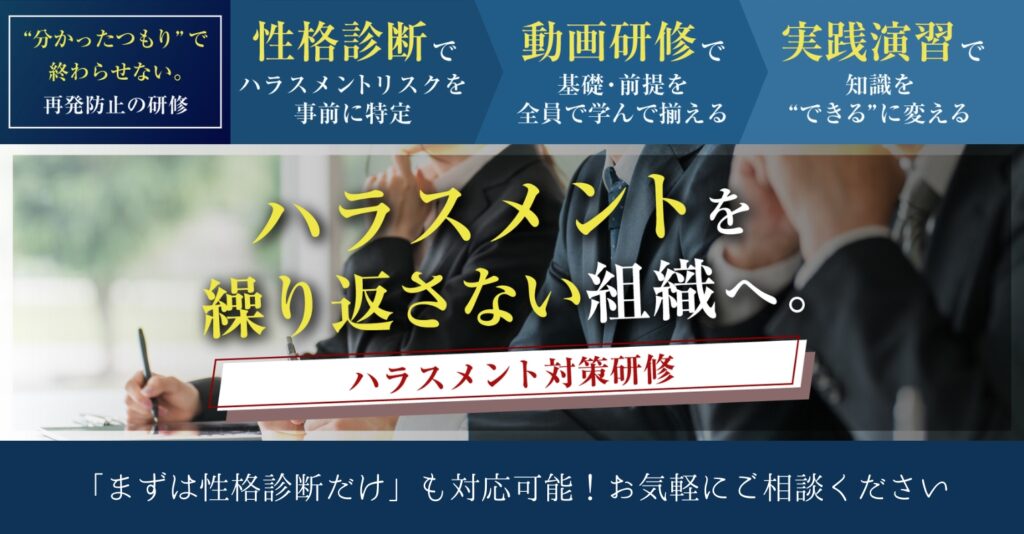

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」
「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」
「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」
ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。
大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。
アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴
- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施
- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習
- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習
- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル
ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。