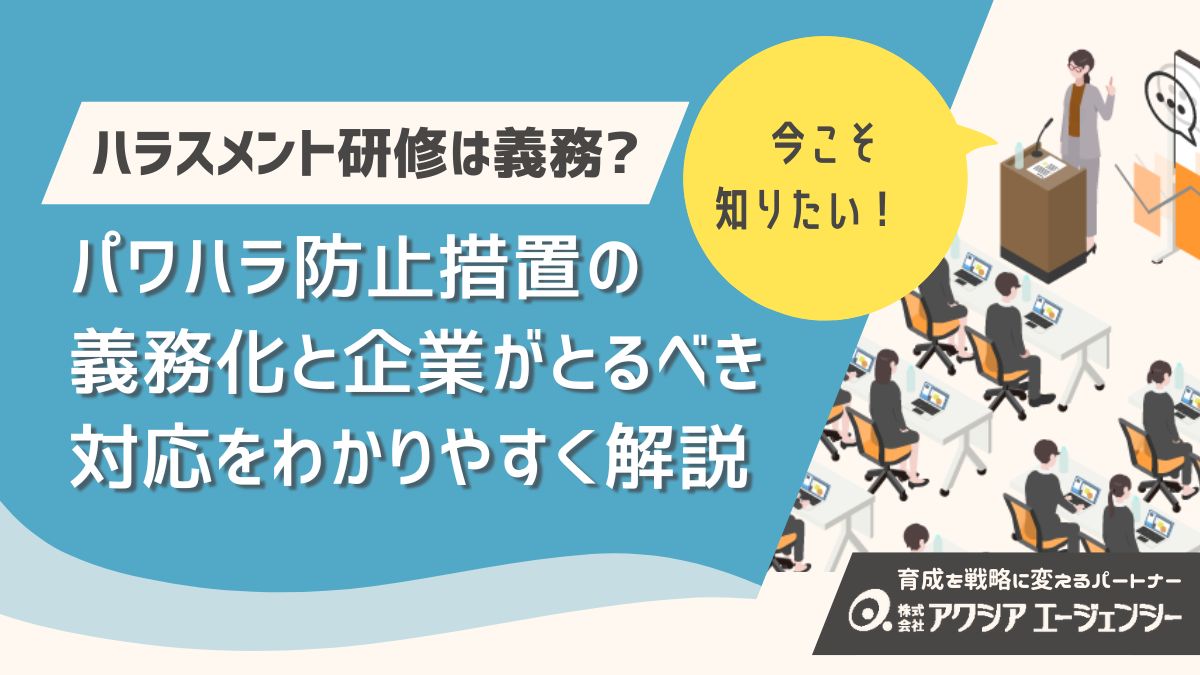ハラスメント研修は義務なのか?企業が混同しやすいポイントを整理
「ハラスメント研修は義務化されているのか?」この質問は、法改正が進む中で多くの企業担当者が感じている疑問のひとつです。特に、2022年4月に中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されたことにより、「すべての企業で研修をしなければいけないのでは?」と混同するケースが増えています。
この記事では、何が法的に義務化されたのか、研修の位置づけとは何かを整理しながら、企業が正しく理解し、実務にどう落とし込むべきかをわかりやすく解説します。
義務化されたのは「パワハラ防止措置」そのものである
結論から言えば、法律で義務化されたのは「研修」ではなく、「パワーハラスメント防止措置の実施」です。
2020年6月に改正された「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」により、大企業には同年4月から、中小企業には2022年4月から、職場におけるパワーハラスメントを防止するための措置が義務付けられました。
この「防止措置」には、以下のような対応が含まれます。
- パワハラに対する企業の方針の明確化と社内周知
- 相談窓口の設置や社内体制の整備
- パワハラが発生した際の迅速かつ適切な対応と再発防止策
つまり、法令上、企業には「ハラスメントを防止するための環境整備」が求められており、研修はそのための手段の一つにすぎないということになります。
「研修の実施」は努力義務だが実務上は不可欠
「じゃあ、研修はやらなくてもいいの?」という声が聞こえてきそうですが、答えはNOです。現行法では、研修の実施自体が明確に義務化されているわけではありません。 しかし、厚生労働省の指針や実務上の運用を見ても、研修は防止措置の中核的な役割を果たしているといえます。
防止措置の1つである「方針の明確化と周知」は、単に社内にポスターを掲示したり、就業規則に一文を加えたりするだけでは不十分です。社員一人ひとりが、
- 何がハラスメントにあたるのか
- どんな行動がグレーゾーンとされるのか
- どこに相談すべきか
- 自分の言動がどう影響を与えるか
を理解し、日々の行動に反映できる状態にするには、教育・研修による浸透活動が不可欠なのです。
実際、ハラスメント問題が発生した企業では、「研修が不十分だった」「管理職がルールを知らなかった」といった事後的な指摘が多く見られます。研修を実施していない企業は、結果的に「措置義務を怠っていた」と判断される可能性もあるという点に注意が必要です。
厚生労働省の指針と企業への影響とは
厚生労働省が公開している「職場におけるパワーハラスメント防止のための指針(2020年施行)」では、企業が講じるべき措置として、従業員に対する「教育・啓発活動」を明確に盛り込んでいます。具体的には、以下のような記載が見られます。
「事業主は、労働者に対して、職場におけるパワーハラスメントに関する方針、内容、対応方法等について、周知・啓発を図るよう努めなければならない」
この“努めなければならない”という表現は、いわゆる「努力義務」とされますが、近年の労務管理においては、「努力義務=実質的な必須対応」という認識が広まりつつあります。
また、労働基準監督署などの監査や相談対応において、「研修は実施していましたか?」という確認項目は当たり前のように登場します。加えて、ハラスメントが発生した際に、「どのような教育を行っていたか」が対応責任の有無に直結するケースも増えているのが現状です。
パワハラ防止措置の法的な全体像
パワハラ対策に取り組む上でまず理解すべきなのは、「何が法律で定められているのか」「企業にはどこまでの対応が求められているのか」という点です。
このセクションでは、パワハラ防止措置の法律的な位置づけと、企業が押さえるべき義務の全体像を整理します。
2022年4月から中小企業も義務化対象に
2019年に成立した改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、企業に対して職場のパワーハラスメントを防止するための措置を講じることが法的に義務付けられました。
- 2020年6月施行:大企業に義務化
- 2022年4月施行:中小企業にも義務化(猶予期間終了)
これにより、すべての企業(規模問わず)に対して法的義務が課される状態となっています。
ここで注意したいのは、違反したからといって即罰則があるわけではないということ。ただし、厚生労働省は企業に対し、ハラスメント対策の実施状況を指導・助言・勧告することができ、改善が見られなければ企業名の公表など、企業の評判に関わるリスクを伴う可能性があります。
つまり、罰則こそなくとも、企業としての信頼や採用・定着力に大きく影響する実質的な義務であると考えるべきです。
防止措置の3本柱と内容(方針、相談体制、再発防止)
厚生労働省の定める「パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務」は、大きく分けて以下の3本柱から成り立っています。
① 方針の明確化と周知・啓発
企業としてパワハラを許容しない旨を明確に打ち出し、それを従業員全体に周知する必要があります。
- 就業規則やハラスメント規程への記載
- 社内イントラやポスター等による掲示
- 上司からのメッセージ、全体朝礼での発信 など
また、この中に社員への教育・研修も含まれており、啓発活動の手段として研修が定番の位置づけになっている点は見逃せません。
② 相談体制の整備
社員がパワハラに関する相談を安心してできるよう、相談窓口の設置と体制の整備が求められます。以下のような要件がポイントです。
- 匿名相談が可能な体制(社外窓口を含む)
- 窓口担当者の研修・力量確保
- プライバシー保護のルール整備
「窓口はあるけれど実質機能していない」では不十分であり、実際に使われる、信頼される体制であるかどうかが重要です。
③ 事案発生時の迅速・適切な対応と再発防止策
パワハラ事案が発生した場合、企業には以下のような義務があります。
- 被害者・加害者へのヒアリングと事実確認
- 必要に応じた加害者への処分や配置転換
- 被害者への配慮措置(配置・フォローなど)
- 同様の事案が再発しないよう教育やルール見直し
つまり、パワハラを放置しない姿勢と仕組みを、組織としてもつことが問われているのです。
「努力義務」と「指導対象」となるリスクの違い
先述の通り、ハラスメント研修は法律上では「努力義務」に分類されます。しかし、これは単なるやってもやらなくても良いことではなく、未実施によるリスクが極めて高いという点を理解する必要があります。
たとえば、パワハラによるトラブルが発生した際に、
- 研修をしていなかった
- 管理職に判断基準が共有されていなかった
- 被害者の訴えが社内で黙殺された
という状況であれば、労基署から指導・是正勧告の対象となるだけでなく、訴訟リスクや企業の社会的信用にも大きな打撃となり得ます。
一方、適切な研修や再発防止策を行っていた企業であれば、「組織としてやるべき対応はしていた」と評価され、法的責任の軽減や信頼維持につながる可能性があるのです。
ハラスメントを放置することのリスク
ハラスメントの未然防止や早期対応が重要であることは、多くの企業が理解しています。しかし一方で、「具体的な被害報告がない」「制度はあるが運用はしていない」などの理由で、実質的に放置されているケースも少なくありません。
ここでは、ハラスメントを放置した場合に企業や職場にどんな影響があるのか、あらためて整理しておきましょう。
職場環境の悪化と業務上の支障
ハラスメントが見過ごされている職場では、社員が安心して働くことができず、業務上の効率や連携にも深刻な影響を及ぼします。たとえば、特定の上司による強圧的な行為や、同僚からの繰り返される嫌がらせなどが続くと、対象となった社員は心身の健康を害し、生産性の低下や欠勤・離職につながるリスクが高まります。
また、職場全体としても「声を上げづらい」「自分の身を守るために他人と距離を取る」といった風潮が強まり、人間関係の分断や組織としての一体感の喪失にもつながります。
「個の侵害」が職場全体の信頼を損なう
ハラスメントの根底には、「相手の尊厳や人権を軽視する姿勢」があります。たとえ業務上の注意や指示の中であっても、人格を否定するような言動や、立場を利用した一方的な支配的態度は個の侵害と見なされる可能性があるのです。
このような行為が放置される職場では、被害者だけでなく、その周囲で働く同僚も「自分も同じように扱われるかもしれない」という不安を抱えるようになります。結果として、エンゲージメントは大きく下がり、企業としての魅力・採用力にも悪影響を与えます。
制度や規定があっても、機能しなければ意味がない
「就業規則にハラスメントの規定はある」「相談窓口を設けている」――こうした制度面の整備が進んでいる企業でも、実際に運用されていなければ“形式的対応”と見なされます。
たとえば、
- 相談してもまともに取り合ってもらえなかった
- 担当者が加害者と同じ部署にいて相談しづらい
- 処分が曖昧で、再発防止につながらなかった
といったケースでは、企業の対応が問われるだけでなく、法的リスクやメディア報道による企業価値の毀損にもつながりかねません。つまり、制度や規定の形ではなく、実態が問われている時代なのです。
なぜ研修が重視されているのか?3つの実務的理由
パワハラ防止措置が法的に義務化された現在、企業として「何をすればリスクを最小化できるか」を真剣に考える必要があります。その中で最も注目されている対策の一つが、ハラスメント研修の実施です。
法令では“努力義務”とされている研修ですが、実際の企業現場では「防止措置の要」として事実上欠かせない取り組みとなっています。
ここでは、なぜ研修がそれほど重視されるのか、3つの実務的な理由に絞って解説します。
1. 社員間の共通理解を深めることができる
ハラスメント対策の難しさの一つは、「感じ方の違い」や「グレーゾーンの曖昧さ」です。たとえば上司が「指導のつもり」でも、部下は「威圧的だった」「人格否定された」と受け取ることがあります。逆に、部下が「何も言われない」と感じたとき、それは“育成放棄”ととられるケースもあります。
このように、言った・言われたではなく、どう受け取られるかが焦点になるため、職場内での共通認識づくりが重要になります。
研修を実施することで、
- 何がハラスメントに該当するのか
- どんな言動が誤解されやすいのか
- 指導とハラスメントの違いは何か
- どこまでが「配慮すべき範囲」か
などを具体的に共有でき、社内の判断基準を揃えることが可能になります。特に多様な価値観や働き方が混在する現代の職場では、この共通言語を持つことが、トラブルの予防に大きな力を発揮します。
2. 管理職が“指導不安”から脱却できる
パワハラ問題が注目されるようになってからというもの、「指導=怖いもの」という風潮が一部で広がっています。結果として、管理職が部下に関わることを避けたり、育成そのものを控えてしまう関係性の希薄化が起きているのが現状です。これは、若手社員の成長機会を奪うだけでなく、現場の生産性低下や離職にもつながるリスクがあります。
研修はこうした状況に対して、「安心して関われる指導スタンス」を取り戻す手段になります。
- どのように伝えれば良いのか
- 境界線はどこにあるのか
- 自分の指導スタイルはどう見られているか
といった疑問に答えることで、管理職が自信を持って育成に向き合えるようになるのです。
また、研修内で実際の事例やロールプレイを交えることで、単なる知識習得ではなく、「腑に落ちた状態」で現場に戻れることも、効果を高めるポイントとなっています。
3. 対外的な企業ブランディングにもつながる
ハラスメント対策の取り組みは、社内の安心安全を守るだけでなく、企業の「見られ方」にも大きな影響を及ぼします。
- SNSや口コミで社風が共有される
- 就職・転職サイトで「働きやすさ」が評価対象になる
- 取引先やパートナー企業がCSR観点で選定を行う
といったように、企業の人材に対する姿勢は社外でも可視化されやすい時代になっています。
ハラスメント研修を継続的に実施していることは、外部から見た際にも「安心して関われる会社」「働く人を大切にしている会社」という印象を与える材料となり、採用・定着・信頼構築において大きな競争力となるのです。
さらに、これからの時代に求められる「心理的安全性」や「ダイバーシティ&インクルージョン」の土台としても、ハラスメント研修は欠かせない存在です。
企業が取るべき具体的対応ステップ
「パワハラ防止措置が義務化されたのは分かった。でも、結局なにから始めればいいの?」そんな疑問を抱く人事・労務担当者は少なくありません。パワハラ対策は一過性の施策ではなく、継続的・組織的に取り組むべきテーマです。
ここでは、今すぐ企業が取り組める具体的なステップを3段階に分けて解説します。大小問わず、どの企業でも応用できる流れなので、自社の現状と照らし合わせながら読み進めてください。
現状把握と職場の課題の言語化
最初のステップは、社内の現状を正しく把握することです。パワハラ防止対策は、「うちの会社は問題が起きていないから大丈夫」という姿勢では機能しません。未然に防ぐには、今ある潜在リスクを見つけ出し、明確な言葉で定義しておくことが重要です。
現状把握の方法としては以下のような手段があります。
- 匿名の社内アンケート調査
- ハラスメントに関するヒヤリ・ハット事例の収集
- 退職者インタビューやエンゲージメントサーベイの分析
- 管理職・人事担当者へのヒアリング
これらをもとに、社内にどんな傾向があるのか、どの職場でどんな不安やズレがあるのかを“言語化”して整理しておくことが、すべての出発点になります。
研修の実施と実務への落とし込み
次に必要なのが、研修の設計と実施です。ここで重要なのは、「形式的に1回やっただけ」で終わらせないこと。むしろ、研修内容をいかに現場での行動に結びつけるかがポイントになります。
研修の成功には以下の要素が欠かせません。
- 職種・役職別に研修を設計(例:管理職向け・一般社員向け)
- 実際の職場で起きがちなケースを取り上げる
- ロールプレイやグループディスカッションで気づきを促す
- 研修後に行動目標や振り返りを設定
また、集合研修だけでなく、動画による補足やeラーニングとのハイブリッド型にすることで、定着度が大きく変わります。特に多忙な現場では、研修の“しやすさ”も大切です。時間や場所に制約されない設計にすることで、受講率が上がり、全社的な意識共有が実現しやすくなります。
実施記録の管理と定期的な振り返り
研修を実施したら、「やりっぱなし」にせず、振り返りと記録を残すことが大切です。これは将来的な法令対応やトラブル対応の面でも、極めて重要なポイントになります。
- 実施日・対象者・内容・講師
- 配布資料・動画URL・質問内容など
- 受講者の理解度チェックやアンケート結果
上記のような内容を体系的に管理しておくことで、「対策をしていた証明」になるだけでなく、再発防止の分析材料としても活用できます。
さらに、定期的に研修の内容や実施頻度を見直し、「今の職場に本当に合っているか?」をチェックする機会を設けることが、ハラスメント対策を継続可能な仕組みにするうえで欠かせません。
どんな研修が効果的か?選び方のポイント
ハラスメント対策に本腰を入れる企業が増える中で、「どのような研修を選べばよいか?」という問いに直面する担当者も少なくありません。特に、研修が形骸化しやすいテーマでもあるため、“効果が出る研修”と“やっただけで終わる研修”の違いを見極めることが非常に重要です。
ここでは、研修を導入する際に押さえるべきポイントを、3つの視点から整理して解説します。
階層別・役割別に設計された研修がベスト
まず最も重要なのが、全員一律の研修で済ませようとしないことです。ハラスメントのリスクや役割に応じた対処の仕方は、管理職と一般社員とではまったく異なります。そのため、対象者ごとに研修内容を最適化することが必須です。
- 指導とハラスメントの境界線
- 注意・フィードバックの伝え方
- 相談を受けた際の初期対応と判断基準
- ハラスメントの種類と具体的な事例
- 受け止め方や自己防衛のポイント
- 被害を感じたときの相談ルートと安心感
こうした階層別の研修設計は、受講者の納得度も高く、「自分には関係ない話」という受け身の姿勢を防ぐ効果もあります。
オンライン×対面のハイブリッド型のメリット
コロナ禍以降、オンライン研修の活用が一気に進みましたが、ハラスメントというセンシティブなテーマでは伝わり方が非常に重要になります。そこで注目されているのが、「動画視聴による基礎学習」+「リアルな対話による実践」のハイブリッド型研修」です。
この形式には、以下のようなメリットがあります。
- 基礎知識を繰り返し確認できる
- 社員全体への均一な知識のインプットが可能
- 時間や場所にとらわれず受講できる
- ロールプレイで具体的な場面を体験できる
- 意見交換や感情の共有により“自分ごと化”が進む
- その場の疑問を解消でき、双方向性が高まる
このように、インプットとアウトプットを組み合わせることで、定着率が大幅にアップします。特に、心理的安全性を高めたい企業にとっては、対話や共感の機会を持つこと自体が対策になるという副次効果もあるのです。
事例・ロールプレイ型で“自分ごと化”させる工夫
「一方的な講義を聞いただけでは記憶に残らない」これは多くの企業で起きている研修あるあるです。特にハラスメント研修のように、抽象的・感情的な要素が強いテーマでは、いかに自分のこととして捉えられるかが成果を左右します。
そこで有効なのが、以下のような要素を取り入れることです。
- 実際にあった裁判例・労務トラブルの紹介
- 自社に近い業種や職種でのケーススタディ
- 参加型のワークショップ形式(グループ討議など)
- NG・OKな言動を比較するシミュレーション
ロールプレイでよくあるのは、
- 上司と部下の1on1面談
- 注意指導を行うシーン
- チーム会議での発言の扱い方
など、日常に即したシーン設定で、実際にやってみること。
受講者はただ知識を得るだけでなく、「こういうとき、どう感じた?」「なぜ不快だったのか?」といった感情の共有を通じて理解を深めることができます。これにより、単なる法令対策ではなく、行動の変容につながる本質的な研修へと昇華できるのです。
ハラスメント研修でよくある質問(FAQ)
ここでは、実際に多くの企業担当者や受講者から寄せられる、ハラスメント研修に関する代表的な質問とその回答をまとめました。法的な疑問から実務的なポイントまで、導入前に知っておきたい情報を確認しておきましょう。
Q1. ハラスメント研修は法律で義務なのですか?
A:いいえ、研修自体は「義務」ではありませんが、防止措置の一環として“実質的に不可欠”とされています。
法律で義務化されているのは「職場におけるパワーハラスメント防止措置の実施」です。この中に「教育・啓発」の項目があり、従業員への周知手段として研修が推奨されているのが実態です。特に厚生労働省の指針でも、研修や教育によってハラスメントの未然防止を図るよう記載されています。
したがって、「研修を実施していない企業」は、法令上は違反していなくても、監査やトラブル時に不備と見なされる可能性があるといえます。
Q2. 義務化されたのはいつから?どの企業が対象?
A:大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から義務化対象になっています。
パワハラ防止措置の義務化は、段階的に施行されました。
- 大企業:2020年6月〜義務化
- 中小企業:2022年4月〜義務化(猶予期間終了)
つまり、現在はすべての企業が対象となっており、規模にかかわらず防止措置の対応が必要です。研修も、こうした背景から多くの企業で導入が進んでいます。
Q3. 研修をしていないと罰則はありますか?
A:現時点では直接的な罰則はありませんが、是正指導や企業名の公表リスクがあります。
労働施策総合推進法では、パワハラ防止措置に違反した企業に対して、厚生労働省が助言・指導・勧告を行えることが明記されています。
さらに、悪質な場合や改善が見られない場合は、企業名の公表が行われることもあるため、社会的信用に大きな影響を与えかねません。また、社内でパワハラが発生し、それが「未教育・未対応」であった場合には、企業側の対応不備として訴訟リスクも高まるのが実情です。
Q4. 小規模な企業でも研修は必要ですか?
A:はい。むしろ小規模企業こそ研修が有効です。
人数が少ない企業では、個人間の距離が近く、関係性の悪化が業務全体に直結しやすいという特徴があります。
そのため、社員全員が「これはNG」「ここまでならOK」といったラインを共通で理解することは、トラブルの予防だけでなく日常の信頼形成にも役立ちます。費用面が気になる場合は、動画+ワークシート型の低価格パッケージ研修なども多数提供されているため、まずは基礎知識の共有から始めることが推奨されます。
Q5. 研修は社内で自前でやっても良いのですか?
A:可能ですが、専門性や公平性の観点から外部研修の併用が望ましいです。
自社の人事部門や管理職が独自に研修を行うことも可能です。ただし、以下の注意点があります:
- 社員が「形式的な取り組み」と感じるリスク
- 外部の最新情報や他社事例を取り入れづらい
- 中立性・客観性が問われる場面で説得力が不足する
こうした背景から、最近では「動画で基礎知識を学習」+「外部講師によるリアル研修で実践」のハイブリッド型が主流となっています。
Q6. 研修の頻度はどれくらいが適切ですか?
A:年1回以上が一般的ですが、状況によっては半期ごとの実施やフォローアップも効果的です。
特に以下のようなタイミングでは、追加実施や補足研修を検討する企業が増えています:
- 新入社員の入社時(導入研修)
- 昇進時や新任管理職への任命時
- 社内トラブル発生後の再発防止対応として
継続的に研修の質と頻度を見直すことで、“学びを習慣化する職場風土”が定着していきます。
義務を正しく理解し、信頼される職場づくりへ
パワハラ防止措置の義務化は、単なる法改正ではありません。それは、企業と働く人々の信頼関係を再構築するための「最低限の約束」であり、これからの組織に求められる“信頼資本”の基本条件でもあります。この記事でご紹介してきたように、研修そのものは法律上の義務ではありませんが、パワハラ防止措置を実効性あるものとするには欠かせない要素です。
防止方針をいくら整えても、実際の言動や空気感が変わらなければ、リスクは消えません。そこで力を発揮するのが、社員一人ひとりの理解と行動を変える「教育・研修」なのです。
法令対応だけでは不十分かも?現場の課題に効くハラスメント研修を


「法令対応はしているのに、現場の指導トラブルが減らない」
「若手が“注意されるのが怖い”と言ってすぐに辞めてしまう」
「研修をやっても一時的で、職場の行動に結びつかない」
ハラスメントの研修は「問題があるから導入するもの」と思われがちですが、実際にはハラスメント予防や安心して育てられる環境づくりを目的に選ばれる企業が増えています。
アクシアエージェンシーの実践型ハラスメント研修は、上司と若手双方の声に寄り添い、職場の関係性を前向きに整えるお手伝いをします。
アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴
- ロールプレイ中心で現場に活かせるスキルを習得
- 管理職と若手双方に対応することで、すれ違いを防ぎ安心できる関係性を築きます
- 実務経験が豊富な講師陣が担当し、納得感のある実践的な学びを提供します
- 研修後のフォロー支援により、学びを定着させ職場での行動変容につなげます
貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に考えていきます。小さな不安や気になることでも、まずはお気軽にご相談ください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。