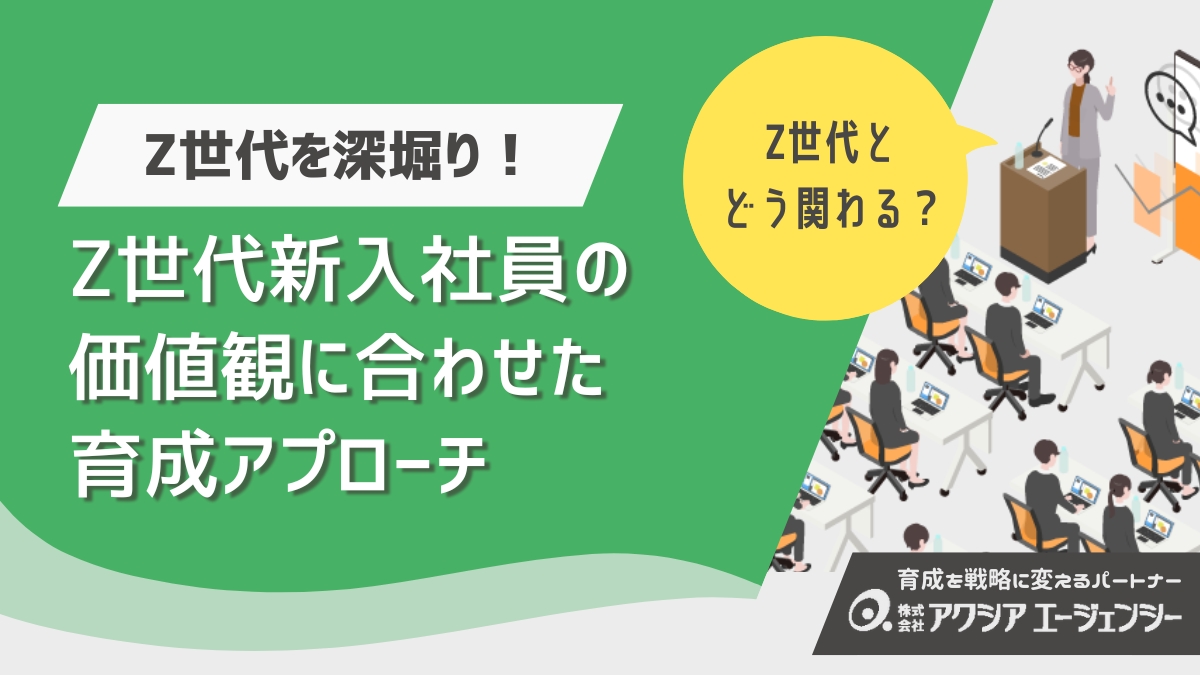少子高齢化による人手不足が深刻化するなか、企業が持続的に成長するためには、若手人材の早期戦力化と定着が欠かせません。なかでも、今後の中核を担うZ世代は、これまでの世代とは異なる価値観や働き方を持つことから、従来通りのマネジメントや育成だけでは成果が出にくいという声が多く聞かれます。Z世代に関する課題は多くの企業が抱えるテーマであり、人材育成全体の見直しにもつながる重要な視点と言えるでしょう。
本記事では、Z世代の定義や特徴を明確にし、職場における行動傾向や価値観を深く理解したうえで、企業がどのように育成し、関係性を築き、組織文化を整えていくべきかを具体的に解説します。人事・マネジメント担当者の皆さまが現場で「これは使える」と思えるような実践的な視点でお届けしていきます。
Z世代とは?
Z世代は、企業の未来を担う存在として注目が高まっている一方で、従来の価値観や働き方とは異なる点も多く、戸惑いを感じている現場も少なくありません。
この章では、Z世代の基本的な定義や生まれた時期、育ってきた文化的背景を明確にしながら、彼らを理解するための土台を築いていきます。世代間の違いを客観的に把握することで、組織としてどのように向き合うべきかのヒントが見えてくるはずです。
Z世代の定義
Z世代の基本とデジタル世代としての特徴
Z世代は一般的に、1997年から2012年ごろに生まれた世代と定義されます。2024年時点では、おおよそ12歳から27歳の年齢層にあたり、大学生や新入社員、若手の社会人として組織の中核に入りつつある層でもあります。英語では「Generation Z」と呼ばれ、アメリカを中心に広まった分類ですが、日本でも人材育成や採用の現場で注目されています。
この世代の最大の特徴は、インターネットやスマートフォンが日常に存在する環境で育ったデジタルネイティブであることです。情報への感度が高く、検索エンジンやSNS、ショート動画などを駆使して、効率的に情報収集を行う力に長けています。特に、「短時間で要点をつかむ」「必要な情報だけを選び取る」といった行動スタイルが顕著で、他の世代と比べてもスピーディーな判断力が見られます。
このように、Z世代はデジタル技術とともに成長したことで、既存の枠にとらわれない柔軟な価値観と、情報の取捨選択に対する高い感度を持っています。
価値観の変化とY世代との違い
Z世代は、社会や他者に対する価値観にも特徴があります。性別や国籍、価値観などの違いを当然のものとして受け入れ、多様性や公平性を重視する傾向が強くあります。誰かに合わせるよりも、「自分がどうありたいか」を大切にし、自分らしい生き方を追求する姿勢が特徴的です。
この点で、Y世代(1980年代〜1990年代半ば生まれ)とは大きな違いがあります。Y世代が「安定」や「キャリアアップ」を重視してきたのに対し、Z世代は「共感できるかどうか」「その仕事が社会的に意義があるか」といった価値基準で物事を判断します。
また、企業に対する忠誠心や帰属意識も相対的に低く、「なぜこの仕事をするのか」「自分とどう関係があるのか」といった目的の明確化を企業側に求める傾向があります。企業は、Z世代が共感できるようなビジョンの提示や、納得感のある説明を行うことが求められます。
Z世代を形づくった時代背景と価値観
Z世代の多くは、義務教育の途中からタブレット学習を経験し、動画やSNSを日常の情報源としてきました。彼らにとって「情報はデジタルで得るもの」であり、検索やSNSのフィードから、自分の関心のある情報を自ら取りに行くことに慣れています。
また、彼らが思春期を迎えた2010年代には、東日本大震災、コロナ禍、社会的分断、気候変動といった大きな出来事が重なり、「未来は予測できないもの」という認識が深く根付いています。そのため、Z世代は計画性よりも柔軟性を重視し、長期よりも短中期的な価値に重きを置く傾向があるといえるでしょう。
一方で、こうした変化の激しい時代に育ったがゆえに、「安定した土台」を強く求める側面も持ち合わせています。表面的には“変化を楽しむ世代”に見えても、その内側では“安心して挑戦できる環境”を求めている、という点に注目する必要があります。
Z世代の文化的背景
デジタル世代としてのリアルとバーチャルの融合
Z世代を理解するうえで最も重要なのは、「オンラインの世界が日常である」という点です。SNSを使ったコミュニケーション、動画による学習や趣味、ECサイトでの買い物など、あらゆる行動がデジタル環境の中で完結する生活様式が根付いています。彼らにとって、リアルとバーチャルの境界はあいまいであり、どちらも“現実の一部”として自然に受け入れられています。
また、ミレニアル世代(Y世代)との比較で見ると、Z世代は“自分らしさ”をより強く意識する傾向があります。Y世代がSNSを通じて「共感」を求めてきたのに対し、Z世代は「信頼性」や「確かさ」を重視します。SNSでも理想を演出するのではなく、自分のリアルな姿をどう表現するかを大切にしているのが特徴です。こうした点からも、Z世代は見せ方より“中身の整合性”を重んじる価値観を持っていることがわかります。
日本社会におけるZ世代の感受性と多様性
日本におけるZ世代は、独特の文化的な感受性を持っています。特に「空気を読む力」や「察する力」が高く、場の雰囲気や暗黙の期待を読み取って行動する傾向が強く見られます。そのため、表立って意見を述べることが少ない場合でも、内心では不満や課題を感じている可能性がある点には注意が必要です。黙っていることが必ずしも“納得している”ことを意味するわけではないのです。
さらに、価値観の多様化が進んでいる現代においては、Z世代とひとくくりに語ることも難しくなっています。たとえ同じ年代であっても、育ってきた環境や経験してきた文化は人によって大きく異なります。そのため、Z世代を理解しようとする際には、「年齢」ではなく「どのような環境・価値観の中で育ったか」に注目する姿勢が重要です。このような視点を持つことで、より丁寧な関係構築や育成が可能になります。
Z世代の特徴と価値観
テクノロジーの進化と社会情勢の変化を背景に育ってきたZ世代は、これまでの世代とは異なる価値観や行動様式を持っています。企業が彼らと信頼関係を築き、共に成長していくためには、その特性を正しく理解することが不可欠です。
ここでは、Z世代が何を大切にし、どのように考え、行動しているのかを掘り下げて解説します。彼らの内なる動機や行動パターンを知ることで、より効果的なコミュニケーションや育成方針を考えるヒントが得られるはずです。
自己成長や貢献を重視する傾向
自分の成長を実感できる学びを求める
Z世代は、自分の能力を高めていく「自己成長志向」が強く、その過程に意味を求める傾向があります。単にスキルを身につけるだけではなく、「学んだことが何に役立つのか」「現場でどう活かせるか」に対する関心が高いのが特徴です。
企業の研修においても、知識を詰め込むだけの講義型より、実際の現場での活用を想定したプログラムや、アウトプットを重視するスタイルに強く共鳴します。「やってみて、振り返って、改善する」といったPDCA的なサイクルを自ら回すことに価値を見出し、能動的に学びを進める傾向があります。
社会に価値を届けたいという志向
Z世代は個人の成長だけでなく、「その成長が誰かの役に立っているか」を非常に重視します。特に災害や気候変動、ジェンダー、人種問題といった社会的なテーマへの関心が高く、「社会的意義のある仕事をしたい」と考える若手が増加しています。
そのため、キャリアについても「何年で管理職になるか」といった役職志向より、「こんな価値を提供できる人になりたい」という“あり方”を重視するケースが目立ちます。企業側がキャリアパスを設計する際には、単なるポジションではなく、成長の機会や社会への接続性を意識した提示が求められます。
柔軟な働き方を求める理由
Z世代が重視するもう一つの大きな価値観が、「柔軟な働き方」です。フルリモート勤務やフレックスタイム制、副業解禁といった制度は、Z世代の志向に非常に合致しています。これは単なるラクをしたいという話ではなく、「自分らしく働きたい」「成果を出せる環境で力を発揮したい」という意欲の表れでもあります。
なぜ柔軟性が求められるのか。それは、Z世代が「時間と労力の配分を自分で最適化したい」と考えているからです。生活の質を保ちつつ、仕事に集中する時間は確保したい。無駄な会議や拘束時間を避け、より意義のある仕事に集中することで、自分のパフォーマンスを高めたいという意識が根底にあります。
さらに、転職やジョブチェンジへの心理的ハードルも低く、「この会社でずっと頑張る」という前提よりも、「自分の可能性を活かせる場所を常に探す」というスタンスが主流になりつつあります。企業にとっては、このような働き方のニーズに応えることが、Z世代の定着率やエンゲージメントを高める上で重要なポイントとなります。
タイパやコスパを意識した消費行動
Z世代の消費行動における最大のキーワードは、「タイパ(タイムパフォーマンス)」と「コスパ(コストパフォーマンス)」です。時間とお金をかける価値があるかどうかを重視する姿勢が非常に顕著で、何かを選ぶときには効率よく満足を得られるかを判断基準としています。たとえば、サブスクリプション型のサービスや、まとめ買いアプリ、ショート動画でのレコメンド視聴などは、まさにタイパ・コスパを重視するZ世代のニーズにマッチした行動です。彼らは価格だけでなく、「それにかける時間の価値」にも敏感なのです。
この傾向は、就職活動や転職においても見られます。企業選びにおいて、「自分の時間を投資する価値があるか」という視点を持ち、報酬や福利厚生だけでなく、働き方の柔軟性や成長機会の有無など、全体のパフォーマンスで判断しています。
結果として、Z世代は「無駄を避ける」「効率よく最大の効果を得る」ことを基準に行動しやすく、情報発信においても短く簡潔で、ビジュアル中心のコンテンツを好む傾向があります。企業がZ世代にアプローチする際は、この価値の設計が極めて重要となるでしょう。
自己表現とアイデンティティの重視
自分らしさを表現し、共感を得る行動様式
Z世代は、自分自身のスタイルや価値観を外部に発信することに積極的な世代です。特にSNS上では、「自分らしさ」を表現することで他者とつながり、共感を得るという行動が日常化しています。これは単なる自己主張ではなく、他者との関係性を築くための手段として自己表現を位置づけている点に特徴があります。
短い文章や画像、動画を通じて「自分はこうありたい」「こんな価値観を大事にしている」といったメッセージを発信し、それを通じて周囲との共通点を見つけていく。こうした行動は、個人の承認欲求だけでなく、共感ベースのつながりを重視するZ世代ならではのスタイルです。
アイデンティティを尊重する柔軟な価値観
Z世代の価値観を語るうえで欠かせないのが、「アイデンティティに対する柔軟な考え方」です。性別、国籍、信仰、職業といった従来のラベルにとらわれず、それぞれの違いを受け入れ、多様性を前提として人と接する姿勢が根づいています。グローバルな社会的背景の中で育った彼らにとって、違いは障壁ではなく当たり前のことなのです。
こうした考え方は、仕事観にも反映されます。Z世代は「会社の一員として与えられた役割を全うする」よりも、「自分らしさを活かせる環境で社会に貢献したい」と考える傾向があります。そのため、企業文化やマネジメントスタイルが画一的であると、モチベーションが下がりやすく、早期離職にもつながりかねません。Z世代の活躍を促進するためには、個々の価値観を理解し、それが尊重される組織環境を整えることが不可欠です。
Z世代の働き方
Z世代は、働く場所や時間、スタイルにおいて柔軟性を重視し、自分らしい働き方を追求する傾向があります。また、個人の成長だけでなく、チーム全体としての協力や学び合いにも価値を見出すため、これまでの「管理型」から「支援型」へのマネジメントの転換も求められています。
ここからはは、Z世代がどのような職場環境や働き方を好むのか、その価値観と具体的な対応方法について詳しく解説していきます。
働く場所より“働き方”を重視する世代
働く「時間」と「場所」への柔軟性を重視
Z世代にとって、職場は「通う場所」ではなく、「自分らしく働く場」であることが求められます。リモートワークやフレックスタイム制度、副業の容認など、柔軟な働き方ができるかどうかは、職場選びや定着における重要な判断基準の一つとなっています。
特に、物心ついた頃からオンライン環境に慣れ親しんできたZ世代にとっては、デジタルツールを活用したタイムマネジメントや、仕事と生活のバランスの最適化はごく自然な発想です。職場は「気軽に立ち寄れる」「必要に応じて活用できる」空間であることが理想とされており、オープンスペースやフリーアドレスの設計も、そのニーズに応える方法の一つです。
「信頼される働き手」でありたいという志向
Z世代は「管理されること」よりも、「信頼されて任されること」に価値を感じやすい傾向があります。そのため、働き方にもある程度の裁量が求められます。ただし、新入社員の段階では業務経験が浅いため、いきなりすべてを任せるのではなく、まずは基本的な業務スキルや知識を丁寧に身につけさせるステップが欠かせません。
その上で、「すでに持っている強みをどう活かすか」という視点を併せ持つことで、本人の納得感を高め、成長意欲を引き出すことができます。たとえば、得意分野や個人の興味関心を活かせる場面を適切に設けることで、早期から「貢献実感」を得られるようになり、職場への定着にもつながります。
チームワークと協力の重要性
Z世代は個人の価値観やスタイルを大切にする一方で、「誰かの役に立てること」「チームで成果を出すこと」にも強い意義を見出しています。ただし、ここで求められているのは旧来型の上下関係に基づく協力ではなく、対等でフラットな関係性における相互支援です。
Z世代の社員が「このチームで働いていて良かった」と感じるためには、オープンなコミュニケーションやフィードバックのしやすさが重要な要素となります。たとえば、雑談や非公式なチャットの活用、1on1ミーティングなどが、安心して意見を言える空気を生み出す要素として注目されています。
また、リーダーには「指示を出す存在」ではなく、一人ひとりの能力や強みを見極め、それを引き出す支援者的な役割が求められます。全体の成果を高めるためには、個々のモチベーションや貢献実感を大切にし、チーム全体での達成感を分かち合う文化の醸成が不可欠です。
若手の「ちょっとした工夫」をチーム全体で認める文化づくり
たとえば、若手メンバーがミーティング資料のデザインを見やすく工夫したとします。そのとき、「それすごく見やすかった!全体の理解が進んだよ」といったポジティブなフィードバックをすぐに返すことで、本人にとっては「自分の仕事が役に立った」という実感につながります。
また、Slackやチャットツール上で「この資料すごく助かった!」といった反応が複数出ることで、Z世代の社員は「自分がチームに貢献できた」と感じやすくなります。こうした日常的な“役立ち合い”こそが、Z世代にとってのチームワークの本質なのです。
自己成長を重視する価値観
Z世代の働き方において最も一貫して見られるのが、「自己成長への強い関心」です。仕事においても、単に給与や待遇だけでなく、「どれだけ自分を高められるか」「成長の実感があるか」という視点で職場環境を見ています。
この背景には、変化の早い社会で自分の価値を持ち続けたいという思いや、AIや自動化が進む未来においても「自分だからこそできる仕事」を目指す志向があります。そのため、教育・研修・フィードバックといった育つ仕組みの有無は、職場選びの大きな判断材料となっています。
Z世代に響く取り組み
- 自己啓発支援制度(書籍購入補助・eラーニングの自由受講)
- 定期的な1on1面談によるフィードバック機会の提供
- 成果だけでなく「成長の過程」も評価する制度設計
Z世代は、結果以上に「過程」に納得できるかを重視します。努力の積み重ねや、自分なりに工夫した点を認めてもらうことで、次の挑戦への意欲が高まります。そのため、フィードバックを通じたコミュニケーションが組織全体に根付いているかどうかが、彼らにとっての「働きやすさ」と「定着」に直結するといえるでしょう。
Z世代の職場での課題
Z世代の価値観や働き方への期待に対し、企業や上司が十分に対応できていないことで、離職やすれ違いが生まれるケースも少なくありません。しかし一方で、Z世代側も職場で成果を出すために必要な姿勢やスキルを身につける努力が求められます。
ここからは、双方の歩み寄りを前提に、現場で起きやすい課題とその対応策について、現実的な視点で整理していきます。
離職率の高さとその原因
Z世代の離職率が高い背景には、企業との間にある「価値観のギャップ」や「働き方の不一致」が関係しています。やりがいやキャリアの成長を重視するZ世代にとって、「この職場で何が学べるか」「どう成長できるか」が明確でない場合、早期の転職を検討する傾向が強くなります。
こうした傾向を踏まえ、企業側はキャリアパスや育成計画の可視化、効率的な業務設計など、働く意味や環境を再構築する努力が求められます。特に納得感のある成長実感を得られる仕組みを整えることが、Z世代の定着に効果的です。
Z世代の中には、「早く成果を出したい」「自分の成長をすぐに実感したい」と考える傾向があることも否めません。これは成長意欲の裏返しでもありますが、現実的には、仕事のやりがいやスキルの熟成にはある程度の時間が必要であることを、育成の過程で丁寧に伝えることが重要です。人事担当者や上司は、短期的な成果だけでなく、取り組みのプロセスや積み重ねの意義についても言葉で説明し、「成長には段階がある」という前提を共有することが、Z世代との認識ギャップを埋める第一歩となります。
Z世代の早期離職を防ぐための対策
- キャリアの見通しを早期に提示する
Z世代は「今この経験が将来にどうつながるか」を重視する傾向があります。業務の中に意味づけを行い、「●年後にはこんなスキルが身につく」「この経験が将来の〇〇に活きる」といった見通しを示すことが大切です。 - 小さな成功体験を積ませる仕組みづくり
成果がすぐに見えにくい業務でも、スモールゴールを設定し「できた」という実感を持てるように支援します。週単位の目標管理や、1on1での進捗確認を通じて「やっている意味がある」と感じられる工夫が重要です。 - フィードバック文化の定着
プロセスを丁寧に認めるフィードバックが、Z世代の定着率を左右します。結果だけを評価するのではなく、「工夫していたね」「考え方が前より深くなったね」といったプロセスを認める文化を育てることで、安心感とやりがいが育まれます。
コミュニケーション不足の影響
職場におけるコミュニケーションの齟齬は、世代を問わず課題となり得ますが、Z世代の場合は特に伝え方と受け取り方のスタイルに違いが見られます。文章や動画など視覚的な情報に慣れているZ世代にとって、口頭だけでの曖昧な指示や雑談をベースとした情報共有は理解しづらく、誤解の原因になることもあります。
そのため、企業側では動画マニュアルやチャットツールの活用など、視覚的で整理された情報伝達を意識することが効果的です。また、悩みや課題を早期に共有できるような仕組みを整えることで、コミュニケーション不足による孤立やストレスの発生を防げます。
Z世代はSNSやテキストでのやりとりに慣れている反面、職場における伝える力や読み取る力にギャップが生じるケースもあります。そのため、報連相や質問の仕方、相手の立場を踏まえた伝え方など、基本的なビジネスコミュニケーションの型を実践の中で教えていくことが必要です。
特に新人期には、「伝えたつもり」「理解しているつもり」が誤解につながりやすいため、人事や現場リーダーが対話を通じて少しずつその感覚を育てていくことが、信頼関係づくりに直結します。企業とZ世代双方が、伝えると受け取るの両方に責任を持つ意識を共有することで、コミュニケーションの質は格段に高まります。
上司との関係性の改善
上司と部下の関係性において、Z世代は「上下関係」よりも「対等で誠実な対話」を重視する傾向があります。一方的な指示や評価に対しては納得感を持ちにくく、不信感やストレスを抱えやすくなることもあります。企業や上司としては、フィードバックの頻度や質を見直し、対話ベースのコミュニケーションを意識することが求められます。定期的な1on1やリアルタイムな声かけによって、行動の背景や意図をすり合わせる機会を増やすことが、信頼関係の構築に効果的です。
Z世代に限った話ではありませんが、近年の若手はフィードバックに対して慎重な姿勢を見せることがあります。だからこそ、企業としては改善のためのフィードバックであることを前提に、丁寧に伝えることが求められます。
Z世代に響くフィードバックの伝え方
- 価値否定に感じさせない表現を工夫する
Z世代は「自分が否定された」と感じると、強い防御反応を示すことがあります。そのため、「あなたの強みをさらに活かすために、この点を変えてみよう」といった前向きな言い換えが効果的です。 - できている点と改善点をセットで伝える
「ここは良かったよ。そのうえで、もっとこうするとさらに良くなる」というように、肯定的なポイントと改善点をバランスよく伝えることで、フィードバックを受け入れやすくなります。
Z世代を育成するための効果的な方法
Z世代は「意味のある成長」「納得感のある学び」「自分らしいキャリア形成」を強く求める傾向があり、これまでの画一的な育成スタイルだけでは通用しない場面が増えています。しかし、すべてを個別最適に対応するのは現実的ではありません。そこで重要になるのが、組織としての方針を保ちつつ、個の違いに配慮した柔軟な育成設計です。
この章では、人事担当者が押さえておきたい5つの育成ポイントを具体的に解説します。
個別の価値観を尊重するコミュニケーション
Z世代の育成において第一に意識すべきは、「一人ひとりの価値観や背景が異なることを前提に接する」ことです。同じ20代でも、育ってきた家庭環境、進路選択、SNSとの関わり方などは多様であり、それが職場での期待や行動スタイルにも表れます。
たとえば、「出世したい」というタイプもいれば、「仕事と趣味を両立したい」「社会課題に関心がある」といった異なる軸を持つ若手もいます。人事担当者は、これらの違いを否定せずにまずは「どう考えているか」を引き出し、その価値観に沿ったフィードバックやサポートを意識することが信頼形成の鍵となります。
実際のコミュニケーションでは、以下のような工夫が効果的です。
- 初期面談や1on1で「将来的にどんな状態になっていたいか」を丁寧にヒアリング
- メールやチャットでは堅すぎない言葉選びで親しみやすい印象を与える
- プライベートな関心事(趣味・学び・ライフプラン)に触れられる場をつくる
もちろん、すべてを個別対応する必要はありません。「個を尊重する姿勢がある」だけで、受け手の反応は大きく変わるのです。
【事例紹介】自己理解を促す研修
Z世代の価値観に寄り添った育成施策として、「自己理解研修」の導入も効果的です。ある企業では、新入社員向けに以下のようなプログラムを実施しています。
- 目的: 自身の性格特性、強み・弱みや価値観を知り、これからの業務に活かす
- 内容: 性格診断レポートや価値観カードを活用したワークを通じて、自身の特性について分析する

「自分が弱みだと思っていたことが逆に強みだったり、その逆もあって新しい自分を見つけれた気がします」
「自分の得意不得意がわかり、今後の業務や人生に活かせるとても有意義な研修でした」
「自己を知る研修を通して、今まで気づいていなかった側面を知ることができて興味深かった」
このような取り組みにより、Z世代が自身の価値観や特性を言語化できるようになり、上司や先輩との関係構築もうまくいきやすくなります。人材育成において対話のスタート地点をつくる手法として、多くの現場で活用が進んでいます。
実践的なフィードバックを重視する
Z世代は、自分がどこを評価され、どこを改善すべきかを具体的に知りたがる傾向があります。そのため、抽象的・一般的なフィードバックでは満足感も納得感も得られにくいのが実情です。
たとえば、「がんばっているね」という一言よりも、「プレゼンの導入部分が特に分かりやすかった。改善点としては、スライドの文字量をもう少し絞るとさらに良くなる」といったような、具体性のある言葉が重要です。
また、フィードバックは特定のタイミングだけでなく、日常の中で繰り返すことが効果的です。
- プロジェクト終了後のレビュー時間を10分だけ確保
- Slackやチャットで即時に軽いコメントを返す
- 月1回の1on1で「最近どうだった?」から始めて気軽にふりかえる
こうした日常の中のフィードバックは、Z世代の「自分の成長を知りたい」「改善したい」という内発的なモチベーションを継続的に刺激します。また、評価制度の透明性と連動させることで、より納得感の高い育成サイクルが実現できます。
キャリアパスとライフプランを描くための企業の役割
Z世代は「今の仕事が将来どんな価値につながるのか」「10年後の自分がどうなっているのか」といった中長期の視点を意識しながら働きたいと考えています。しかし現実には、社会人としての経験が浅いため、将来像が描ききれず不安を感じているという声も少なくありません。
ここで人事や上司が果たすべき役割は、「視野を広げるきっかけ」を提供することです。
- 定期的なキャリア面談の実施(年1回以上が望ましい)
- 他部署とのジョブローテーションや社内兼業制度の設計
- モデルとなる先輩社員のキャリア事例を社内で共有
また、ライフイベントとの両立(育児・介護・副業など)についても、選択肢と支援制度を整理して可視化しておくことで、Z世代は長く安心して働けるイメージを持ちやすくなります。
企業が将来の選択肢を提示することは、「ずっとこの会社にいなさい」という意味ではなく、「この会社でも、自分の人生を築いていける」と感じてもらうための信頼構築につながります。
メンター制度の導入
Z世代は「困ったときに誰に相談すればいいか」が明確でないと、不安や孤立感を抱えやすい傾向があります。そこで有効なのが、信頼できる先輩との継続的な関係性を築くためのメンター制度です。
メンター制度導入のポイント
- メンター選定にあたっては、経験年数だけでなく対話力を重視
- メンター・メンティー双方の「目的」や「期待」を初回面談で共有
- 月1回以上のセッションを推奨し、進捗確認や雑談の時間も設ける
- メンター活動に対する評価・表彰制度も併用することで質を維持
また、制度の形式ばかりが先行してしまうと、ただ「形式的に面談を行うだけ」の仕組みに陥りがちです。人事としては、定期的にフィードバックを回収し、運用上の課題をこまめに修正する進化型制度として育てていくことが大切です。
メンター制度は、育成だけでなく組織文化の醸成にもつながる重要な施策です。Z世代が「この職場には信頼できる人がいる」と思える環境があることで、安心感と自律的な行動が両立されやすくなります。
Z世代との良好な関係の築き方
Z世代と信頼関係を築き、組織の一員として活躍してもらうためには、関係構築の「質」と「継続性」が重要です。単にフレンドリーであればよいという話ではなく、価値観や育ってきた背景への理解、安心して働ける組織設計、適切なサポート体制など、複合的な要素が求められます。
この章では、人事やマネジメント層が取り組むべき「関係づくり」のポイントを4つに分けて詳しく解説します。
フラットな組織文化の必要性
Z世代は、上下関係にとらわれたヒエラルキー型の組織文化よりも、「誰でも意見を言える」「立場に関係なく話し合える」環境に魅力を感じる傾向があります。特に、「正解が1つではない」時代を生きてきた彼らにとって、意見を共有しやすい環境は、自己表現と仕事の納得感を両立させる重要な条件となります。
フラットな文化を築くためには、まず社内の価値観や目的を共有する場を設けることが効果的です。定期的に実施されるセミナーやワークショップを活用し、「この組織が大切にしていること」「どこを目指しているのか」を、目次のように整理して伝えることで、共通認識が深まります。
また、上司が率先して若手の意見を引き出す姿勢を見せることも大切です。会議や雑談の場で、「トップから言われたからやる」のではなく、「現場の声を起点に考える」文化を醸成することが、Z世代との信頼構築に直結します。
重要なのは、形式的なフラット風ではなく、本当に意見が届く・形になる体制を整えることです。発言機会を与えるだけでなく、「発言がどう活かされたか」を振り返るプロセスまで含めて設計することで、信頼と協働の関係が築かれていきます。
多様な価値観の理解
Z世代は、多様性を前提とした環境で育ってきた世代です。国籍、性別、家庭環境、考え方などの違いを「当然のこと」として受け入れる素地があり、むしろ「一律であること」に違和感を覚えることさえあります。
企業がZ世代と良好な関係を築くためには、社内制度・評価軸・コミュニケーションスタイルの中に多様性への配慮を組み込むことが求められます。
- 柔軟な服装・勤務形態の許容
- パートナーシップ制度やLGBTQ+支援に関する明文化
- 異なる考えを歓迎するファシリテーションの研修導入
また、一人ひとりの価値観を丁寧に理解しようとする姿勢が、Z世代にとっての「この組織にいてよかった」という実感につながります。社内での意見交換の場も、同質性を前提としたものではなく、異なる視点に触れる学びの場として設計すると、より前向きな空気が生まれます。「わからないから排除する」のではなく、「わからないから聞いてみる」文化の醸成が、人事施策の根幹となるでしょう。
サポート体制の強化
Z世代は、情報が多すぎる現代社会の中で常に「選択の連続」にさらされており、その分「迷ったときに相談できる相手がいるかどうか」を非常に重視します。そのため、組織としてのサポート体制がどれほど明確に可視化されているかが、安心感や信頼の獲得に直結します。
まず、Z世代にとって「支援がある」と感じられる状態とは、以下のような要素が揃っていることを指します。
- 相談窓口やフォロー体制が明文化されている
- 研修やOJTの目的・流れがわかりやすく整理されている
- 上司や人事との定期面談が制度として存在し、実際に機能している
また、業務に関する具体的な支援ツール(業務マニュアル、よくある質問、チャットボットなど)を整備し、「困ったときに頼れる場所がある」という状態を維持することが、Z世代の不安軽減につながります。
対応においては、ただ「優しくする」のではなく、「しっかりと説明し、必要な情報を適切に提供する」ことが重要です。特に現場のリーダーやOJT担当者には、タイムリーで具体的なフォローができるよう、人事からノウハウを提供することも有効です。
心理的安全性を高める取り組みと職場環境整備
心理的安全性とは、「この職場で自分の意見や感情を安心して表現できる」と感じられる状態を指します。Z世代はこの点に非常に敏感であり、たとえ待遇や制度が整っていても、「発言できない」「失敗できない」空気感がある職場では、パフォーマンスが著しく下がる傾向があります。
このような職場環境を整えるためには、信頼・尊重・対話の3要素を軸にした施策設計が欠かせません。
- 日報や1on1で「不安なこと・迷っていること」も話題にできる構成にする
- 上司が率先して「自分もミスする」と語ることで、失敗を共有する文化を作る
- アイディアや意見を出した社員に対し、「まずは受け止める」対応を徹底する
また、物理的な環境整備も心理的安全性に影響します。音や視線を気にせず会話できるミーティングスペースや、リフレッシュルームの設置、壁の掲示物によるポジティブなメッセージの発信など、五感に働きかける職場設計も有効です。
人事担当者としては、アンケートやヒアリングを通じて社員の「声にならない声」を把握し、定量・定性的に施策の見直しを続けることが、心理的安全性の基盤を育てる第一歩になります。
Z世代と成功する企業文化の構築
Z世代が「この会社で働き続けたい」と感じるためには、共感できる企業文化の存在が欠かせません。特に、フラットな関係性、多様性の尊重、自律的な働き方といったキーワードが、Z世代に響く重要なポイントとなります。
この章では、Z世代との協働を前提にした組織文化づくりの視点と実践方法を紹介します。
フラットな組織での関係性構築
Z世代は、年功序列や上下関係が強調される組織よりも、誰もが対等に意見を述べ、協力し合えるフラットな関係性を重視します。そのためには、「上司=指示する人」「部下=従う人」という構造を見直し、役割は異なっていても対等な関係としてチームが機能する仕組みづくりが求められます。
具体的な工夫の例
- 1on1ミーティングの中で、上司もフィードバックを受ける側としての姿勢を見せる
- 「若手からの逆提案歓迎」などのカルチャーを制度に組み込む(提案掲示板、ボトムアップ制度など)
- プロジェクトにおいてリーダーシップを共有・分担する形式(タスクごとに責任者を変えるなど)
これにより、Z世代は「自分にも発信する権利がある」「チームの一員として認められている」と感じやすくなります。
また、フラットな関係性は馴れ合いとは異なります。組織文化の中に「信頼をベースにした対話のルール」を整備し、相互にフィードバックをし合える仕組みを整えていくことが必要です。このような環境が整えば、Z世代だけでなくすべての社員が声の届く職場としての一体感を感じ、エンゲージメントの高い組織文化が自然と構築されていきます。
多様性を尊重する職場環境の整備
Z世代は「多様性=当然」ととらえる世代であり、性別、国籍、年齢、働き方、考え方などの違いが尊重されているかどうかを、職場選びの重要な軸としています。そのため、企業文化の中に個を尊重する姿勢が自然と根付いているかが、定着率や活躍の度合いにも直結します。
そのために、まずは採用・評価・配置において多様性をどう活かすかという視点を持つ必要があります。
- 採用時に「どのような視点を加えてくれるか」を評価基準に組み込む
- バックグラウンドが異なるメンバーを混成したチーム構成を意識する
- 意見の違いを歓迎する研修・ディスカッション機会を設ける
さらに、Z世代の社員が「違いを言える」「違いを聞いてもらえる」と感じるためには、上司や先輩の受け止める姿勢の育成が必要です。たとえば、「そういう考えもあるね」「初めて聞いたけど面白い」といった反応一つで、相手の心理的安全性は大きく変わります。
変化を受け入れることは、組織にとってリスクではなく可能性です。Z世代が当たり前に感じている多様性のある状態を、企業文化の前提条件として再定義していくことが、これからの組織づくりには不可欠です。
自律的な働き方を促進する方法
Z世代は「自分の裁量で、納得感のある働き方をしたい」という意識が非常に強い世代です。仕事の意味やゴールを理解した上で、時間や進め方を自分で設計できる働き方を望んでいます。
このニーズに応えるためには、単にフレックスタイムやリモートワークを導入するだけでなく、自律できる状態を組織としてサポートする必要があります。
- プロジェクトの目的・スケジュール・役割分担を明確に可視化する
- タスク管理ツール(Notion、Asana、Backlogなど)を活用し、進捗を自分で把握できるようにする
- 週1の進捗共有ミーティングで、困りごとや改善アイデアを気軽に共有できる場をつくる
また、業務目標を上司が一方的に決めるのではなく、目標設定の段階から本人の意見を取り入れるプロセスを整えることで、自律性と責任感の両立が可能になります。自律とは、「放任」でも「完全自由」でもありません。ルールや枠組みの中で、自分の意思と裁量を発揮できるよう支援することが、Z世代の活躍を後押しする重要なポイントになります。
Z世代への適切なアプローチ
Z世代の活躍を引き出すには、価値観や行動様式を一方的に理解しようとするだけでなく、「どのように関わるか」のアプローチ方法を工夫することが欠かせません。
この章では、Z世代と信頼関係を築き、組織の一員としてしっかりと定着してもらうために、人事やマネジメント層が意識すべき具体的な接し方や設計手法を紹介します。
価値観の尊重と理解
Z世代との関係づくりにおいて、もっとも大切な出発点は「相手が何を大事にしているか=価値観」を正しく捉える姿勢です。自分とは異なる優先順位を持つ若手に対して、「理解できない」と突き放すのではなく、「なぜそう考えるのか?」を丁寧に聞き取るコミュニケーションが信頼のベースになります。
Z世代が重視する価値観
- 自己成長・学びの実感
- 意味のある仕事・社会貢献性
- ワークライフバランス(時間の使い方の最適化)
- 多様性と自分らしさの尊重
- オープンでフラットな対話環境
これらの価値観を「一覧表」のように社内で共有し、上司・先輩・人事が共通言語として持っておくことで、コミュニケーションの齟齬を減らせます。
また、Z世代が使う言葉や表現(タイパ、コスパ、エモい、空気読むなど)に対する感度を高め、言葉の意味のギャップを埋める姿勢も大切です。相手の意図を確認しながら対話を進めることで、互いの理解が深まります。共感的な聞き方・応答を実践することも重要です。たとえば、「なるほど、そう感じたんだね」「その視点は気づかなかった」などの言葉を添えることで、Z世代は「自分の考えが受け入れられた」と感じやすくなります。
失敗を受け入れる文化の醸成
Z世代は「自分の行動がどう評価されるか」に敏感な一方で、挑戦意欲やクリエイティブな力も大きな強みとして持っています。この力を引き出すためには、「失敗しても大丈夫」「次に活かせば良い」という心理的安全性を育む文化が不可欠です。
実際、Z世代の多くは、ミスをした際に「評価が下がるのではないか」「信頼を失うのでは」と不安を抱える傾向があり、その結果、慎重になりすぎて本来のパフォーマンスを発揮しにくくなることがあります。
解消するには
- 「失敗から何を学んだか」に注目してフィードバックを行う
- 上司や先輩が「自分の失敗談」を積極的に共有する
- 小さな成功体験を可視化し、挑戦したこと自体をポジティブに捉える
また、社内で過去にあったチャレンジと成功の事例をストーリーとして共有する仕組み(社内報、朝礼、社内SNSなど)も、若手の挑戦を後押しする文化づくりにつながります。失敗を許容するというのは「甘やかす」ことではなく、学びと成長を伴う行動を肯定的に評価する風土をつくることです。
期待値の明確化と合意形成
Z世代との関係において、最も多く聞かれる課題のひとつが「何を求められているのかがわからない」という声です。これまで以上に、あうんの呼吸では伝わらない時代になっており、業務の目的・期待される成果・役割の明確化は、対話による合意形成を通じて行う必要があります。
意識すべきこと
- 業務依頼時に「何を・いつまでに・どのようにしてほしいか」を具体的に伝える
- 新しい仕事を任せる際には、「なぜあなたに頼むのか」を補足することで納得感を高める
- チーム内での役割分担や進め方を事前に共有し、合意の上でスタートする
さらに、期待値は一度共有して終わりではなく、定期的にすり合わせを行うことが重要です。月次面談やプロジェクトごとの中間レビューなどを設け、「今の方向性で合っているか」「変更すべき点はないか」を確認し合うプロセスを取り入れると、トラブルやすれ違いの未然防止につながります。
Z世代は「自分がどこを目指しているのか」「何を期待されているのか」が明確になったときに、本来の能力を存分に発揮する力を持っています。だからこそ、指示よりも共通理解を土台としたアプローチが求められるのです。
まとめ
Z世代は、自己成長や社会貢献への意識が高く、多様性と自律性を重んじる世代です。これまでの常識が通用しにくいと感じる場面もあるかもしれませんが、彼らの価値観を理解し、適切な関わり方や環境づくりを行うことで、確かな戦力として成長していく可能性を秘めています。
企業が一方的にZ世代に合わせるのではなく、組織としての方針を保ちながら、個々の強みや特性を活かす設計へと転換していくことが、今後の人材育成戦略の鍵となるでしょう。Z世代とともに未来をつくるための第一歩として、この記事が社内での対話や仕組みづくりのヒントとなれば幸いです。関連施策とあわせて実行することで、よりうまくZ世代と向き合っていくことができるはずです。
若手も管理職も、成長を実感できる研修を


「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」
「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」
「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」
若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。
アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。
アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴
- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供
- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走
- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決
- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供
研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。