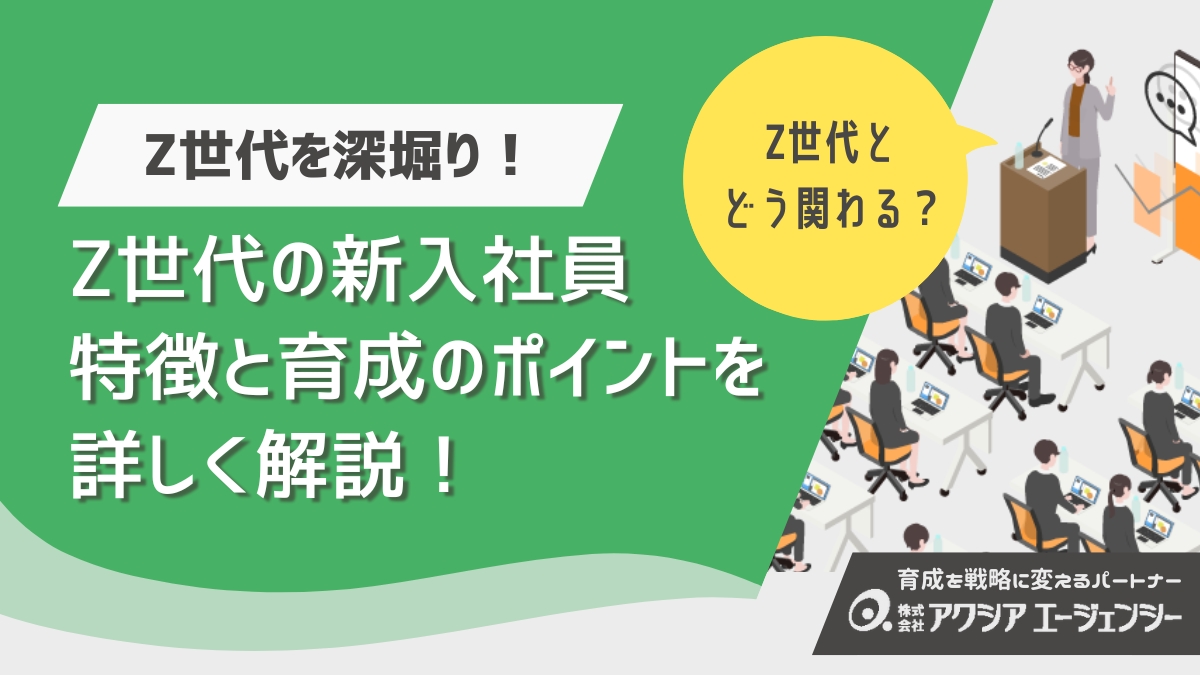新入社員の受け入れを迎える時期になると、「最近の若手はちょっと違うな」と感じる方も多いのではないでしょうか。とくに近年は、“Z世代”と呼ばれる1997年〜2012年生まれの新卒社員が社会に出始め、これまでの世代とは異なる価値観や行動パターンに戸惑う声が企業の現場からも聞かれるようになりました。
私自身、営業現場で10年以上新卒メンバーを受け入れ、その後は人事として採用や研修に関わってきましたが、「世代が変われば育て方も変わる」ことを日々実感しています。とはいえ、「Z世代だから特別扱いをすべき」と言いたいわけではありません。
大切なのは、Z世代の背景や特徴を一括りにするのではなく、なぜそうした傾向が生まれたのかを丁寧に捉え、どう理解し、どう育てるかを冷静に考えていく姿勢です。
この記事では、Z世代の新入社員が持つ特徴や育成上のポイントを、多角的な視点から整理・解説していきます。Z世代とこれからどう関わっていくかに悩む人事・育成担当の方々にとって、ヒントとなる内容をお届けできれば幸いです。
Z世代新入社員の基本的な特徴
Z世代の新入社員が増える中で、彼らの価値観や行動様式に戸惑いを感じる現場の声を多く耳にします。実際、営業現場で10年以上新卒と関わってきた私も、「以前の世代とは何かが違う」と感じる場面が増えてきました。
もちろん、世代が変われば考え方や行動パターンが異なるのは当然のことです。ただし、Z世代にはZ世代ならではの背景や特性があるということを理解することが、今後の育成や職場づくりにおいて欠かせないポイントとなります。
このパートでは、Z世代がどのような時代を生きてきたのか、なぜ今のような価値観を持っているのかを紐解きながら、「どのように接し、どう育てていくべきか」の土台となる情報を整理していきます。
Z世代の定義と背景
Z世代とは、一般的に1997年から2012年頃に生まれた世代を指します。現在の新入社員の多くがこの世代にあたり、企業にとってはまさにこれからの職場の中心になっていく存在です。私自身、営業現場で10年以上、新卒メンバーの育成に関わってきましたが、Z世代が入社してくるようになってから、「新人のタイプが明らかに変わってきた」と強く感じています。
Z世代は、子どもの頃からインターネットやスマートフォンに触れ、SNSを通じて人と関わることが当たり前の環境で育ってきました。家庭や学校でもデジタル機器が日常的に使われる時代背景の中で、情報にアクセスするスピードや選択肢は飛躍的に広がりました。
また、少子高齢化や経済停滞、そしてコロナ禍による生活環境の変化など、社会的にも大きな節目を経験してきた世代でもあります。大学生活の一部をオンラインで過ごした学生も多く、リアルな人間関係を築く場が限られた経験も影響しています。
このような背景から、Z世代の新入社員は、これまでの世代とは異なる前提で社会に出てきていることをまず理解することが大切です。育ってきた土壌が違えば、価値観や行動の基準も当然違ってきます。その前提を押さえることで、育成やコミュニケーションの設計にも説得力が増していくと私は感じています。
| 生まれた年 | 1997年~2012年ごろ(現13~28歳ごろ) |
| 育った環境 | SNS・スマホ・ネットが当たり前のデジタルネイティブな環境 |
| 価値観の特徴 | 自分らしさ重視・意味のある仕事を求める・柔軟性重視 |
| 強み | デジタルネイティブ・柔軟な発想力・自己表現が得意 |
| 苦手とされる点 | 報連相のタイミング・曖昧な指示・対面コミュニケーション |
他世代との違い
Z世代の新入社員と接していてまず感じるのは、「自分の考えや価値観を大切にしている」という姿勢の強さです。これは、ミレニアル世代以前のように「会社に合わせる」「空気を読む」といった感覚とは、明らかに異なります。
この違いの背景には、Z世代が育った社会の変化があります。たとえば、家庭でも学校でも、「あなたの個性を大切にしよう」という教育が当たり前になり、画一的なルールや評価に対しては違和感を持ちやすい傾向があります。
さらに、SNSなどを通じて常に他人と比較される環境で育った彼らは、「他人と同じであること」よりも「自分らしさ」を重視し、その表現にも積極的です。その分、承認欲求が強く、フィードバックや共感を求める場面が多いというのも、現場で感じるポイントです。
| Z世代(1997年~) | ミレニアル世代(1981~1996年) | 団塊ジュニア世代(1971~1980年) | |
|---|---|---|---|
| 情報収集手段 | SNS・動画・検索 | WEB・ブログ・SNS | 書籍・新聞・TV |
| コミュニケーション傾向 | チャットやスタンプ、共感重視 | メール・SNSに適応 | 対面や電話が主流 |
| 重視する価値観 | 自分らしさ・意味のある仕事 | 成長・成果・ワークライフバランス | 安定・上下関係・評価制度 |
| 教育スタイルへの適応 | 自己主導型・個別対応が合いやすい | 自己成長型・ロジカル思考を好む | 指示型・経験重視の傾向 |
| 承認・評価への反応 | 共感や頻度重視、「見てもらえているか」がカギ | 達成評価・成果に対する認知が必要 | 結果よりもプロセスや姿勢を評価されたい |
ただし、「違うから仕方ない」と受け入れるだけでは、組織は成り立ちません。私たちが持つビジネスの基本やチームで働くうえで必要なスキルは、しっかり伝えていく必要があると思います。
Z世代の個性や考え方を尊重しつつも、「会社の一員としてどう動くか」を共に考えていく姿勢こそが、世代間の信頼関係を築く第一歩になると私は感じています。
Z世代が育った学校教育の変化
Z世代が育った教育環境には、これまでの世代とは大きな違いがあります。特に顕著なのは、教育現場におけるデジタル化の加速です。小中学校でのICT教育の導入、高校・大学でのオンライン授業の普及は、Z世代にとっては当たり前の経験となっています。
例えば、授業にタブレットを活用したり、eラーニングで自分のペースで学ぶスタイルに慣れていることから、「決まった時間・決まった場所で学ぶこと」に強いこだわりがないという傾向も見られます。自ら検索し、動画などで学ぶ「セルフラーニング力」がある一方で、受け身型の一斉講義に対しては集中力が続きにくいという声も現場では聞かれます。
さらに、近年はプロジェクトベースの学習(PBL)やグループワークも増え、協働しながら成果を出すスキルや、自己表現を重視する機会が多く設けられてきました。このような教育経験は、企業に入ってからのチームワークや発信力にも一定の影響を与えています。
教育の変化はZ世代の価値観にもつながっており、「自分の意見を持ち、共有すること」が自然な行動となっています。これを理解していないと、企業側が想定する「新人らしさ」と、実際の行動との間にギャップが生まれてしまう可能性があります。
社会経済の動向と新入社員への影響
Z世代が社会に出るまでの間に経験した社会的・経済的な出来事の影響も大きな特徴の一つです。特に、コロナ禍は彼らの学生生活や就職活動、そして社会人としてのスタートに大きなインパクトを与えました。オンライン授業や就活のWeb面接が一般化したことで、「人と直接会う機会の少なさ」や「実感を持ちづらい就職プロセス」に不安を感じる声も少なくありませんでした。
こうした経験から、Z世代の新入社員は、環境の変化に柔軟に対応できる力を持ちつつも、対面での関係構築には慎重になる傾向があります。
また、社会全体が変化の激しい時代に入ったことで、「会社に依存しない生き方」「自分でキャリアを築く」という意識も高まっています。終身雇用や年功序列といった価値観はすでに薄れつつあり、Z世代は「今の会社でどんな経験が得られるか」「自分の成長につながるか」を重視する傾向が見られます。
加えて、情報化社会により、企業の透明性や社会的責任への感度も高いのが特徴です。ブラック企業の話題やSNSでの企業の評判が、入社前から意思決定に影響を与えるようになっており、「働く場所を選ぶ力」が以前の世代より格段に高くなっています。
こうした社会経済の背景を理解せずに従来型の新入社員像を当てはめると、ミスマッチや早期離職を招くリスクもあります。企業としては、Z世代が置かれてきた時代背景を踏まえたうえで、現代的な価値観に合った関わり方を考えることが求められます。
Z世代の新入社員が抱える課題
Z世代の新入社員は、柔軟な発想力やデジタルリテラシーの高さといった強みを持つ一方で、職場でのコミュニケーションやプレッシャーへの対処といった面でつまずきやすい傾向があります。営業現場でマネジメントをしていた頃から、新人たちの悩みの質が少しずつ変わってきているのを実感しています。これは、育ってきた環境や価値観の変化が大きく関係しています。
たとえば、Z世代はテクノロジーが生活の一部となっている時代に育ち、学校教育でも「個性」や「協働」が重視される傾向が強まりました。また、コロナ禍による学生生活の制限も、社会に出た際の適応に影響を与えています。
ここでは、Z世代の新入社員が直面しやすい2つの課題を取り上げ、職場側がどのように理解し、関わっていくべきかを考えていきます。
職場でのコミュニケーションの難しさ
Z世代の多くは、テキストやスタンプを使ったライトなやりとりに慣れています。そのため、仕事の現場で必要とされる対面での意思疎通や、状況を読みながらの会話に不安を感じるケースが目立ちます。
これは、教育現場での変化も関係しています。近年は協働や個性重視の学習スタイルが主流になり、正解のない課題に向き合う柔軟さは育まれたものの、「報告・連絡・相談」といったビジネス上の基本動作を経験する機会は限られていたと言えます。
そのため、職場では「どのタイミングで報告すればいいかわからない」「先輩に声をかけるのが怖い」といった戸惑いが出やすくなります。放っておけば、情報不足や孤立感につながる可能性もあります。
まずは、新入社員同士がリラックスして話せる関係づくりを支援することが、全体のコミュニケーション活性化の第一歩になります。そして徐々に、上司や先輩とも信頼関係を築けるような導線を用意することが、安心して発言できる環境づくりに効果的です。
プレッシャーへの対処と影響
Z世代の新入社員について、「プレッシャーに弱い」と語られることがあります。ただし、それは単に「打たれ弱い」といった精神的な脆さではなく、育った環境や社会構造によって形成された傾向として理解する必要があります。
SNSと評価への敏感さ
まず一つは、SNSやデジタル環境の影響です。Z世代は、子どもの頃からスマートフォンと共に成長してきた世代です。常にSNSで他人の情報に触れ、成功例や「映える」日常が可視化された世界の中で生きてきた彼らは、自然と他人の評価や期待に敏感になりやすい傾向があります。
数値評価に慣れた価値観
また、教育や社会の変化も大きな影響を与えています。内申点や偏差値といった「数値で評価される」環境の中で過ごしてきたことで、「失敗しないこと=正しいこと」という価値観が根付きやすく、小さなミスにも強いストレスを感じてしまう傾向があります。
自己理解をベースに働く
Z世代はメンタルヘルスへの意識が高い世代でもあります。無理をして頑張るよりも、自分の限界を理解して調整する力に長けており、それを「弱さ」と切り捨てるのではなく、「自己理解力」や「持続可能な働き方への感度の高さ」として捉えることができます。
社会不安と未来への不透明感
そして、社会全体の不安定さも大きな要因です。コロナ禍による学びの断絶や孤独感、気候変動や経済不安といった問題は、Z世代にとって「将来が読めないことの当たり前化」を生み出しました。見えない不安にさらされながらの社会人生活のスタートは、想像以上に重いものなのです。
こうした背景を理解せずに「もっと根性を持て」と言っても、Z世代には響きません。彼らが感じるプレッシャーの背景を丁寧に捉えた上で、どう向き合うかが、育成する側に求められる視点だと私は思います。
大切なのは、プレッシャーと向き合う方法を一緒に探す姿勢です。感情を整理する時間の確保、相談しやすい関係性づくり、失敗を許容する空気感。こうした職場の支援体制こそが、Z世代の可能性を引き出す鍵になります。
Z世代の特性と価値観
近年、若手社員の行動や考え方に対して、「これまでとは違うな」と感じる機会が増えてきました。それは単なる世代間ギャップではなく、Z世代が育ってきた環境や価値観の変化によるものだと考えるべきでしょう。
私自身、営業現場でのマネジメントや人事としての採用活動を通じて、「今の若手はこういう考え方をするんだな」と気づかされることが多くなりました。その中で大切だと感じるのは、Z世代を一括りにするのではなく、どんな特性や背景があるのかを丁寧に理解する姿勢です。
このパートでは、Z世代の特徴的な強みであるデジタルリテラシーや、近年特に注目されている承認欲求や自己肯定感との関係性について掘り下げながら、職場でどのように関わるべきかのヒントを探っていきます。
デジタルネイティブとしての特性
Z世代の新入社員が持つ最大の強みの一つが、「デジタルツールを自然に使いこなす感覚」です。情報収集、ツール操作、SNS活用など、私たちが習得してきた技術を、彼らは前提として身につけているのが大きな違いです。
たとえば、業務で新しいアプリケーションを導入した際でも、マニュアルなしで操作方法を理解し、自ら調べて使いこなすといった姿勢が多く見られます。また、「もっと効率よくできる方法はないか」と改善提案をしてくれる場面も少なくありません。
このような特性は、単なる操作スキルというよりも、自ら課題を見つけ、ツールを手段として解決しようとする主体性や柔軟性の表れとも言えます。特にバックオフィス業務や情報共有、資料作成などの分野では、Z世代の提案によって業務の質やスピードが向上するケースも出てきています。
一方で、全員がすべてにおいて得意というわけではありません。ときには使い慣れたツールでしか動けなかったり、アナログなやりとりに戸惑いを見せる場面もあるため、「強みを活かしつつ、ビジネスに必要な基本的スキルも補っていく」という育成バランスが求められます。
彼らのデジタルリテラシーを活かすには、既存のやり方に無理に合わせるのではなく、「新しい発想でどう改善できるか」を一緒に考える姿勢が効果的です。これが、Z世代の能力を最大限に引き出す関わり方だと私は感じています。
承認欲求と自己肯定感
SNS文化が育てた「認められたい」という意識
Z世代の新入社員と関わっていて感じるのは、「認められること」や「共感されること」への強いニーズです。これは決して「褒められたいだけ」ではなく、自分の存在意義や取り組みが誰かに伝わっているかを気にする傾向と言い換えることもできます。
この背景には、SNS文化の影響もあると考えられます。投稿に対する「いいね」やコメントなど、常に他者の反応がある環境に慣れているため、職場においてもフィードバックがないと「見られていない」と感じてしまうことがあるのです。
承認されないとモチベーションが低下しやすい
Z世代は自己表現を重視し、自分の意見や考えをきちんと伝えたいという意識が強い傾向にあります。一方で、自分の気持ちが理解されなかったり、努力が見過ごされたと感じると、急激にモチベーションが下がることもあります。
日常のフィードバックが自己肯定感を育てる
このような傾向に対して、私たちができることは、ポジティブなフィードバックを惜しまないことです。特別な場面でなくても、「ありがとう」「助かったよ」といった一言が、Z世代の自己肯定感を高め、前向きな行動につながる大きな原動力になります。
また、結果だけでなく、プロセスや取り組み姿勢を評価する視点も忘れてはいけません。小さな成功体験の積み重ねが、Z世代の安定した成長につながっていくのです。
Z世代の新入社員を育成する際のポイント
Z世代の新入社員を迎える中で、育成のあり方を見直す必要性を感じている企業は少なくありません。「新人が変わった」と感じたとき、私たちがまずすべきことは、何が変わり、なぜそうなったのかを理解することです。ただし、Z世代の特性を理解したからといって、何もかもを合わせる必要があるわけではありません。
重要なのは、社会人としての成長を促すという本質を見失わずに、価値観の違いに柔軟に向き合っていくことです。私自身、営業現場で新人を育てていたときも、人事として採用・研修に関わるようになってからも、「世代が変われば教え方・伝え方も変える必要がある」と実感する場面が増えてきました。
このパートでは、Z世代とより良い関係を築きながら、職場への定着と活躍を支援するための育成のポイントを、実践的な視点で4つご紹介していきます。
価値観を理解し尊重する
「何を大事にしているのか」を知る姿勢
Z世代を育てるうえで、まず大切なのは「彼らが何を大事にしているのか」を知ろうとする姿勢です。価値観とは、行動の基準や判断の軸になるものであり、表面に出にくいぶん、誤解されやすい領域でもあります。
Z世代は、「やらされ感のある仕事」や「説明のないルール」に違和感を覚える傾向が強いです。裏を返せば、自分の行動がどんな意味を持ち、どんな価値につながるかを理解できれば、前向きに取り組む意欲が生まれるということでもあります。
納得感を生む伝え方
たとえば、「報連相は社会人としての基本だよ」と伝えるだけでなく、「なぜ報連相が必要なのか」「誰のためにやるのか」といった背景や目的を合わせて伝えることで、Z世代も納得して行動できるようになります。
こうした価値観の違いに触れると、「甘い」「考えが浅い」と感じる場面も正直あります。しかし、頭ごなしに否定せず、一度彼らの視点を理解する努力をしてから伝えるべきことを伝える。この順番を間違えないことが、信頼関係の構築と早期の職場定着につながるのです。
承認の機会を意識的に作る
Z世代の承認欲求とその背景
Z世代の多くは、「自分の頑張りを見てほしい」「存在を認めてもらいたい」という承認欲求を、より強く持っている傾向があります。これはSNSの影響だけでなく、「個性を大切にする」教育を受けてきた背景や、成果主義の強い社会で育ってきたことが関係していると考えられます。
小さなフィードバックが大きな安心に
こうした背景から、小さな成功や努力が正しく認識され評価されるかどうかが、本人のやる気や今後の行動に直結しやすいのです。たとえば、「この業務は助かったよ」「その視点いいね」といった何気ない一言でも、「ちゃんと見てくれている」という安心感につながり、自信を持つきっかけになります。
また、人によっては、人前での表彰よりも、日常的なやりとりの中での認められた感を重視する傾向があるため、一人ひとりに合ったアプローチが求められます。
第三者の視点や場づくりの工夫も効果的
定期的なフィードバックだけでなく、チーム内での成果発表や、全社的な情報共有ツールでの取り上げなど、第三者の視点に触れる場をつくることも効果的です。
承認を通じて、「この職場に自分の居場所がある」と感じられるようになると、自発的な行動やチャレンジ精神が生まれやすくなります。このプロセスを丁寧に設計することが、育成の質を大きく左右します。
自己考察を促す機会を設ける
Z世代が「納得感」で動く理由
育成において忘れてはならないのが、「考える力」を育てることです。Z世代の新入社員は、受け身ではなく、「自分で納得し、意味を見出したときに行動が加速する」傾向があります。そのためには、自己考察の機会を意図的に設けることが非常に重要です。
気づきを引き出す問いかけの工夫と質問例
具体的には、定期的な1on1ミーティングや振り返り面談などの場を通じて、「最近の業務で得られた気づき」や「うまくいったこと・つまずいたこと」について問いかけてみましょう。こうした対話を通じて、本人が自分の変化や成長に気づくことができます。
- 成功体験から学びを深める
「今日の業務で一番うまくいったと感じたのはどこだった?」
「その成功に、自分のどんな工夫や姿勢が影響したと思う?」 - 失敗やモヤモヤを前向きに振り返る
「最近ちょっとつまずいたこと、何かあった?」
「そのとき、どう感じた?どうすれば次はもっと良くできそう?」 - 自分の変化を実感する
「入社した頃と比べて、できるようになったと感じることは?」
「最近、成長してるかもって感じた瞬間はあった?」 - 他者視点を取り入れる
「上司や先輩の行動で“真似したいな”と思ったことは?」
「もし後輩が同じ状況にいたら、どんなアドバイスをする?」
正解よりも思考のプロセスを大切に
また、自己考察を促すうえでは、正解を求めすぎないこともポイントです。「これはどういう意味だったと思う?」「次はどうしたらもっと良くなりそう?」といった問いかけを通じて、思考のプロセスを引き出すことに重きを置きましょう。
このような対話を重ねることで、新入社員は単に仕事をこなすだけでなく、「自分の成長に向き合う力」を身につけていくようになります。この習慣が根付くことで、将来的には自律的にキャリアを築いていける土台が育ちます。
【研修事例】自己理解研修の導入で“考える力”に火をつける
Z世代の新入社員は、自分自身の価値観や働く意味をしっかり理解したうえで行動したいと考える傾向があります。だからこそ、入社直後のタイミングで自己を知る機会を設けることが、その後の育成をスムーズにする重要なきっかけになると私は感じています。
たとえば、ある企業では新入社員向けに「自己理解研修」を実施しています。この研修では、性格診断レポートや価値観カードを用いて、自分の思考傾向や行動特性、仕事で活かせる強みや、気をつけたい弱みに気づくことを目的としています。

「自分が弱みだと思っていたことが、実は強みにもなり得ると知って前向きになれた」
「得意・不得意を客観的に理解できたことで、今後の業務にどう活かせるかが見えてきた」
「今まで考えていなかった自分の価値観に気づき、自分自身に少し興味が持てるようになった」
Z世代にとって、なんとなく働くことはモチベーションにつながりません。だからこそ、まずは「自分がどういう人間で、何に価値を感じるのか」を言語化できるようにすることが、その後の育成やフィードバックの質を大きく左右します。
このような「内省型の研修」は、一人ひとりが自分と向き合い、他者との違いを前向きに受け止めるきっかけにもなります。結果として、職場でのコミュニケーションや主体的な学びを促進するベースになるのです。
新入社員研修での工夫
実践的で納得感のある研修にする
Z世代の特性に合った研修設計は、入社後の成長スピードや定着率に直結します。特に重要なのが、「実践的で、納得感のある内容」になっているかどうかです。
従来型の講義中心の座学だけでは、Z世代にとっては抽象的すぎて、「これが現場でどう役立つのか」が見えづらくなります。そのため、実務シーンに近いロールプレイや、現場社員との対話型セッションなど、実践的なスタイルを取り入れることが効果的です。
未来をイメージできる内容にする
成功事例や先輩社員の体験談を織り交ぜることで、「こういう風に成長できるんだ」と自分の未来像を具体的に描けるようになります。
また、学んだ内容をすぐに使ってみる→フィードバックをもらう→振り返るという学習サイクルを早期から回すことで、実践と内省がセットになった深い学びにつながります。
社会人としての第一歩を支える場として設計する
新入社員研修は、単なるスタート地点ではありません。「その会社でどう成長していけるか」「どんな価値を創っていけるのか」を伝える場として設計することが、Z世代の納得感とエンゲージメントを高めるカギになります。研修と現場配属のつながりを意識し、学びの補助線となる導線を整えておくことが重要です。
Z世代とのコミュニケーションのポイント
Z世代の新入社員と良好な関係を築くためには、コミュニケーションの「質」と「設計」がこれまで以上に重要になっています。単に話す機会を増やすだけでは不十分で、どんな姿勢で、どのような方法で伝え合うのかによって、関係の深まり方は大きく変わってきます。
Z世代は、自分の考えや感情を言葉にすることに抵抗が少なく、それを受け止めてもらえる環境を求める傾向があります。とはいえ、それは「好き勝手に言いたい放題でいたい」ということではなく、自分の存在や意見が職場の中でちゃんと意味を持っているかどうかを重視しているということです。
また、彼らは対話を一方通行ではなく、双方向のキャッチボールとして捉えているため、「上司が指示する・部下が従う」だけの関係では信頼関係を築くことが難しくなってきています。
このパートでは、Z世代とのコミュニケーションをより円滑に、そして前向きな関係性に発展させるために、特に意識したい3つのポイントを紹介します。現場でもすぐに活用できるよう、実践的な視点で整理しています。
フィードバックを定期的に行う
Z世代の育成で欠かせないのが、定期的かつ具体的なフィードバックです。この世代は、「今の自分が何を期待されていて、どこまでできているのか」を常に把握したいという志向が強く、曖昧な評価や感覚的な指導には不安を感じがちです。
そのため、1on1ミーティングや業務レビューなどの形で、フィードバックを定期的な習慣として組み込むことが重要です。ただしこれは、単に評価を伝えるということではありません。Z世代が求めているのは、「あなたのこういう行動が、こういう影響を与えた」というような、自分の行動と結果の因果関係が見えるようなフィードバックなのです。

「先日の企画書、相手の課題にしっかり寄り添った構成になっていて、プレゼンもスムーズだったね。特に●●の提案はお客様にも好評だったよ。」
さらに、結果だけでなく、過程や姿勢も丁寧に拾い上げることが求められます。たとえば、「準備が丁寧だったから当日の進行がスムーズだったよ」といった言葉は、Z世代にとって非常に響きます。努力のプロセスが見られているという実感が、次の行動への意欲につながるからです。

・「こまめに進捗を報告してくれたおかげで、全体の調整がすごく助かったよ。そういう姿勢はチームにとっても大事だね。」
・「資料の構成、最初より見やすくなってたね。自分なりに工夫してるのが伝わってきたよ。」
また、評価基準や期待値が明確であることも安心材料になります。「これができれば合格」「この水準まで成長すれば次のステージへ進める」という明確なマイルストーンを共有することで、成長の方向性がぶれにくくなります。

・「今回の説明は少し長くなってしまったけど、要点を絞ればもっと伝わりやすくなるよ。次は“結論→理由”の順で話すと、さらに良くなると思う!」
・「今の段階で、タスク管理や報連相は問題なくできてるから、次の1か月では“提案”の部分を少しずつ任せていきたいと思ってるよ。」
このように、定期的なフィードバックは、単なる評価ではなく、成長の手ごたえを与える“対話”として設計することが大切なのです。
非対面シーンでの接触を考慮する
Z世代は、生まれたときからインターネットやスマートフォンが存在する世界で育った真のデジタルネイティブです。対面のコミュニケーションももちろん大切ですが、非対面での接点も同じくらい、いや場合によってはそれ以上に重視しているという点は見落とせません。
たとえば、SlackやTeamsといったビジネスチャット、社内SNS、オンライン会議ツールなどを活用することで、物理的な距離を超えてつながっている感覚を持たせることができます。特に入社初期など、緊張が強いタイミングでは、こうした非対面でのやり取りが心理的な負担を軽くするケースも多いです。
非対面の接点があることで、「聞きたいけど今は忙しそう」「面と向かってはちょっと言いにくい」といったハードルを下げることができます。また、リアルタイムでなくてもやりとりが残るため、情報の共有や振り返りがしやすいというメリットもあります。
一方で、非対面コミュニケーションには表情やニュアンスが伝わりづらいという弱点もあります。そのため、定期的に対面の場を設けることも欠かせません。大切なのは、「どちらか」ではなく「どちらも活かす」設計を意識することです。
Z世代は、コミュニケーション手段に柔軟である一方、一貫性のある対応や丁寧なやり取りにはとても敏感です。「チャットだから適当でいい」ではなく、非対面だからこそ丁寧さを心がけることで、より深い信頼関係が築かれていくのです。
Z世代新入社員の特性を活かす方法
Z世代の新入社員と関わる中で、彼らが持つ可能性や強みをどう活かしていけるかを考えることは、今後の組織づくりにおいて非常に重要なテーマです。指示待ちではなく、「自分で考えて動きたい」「意味のある仕事をしたい」という志向を持っている彼らは、うまく関われば驚くほどの成長スピードを見せてくれる世代でもあります。
その反面、方向性や期待が曖昧なまま放任してしまうと、不安や孤立感を抱えやすくなるリスクもあります。だからこそ、適度な自由と明確な指針を両立させることが、Z世代のポテンシャルを引き出すカギだと私は考えています。
このパートでは、Z世代の特性を活かすための具体的な方法として、「自律的な成長を促す仕組み」と、「共感と理解を深めるワークショップ」の2つを取り上げてご紹介します。
自律的な成長を促す機会の提供
Z世代は、自分のペースで学びたい、自分のやり方で成長したいという“自律志向”が強い世代です。とはいえ、「自由にやっていいよ」と放り出すだけでは、迷いや不安が先行し、逆に動けなくなってしまうケースも少なくありません。重要なのは、自由に考え行動できる「余白」を与えながらも、何を期待されているか、どこに向かえばいいのかという「道筋」を明確にすることです。
たとえば、あるプロジェクトで「どんな成果を出してほしいか」「どんな判断基準を大切にしているか」といったことを具体的に共有したうえで、進め方や手段は本人に委ねるようなスタイルが効果的です。これにより、「任されている」という実感と、「何をすべきかが分かっている」という安心感を両立できます。
また、社内で自由に学べる研修コンテンツやオンデマンド学習の提供も、Z世代の学びたい意欲に応える手段になります。自分の関心に応じて選べる学習機会は、モチベーションにも直結します。
加えて、組織として支援体制を構築することも欠かせません。たとえば、ロールモデルとなる先輩社員によるメンタリングや、業務内での“チャレンジの場”の設計などが、自律的な行動を後押しします。
Z世代は、変化に柔軟で創造的な発想を持つ人が多いです。彼らの力を引き出すには、「何をすべきか」ではなく「どう育てたいか」を見据えた育成の視点が必要なのです。
実際にどんなやり方があるのか?
例① 新人がチームのPR企画を担当する場合
「2週間後にSNSで配信する企画案を提案する、というゴールだけ決めておき、リサーチ方法や資料のまとめ方は本人に任せる」
➤ 成果のイメージは共有しつつ、アプローチは自由に選べることで、自主性と責任感を育てられる。
例② 社内にオンデマンド研修ポータルを用意
「ビジネスマナー」「Excel基礎」「デザイン思考」「ロジカルシンキング」など、興味や業務に合わせて自分で選んで受講できる」
➤ 自分の関心に合わせて学べることで、モチベーションアップ&成長実感も得やすくなる。
例➂ OJTの一環として“リーダー役”に抜擢
「小さな社内ミーティングの進行役を任せる」「イベントの一部運営を担当させる」など
➤ 責任あるポジションを任せることで、“信頼されている感覚”が自律性を引き出すきっかけになる。
共感と理解を深めるワークショップ
Z世代は、相手の考えや価値観に共感しながら関係を築くことに重きを置く傾向があります。だからこそ、相互理解を深める場としてワークショップ形式の取り組みはとても有効です。
ワークショップでは、正解を求める場ではなく、自由に意見を出し合い、感じたことを共有する空間を設けることがポイントです。たとえば、「入社して感じたギャップ」や「理想の働き方」などをテーマにすると、共通の体験をもとに共感しやすくなり、安心して発言できる雰囲気が生まれます。
また、複数の視点を尊重することも大切です。Z世代は「多様性を前提とした価値観」を持っている人が多く、一つの正解に縛られない対話に安心感を持つ傾向があります。「違いがあることは前提で、そのうえでどう一緒に働くかを考える」こうしたスタンスを共有するだけでも、組織の一体感は大きく変わってきます。
私の経験でも、あるチームで「互いの強み・弱みを言語化して伝える」というワークを行った結果、普段の会話では出てこない本音や気づきが生まれ、チーム内の信頼関係が格段に深まったことがあります。こうした対話の場が、新人の心理的安全性の確保にもつながるのです。
ワークショップの内容は、難しいものである必要はありません。むしろ、身近で共感しやすいテーマを選ぶことで、自分ごととして捉えられる機会が増えます。Z世代の特性を活かした関係づくりには、こうした仕掛けが非常に有効です。
Z世代と共に成長する企業のあり方とは
ここまで見てきたように、Z世代の新入社員はこれまでの世代とは異なる価値観や背景を持ち、それが職場での行動や期待にも大きく影響しています。彼らの特性を「理解する」だけではなく、「どう活かすか」「どう成長につなげるか」を具体的に考えることが、これからの人材育成において欠かせません。
私たち企業側が、Z世代の新入社員を一方的に適応させるのではなく、お互いの価値観をすり合わせ、共に前に進むための土台をつくること。それこそが、これからの時代に求められる組織の姿勢だと感じています。
このパートでは、Z世代の理解がもたらす企業の未来像と、より良い職場環境づくり、そして持続的な成長を実現するためのアプローチについて整理していきます。
Z世代の理解がもたらす企業の未来
Z世代の新入社員をただの“新人”として捉えるのではなく、企業の未来を担う存在として理解しようとする姿勢が、これからの人材戦略において不可欠になっています。特に、2024年以降の新卒採用においては、「Z世代だからこそ持つ感性」や「育ってきた環境」への深い理解が企業の差別化につながっていくでしょう。
Z世代は、「意味のある仕事がしたい」「個人の成長と会社の成長がつながってほしい」という思いを持っており、その価値観を尊重しながら活かすことができれば、新たなイノベーションや風通しのよい組織文化の実現も十分に可能です。
また、コロナ禍を経た今、社会の価値観も大きく変わりました。柔軟な働き方、多様な選択肢、心理的安全性のある職場が求められている中で、Z世代の声に耳を傾けることは、単なる若手育成ではなく、企業全体の進化に直結する取り組みと言えるでしょう。
これからの採用や人材育成は、単なる“戦力補充”ではなく、共に未来を創っていくパートナーとして、どのように関わっていくかが問われる時代です。Z世代への理解は、その出発点であり、企業の持続的な成長の鍵になると私は考えています。
職場環境改善の必要性
Z世代の新入社員が能力を発揮し、長く活躍するためには、安心して働ける職場環境の整備が欠かせません。その中でも、特に注目すべきは「柔軟性」「人間関係」「業務効率」の3つの要素です。
柔軟な働き方で満足度を高める
柔軟な働き方は、Z世代の価値観に強くフィットする要素です。リモートワークや時差出勤、副業の容認など、「自分らしい働き方」ができる環境があればあるほど、Z世代の満足度や定着率は高まりやすくなります。
フラットな関係性とコミュニケーションの設計
縦の関係にこだわらず、意見が言いやすい風土をつくることが、Z世代のモチベーション向上に直結します。たとえば、朝礼での一言共有やランチ会など、日常的なコミュニケーションの設計が鍵になります。
業務効率の改善で働きやすさを実感させる
無駄な業務や曖昧な指示が多いと、「意味が見えない」「生産性が低い」と感じてしまいます。ツールの見直しや業務フローの最適化を進めることで、Z世代だけでなく全社員にとって働きやすい環境が整います。
持続可能な成長のためのアプローチ
Z世代の特性を活かしながら企業として成長していくためには、時代に合った「成長戦略」が求められます。単なるスキルアップ支援だけではなく、共感・つながり・意味のある成長体験をどう設計するかがポイントになります。
Z世代の共感を得る成長戦略
SNSを活用した情報発信は、企業ブランドの形成だけでなく、Z世代の共感を得る手段として非常に効果的です。社内イベントの様子、社員の声、働き方の工夫などを外部に伝えることで、採用力の向上にもつながります。
また、キャリア開発の観点では、明確なアクションプランの提示が重要です。「このスキルを身につければ次のステージに進める」といった具体的な成長ルートを可視化することで、Z世代の目標意識とモチベーションを高めることができます。
失敗を許容する成長環境づくり
挑戦して失敗しても許される風土を整えることは、持続可能な人材育成の要です。定期的なフィードバックとあわせて、自分の成長を振り返る場を用意することで、Z世代のキャリア形成を長期的に支援できます。
このようなアプローチを取り入れることで、Z世代の新入社員がただ“育つ”だけでなく、企業の変革や推進力としての役割を果たしていく未来を実現できるのです。
まとめ
Z世代の新入社員は、デジタルに強く、柔軟な発想力と自己表現力を持つ一方で、プレッシャーへの感受性や対面でのコミュニケーションに不安を感じやすいなど、これまでの世代とは違った傾向があります。こうした特徴は、育成やマネジメントの面で課題とされがちですが、裏を返せば組織のあり方そのものを見直すきっかけにもなり得る重要なシグナルでもあります。Z世代に合わせるだけでなく、私たち自身の関わり方や伝え方をアップデートしていくことが、これからの企業成長に不可欠なのです。
彼らを受け入れ、育てるということは、単に人材を“戦力化”することではなく、未来に向けての新しい組織文化を育むことでもあります。一人ひとりの声に耳を傾け、共に考え、共に成長していく。そうした姿勢こそが、次の時代の人材育成の土台になっていくはずです。
Z世代を知ることは、企業の未来を考えること。変化を前向きに受け止め、共に新しい時代を切り拓いていきましょう。
若手も管理職も、成長を実感できる研修を


「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」
「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」
「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」
若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。
アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。
アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴
- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供
- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走
- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決
- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供
研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ
中井 美沙
株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。