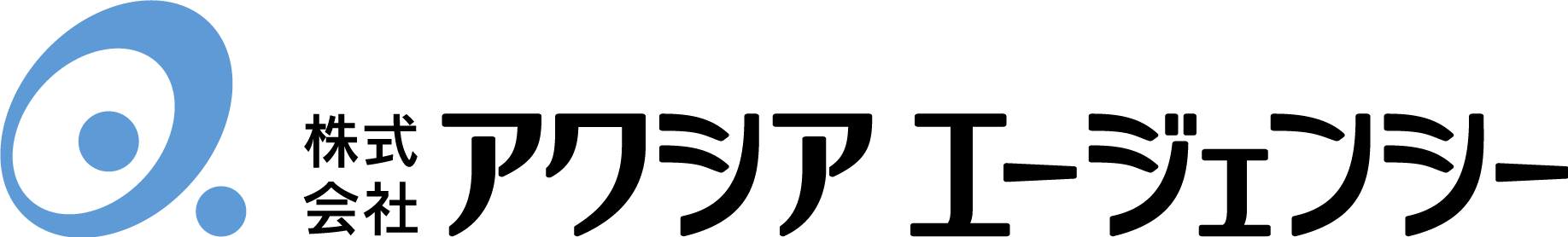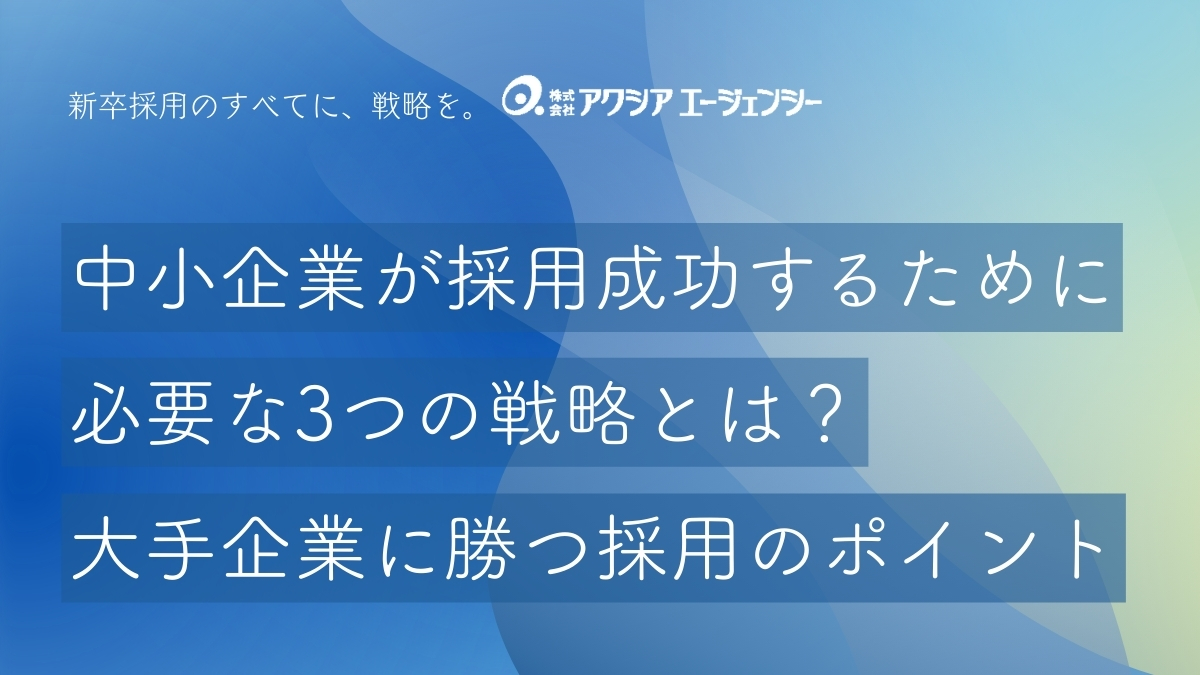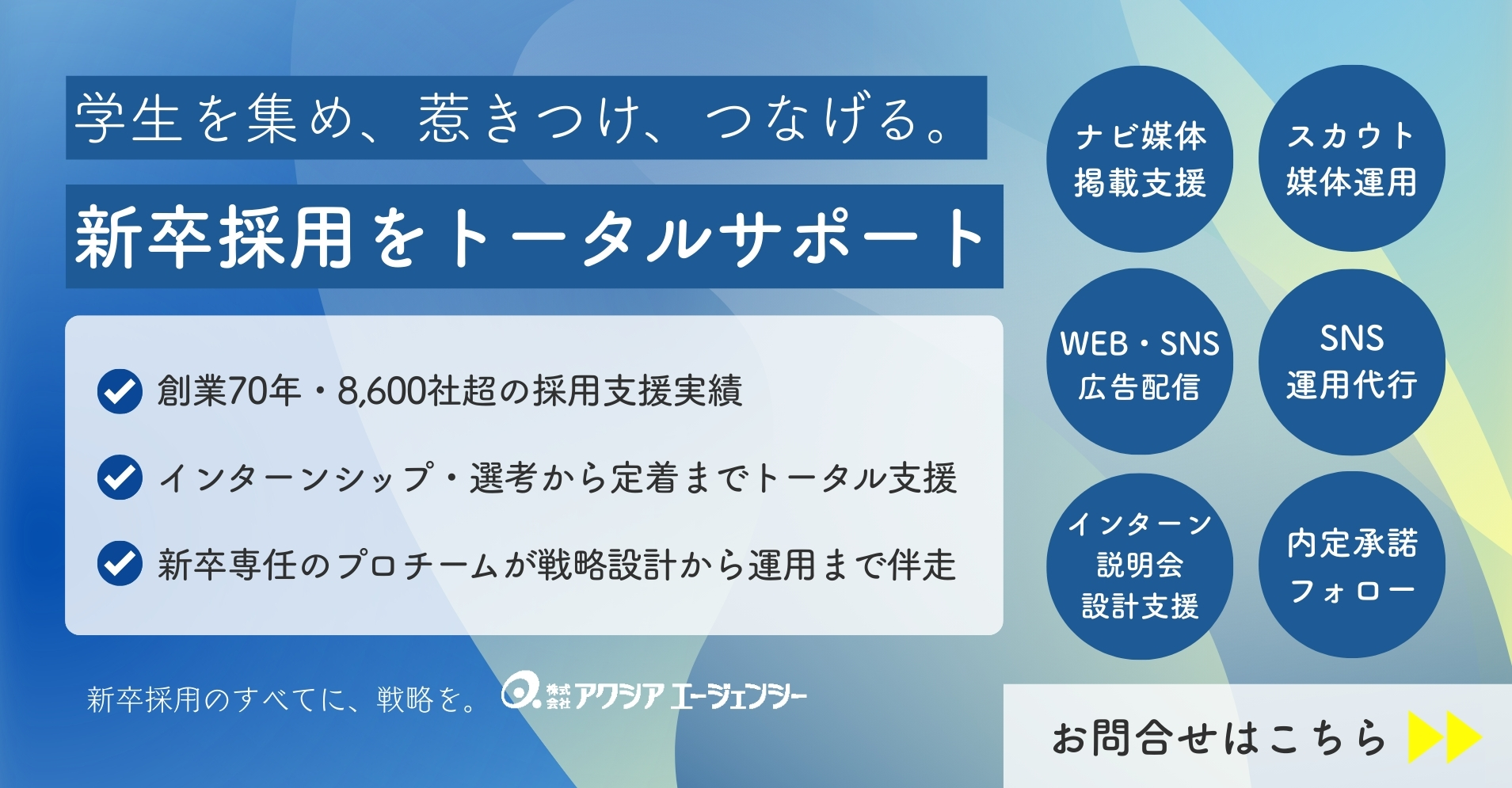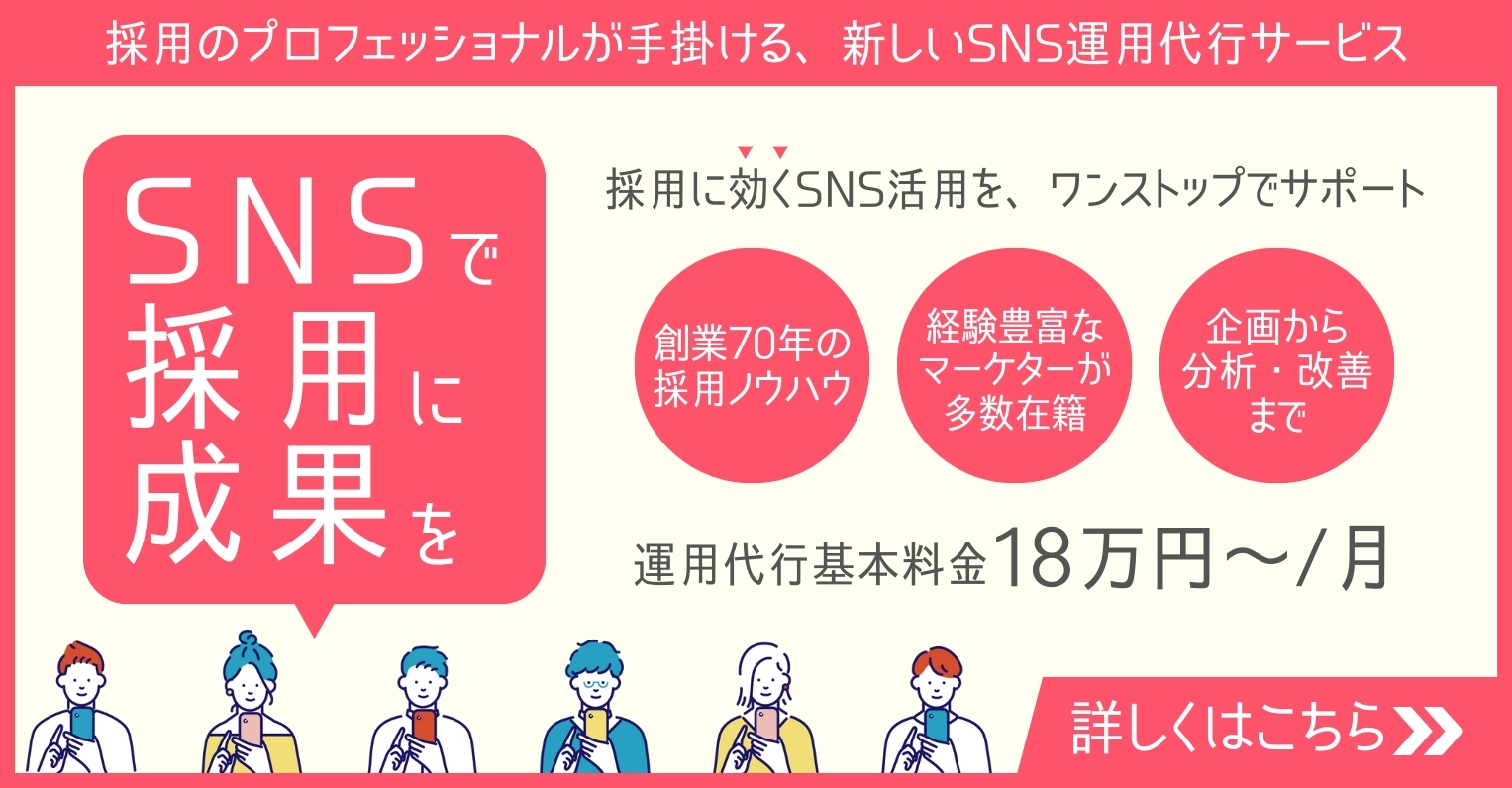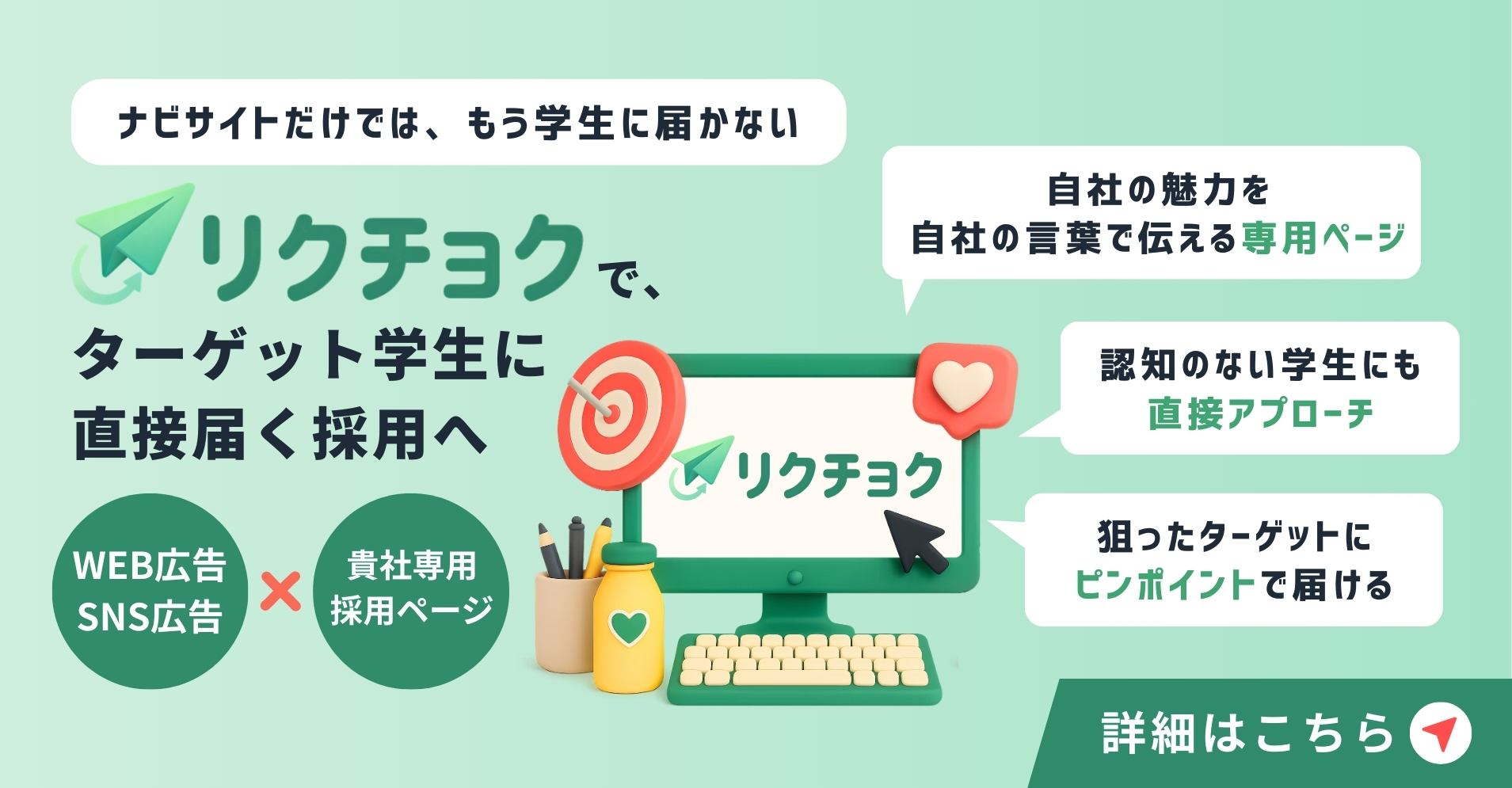中小企業における新卒採用の難易度は、年々高まっています。「母集団が集まらない」「辞退が多い」「自社の魅力が伝わらない」といった声は、あらゆる業種・地域の企業で共通しています。
一方で、大手企業はインターンやスカウトサービスを活用し、学生との早期接点を築くとともに、採用ブランディングや選考設計にも多くのリソースを投下しています。中小企業にとっては、リソース面でのハンデを感じやすい構造です。
しかし、中小企業だから採用できない、というわけではありません。限られた環境の中でも、戦略的に採用活動を設計し、成果を上げている企業は確実に存在します。本記事では、そうした企業に共通する「3つの戦略」をもとに、中小企業が新卒採用で成果を上げるための具体的なポイントを解説します。


なぜ中小企業の新卒採用は難しいのか?
現在、多くの中小企業が新卒採用活動において深刻な課題を抱えています。ナビサイトへの掲載や説明会開催といった従来の手法だけでは母集団形成が進まない、ようやく選考に進んだ学生が途中で辞退してしまう、企業の魅力が正しく伝わらない──こうした課題が日常的に発生しています。
その背景には、学生側の動きの変化だけでなく、求人倍率の構造的な差、そして中小企業特有のリソース不足などが複雑に絡んでいます。ここでは、中小企業の新卒採用がなぜ難しいのかを、具体的なデータとともに3つの観点から整理していきます。
応募が集まらない母集団形成の壁と求人倍率の現実
中小企業にとって最大の採用課題の一つは、そもそも応募者が集まらないという問題です。これは「求人倍率」に表れています。2025年卒対象の調査によると、従業員300名未満の中小企業の求人倍率は約6.5倍、つまり1人の学生を6.5社で取り合っている状態です。過去には9.9倍(2019年)に達したこともあり、この傾向は年々深刻さを増しています。
一方、大手企業(従業員5,000名以上)の求人倍率はわずか0.34倍です。これは、3人の学生が1社の内定を争っている構図。つまり、大手企業は「選ばれる側」であり、中小企業は「選ぶ側」になる前にまず“選ばれること”に苦労しているのです。
就活チャネルの多様化とナビ依存のリスク
加えて、学生の就職活動に対する価値観や行動も大きく変化しています。最近では、たくさんの企業に応募するより、厳選した数社に集中する学生が増加しており、全体の応募社数は減少傾向にあります。また、ナビサイトだけでなく、スカウトサービスやSNSなどを通じて企業を探す動きも活発になってきました。
こうした中、ナビサイトへの掲載のみに依存した採用活動では、学生に見つけてもらうこと自体が難しくなりがちです。「待つ採用」から抜け出せていない中小企業にとっては、さらに不利な状況に置かれていると言えるでしょう。
このように、構造的に不利な市場で、しかも学生の行動が分散化している状況の中で、ただ待つだけの採用活動では成果を得ることは極めて困難です。企業側から積極的にアプローチを仕掛け、接点を設計していく必要があります。
内定を出しても辞退される現実とその心理的要因
母集団ができたとしても、内定辞退のリスクが次の壁になります。特に大手企業との併願がある場合、中小企業は辞退されやすい傾向があります。ある人事担当者はこう語ります。「せっかくインターンから丁寧に関係を築いた学生に、最終的に「やっぱり大手企業の方が安心感があるので」と言われて辞退された。」このような例は少なくありません。
内定辞退の要因は複合的
- 企業の将来性や安定性が見えにくい
- 配属やキャリアの展望が不透明
- 働いている社員のリアルな声がわからない
- 知名度のある企業に決まった方が周囲に言いやすい、という心理的な壁
上記のように、待遇やネームバリューだけでなく情報の不十分さと、比較対象として負ける不安感が根本にあります。
これを解決するには、選考途中から継続的なコミュニケーション設計が必要です。たとえば、選考中に個別フィードバックを渡す、先輩社員との面談を入れる、会社の裏側や社風を伝えるSNSコンテンツを配信するなど、自社を選びやすくするための支援が重要になります。
中小企業にとって採用活動は点ではなく、線で設計することが内定承諾につながるカギになります。
伝わらない魅力と採用ブランディングの課題
中小企業には、中小企業ならではの魅力があります。たとえば、裁量権の大きさ、意思決定のスピード、現場に近い経営、幅広い業務経験、若手のうちから活躍できる環境──いずれも学生にとって魅力的な要素です。
しかし問題は、それが十分に言語化されていない、あるいは伝える工夫がなされていないことにあります。
よくあるのが、パンフレットやナビサイトがテンプレート的で、「どの企業も同じような説明」に見えてしまうケースです。これでは、学生に選ばれる要素にはなりません。
そこで求められるのが採用ブランディングの強化です。ブランディングとは、単なるロゴやコピーライティングではありません。「この企業は自分に合いそう」と学生が感じるすべての接点づくりがブランディングです。
- 社員の顔が見えるSNS発信
- 社長や現場社員による動画メッセージ
- 働く価値を言語化したミッション・ビジョン・バリューの発信
- オフィスツアーや現場密着レポートの配信
これらを採用活動の中に組み込み、見えない価値を見える化することが、中小企業が勝つための本質的なブランディングになります。
中小企業の新卒採用が難しいのは、人が集まらないからだけではありません。そこには、求人倍率の現実、応募者数の減少、学生の行動の変化、そして伝え方の不足といった構造的かつ複合的な課題があります。
ただし、これらの課題は変えられない宿命ではありません。むしろ、採用活動の設計を見直すことで突破できる領域です。学生がなぜ中小企業を選ばないのか、その本質に目を向けることで、自社の伝え方や出会い方は大きく変わっていきます。
次のセクションでは、学生の本音や価値観を深掘りし、中小企業が逆転するために知っておくべき視点を一緒に考えていきます。
学生はなぜ大手企業を選ぶのか?中小企業が逆転するために知るべき価値観
多くの学生が新卒採用で大手企業を志望する背景には、単なる給与や知名度だけでない、深層心理に根ざした価値観があります。この価値観の変化を正しく理解しなければ、中小企業は戦えない土俵で戦ってしまうことになります。
ここでは、学生が企業を選ぶときに重視している要素をひもときながら、逆転のヒントを探ります。
学生が企業に求める安心感・成長・ブランド力の正体
近年の学生が企業に対して抱く希望は、画一的ではありませんが、共通する傾向があります。代表的なのが以下の3点です。
- 安心して長く働ける環境があるか
- 自分が成長できる仕事・上司・制度があるか
- 家族や友人に自信を持って伝えられる会社か(ブランド力)
このうち、「安心感」と「成長環境」は学生自身の将来を考えたときの不安に起因しています。初めての社会人生活に対し、安定した環境でスキルを身につけられる場所を求めるのは自然な感情です。
また、ネームバリューや認知度といったブランド力も、判断材料のひとつです。学生自身だけでなく、親や周囲の目を気にする文化もいまだ根強く、特に地方出身の学生ほど「知っている会社」であることが安心材料になります。
中小企業が見落としがちな「共感」の重要性
中小企業が採用広報や選考の中で見落としがちなのが、学生が感情移入できる要素=共感設計です。理念やミッション、社長の想い、社員インタビュー、働く現場の様子などを伝える際、事実や制度だけで終わってしまっているケースが多く見られます。
しかしZ世代・α世代の学生は、「なぜその仕事をしているのか」「どんな価値観を持っているのか」といった人としての共感ポイントを大切にします。これが伝わらないと、「なんとなく距離を感じる」「自分ごと化できない」として志望度が上がりません。
選ばれる企業になるためには、情報の中身よりも、伝え方の解像度が重要です。制度紹介よりも「それを使ってどう成長したか」、社風よりも「どんな人たちがどんな空気感で働いているのか」を描く必要があります。
Z世代が注目するリアルさと信頼できる情報源
企業が発信する情報に対して、Z世代の学生は非常に敏感です。表面的な言葉や、作り込まれたパンフレットよりも、リアルな声や日常の雰囲気を知りたいというニーズが強まっています。
- 社員の日常を映したInstagram投稿
- 若手社員によるYouTube社内ツアー
- noteや採用ブログでの赤裸々な体験談
- 就活会議やONE CAREERでの口コミ
こういった自分と同じ目線の人からのリアルな情報こそ、学生の判断軸になっています。言い換えれば、中小企業も工夫次第で信頼される発信元になることが可能なのです。つまり、知られていないから選ばれないという状態は、情報戦略の差であって、魅力の有無ではありません。
学生が大手企業を選ぶ理由には、給与や規模だけでなく、安心感・成長感・共感性・情報の透明性といった価値観の影響があります。逆に言えば、中小企業がこれらの価値にどうアプローチするか次第で、逆転のチャンスは十分にあります。中小企業にしか語れないリアルな物語、価値観、距離の近さこそが武器です。
次のセクションでは、それをどのように形にして発信していくか、採用ブランディング戦略の具体策を解説していきます。
戦略① 採用ブランディングを強化する
求人倍率や知名度の差という構造的ハンデを背負う中小企業が、採用市場で成果を出すには、「自社をどう伝えるか=採用ブランディング」の強化が欠かせません。採用ブランディングとは、単なる企業PRやおしゃれなロゴではなく、「この会社で働いてみたい」と学生に思わせるための共感づくりと信頼構築の仕組みです。
ここでは、採用ブランディングの基本的な考え方から、具体的な実践例まで紹介していきます。
学生に「選ばれる会社」になるために必要な視点
採用ブランディングの第一歩は、自社の良さをアピールすることではありません。大切なのは、学生が企業に求めていることと自社の強みをどうつなげるかという視点です。
たとえば、成長できる環境が学生の関心であれば、自社でどんなスキルや経験が得られるのかを具体的に伝える必要があります。また、安心感を求める学生に対しては、働く人のリアルな声やサポート体制を丁寧に紹介することが効果的です。
つまり、ブランディングとは企業目線の魅力を押し出すことではなく、学生目線で響く魅力に翻訳して届けることが本質なのです。
SNS・動画・口コミを活かした情報発信の工夫
いまの学生は、リクナビやマイナビなどのナビサイトや会社案内だけでは企業を判断しません。SNS・YouTube・就活系口コミサイトなど、さまざまな非公式チャネルを通じて企業をリサーチしています。だからこそ、中小企業も公式メディア以外での露出を意識した情報発信が必要です。
- Instagramでの社員紹介や社内風景の投稿
- TikTokでの短尺オフィスツアー・働き方紹介
- YouTubeでの社員対談や1日の仕事密着
- noteでのリアルな入社ストーリー
こうした発信が学生の共感や信頼感を生み出し、「この会社、なんかいいかも」と感じさせるきっかけになります。特にスマホで完結する情報取得が主流の今、動画やSNSは重要なタッチポイントです。
社員を巻き込んだストーリー設計と社内広報
採用ブランディングで最も熱量が伝わるのが、実際に働く社員のストーリーです。どんな思いで入社し、どんなやりがいを感じ、どんな未来を描いているのか──このようなリアルな声こそが、ブランド価値そのものです。
そのためには、採用担当だけでなく、現場社員を巻き込んだコンテンツ作成やイベント設計が不可欠です。
現場社員を巻き込んだコンテンツ例
- 若手社員による「就活中の自分に向けたメッセージ動画」
- チームの1日に密着したレポート
- 社員が語る「自社のちょっと変わったところ」座談会
これらは、単なる情報ではなく、企業文化や価値観がにじみ出る最高のブランディングツールです。加えて、社内向けの広報(社内報・掲示・Slackチャンネルなど)も充実させることで、採用活動への共感と協力が広がり、全社的に採用を支える空気が生まれるのです。
中小企業の採用活動において、ブランディング=高コストなマーケティング施策というイメージは誤解です。本質は「誰に、どんなメッセージを、どう伝えるか」という設計と工夫です。採用ブランディングを強化すれば、知名度や規模では劣っても、「共感で選ばれる企業」になることは十分に可能です。
次は、実際にどんなチャネルや手法を選んで採用活動を行うべきか─に進んでいきます。
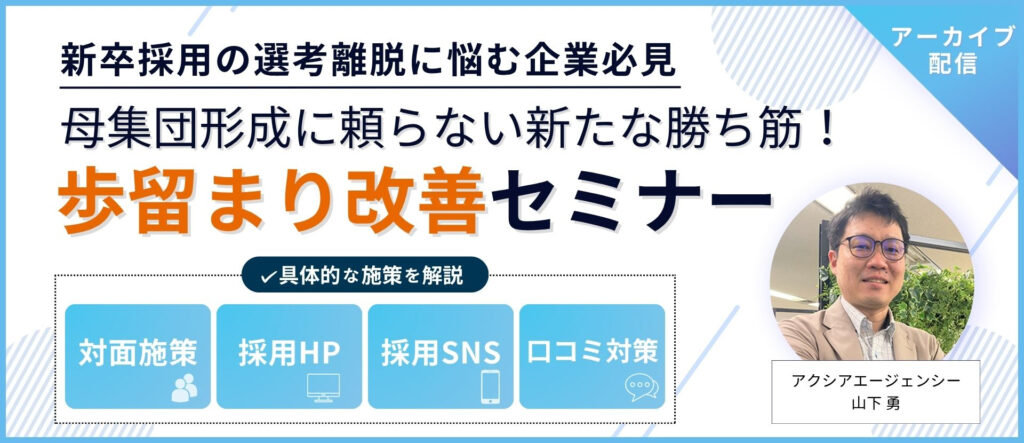
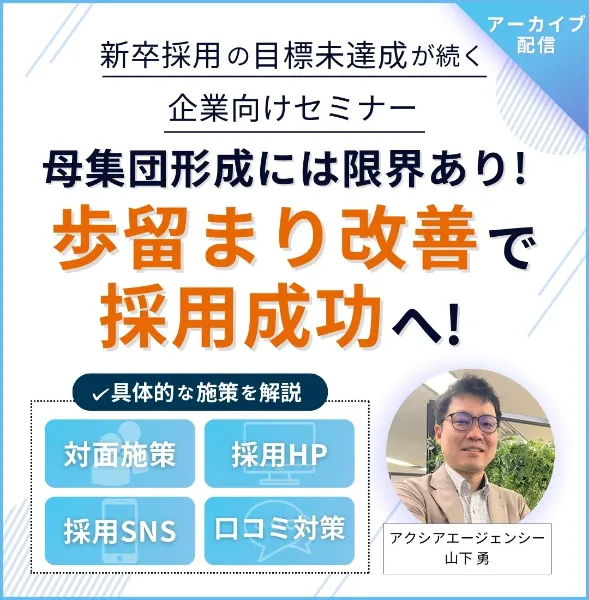
戦略② ターゲットに合った採用手法を選ぶ
多くの中小企業が新卒採用でつまずく理由のひとつが、ナビサイトだけに頼った採用活動から抜け出せていないことです。近年の学生は、ナビサイトに加えてスカウトサービス、SNS、リファラル、大学経由、イベント型採用など、多様なルートで情報を得ています。
だからこそ、自社の採用ターゲット(人物像)に合わせて、最適な採用手法を組み合わせていくことが、母集団形成のカギになります。
ナビに頼らない母集団形成の選択肢
ナビサイトは全国に広く情報を届けられる反面、「多くの企業の中に埋もれやすい」「説明会予約までつながりにくい」といった課題もあります。そこで中小企業にこそ活用してほしいのが、絞り込んだ接点設計ができる採用手法です。
- 逆求人・スカウト型サービス(OfferBox・キミスカなど)
→ 興味を持ってくれた学生とだけ接点が持てるため、効率的で歩留まりが良い - 合同説明会や中小企業限定フェア
→ 知名度に関係なく、直接出会って印象を残せる場 - 地域・業界特化型の採用支援サービス
→ 地域密着の志望層とマッチしやすい - 大学キャリアセンターや教授推薦
→ 高い信頼性と、マッチ度の高い人材との出会いが期待できる - Web広告・SNS広告(Google・Instagram・YouTubeなど)
→ 興味関心・エリア・属性などで学生をピンポイントにターゲティング可能。 少額からでも運用でき、ナビ非登録層へのリーチが広がる
こうした手法をうまく活用することで、ナビだけでは出会えなかった層との接点が広がり、自社と相性の良い学生に発見される確率が高まります。
スカウト・自社メディア・紹介活用のポイント
採用チャネルを広げるうえで効果的なのが、情報を届ける型から、自社に惹きつける型への転換です。それを支える手法が以下のようなものです。
- ダイレクトリクルーティング(スカウト送信)
→ テンプレではなく、学生のプロフィールに合わせたメッセージが鍵。 「見てくれてる感」「自分を理解してくれてる感」が返信率に直結 - 自社採用サイトやnoteなどのオウンドメディア
→ 自社の理念・文化・働く環境などを、自由に深く伝えられる。SEOやSNSとの連携で待ちの広報が可能になる - 内定者や若手社員によるリファラル紹介
→ 「友人に勧めたいと思える会社か?」という視点での改善にもつながる
これらは単独ではなく、組み合わせることで効果を発揮します。ターゲットの行動特性に合わせて情報を届ける設計力が成果を左右します。
選考の早期化・柔軟化でエントリー率を高める
母集団形成だけでなく、その後の選考フローも採用成功には不可欠です。特に、学生の行動が早期化している今、選考開始のタイミングや柔軟なフロー設計が差を生みます。
中小企業が導入すべき工夫
- インターン参加者への早期個別面談の設定
- 選考ステップを圧縮し、早めの内定出しを実現
- 面談や説明会のオンライン対応で時間的ハードルを下げる
- オープンチャットやSlackでの気軽な接点維持
これらにより、学生が比較検討しやすくなるだけでなく、心理的距離も近づきやすくなるのです。
大手企業が3月解禁を意識する一方で、中小企業は出会った瞬間から関係構築を始められるのが最大の武器。そのための選考設計と接点づくりが、結果的にエントリー率・承諾率の向上へとつながります。
今や採用活動は、ナビサイト中心の一斉型から、ターゲットに合わせた個別最適型へと進化しています。中小企業にとっては、むしろ大手企業と同じ土俵で戦わずに、独自のルートで自社に合う人材と出会える手法を選ぶことが勝機なのです。
次のセクションでは、その中でも特に重要な初期接点であるインターンについて、中小企業がどのように設計すれば魅力が伝わり、辞退を防げるか─を解説していきます。


戦略➂ インターンを企業の魅力体験の場に変える
近年、新卒採用の現場では、インターンシップが採用活動の中心的な役割を果たすようになってきました。従来のような、インターン=お試し就業体験ではなく、企業の採用戦略や母集団形成における初期接点の重要な手段として位置づけられています。
中小企業にとっても、この変化は大きなチャンスです。採用ブランディングや選考体験の価値を学生に伝えるうえで、インターンはもっとも密度の濃い接点であり、活用次第で辞退の防止、志望度の向上、そして優秀層とのマッチング率の向上が見込めます。
このセクションでは、新卒採用で成果を出すために中小企業が押さえておきたいインターン設計のノウハウや、おすすめのアプローチについて具体的に解説します。
なぜ今、インターンシップが新卒採用に不可欠なのか?
まず大前提として、今の学生にとってインターンに参加することは非常に当たり前の行動になっています。マイナビやリクナビの調査でも、約8割以上の学生が何らかのインターンに参加しているというデータが出ています。しかも、1社だけでなく3社以上に参加している学生が多数派です。
その理由は明確です。学生は、就職活動を進めるにあたり「ミスマッチを避けたい」「会社の中身を早めに知りたい」という想いを強く持っています。つまり、求人情報や説明会だけでは企業を判断できない時代に入っているのです。
このような状況下で、中小企業がインターンはやっていない、一方通行の説明会しかないという状態では、出会いのきっかけすら失われてしまいます。インターンという体験の場を通じて企業の価値を伝えることが、新卒採用の成功を左右する最大のポイントとなっているのです。
就業体験で終わらせないインターン設計のノウハウ
インターンを効果的に機能させるためには、とりあえず仕事を見せる、一方的に話すという形式から脱却し、学生が心を動かされる体験を意識した設計が必要です。ここでは、中小企業が取り組みやすく、なおかつ成果につながりやすいノウハウを3つの視点でご紹介します。
①双方向型ワークの設計
おすすめは、実際の仕事をテーマにしたグループワークや、リアルなビジネス課題を元にしたディスカッション型ワークです。これにより、学生は受け身にならず、自ら考え・発言し・手応えを得ることができます。
②フィードバックの質を高める
ワーク後や個人対応時に、社員から丁寧なフィードバックを受けることで、学生は自分の強みや成長の可能性に気づきます。これは志望度の向上やこの会社に入りたいという感情の後押しになります。
③「社員の素顔」が見える交流設計
社員との座談会や1on1トークなど、学生がリラックスして話せる場をつくることで、社風・人間関係のリアルさを実感させることが可能になります。これは、大手企業にはない中小企業の強みとして非常に効果的です。
学生が参加して良かったと感じるおすすめインターンの特徴
実際に学生から好評を得ているインターンには、いくつかの共通点があります。
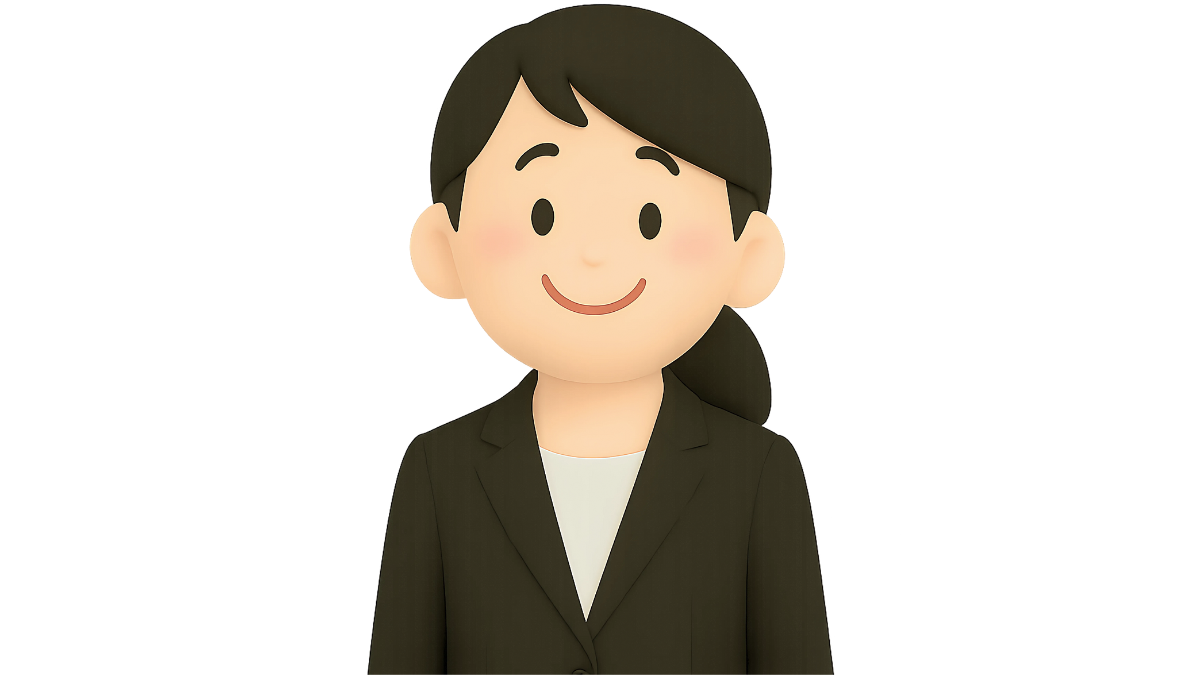
「自分の成長につながるフィードバックがあった」
「社員の人柄や会社の雰囲気がよくわかった」
「社長や経営層とも話せてこの会社の本気度が伝わった」
「インターン後の流れ(面談や選考)が明確で不安がなかった」
「少人数で一人ひとりを大切にしてもらえた感覚があった」
これらの要素は、いずれもコストをかけなくても実現可能です。つまり、中小企業でも十分に選ばれるインターンを設計できるということです。
さらに効果的なのが、インターン参加者限定での早期選考や特別イベントの案内です。自分は特別に扱われているという感覚は、学生の志望度と承諾率を劇的に高めます。
インターンと選考をどうつなぐ?辞退を防ぐ導線設計
インターンシップは、単なる体験で終わらせず、採用プロセスの導線設計とセットで考えることが重要です。特に中小企業は、大手企業のように3月から一斉に選考開始というわけにはいきません。だからこそ、出会った瞬間から関係を育てていく設計が必要です。
おすすめのステップ設計
- インターン参加前から期待値を明確に伝える(社風、目的)
- インターン後すぐに個別面談を設定し、感想・不安をヒアリング
- 早期に「次の接点(1次面談・職場見学)」を提示する
- 参加者限定のSlack・LINEグループなどで関係性を継続
- 選考希望者には特別ルートを案内し、スムーズに内定へ
こうした設計により、学生の気持ちが離れてしまう前に「この企業ともっと関わりたい」という状態を維持し続けることができるのです。
新卒採用において、中小企業が他社と差別化し学生に選ばれるためには、知名度よりも体験の質が重要です。そして、インターンはその体験の質をもっとも高く設計できる舞台です。
今回ご紹介したようなノウハウや工夫を活かしながら、ぜひ貴社らしい、そして学生にとっても意味のあるインターンシップを実現してください。
中小企業の採用力は設計力で逆転できる
新卒採用において、中小企業が成果を出すために必要なのは、資金力や知名度ではなく「採用の設計力」です。誰に・何を・どう伝えるかを見直し、自社に合った戦略を実行することで、十分に結果を出すことができます。
- 採用ブランディングの強化
共感を軸に、SNSや動画を活用して「選ばれる企業」になる。 - ターゲットに合った採用手法の選定
ナビに依存せず、自社と相性の良いチャネルを使い分ける。 - インターンの魅力体験化
学生が“働くイメージ”を持てる設計で、辞退リスクを防ぐ。
大切なのは、大手企業に勝つことではなく、自社らしさで選ばれる存在になること。採用の仕組みを見直すことが、これからの組織づくりの第一歩です。
採用に必要なのは、知名度より「設計力」
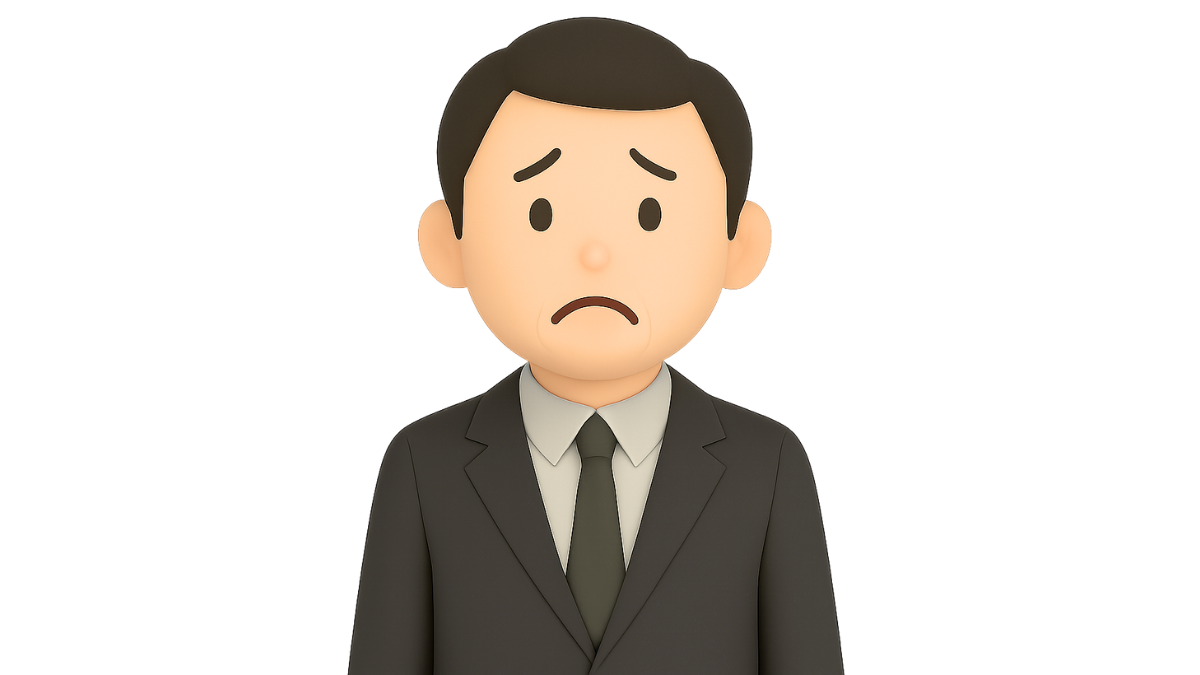
「ナビに出しても応募がゼロの日も…」
「学生とやっと出会えても、大手に行ってしまう…」
「採用担当専任じゃないから、設計も運用も手が回らない…」
少人数・兼任・低予算…中小企業の採用には特有のハードルがあります。アクシアエージェンシーは、中小企業の現場に合わせた採用支援を行っており、貴社のリソース内でできることを一緒に考え、ご提案いたします。
アクシアエージェンシーの強み
- 採用業務専任のご担当者様がいなくても進められるよう、わかりやすくサポートします
- 限られた予算内でも効果的なチャネル・設計をご提案します
- ナビ・スカウト・SNS広告など、媒体選定から原稿作成も対応します
- 面接・選考まわりの改善提案やフォロー導線もご相談ください
- 採用に慣れていない方でも、安心してご利用いただけます
「まずは何を見直せばいいのか知りたい」その段階からでも大丈夫です。中小企業の採用課題、一緒に設計から考えてみませんか?
監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長
神津秀明
人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。
採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。