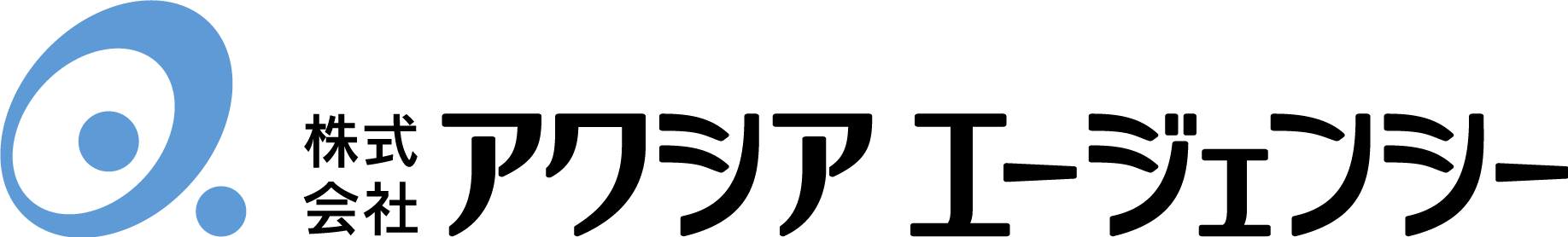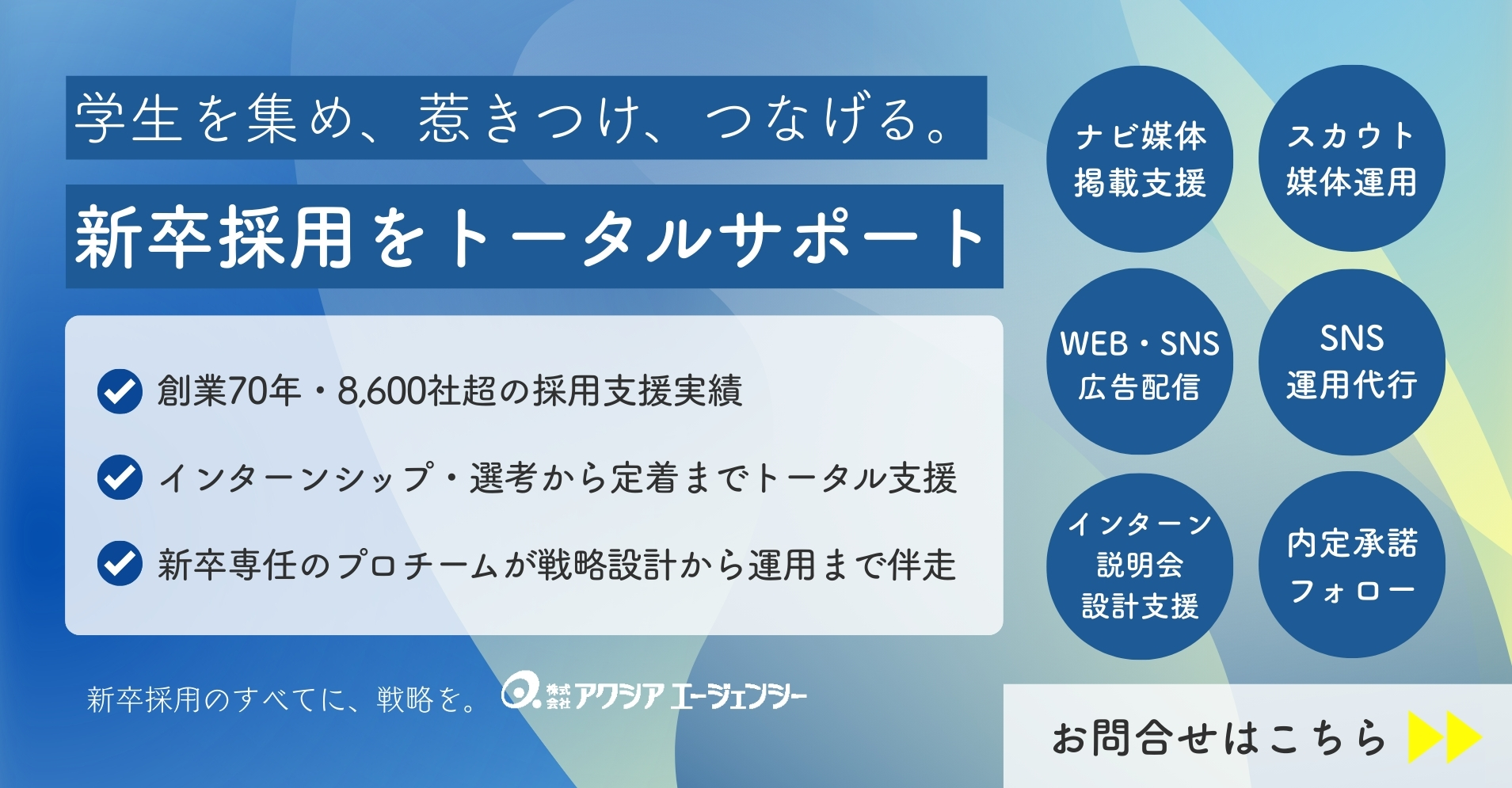学生のインターンシップ参加率は年々上昇しており、2024年卒の学生では約9割が何らかのインターンシップに参加したという調査結果も出ています。また、企業の多くがインターンシップ参加者を早期選考の対象とする傾向を強めており、就活の早期化もますます進んでいます。
このような状況下で、企業にとってインターンシップは単なる採用広報ではなく、戦略的な母集団形成・動機づけ・早期囲い込みの場となっています。中でも、学生に「面白い」「成長できた」と感じさせるような魅力的な内容設計が、エントリー数や内定承諾率に大きく影響する時代です。
本記事では、学生の心をつかみ採用に繋げるために、企業側が知っておくべきインターンシップ設計のポイントを徹底解説します。業界・職種体験型や新規事業立案型、ビジネスゲーム形式、AI・データ分析体験型など、多様なプログラム設計の考え方を紹介しながら、学生に選ばれるインターンシップのつくり方を具体的に解説します。
学生に選ばれるインターンシップとは
インターンシップは、単なる参加型イベントではなく、学生が企業を知り、自分の将来像を描くための重要な場となっています。だからこそ、企業側も「選ばれるインターンシップ」を意識した設計が必要です。
では、学生にとって魅力的なインターンシップとは、どのようなものなのでしょうか。
インターンシップの目的と役割を再定義する
企業にとってのインターンシップは、近年ますます重要性を増しています。かつては「採用広報」や「会社紹介」としての意味合いが強かったインターンシップも、現在では優秀な学生と早期に接点を持ち、採用に繋げる戦略的なチャネルとして活用されるケースが主流になっています。
特に学生のインターンシップ参加率は90%を超える水準にあり、多くの企業が「インターンシップ参加者から早期選考に進める仕組み」を導入しています。こうした背景から、インターンシップの設計には以下のような多層的な役割が求められています。
- 学生にとっての「リアルな業務体験の機会」
- 企業にとっての「優秀人材とのマッチング機会」
- 採用活動全体を効率化する「早期母集団形成」
- 志望度を高める「動機づけコンテンツ」
企業側がインターンシップを単なる説明会や雑務体験にとどめてしまうと、学生の印象は一気に悪化し、選ばれない企業になってしまう可能性が高まります。インターンシップは企業ブランドそのものを体験させる接点と捉えることが不可欠です。
学生がインターンシップに求めていることとは?
学生側の意識にも大きな変化が見られます。以前は「就職活動の前哨戦」程度に捉えられていたインターンシップですが、今や就職先を見極める重要な材料となっています。特にZ世代の学生は、企業選びにおいて以下のようなポイントを重視する傾向があります。
- 自分が成長できる環境かどうか
- どんな社員と働くのか、人間関係はどうか
- 自分の力がどこまで通用するのか試してみたい
- 実務に近い形で仕事の内容を知りたい
こうしたニーズを満たすために、企業は「内容が面白い」「学びがある」「リアルな体験ができる」インターンシップを企画・提供する必要があります。
たとえば、単なる会社説明会型ではなく、学生が自ら手を動かし、考え、アウトプットするワークショップ型の設計が評価される傾向にあります。さらに、現場社員との交流やフィードバックの時間を設けることも、学生がその企業に対して親しみやすさや信頼感を持つ大きな要因となります。
採用に繋がるインターンシップの特徴と共通点
インターンシップを採用に直結させるには、表面的な体験に留まらず、設計段階から「どのように採用と接続するか」を逆算して考えることが必要です。ここでは、採用成功に繋がった企業のインターンシップに共通する特徴を整理します。
①実務に近いリアルな体験
学生が将来働くイメージを持てるように、実際の職種や業務に近いタスクを体験させることが重要です。
たとえば、営業職希望の学生には商談ロールプレイ、マーケ職希望にはキャンペーン企画、エンジニア志望にはプロトタイピング体験など、実務のエッセンスが詰まったプログラムが効果的です。
②チームでの協働要素
学生同士でチームを組み、課題解決やプレゼンテーションに取り組ませる形式は、協調性・リーダーシップ・コミュニケーション力の可視化にも繋がり、評価やフィードバックにも活用しやすい形式です。
また、学生にとっても「一体感」や「達成感」が得られる設計となるため、満足度が高まります。
③明確なフィードバックと評価の場
インターンシップを通じて「何を評価されたか」「どんな点が良かったか・課題か」を伝えることで、学生側は自己理解が進みます。企業側も、その学生の課題解決能力・思考力・行動特性などを把握することができ、選考判断に活かしやすくなるというメリットがあります。
④社員との自然な接点・文化の共有
単にプログラムをこなすだけでなく、社員との座談会やランチ交流、オフィスツアーなどを組み込むことで、学生に企業文化や雰囲気を感じさせることができます。採用の成功には「人・空気感への共感」も大きく影響するため、この設計は極めて重要です。
このように、学生に選ばれるインターンシップを実現するには、学生の視点に立った企画設計と、採用戦略との一貫性が求められます。単発の体験提供で終わるのではなく、「この会社に入りたい」と感じてもらえるストーリーと体験の連動が鍵になるのです。
魅力的で面白いインターンシップの内容の設計ポイント
インターンシップの価値を高めるうえで、「面白い」「実践的」「印象に残る」体験をどう設計するかは非常に重要です。ただし、単にユニークであるだけではなく、学生が関心を持ちやすいテーマや企業理解につながる内容であることが求められます。
ここでは、企業が設計しやすく、かつ学生満足度・採用効果の高いインターンシップの内容分類を6タイプに分けて、それぞれの特徴と設計ポイントを紹介します。
業界・職種体験型インターンシップ
実際の業務を学生が疑似体験できるワークショップ形式のインターンシップは、参加者に高く評価されやすいです。たとえば広告業界ならキャンペーン企画、建築業界なら設計アイデア出し、IT業界なら簡単なUX改善提案など、職種に直結したテーマを用意することで、学生はより鮮明な働くイメージを持てます。
また、参加者が「ただ見るだけ」ではなく、自分で手を動かす体験・発表機会・フィードバックが含まれていると満足度が大きく向上します。
盛り込みたい要素
- 実務に近いテーマ(営業同行、提案資料づくり、マーケティング設計など)
- 実際の社員が設計・フィードバックに関与すること
- 個人とチーム両方でのアウトプット
新規事業立案型インターンシップ
学生がチームで企業の課題解決や新しいサービス・ビジネスモデルの立案に挑戦するタイプのプログラムです。実際の企業課題や市場データを提供することで、参加者にとっては「本当にビジネスに関わっている感覚」が得られる構成になります。
この形式では、ロジカルシンキング・プレゼン力・チームワーク・仮説構築力など、選考でも評価したいスキルが見える化されやすいメリットもあります。
設計のコツ
- 自社事業と関係のあるテーマを設定
- 初日に調査・中日に相談・最終日に発表というストーリー設計
- 優秀チームへの表彰や後日のフォロー面談を導入
ビジネスゲーム型インターンシップ
ボードゲームやシミュレーションを活用した「楽しさ重視」の体験型インターンシップです。たとえば、「利益最大化を目指す会社経営シミュレーション」や「営業活動ロールプレイ」など、ゲーム性と学びが融合した設計は、学生に強く印象を残します。
ゲーミフィケーション要素が加わることで、内向的な学生も自然に発言しやすくなり、企業理解とスキル確認が同時に可能となります。
活用シーンの例
- 総合職採用でチームプレイを重視する場合
- ゲーム後の社員交流やフィードバックタイムとの組み合わせ
- オンライン開催でも実施しやすい
企業文化体験・社員交流型インターンシップ
学生が「一緒に働く人の雰囲気」「会社の価値観」「働く環境」を体感できるインターンシップです。職場見学、社員座談会、メンター付きのミッション形式などを組み合わせることで、学生の企業への親近感や共感を生みやすくなります。
採用においては、「仕事内容」よりも「人」や「カルチャー」が決め手になるケースも多いため、現場社員の登場機会をどれだけ作れるかが重要です。
ポイント
- 若手社員との1on1トークや少人数座談会
- 部署横断型プロジェクト体験(例:マーケ×エンジニア)
- 企業理念や働き方に触れる場づくり
プログラミング体験インターンシップ
文系・未経験の学生にも間口を広げやすいのが、簡易的なプログラミング体験型です。たとえば「HTMLを使って簡単なLPを作る」「Pythonで自動計算ツールをつくる」など、自分の手で動かす感覚を持てる内容が喜ばれます。
難易度が高すぎると挫折するため、必ず「初学者向けチュートリアル」「サポート体制」をセットで設計しましょう。
実施のヒント
- オンライン教材+当日サポート体制を整備
- 成果物を残して達成感を持たせる
- エンジニア社員との懇談でモチベーション向上
AI・データ分析体験型インターンシップ
データサイエンスやAIに関心のある学生向けに、「ビジネスデータの可視化」や「機械学習モデルの構築体験」などを提供するパターンです。専門知識が必要な分野ですが、ExcelやTableauを使った分析演習、簡易チャットボット作成など、身近なテーマから入ると理解度も高まります。
設計例
- 実際の社内データを加工し、営業課題の分析を行うワーク
- ChatGPTなど生成AIツールの活用体験
- 初心者向けでもステップアップできるよう段階的に設計
このように、内容の「面白さ」だけでなく、実際の仕事に近く、学生のキャリア形成に役立つ体験を提供することが、魅力的なインターンシップには欠かせません。学生のエンゲージメントを高めるインターンシップ企画は、採用成功にも直結する強力な接点になるのです。
学生のエンゲージメントを高めるための設計とは
インターンシップを通じて企業への志望度を高め、採用につなげるためには、単にプログラムの内容が面白い・役立つというだけでは不十分です。学生が自分ごととしてプログラムに関わり、企業と心理的なつながりを持つこと=エンゲージメントの醸成が非常に重要な観点です。
ここでは、学生の心に火をつけるインターンシップ設計のための「エンゲージメント向上ポイント」を4つに分けて整理します。
興味関心を引くテーマ設定の工夫
インターンシップ開始前から学生の心をつかむには、「今の自分に関係がある」「おもしろそう」と感じさせるテーマ設定が鍵になります。たとえば、学生が日頃から関心を持っているキーワード(SNS、生成AI、SDGs、ベンチャー思考など)をタイトルやワークに取り入れることで、参加前の期待感が大きく高まります。
また、「〇〇体験」「〇〇チャレンジ」「〇〇ミッション」のようなアクティブで自己投影しやすいネーミングを使うことも効果的です。タイトル段階で「他のインターンシップと違う」「面白そう」「実践的だ」と思わせられるかが勝負です。
参加前〜参加後のコミュニケーション設計
エンゲージメントを高めるうえで、「参加当日だけが本番」ではありません。申し込みから実施後のフォローまで、一連の接点でどれだけ丁寧にコミュニケーションを設計できるかがカギを握ります。
- 参加前:サンクスメールや事前課題の送付、担当社員の紹介
- 実施中:ファシリテーターやメンターによる対話機会の設計
- 終了後:フィードバックや振り返りアンケート、メッセージ送付
これらを通じて、「自分は大切に扱われている」「ちゃんと見られている」という感覚が生まれ、学生の企業理解・好意度が飛躍的に高まります。
オンライン/対面で異なる運営の工夫
ハイブリッドなインターンシップが一般化した今、開催形式に応じたエンゲージメントの高め方の工夫も欠かせません。
- 対面形式の場合:空気感・社風・雑談の重要性を活かせる
- オンライン形式の場合:映像やチャット、ツールを駆使して双方向性を担保
たとえばオンラインでは、アイスブレイクやブレイクアウトルームを多めに設定し、参加者同士・社員との交流が希薄にならない工夫が重要です。また、SlackやLINEオープンチャットなどを使った当日限りのグループも人気です。
学生の心理を可視化してフォローに活かす
実施後に学生が「どう感じたか」「どこでモチベーションが上がったか」「何に共感したか」を把握することは、次回以降の設計改善だけでなく、採用アプローチのパーソナライズにもつながります。
アンケートだけでなく、感想文や簡単な行動ログ(チャット、発言、ワークシートなど)を記録し、学生個人の関心領域や強み・課題を見える化しておくことで、フォロー面談や本選考の際に非常に有効です。さらに、これらの情報を「選考評価とは別枠で扱う」と伝えることで、学生の本音を引き出しやすくなる効果もあります。
エンゲージメントを高めるインターンシップとは、単に中身が優れているだけでなく、参加前から参加後まで一貫した関わりの質が設計されています。「また話したい」「もっと知りたい」と思ってもらえるインターンシップこそが、採用に強くつながるのです。
インターンシップを採用に繋げるための工夫
インターンシップは、企業と学生が直接出会える貴重な場であり、将来の入社意欲を高める最初の接点です。せっかく工夫を凝らして設計したインターンシップであっても、それを採用成果に繋げられなければ意味が半減してしまいます。
ここでは、面白く魅力的なインターンシップ体験を、「選考への導線」「内定承諾率の向上」「入社意欲の継続」に繋げるための具体的な工夫を4つ解説します。
内定フォローに繋がる仕組みの設計
インターンシップの中で「学生が活躍した」「フィードバックが刺さった」「社風が合いそうだ」と感じた瞬間は、その学生を将来の入社候補と捉えるうえで極めて重要なサインになります。
企業としては、そうした学生に対して、インターンシップ終了後も継続的に接点を持ち、早期選考や個別面談への導線を自然に組み込んでおくと効果的です。
- 「インターンシップ参加者限定」の説明会・OB訪問・職場見学
- インターンシップでの評価をもとにした個別フィードバック面談
- 採用広報では伝えきれない企業の魅力を深掘るメールコンテンツ
これらを通じて、学生の温度感が高いうちに採用コミュニケーションを強化することがポイントです。
評価とフィードバックの有効活用
インターンシップの中で得られた情報や評価を、選考プロセスに活かす仕組みを構築することで、採用の精度が飛躍的に高まります。たとえば、以下のような要素は、面接やエントリーシートだけでは把握しにくい資質やスタンスを浮き彫りにしてくれます。
- 課題に対する姿勢(粘り強さ、論理性、行動力)
- チーム内での役割(リーダーシップ、協調性)
- 自己認知の深さ(フィードバックへの反応)
評価は、選考としての合否判断ではなく、将来の伸びしろや企業との相性を見る視点で整理するのがコツです。また、学生にもフィードバックを返すことで、「自分を見てくれている」という信頼感が醸成されます。
学生の記憶に残るシーンを意図的に設計する
学生がインターンシップを振り返ったときに、「あの時間が印象的だった」「あの社員の言葉が忘れられない」といった具体的な記憶があることは、志望度の持続や意思決定の材料として非常に重要です。こうした記憶に残る瞬間を意図的に設計するには、以下のような方法があります。
- 初日の冒頭で社員の熱いストーリーを語る時間を設ける
- 社員との1on1で「あなたのために時間を使った」と感じさせる対話を設ける
- 成果発表の場で、役員や部長からの本気コメントを受ける機会を作る
「面白かった」で終わらせるのではなく、「この会社で働きたい」と思わせるために、人とのつながりとストーリー性を意識した場づくりが必要です。
インターンシップ体験を「企業らしさ」に接続する
どれほど実践的な内容であっても、「他社でも同じことができる」と思われてしまっては意味がありません。大切なのは、そのインターンシップが“その企業らしさ”と結びついていることです。たとえば、以下のような要素が企業らしさを伝えるポイントになります。
- ミッションやバリューを反映したワークテーマ
- 実際の社内プロジェクトを題材にするケーススタディ
- 組織文化に基づいたフィードバックや評価軸の明示
「うちの会社だからこのインターンシップだったんだ」と思ってもらえるように、内容と企業カルチャーが一貫しているかを見直すことが、採用への接続をより確かなものにします。
このように、インターンシップの設計段階から「採用に繋げる」視点を持ち、学生との関係性を中長期的に捉えることが、入社への確度を高める鍵となります。企業にとってインターンシップは、選ぶ場ではなく選ばれる場でもあるという意識を忘れず、関係構築を重視した設計を行いましょう。
NGなインターンシップ設計例とその改善策
どれほど意図を持って企画したインターンシップであっても、学生の期待値とのズレや参加後の不満足感が生まれてしまえば、逆効果になってしまうリスクがあります。特にZ世代の学生は、企業との関係において共感・納得・体験価値を強く重視するため、表面的な設計や一方通行なコミュニケーションはすぐに見抜かれてしまいます。
ここでは、実際にありがちなインターンシップ設計のNGパターンと、その改善策について解説します。
学生がつまらないと感じる原因とは
「インターンシップに参加したけれど、何も得られなかった」「企業のイメージが悪くなった」という感想が出てしまうケースには、次のような共通点があります。
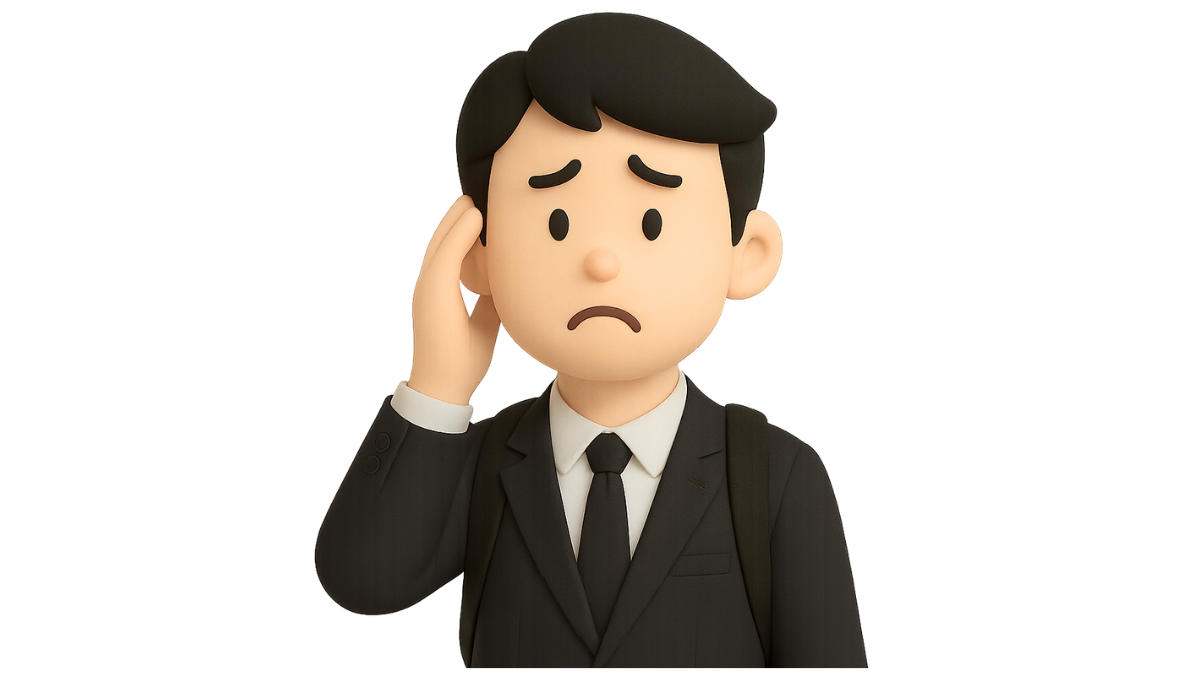
「座学中心のプログラムで、聞いているだけでは退屈だった」
「業務体験がほとんどなく、実態が見えなかった」
「説明ばかりで双方向性がなく、社員との接点もほぼなかった」
「自分の考えや強みを活かせる場面がなかった」
これらは、インターンシップというよりも「会社説明会の延長」「社員によるプレゼン会」に近い設計です。特に情報感度の高い学生は、「他社の方がちゃんと体験できた」と比較し、志望度を下げる要因となってしまいます。
一方通行のインターンシップが失敗する理由
企業が伝えたい情報だけを詰め込んだインターンシップ設計では、学生は受け身になるだけで、関係性もエンゲージメントも生まれません。いわば「企業発信型」の設計になってしまっているのです。
- 学生が主体的に参加する機会がない
- 発言・発表・ワークの場がない
- フィードバックがない、または形式的
このような構成では、学生は「ただ聞いて終わった」「情報を渡されただけ」という感覚を持ち、企業理解や興味は深まりません。さらに、採用への転換率にも大きく影響するため、改善が不可欠です。
インターンシップを改善するための3つのポイント
つまらない・一方通行なインターンシップを改善し、魅力的かつ採用成果にも繋がる設計へと進化させるには、以下の3つのポイントが重要です。
①双方向・参加型の構成にする
学生が手を動かし、頭を使い、アウトプットを出す設計を意識しましょう。
- グループディスカッションや発表パートの導入
- ミニワークショップやロールプレイの活用
- 発表に対して社員がフィードバックする時間の設計
上記のように、参加者ではなく体験者としての関わりを作ることが鍵です。
②「実際の仕事」をイメージできる内容にする
企業説明や理念の紹介ばかりではなく、学生が「この会社で働くとはどういうことか」を肌で感じられるよう、実務に近いワークやストーリーを組み込みましょう。
- 実在のプロジェクトを元にした課題出題
- 職種別の体験パートの分岐設計
- 成果物の共有タイムや振り返りシートの導入
学生が働く自分を想像できる内容にすることで、エンゲージメントと志望度が高まります。
③一貫したフィードバックとフォローの設計
「あなたのこういう点が良かった」「ここはこうすればもっと良くなる」といった個別性のあるフィードバックは、学生にとって非常に印象に残ります。また、インターンシップ後のアプローチ設計にも繋がるため、評価・メモ・振り返りの仕組みも整えておきましょう。
NGなインターンシップ設計を回避するためには、学生視点の共感設計・双方向性・リアリティ・一貫性がポイントになります。「とりあえず企画した」インターンシップはすぐに見抜かれ、学生の心には残りません。しっかりと体験価値を設計し、参加してよかったと思える時間を提供することが、採用への最大の近道です。
実施前後で見るべき指標と改善方法
どれだけ魅力的なインターンシップを設計・実施しても、成果が可視化されていなければ、改善も再現もできません。採用に直結するインターンシップを実現するには、実施前から評価の軸を設け、実施後に必ず振り返るPDCAの仕組みが重要になります。
ここでは、インターンシップの効果測定を行うために企業が見るべき指標と、次回に活かすための改善の進め方を整理します。
満足度調査で見るべき質問項目
インターンシップ後のアンケート調査は、多くの企業が実施していますが、単なる「楽しかった/つまらなかった」では意味がありません。本当に見るべきは、「どこに満足・不満を感じたのか」「企業理解や志望度にどんな影響があったか」という定性的・定量的な両面のデータです。
おすすめの設問例
- インターンシップを通じて企業への理解は深まりましたか?(5段階評価)
- 社員や社風に対して、どのような印象を持ちましたか?(自由記述)
- 内容のボリューム・難易度は適切でしたか?(過不足の感覚)
- 本選考への参加意欲は変化しましたか?(上がった/変わらない/下がった)
- 印象に残った場面・やり取り・フィードバックは?(自由記述)
こうした設問を通して、「どのパートが評価されているか/足りなかったのか」が見える化されます。
採用への転換率をどう捉えるか
インターンシップが採用に繋がっているかを評価するうえで、以下のような定量的指標(KPI)を定めておくと、目的と成果のギャップが見えてきます。
チェックすべき主なKPI
- エントリーからインターンシップ参加への転換率
- インターンシップ参加者の本選考エントリー率
- インターンシップ参加者の面接通過率/内定率
- インターンシップ経由内定者の承諾率
- 内定辞退率と理由(特にインターンシップ参加者)
また、単なる人数ではなく、質の高い学生をどれだけ早期に囲い込めたかという観点も重要です。必要に応じて、参加者の属性(大学・学部・志望傾向など)を分析しましょう。
PDCAを回すインターンシップ運営体制とは
成果の分析だけでなく、改善と再設計のサイクルを継続的に行うための「体制づくり」も成功のポイントです。特に採用チームと現場(人事・配属部署・社員メンター)が分断している企業では、PDCAが止まりがちです。
理想的な体制の例
- インターンシップ終了直後に振り返りミーティングを設定
- アンケート・行動ログ・社員フィードバックを統合して分析
- 良かった点・課題点をスプレッドシートなどで可視化し、次期設計会議に活用
- 社員向けにも「インターンシップ参加者へのフィードバック方法」研修を導入
このような体制を整えることで、毎年同じような反省を繰り返す状態から脱却し、成果を積み上げていくインターンシップ運営が可能になります。
定性的データと行動ログの活用
満足度アンケートや選考実績とあわせて、学生の行動そのものをログ化・定性的に記録しておくことも有効です。
- ワーク中の発言ログやワークシートの保存
- チャットツールのやり取り(オンライン開催時)
- 社員からの一言メモ(学生ごとの観察記録)
こうした細かな情報が蓄積されることで、次回の設計や学生ごとの対応精度の向上にも繋がります。また、面接時や内定者フォロー時に「あのときのワークでの姿勢が良かった」と言えると、学生のエンゲージメントは一気に高まります。
このように、インターンシップを「やりっぱなし」で終わらせず、数字・声・行動という三方向のデータを活用して検証・改善を重ねていくことで、企業にとっての本当の資産になっていくのです。
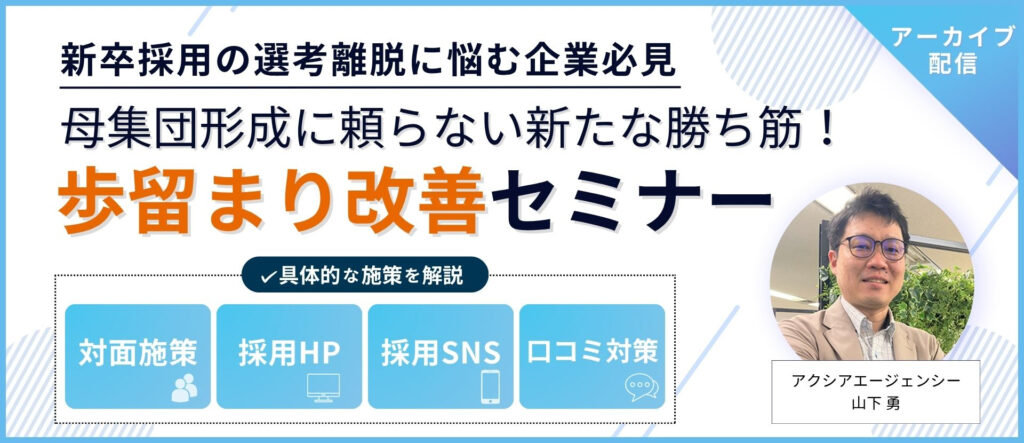
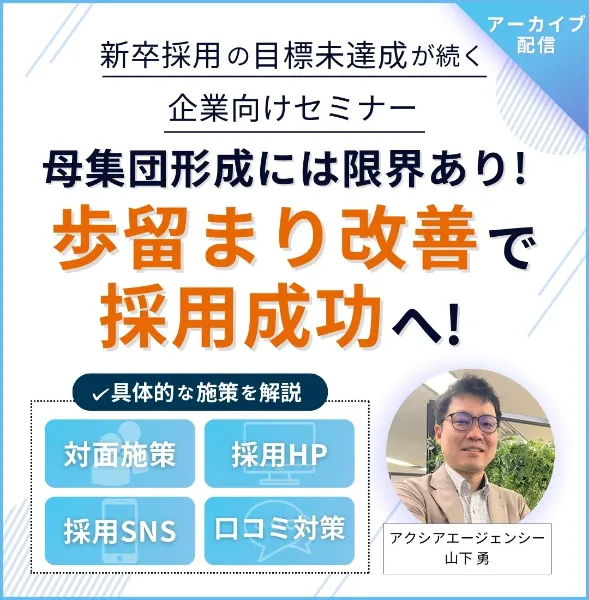
学生の心をつかむインターンシップで採用成功へ
学生の価値観や就活の早期化が進むなかで、企業が優秀な人材を採用し、長く活躍してもらうためには、インターンシップの設計そのものが戦略的である必要があります。単に面白いだけでも、情報提供型でもなく、企業と学生双方の目的に寄り添い、エンゲージメントを育て、入社意欲につなげる構造が求められています。
本記事では、採用に直結するインターンシップをつくるために押さえておくべき重要な観点を網羅的に整理しました。
学生に選ばれるインターンシップをつくるには
- 実際の業務に近いテーマや体験の提供
- 学生の関心を引くユニークで実践的なコンテンツ設計
- 社員との自然な接点、企業文化を感じられる交流機会
- 参加後のフォローや早期選考への導線設計
- 満足度や転換率をデータで検証し、PDCAを回す体制構築
これらの要素を組み込むことで、インターンシップは単なるイベントではなく、採用戦略の中核となる強力な武器になります。学生は今、情報にあふれた時代に生きており、どんな企業も比較対象となり得ます。そんな中で「この会社、ちょっと違うな」「ここでなら働いてみたい」と思わせる体験を設計できるかが、インターンシップの価値と採用成果を大きく左右するのです。
企業が自社らしさを活かしつつ、学生の目線にも立ったインターンシップを設計できれば、単なる母集団形成を超えて、将来の戦力となる人材との関係構築に繋がります。採用活動の第一歩として、今こそインターンシップを見直し、進化させていくことが求められています。
“選ばれる企業になるインターン”を、一緒に設計しませんか?
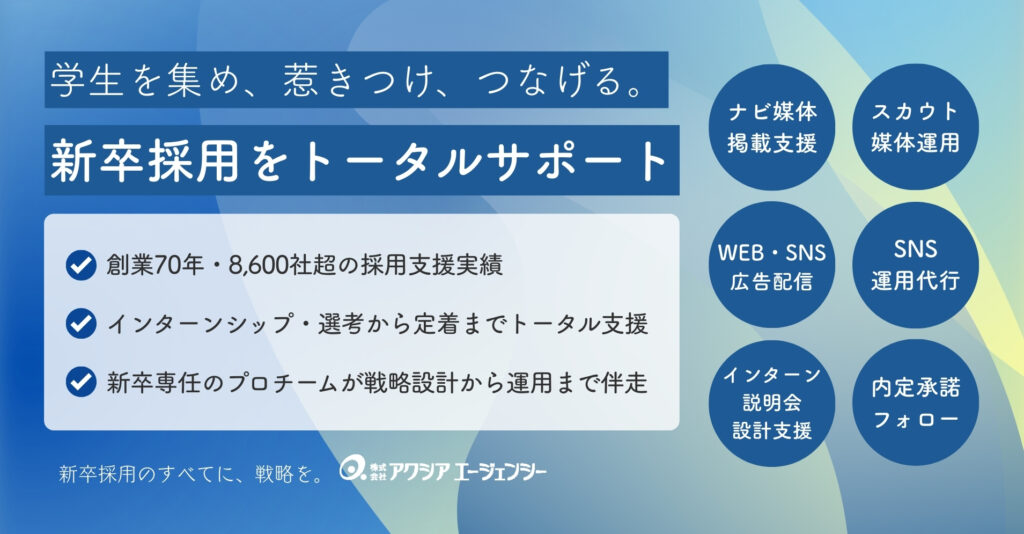
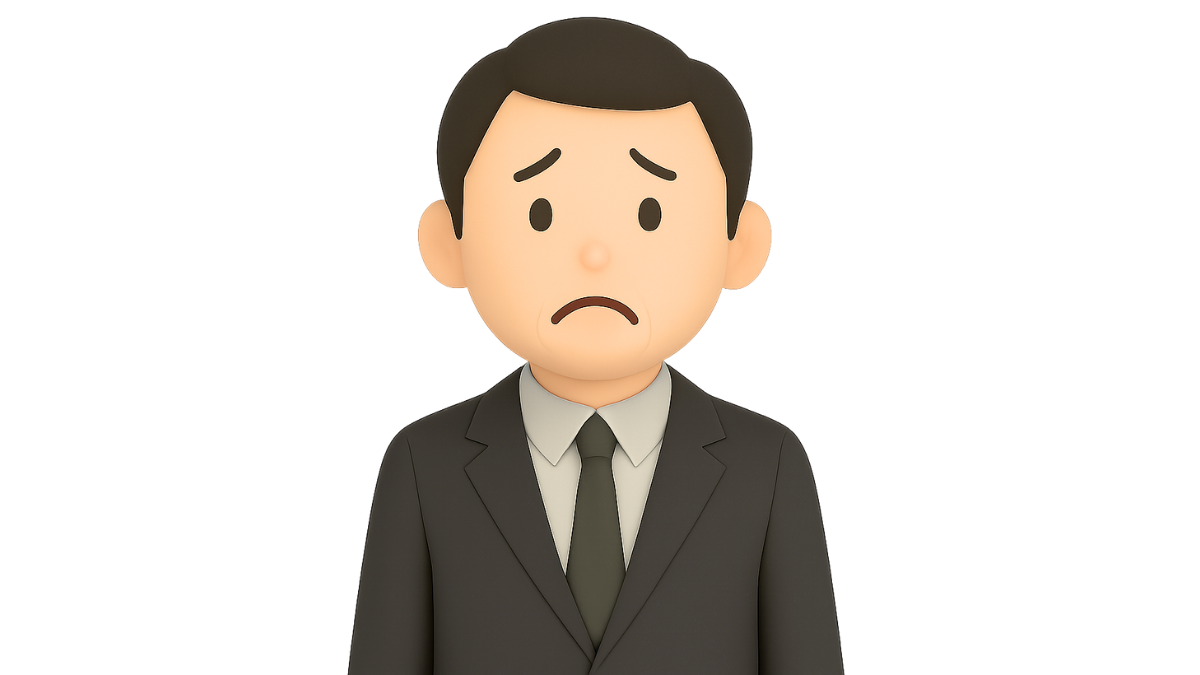
「1dayインターンは集まるけど、本選考に全然進まない…」
「参加後のフォローまで手が回らないし、何をすればいいか分からない」
「学生にとって印象に残るプログラムって、どう作ればいいんだろう…」
学生との最初の接点であるインターン。「とりあえず実施している」だけでは、志望度は高まりません。
私たちは、体験価値の設計 × 選考への導線づくりを軸に、採用成果に直結するインターンの構築をサポートします。
アクシアエージェンシーの強み
- ワーク型・体験型・座談会型など、目的に応じたインターン設計をご提案します
- コンテンツ企画から当日の運営サポートまで一貫して対応いたします
- 学生アンケートや行動データをもとに、改善提案やPDCA運用を行います
- SNSやWeb広告を活用した集客施策もご支援いたします
- 参加後の志望度向上や、選考移行につながる導線設計も得意としています
「まず何から始めればいいかわからない」そんな状態からでも大丈夫です。ゼロから一緒に、成果につながるインターンをつくりましょう。
監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長
神津秀明
人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。
採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。